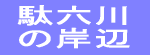 |
駄六川の岸辺 > 変わり囲碁 |
三角盤碁(※) |
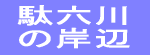 |
駄六川の岸辺 > 変わり囲碁 |
三角盤碁(※) |
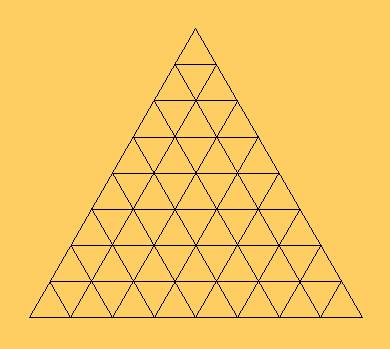 |
囲碁のルールは将棋やオセロより、実は簡単なんですよね。対戦者が交互に置いていく石の生死さえ判断できるようになれば、もう遊ぶことができます。将棋の桂馬なんて、考えれば妙な移動ができるし、敵陣に入れば駒がひっくり返るのも、初めはとてもわかりづらいものです。 囲碁の盤面を正方形から三角にしてみました(左図)。本式の十九路では図が複雑になるので九路盤、すなわち各辺に対し8分割した小さな三角形を並べる図を示しますが、当然十九路でも同様に扱うことができると思います。 なお以下では、通常の正方形の碁を「正方碁」と呼ぶことにします。 |
| ここで、最大の基本ルール「死活」は、次図のようになります。 |
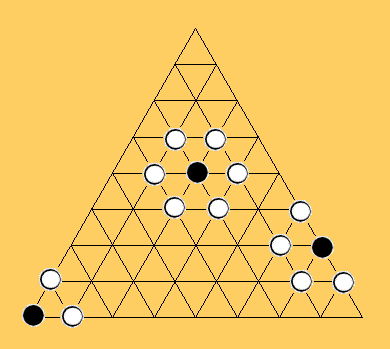 |
1.中央では、周辺をすべて囲まれると死。左図中央では黒石が白石6個に囲まれたため、アゲハマとして取られてしまいます。 2.図左下は、スミの死活を示します。これも黒石が白石に囲まれたため、取られてしまいます。 3.図右部は辺の死活です。上と同様、黒死です。 |
| このように、正方の盤を変形させても基本的には囲碁のルールはそのまま準用できます。・・・ということは、もっと妙な図形でも大丈夫なのではないでしょうか・・・ |
※ ここで紹介した碁は以前、「三角碁」と呼んでいましたが、同名が社団法人発明学会の「アイデア宝庫」に登録されていました(登録番号:2003-4-002、品名:三角碁ゲーム)。こちらの方は碁石が三角形で、私の提案するものとはまったく異なる種類のものですが、先行発明者の方に敬意を表し、当方が「三角盤碁」と名称変更させていただきました。(2003-12-31記) |
|
|
りん碁 |
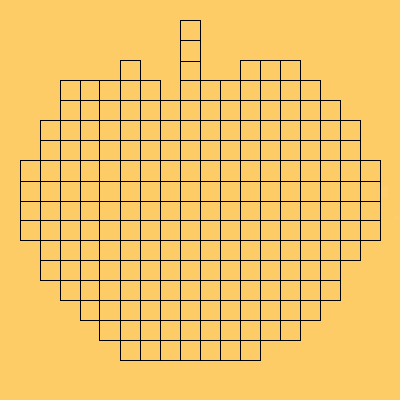 |
左の図が「りんご」に見えなかったら、ごめんなさい。 こんな形の盤でも、囲碁ができます。これを「りん碁」と呼びます。他の形では、例えば京都府北部の日本海側の地図を形取り「たん碁」という碁盤もできます。なお新潟県を形取った「えち碁」は、佐渡島の扱いがむずかしいと思います。特別ルールを作らざるをえないでしょう。(この特別ルールを適用した碁を「ハミ碁」と呼びます。) さらに、イギリスの地図を使えば「エイ碁」、自分勝手な図を描けば「エ碁」、同型の人物図2つで「フタ碁」、ランダムな数字を並べて「ビン碁」など、多くの派生種が可能です。 |
| 下図は「りん碁」の対戦中の図(途中譜)です。次は白番ですが、さて、最善手はどこでしょう? |
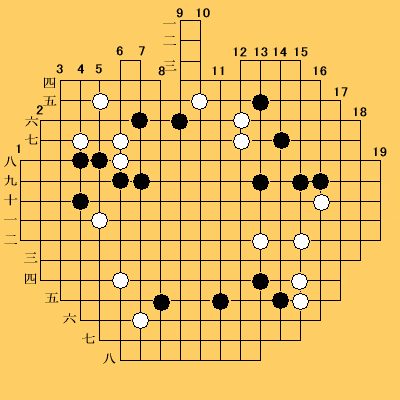 |
左図の横線を示す番号で、「十一」以上は「十」を省略しています。 このような形だと、スミとヘンの値打ちのバランスが通常の正方碁とは異なる点に注意が必要です。例えば上辺中央、りんごの「くき」の箇所は、けっこう値打ちがありそうに見えます。 また右下の白石群は、普通ならかなり広大な領域を占める形でしょうが、ここではスミが欠けているため、さほどでもありません。ただ正方碁での「3三への打ち込み」はありえないので、堅い構えではあります。 さて最善手の検討ですが、実は作者の私にもわかりません。左下から中央にかけて白模様にしたい気持ちと、上辺7の六及び9の六の黒石を殺したい気持ちなんかが出てきます。 |
|
|
ベクトル囲碁、「多次元空間囲碁でわかるマトリックス数学ゲーム」 |
|
友人「み枡屋」亭主氏に上の三角盤碁、りん碁の評価をお願いしたところ、次の提案がありました。 > 数学の先生集めて、ベクトル囲碁もどうや。碁石はスカラーやろそれに方向を与えて 確かに通常の碁では、石はどちらの方向へも向いたものではありません。複数個の自分の石と相手の石の配置で陣取りの方向が現れてはきますが、個々の石1個は、それだけではどちらを向いているものかわかりません。 簡単のため正方碁の盤で、白石黒石に前後左右4方向の矢印を付けます。そのベクトル量も簡単のため「1」とします。矢印が向かう方向を正面とみなします。逆に矢印の根元側(出発側)は背です。 と、考えていったのですが、敵がこちらを殺しているが、こちらは別の敵を殺し、さらにその敵は味方の他の石を殺し・・・という入り組んだ着手が可能であると思われます。友人の言うように「数学の先生」に任せないと、私には歯が立たないので、この程度であきらめました。さらに「多次元空間でわかる・・・」になると、まったくお手上げです。 |
|
|
| このページ最終更新日 : January 5, 2004 |