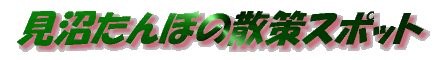
【さぎ山記念公園】
(さぎやまきねんこうえん)
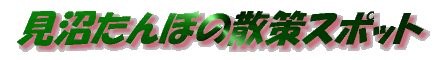
|
五斗蒔橋を通り過ぎて、見沼代用水東縁沿いに「緑のヘルシーロード」を約950mくらい進んでいくと、さぎ山記念公園の裏手にでます。 さぎ山記念公園には、さぎ山記念館、青少年野外活動センター(キャンプ場)、フィールドアスレチックの森、水とメルヘンの広場、芝生広場などがあります。 休日には、釣りを楽しむ人や、のんびりと芝生でくつろぐ人でいっぱいです。 さぎ山記念館では、さぎのはく製や、さぎ山の歴史等のパネル・写真が展示されています。 |
 |  |
 |  |
|
【交通のご案内】 (バス) 浦和駅西口より さぎ山記念公園行 約30分 【歴史】 「野田のさぎ山の歴史」
この付近は、かつて”野田のさぎ山”と呼ばれるサギの集団営巣地でした。サギがここに巣を作るようになったのは、享保年間(1716〜35)徳川八代将軍吉宗の頃です。当時江戸への食糧供給を目的に行われた見沼干拓事業により、沼が浅い水田となりサギの格好なエサ場がにわかに出現したことが原因の一つであるといわれています。以来、紀伊徳川家より御囲鷺として保護されてきました。 この地の主要街道である一般国道122号は昔、日光の御成街道と呼ばれ、徳川将軍が日光参詣の途中、このさぎ山に立ち寄り上覧をした記録も残っていいます。 その後、明治、大正の頃は禁猟区として保護され、昭和13年には野田村鷺繁殖地の名で天然記念物に指定され、続いて昭和27年には特別天然記念物に指定されました。当時の指定面積は1.4haほどで5軒の農家の屋敷林にサギが巣をかけていました(このような状態をさぎ山と呼んだ。)。ここに来たサギは5種類でチュウダイサキ、チュウサギ、コサギ、アマサギ、ゴイサギがいました。 昭和32年頃巣の数六千個を数えていたさぎ山もだんだん減りはじめ、昭和47年には0となり、色々の手当をしたにもかかわらず飛来はあるものの営巣はされず、他の場所に移動してしまいました。いなくなった要因はいろいろあると考えられますが、何といっても水田の減少によりエサが少なくなったことが大きな理由と考えられます。 このような状態からサギを野田に人為的に戻し将来にわたって維持していくことは殆んど不可能な状況となり昭和59年に特別天然記念物及び天然記念物の指定解除となり徳川時代から約250年、指定されて以来77年の歴史を閉じることになったものです。 このさぎ山を記念してその名前が永久に残るよう、また、長く市民に親しまれてきたサギたちを偲ぶ縁として記念館と共に、サギをかたどったモニュメントを配置した公園を設けたものです。(昭和61年5月開園) (浦和市立さぎ山記念公園のパンフレットから) |