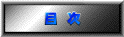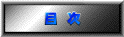
フリーマンの随想
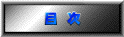
|
[ その1 ] 章様、カホル様 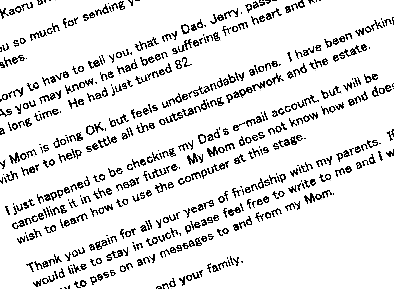 写真とともに年末のご挨拶状をお送りいただき、有難うございます。 写真とともに年末のご挨拶状をお送りいただき、有難うございます。大変残念なことを申し上げますが、私の父ジェリーは、11月24日に亡くなりました。 ご存知のように、 彼は心臓と腎臓を長いこと患っていました。 ちょうど82歳になったばかりでした。 母は体は大丈夫ですが、お分かりのようにすっかり寂しがっています。 私はこのところずっと、 彼女を助けて残された書類や資産を整理するために働いております。 今もたまたま、父のEメールアカウントを調べていたところでした。 でも、近い将来、このアカウントは処分します。 母は使い方も知らないし、 この年齢でパソコンの使い方を習おうという気もありませんので。 私の両親との長い間の友情を、改めて感謝申し上げます。 もし今後も母と連絡なさりたいのでしたら、 どうぞご遠慮なく私にメールをください。 母に伝えますし、母からのメッセージはそちらにお伝えします。 お二人とご家族のお幸せを祈りつつ。 マーゴ ホーリー [ その2 ] ワンダ様、マーゴ様 貴女からのメールでこの悲しい報せを聞き、カホルと私とは大変驚き悲しんでいます。 ジェリーがもうこの世にいないとは信じられません。 もし幾らかでもあなた方の救いになるのでしたら、私どもはあなた方の悲しみを分担したいほどです。 私がジェリーに初めて会ったのは1970年代半ばのことでした。 ワシントンDCでホワイトハウス見学ツアーの行列に並んでいたとき、隣り合った二人は挨拶を交わし、 名刺を交換後10分ほど話し合いました。 ともに技術者だったので、二人はたちまち意気投合し、良い友人となりました。 それ以来、毎年12月にはクリスマスカードを交換し近況を伝え合ってきました。 彼は趣味の写真の技術について、 何度も私に質問してきました。 1988年、私は勤務先の会社の北米最初の生産工場の建設チームのリーダーとして米国のサウスカロライナ州に移住しました。 一方、1990年代、現役を退いたジェリーは、ワンダと共に、 カナダの寒い冬を避けてフロリダで毎年数ヶ月を過ごすのが常でした。 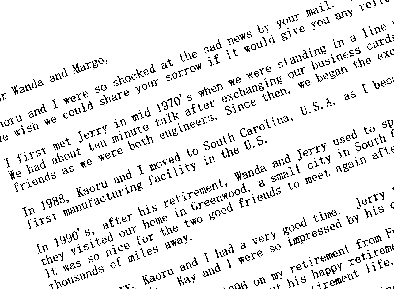 ある年の春、フロリダからの帰途、
二人はサウスカロライナ州の小さな町グリーンウッドにある私の家に立ち寄って、3日を過ごしてくれました。
何千マイルも離れて20年も会うことのなかった二人が再び異国で会えるなんて、本当にすばらしいことでした。 ある年の春、フロリダからの帰途、
二人はサウスカロライナ州の小さな町グリーンウッドにある私の家に立ち寄って、3日を過ごしてくれました。
何千マイルも離れて20年も会うことのなかった二人が再び異国で会えるなんて、本当にすばらしいことでした。ワンダとジェリーと、カホルと私とは、とても素敵な時を過ごしました。 ジェリーは、祖国ポーランド、リビア、イタリア、 そしてカナダでの、数奇で苦難に満ちた経歴とその後の成功について、熱心に語り続け、 私とカホルは彼の勇気と強固な意志に非常な感銘を受けました。 1996年、私は日本に帰ると同時に会社を辞めましたが、私の退職の理由のひとつはジェリーの勧めでした。 彼は自身の幸せな退職後の生活について私に何度も話してくれました。 カホルと私とは、今、 平和で幸せな退職後の生活を送りながら、彼のあのときの示唆に、とても感謝しているのです。 ワンダとマーゴ、最後に再び私どもからの衷心よりの弔意をお受けください。 熊井 章 [ その3 ] ジェリー・ベレスが私に語ってくれたその数奇な人生 ジェリー・ベレスは1923年、ポーランドに生まれた。 第2次大戦中もナチスと戦う苦しい青年時代を送ったあと、 大学を出て機械技術者となった彼は、妻ワンダとともに、 カダフィー大佐が1969年以降政権を握っていた北アフリカのリビアに派遣され、石油資源開発その他の支援事業に携わった。 当時ポーランドは共産主義国家であったし、リビアは頑強な反米の国だったから、両国は友好的なのだった。 しかし、ジェリーは次第に共産主義やリビアの国際テロ支援活動に疑念を抱きはじめた。 ついに彼は決死の覚悟で、 リビアのかつての宗主国であったイタリア経由カナダへの亡命を試みる。 当時、技術者には国籍を与えて積極的に迎え入れていたカナダに渡るためだ。 その亡命の経緯についてはあまり多くを語ってはくれなかったが、彼らは当然ながらイタリア滞在中はどん底の生活を強いられた。 カナダに渡るための貨物船が予定が変わって1カ月も出航せず、その間、 彼らは港町で一日に一食だけ粗末なパンをかじる日々を強いられたという。 こうして、やっとの思いでカナダに渡ったジェリーは、オタワに住んで水道会社の技師の職を見つけた後、 非常な努力を続け、実績を上げて次第に成功していった。 経済的なゆとりも出来てきたし、子供も授かった ( 米国のワシントンで私と会ったのはこの頃。 彼の英語はまだ決して流暢とは言えなかった )。 ついに相当の地位に昇ったあと、60代の半ばで彼は退任し、静かで幸せな老後の生活を始めた。 毎年暮れになると、 ワンダと共にオタワからはるばる2千kmも南のフロリダのセント・ピータースバーグ ( 大リーグのデビルレイズの本拠地 ) までドライブし、コンドミニアムを借りて数ヶ月暖かい冬を過ごすのが常だった。 米国に住むようになった私が何度も誘ったので、1990年代のはじめのある年の春の土曜日の午後、二人はフロリダからの帰途、 私どものサウスカロライナ州の家を訪ねてくれた。 そのときのことを私は今でも鮮明に思い出す。 その日、町のあるスーパーの駐車場に車を停めた彼が、 私の家に電話をかけてきて、そこで待っているから迎えに来てくれと言った。 そのスーパーに私が車で駆けつけたとき、 20年も会わなかった二人は、瞬時にお互いを認識でき、しっかりと抱き合った。  彼らは私の家に2晩泊まってからカナダに戻って行き、次の春もまた訪ねてきて泊まっていった。
私の家で、彼はもう流暢に話せるようになった英語で、次から次へとその数奇な生涯について情熱的に語り続けた。
妻のワンダは、初回の来訪時は 「 うつ病 」 にかかっていたし、移住後も英語の習得に熱心でなかったらしく、寡黙だったが、
2回目の来訪時は投薬のおかげで快活になっていた。 彼らは私の家に2晩泊まってからカナダに戻って行き、次の春もまた訪ねてきて泊まっていった。
私の家で、彼はもう流暢に話せるようになった英語で、次から次へとその数奇な生涯について情熱的に語り続けた。
妻のワンダは、初回の来訪時は 「 うつ病 」 にかかっていたし、移住後も英語の習得に熱心でなかったらしく、寡黙だったが、
2回目の来訪時は投薬のおかげで快活になっていた。その2回の来訪の中間の時期に、彼らは祖国ポーランドに、亡命後初めて帰国して故郷の町を訪ねたという。 あの民主化運動が成功し、国民の直接選挙によって選ばれた初めての大統領に 「 連帯 」 のワレサが当選したのが1990年だったから、 その2年後あたりということになる。 もう亡命者が捕らえられることもないと考えたからだろう。 そのとき、海外で成功した彼ら夫婦に対し、親戚知人たちはひたすら 「 たかり 」 と 「 物乞い 」 を試みたという。 無理もない。 当時のポーランドは極度に貧しかったのだ。 でも、彼らはそのことにすっかり愛想を尽かしたらしい。 「 もう2度とポーランドになんか帰らない 」 ときっぱり言い放った彼らに対し、「 日本に一日も早く帰りたい 」 と考えていたカホルは、 不思議で不思議で仕方なかったようだ。  わき道にそれるが、海外に住んでいる者にとって 「 帰りたい ( あるいは帰ることができる ) 母国
( 日本 ) があるという事がどんなに幸せなことか 」 ということを、私たちはその後も幾たびとなく学んだ。
ベトナムから、ロシアから、またバングラデシュや中国から米国に渡ってきて、
貧しく苦しい生活に喘いでいる人たちが私たちの町にも数多くいた。
差別に耐え、努力に努力を重ね、やっとのことで米国の市民権を取得したとき、彼らがどれほど大喜びしているか、
招かれたお祝いの席で私たちは知った。 かれらは一様に 「 故国には戻りたくない 」 とも言った。
中には 「 戻ったら多分反対派に殺されるかも知れない 」 と考えている人たちもいた。
私たちに向かっては 「 なぜあなた方は米国人になりたがらないのか? 」 といぶかった!
わき道にそれるが、海外に住んでいる者にとって 「 帰りたい ( あるいは帰ることができる ) 母国
( 日本 ) があるという事がどんなに幸せなことか 」 ということを、私たちはその後も幾たびとなく学んだ。
ベトナムから、ロシアから、またバングラデシュや中国から米国に渡ってきて、
貧しく苦しい生活に喘いでいる人たちが私たちの町にも数多くいた。
差別に耐え、努力に努力を重ね、やっとのことで米国の市民権を取得したとき、彼らがどれほど大喜びしているか、
招かれたお祝いの席で私たちは知った。 かれらは一様に 「 故国には戻りたくない 」 とも言った。
中には 「 戻ったら多分反対派に殺されるかも知れない 」 と考えている人たちもいた。
私たちに向かっては 「 なぜあなた方は米国人になりたがらないのか? 」 といぶかった!
2回目の来訪のときも、何度となく 「 今度カナダに来たら寄ってくれ 」 と言いながら、カナダに向かってベレス夫妻は走り去って行った。 しかし、私たちは翌々年日本に帰ってしまい、その機会も失って、毎年12月に長い挨拶状を交わすだけになってしまった。 あんなに精力的だったジェリーも、あれから十数年、もう82歳になっていたのか・・・。 彼は私に向かって何度も 「 お前はいつまで働くのか。 人間は努力し成功したらリタイアして人生をゆっくりと楽しめ 」 と言っていた。 それに触発されたことも一因となって、数年後、私は自発的に職を辞し、日本に帰り無職の生活に入った。 それを報せると彼は大喜びしてくれた。 言ってみれば、30年前のワシントンでの偶然の出会いが、 めぐり巡って10年前からの私の今の生活様式を決めているとも言える。 ジェリーよ、安らかに異国に眠れ。 [ その4 ] 日本はいつまで 「 帰りたい母国 」 であり続けるのだろうか 私が米国にいた頃 ( 特に80年代後半から90年代前半 )、日本は 「 非常に多くの点で米国より優れた良い国 」 だった。 しょっちゅう、私は 「 日本に学びたいのだが・・・ 」 と、あの自信満々で誇り高い米国人たちから、 いろいろなことを尋ねられたものだった。 地域の大学、商工会議所、ロータリークラブなどからしばしば講演を依頼されるだけでなく、 カホルと二人で食事しているレストランで、いきなり隣席の紳士から丁重な質問を受けた事さえあった。 「 なぜ日本では夜でも安心して街を一人で歩けるのか 」、「 なぜ日本の製品は故障が少ないのか 」、 「 なぜ日本の市街にはゴミが散らかっていないのか 」、「 なぜ日本は失業率があんなに低いのか 」、 「 日本の親たちの教育法は米国のそれと、どこが違うのか 」、「 日本の会社でのトップのリーダーシップを学びたい 」・・・。 ( このうち、2番目と6番目以外は、私は自信がなく講演を受諾できなかったけれど ) しかし、恐らく今はもう、米国でそういう体験をすることはないだろう。 それどころか、日本に帰るより、 米国に住み続けていたほうが、まだ幾らか 「 まし 」 だと、日本人たちが考えるようにさえ、 次第になりつつあるような気がしてならない。 |