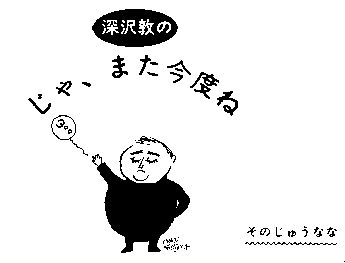
この文章は「シアターガイド 1998年3月号」(発行モーニングデスク)に掲載されたものです。
「シアターガイド」にこのサイトへの掲載を認めていただきました。
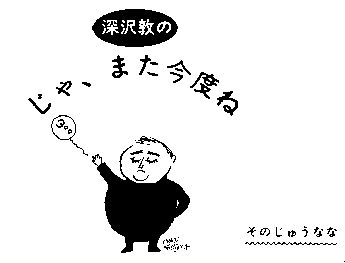
ボクが18才で東京に出て来て初めて観た芝屠が劇団3○○の「夜の影」でした。当時のボクは原田真二をマネて髪はカーリー・ヘアー、部活は、「ミュージカル研究会」、小劇場の小の字も知らない、やけにルンルンした学生でした。そんなボクが何で3○○を観に行こうと思ったのか、そこがどうしても思い出せないのですが、先輩の稲葉さんと同級生の美登里と三人で建て替え前のモリエールに行ったのです。開演前、ギュウギュウの客席でやけに興奮したのを覚えています。それは客席のなんなんだかやけにとがった神経を感じたからで、「僕が東京に出たかったのは何かこんな感じの中にいたいってことかナ」と思い「きっとこの劇団旬なんだろうな」と今さらのように思いました。そして舞台は始まりました。それは客のとがった神経よりももっととぎすまされた神経でせまってくる大人の役者たちのつくる繊細な舞台でした。「話わからなかったのになんで俺泣いているんだろう」などと思いながら三人ともあまり口を利かず帰りました。のちにえりちゃんがエッセイで「芝居を観るという事は“パンを2つ買って来て”とおつかいに出て、きれいなバラがあって結局パン1つとバラを買って帰るときの後ろめたさがある」みたいな事を書いていましたが、まさにそんな気分でした。それから美登里は何か付き合いがヨソヨソしくなり、半年ほどたったある日、部の同級生の集まりの時「私3○○に入団したんで部の公演には出れません」ときたのだ。ボクは何て大胆な女なんだと思いつつ、うらやましくもありました。
それから2年ほどしてまたもや彼女が「敦、新人の歌、スゴすぎるので教えてくれない」と言うのです。ボクの方も卒業を前に、歌を教えることでなんとか暮らして東京にいたいという思いもあって、勉強させてもらうつもりで引き受けたのです。そして訪れた稽古場は、一本の緊張の糸がはちきれんばかりにピーンとはっていました。当時の渡辺さんは(どうしてもあの頃を思い出すとえりちやんとは呼べなくなる)今より全然とがっていて「あっよろしくお願いします」とあいさつされたものの、目は決して笑わない人に見えました。稽古は新人の場面で止まっていました。そこに光永吉江さんが「もういいよ私の所の稽古してよ」と一言。ボクは完全に凍っていました。そのあとしばらくしてボクの歌の時間になったのですが、歌うのはさきほどの新人で、声はちぢこみ、僕も教えながら声はふるえ、注意する言葉はカンでしまい、もう散々なレッスンでした。その時おじさん(東銀之介さん)が「私は歌いませんから御安心を、どうそよろしくお願いします」と声をかけてくれたのです。あれから十数年、ホクのレッスン初日と打ち上げに必ず「また今回もお世話になります」「どうもありがとうございました」と、おじさんはボクの耳もとであのいい声であいさつしてくれました。『ガーデン』の時もそうでした。そしてそれが最後のおわかれになってしまいました。もう書くスペースがなくなってしまいました。初めて観た劇団とこんなに長く付き合ってこれたボクは幸せです。3○○の描く夢を感じられる自分でいられることが、東京で暮らしているボクの実感でした。
indexにもどる