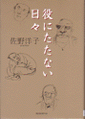|
女も68歳過ぎて、ババアと自覚したらもう怖いものは何もない、とさては開き直ったのか!という観ある、日記風エッセイ集。
佐野さんが時々気にするのは、ついに呆けてきたのか? ということぐらい。
何も怖くないと思えばすべて本音をぶちまけて気楽にしていられる、という佐野さんの気構えが感じられるようで楽しい。
そう思ったら、本書の「役にたたない日々」という題名は凄いものだと思えてきました。最初は、だらだらと過ごす程度の意味と受け留めていたのですが、自嘲も混じえながら自らの日々を切って捨てて平然としている観があるのです。その覚悟の程、小気味良し。
その証のような文章を本書中から引用すると、
「六十八歳は閑である」「六十八のバァさんが何をしようとしまいと注目する人は居ない。淋しい? 冗談ではない。この先長くないと思うと天衣無縫に生きたい」とのこと。
そんな佐野さんが、世間のオバサマたちと同じく韓国ドラマに夢中になったというのですから、何とも愉快。
しかし、これだけ長寿社会となった日本にあってみれば、六十八歳という年齢、まだまだという年齢でもある筈。
それなのにガンの転移が見つかり、余命2年位と宣告されたのだそうです(既に残り1年とのこと)。
それでも佐野さんは少しもめげたりしない。
「二年と云われたら十数年私を苦しめたウツ病がほとんど消えた。人間は神秘だ」
「人生が急に充実して来た。毎日がとても楽しくて仕方ない。死ぬとわかるのは、自由の獲得と同じだと思う」と書いている。
宣告されてかえって“役にたたない日々”が“輝かしい日々”に変わり得た、というなのでしょう。
それを知るためには、まず本書を読んで佐野さんのいう「役にたたない日々」の様子を是非味わってみてください。
|