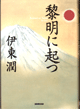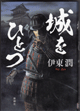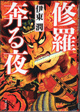| 「黎明に起つ」 ★☆ | |
|
|
関東の地に覇権を唱えた北条早雲の生涯を描いた歴史時代小説。 伊東潤作品を読むのは初めてですが、これまで何度も名前に触れようともその足跡を殆ど知らなかった北条早雲を描いた歴史小説ということで手に取った次第。 もっとも北条早雲、そうした呼び名で呼ばれたことはなく、元々の名前は伊勢新九郎、得度して早雲庵宗瑞。「北条」という名前はその嫡男=氏綱からだそうです。 新九郎が成長した時代は足利将軍・義政の治世下。しかしその後半から将軍位の後継争いから内乱が激しくなり、故郷の備中を捨てて新九郎が向かった関東でも堀越公方足利家と関東管領上杉一族が内部対立し相克するといった混乱状態。 そうした中、武士のための足利体制から脱却し、新九郎は民のための新しい国造りを目指す、というのが本作品のコンセプト。 信玄、謙信、信長と各地で戦国大名が勢力を競い合った時代から比べると、小勢力がその時の事情で集合離反を繰り返しお互いに足を引っ張り合っているだけと思われる状況で何とも張り合いがないという印象で、この時代が余り書かれることのなかった理由が納得できる気がします。 それでも上杉、長尾、武田という名前も登場し、足利体制が崩壊し下剋上を経て戦国時代へと移行する過渡期、あるいは黎明期であることがよく感じられます。 本作品自体は、地味で実直な歴史小説といった印象、エンターテインメント性にはやや欠けています。関東の覇者=北条家の経緯を紐解くことに興味がないと物足りないかもしれません。 1.雲心月性/2.雲蒸竜変/3.雲煙縹渺 |