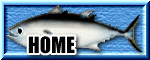|
青い金魚,そしてくり抜かれた体. −6 ぼくの毎日は忙しかった。 ぼくは友達と仲良くすることが大事だと思い、みんなと仲良くするよう心を砕いた。相手の喜ぶことをした。相手が何が好きで、何を望んでいるのかをいつも考えた。ドラマの好きな子とはドラマの話を、アニメの好きな子とはアニメの話を、スポーツの好きな子とはスポーツの話を、勉強の好きな子とは勉強の話を、悪ぶるのが好きな子とは悪ぶって、ギャグが好きな子にはギャグを、女子にもいつも気を使った。 幸一をいじめているやつもぼくがいけばいじめることをやめた。ぼくがいじめることよりも楽しいことに彼らの目を向けたからだ。 ぼくは生まれてから小3まで大阪にいた。偶然にも幸一もそうだった。 越してきて大阪弁がまず目立った。笑われた。ぼくは驚き、すぐにテレビで標準語を勉強し、すぐにそれを話せるようにした。でも中には大阪弁を面白がるグループもいて、彼らとは大阪弁で話した。 4年の遠足のとき、その2つのグループと一緒になり、ぼくはその中で大阪弁を話したり話さなかったり。友達はそれを面白がったが、ぼくは必死だった。解散の声を聞き、友達とも別れた時ぼくはくたくたになっていた。 帰ってきたぼくを見て母さんはすぐにぼくを布団の中に押し込み、体温計をぼくに渡した。 5年の2月頃、クラスルームで来年のクラス替えで一緒になりたい友達、なりたくない友達を書かされた。 ぼくはクラス全員の名をびっしり小さな字でなりたい欄に書き、なりたくない欄には、いません!と大きく書いた。 ぼくはその結果が知りたかった。この結果は公表しませんと先生に言われていたが、何とかして知りたかった。いつもそのことが頭のすみにあった。 春休みに入る前、先生が何かの話のついでに、リュウ君は人気者ね、と言った。ぼくはあのアンケートのことだとすぐにわかり、心の底からほっとした。本当にほっとした。報われた、という言葉が思い浮かんだ。しばらくの間ぼくは本当にうきうきとした気持ちでいられた。
6年の秋だった。 夏休みが終わり、だらだらと休み癖が続く9月も終わったころ、ぼくは何か物足りないものを感じていた。 それが何かわからなかったが、いつもの秋とは違っていた。いや物足りなさというよりか、何かこれまでに無いものが新しく生まれていた。それは妙な圧迫感だった。何かが楽になったが何かがぼくを不安にさせた。 やがてそれが幸一とぼくとの歩くときの変化であることに気がついた。 ぼくたちは学校へもスイミングへも塾へもいつも行き帰りは一緒だった。 そしていつもぼくがその移動の時間を仕切っていた。幸一は道々で見る雲や空や飛ぶ鳥や花の色にいつも立ち止まり、突然消え、突然現れ、ぼくはそんな幸一を目的地まで連れて行くことが仕事だと思っていたのだ。 |