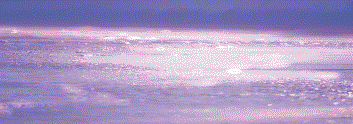|
青い金魚,そしてくり抜かれた体. −10 今日の給食はピザだった。 2,3週間に一度ぐらいのペースでピザが出る。 けっこう人気がある。ぼくも好きだった。 班ごとに別れ机にピザと野菜スープ、サラダが置かれている。 もう食べだしているやつがいる。その日その日に係りがいただきますの合図をして食べ始めるのだが、いつも誰かが先に食べ始めそれにみんなが続き、それに遅れないようにいただきますが言われた。一緒に食べる先生もそれを気にはしない。 ぼくは口を拭いたハンカチを床に落とした。 それを拾うときハンカチの横に転がっていたハエの死体が小指についてきた。 干からびていたハエはそのままぼくの机の端に落ち、ぼくはそれをつまみまた床に捨てようとして、幸一の食べかけのピザに落としてしまった。ハエはピザの黒ずんだトマトの中に埋もれ、隠れた。 幸一が指でそのピザをつかんで食べた。ぼくと目があった幸一はいつものようににっこりと笑うとゆっくりと口を上下に動かし始めた。歯に軽くグシャとした感じが残り、思わず口を止め、顔をしかめる。と思った。しかし幸一はそのまま細いのどを動かし飲み込んでいく。 死んだハエが幸一の食道を通り胃へと向かう。それもほこりにまみれ干からびたハエだ。 ぼくの鼻から思わず笑いの息が漏れた。 「幸ちゃん、おいしい?」 ぼくは言っていた。 「うん。」 幸一は唇を赤くして答えた。ぼくは笑いをこらえようとして、スープにむせた。 「だいじょうぶ?」 幸一が聞いた。 「ピザおいしいよね?」 「うん。」 幸一が言った。
年が明けた。 まだ雪は降っていない。 幸一は雪が降ってくるといつも雪に向けて口を大きく開けくるくると舞った。 今年はそれをまだ見ていない。 1月の下旬、今年最初のピザの日だった。 ぼくは虫の死がいを持っていた。 いつも通りそっと幸一のピザに入れた。 そのとき声が教室に響いた。それはあまりも大きく教室中に響き渡り、ぼくはいったい何が起きたのかわからなった。 「見たろ、幸一、リュウが今いれたろ?ヘンなもの入れたよな。確かめてみな。いつも入れてたんだ。へんなもの、汚いもの入れてたんだ。俺、ウソなんか言ってなかったよな。見たよな。幸一、見たよな、俺ウソなんか言ってなかったろ?」 幸一と実が教壇近くでぼくを見ていた。 クラスのみんながぼくを見ていた。 幸一はうつむいていた。かたく固まっていた。 顔が上がった。 ぼくを見た。 餓死寸前の小犬が死ぬ間際の最後の力をふりしぼり、これまでのわずかな生きてきた時間を確かめでもするように、すがるようにぼくを見た。 幸一の目は大きく見開かれぼくに向かった。 口が大きく開いていた。白い歯とだらんとした赤い舌が見えた。 幸一の体は少しずつ縮まっていき、小さくなっていき、力が抜け、ひざが折れ床に座り込んだ。 でも目だけがぼくに向けられる。 悲しいのだろうか?驚いたのだろうか?くやしいのだろうか?苦しいのだろうか?怒ってるのだろうか?あきらめたのだろうか? こんな幸一の顔なんて。 雪を喜ぶ幸一の顔がぼくは見たかった。虫やふんやゴミを入れながらも僕は幸一の雪を見て喜ぶ顔を見たかった。 こんな幸一の顔なんて。 ぼくは何をした? ぼくは何かとんでもないことをしたのだろうか。 ぼくは何かいけないことをしたのだろうか? 「リュウちゃん………。」幸一がつぶやいた。 ぼくは教室を出た。 「リュウ、おまえ最低のやつだな。」実が言った。 「クズだよな。」他の誰かが言った。 ぼくは廊下に出た。窓から雪が見えた。初雪だ。幸一は気付いていないだろう。 真っ白な雪。 見てる間に雪は窓の枠の中を白く一杯に埋めた。激しい雪だった。雪は斜めに速度を増していく。 そうだ、ぼくはクズだ。最低のやつだ。それはまちがいない。ぼくはクズだ、人間のクズだ。間違いない。くずだくずだくずだ。クズだクズだクズだクズだ。クズだクズだ。クズだクズだ。 クズだクズだ。クズだクズだ。 クズだクズだ。クズだクズだ。クズだクズだ。クズだクズだ。クズだクズだ。クズだクズだ。クズだ。 ぼくは、ぼくが、クズだということが、はっきりと、わかった。 ぼくはクズなんだ。 窓の外は雪。 廊下は暗く長く伸びていた。でも両足に僕の体の重みがはっきりと感じられた。苦しい息が、でも確かだった。窓の外は白い雪。ぼくの歩く廊下は暗く長く伸びていた。 |