CONDUCTOR 福永陽一郎
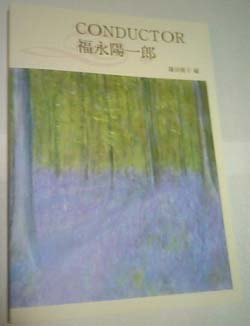
2010年2月10日、「陽ちゃん」こと福永陽一郎氏の没後20年の日。
福永氏の文章の魅力を伝えたい、
遺された珠玉の文章を集めた「CONDUCTOR 福永陽一郎」が発行されました。
と鎌田雅子氏が11年間にわたって発行を続けた<CONDUCTOR>を、
B5判200ページあまりの冊子として改めて編集したものです。
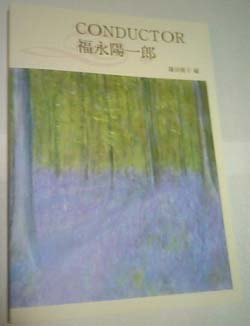
2010年2月10日、「陽ちゃん」こと福永陽一郎氏の没後20年の日。
福永氏の文章の魅力を伝えたい、
遺された珠玉の文章を集めた「CONDUCTOR 福永陽一郎」が発行されました。
と鎌田雅子氏が11年間にわたって発行を続けた<CONDUCTOR>を、
B5判200ページあまりの冊子として改めて編集したものです。
まさに陽ちゃんは不滅。
陽ちゃんの呪縛力は永遠なのだ、と羨ましく思う。
再読、熟読の果て、この一冊で陽ちゃんの魔力を
現代の生きる力にして欲しい。
(畑中良輔)読むたびに、夫の存在が生き生きと蘇ってきて、
嬉しさと恋しさに、胸が熱くなります。
音楽を愛する人達にとって糧となることがあれば、
これ以上の喜びはありません。
(福永暁子)オペラや合唱への思い、アマチュア団体への優しさ、
一方で鋭い筆致で綴られた演奏論。
先生の文章を探しながら読んでいくうちに、
こうしてめぐりあった文章を、
福永先生を敬愛するたくさんの人に改めて読んでいただきたい
と思うようになりました。
(鎌田雅子)
本文より抜粋やっぱり歌をうたう場合、言葉がわかるということが
とても問題だと思うんですよね。
言葉をわからずにうたっているということは、意味がないということが――
あまり最近でもないでしょうけれども、考えられ始めて、
日本人は日本語の歌をうたうのが本当ではないかということに
なってきたんじゃないかと思う。
(「合唱指揮のポイント(その1)」より)私は合唱とともに生き合唱とともに死ぬのだと自覚している。
自分の「生」と同一である以上、私は、合唱に関して真剣にならざるを得ない。
私にとって「合唱とは何であるか」という課題は、
真剣勝負で立ち向かうべき相手であった。
(「日本の合唱は、今」より)このところ、日本人の音感はずいぶん違ってきた、
若い世代にとって「西洋音階」は、いまや何ほどのことでもない。
そして、その条件下にあってこそ、もう一度振り返って、
二人以上の声が相手との関連で”音”を見つけることから
再出発することが必要なのではないか。
外面的な技術の上達を追求する余りに犯した、
合唱を「音楽」でない方向へ進ませた「あやまち」を、
今こそ正すべきであろう。
(「日本の合唱は、今」より)(上記は、HP作成者が任意に抜粋したものです)
目次より
- 詩と音楽
- イタリアオペラ雑感
- 大学合唱の現状と課題 問題点はなにか
- 聴衆不在の音楽会
- メンタル・ハーモニー考
- 合唱は手軽な楽しみか
- 《椿姫》と私のこだわり
- 《カバレリア・ルスティカーナ》など<オペラ合唱曲>
- 原語主義と訳詞主義への行きすぎについて
- 男声合唱曲アルバム−主な曲と楽譜の手の入れ方
- コーラスにおけるピアノ伴奏の役割
- ヴェルディの鎮魂ミサ曲
- マーラー:歌曲集《さすらう若人の歌》《少年の魔法の角笛》
- レコード解説*ドビュッシー/ラヴェル
- <ライナー・ノート>日本民謡および日本民俗音楽を素材とする合唱音楽について
- わたしと「同志社グリークラブ」
- <対談>合唱指揮のポイント
- <外からみた合唱連盟 2>日本の合唱は、今
- <対談>フルトヴェングラーを再評価する
- 《アイーダ》上演史 日本版
- <海外LP視聴記>ムラヴィンスキー
- 「十の詩曲」による六つの男声合唱曲
- 《交響曲第四番》ブラームス
- クヮルテット結成のすすめ
- <対談>学生合唱ひとすじに
- オペラ演奏にあらわれたカラヤンの新側面
(上記は、HP作成者が任意に抜粋したものです)
お問い合せやお申し込み先
《CONDUCTOR》編集部 鎌田 雅子
〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町3-17-16
TEL & FAX 03-3923-5304
Email:masako-k-g@nifty.com頒価 \2,000(送料込み)
ご住所・お名前・お電話番号をご記入の上、FAXまたはEmailにてお申し込み下さい。
「陽ちゃん」の音楽に直接・間接を問わず触れたことのある みなさま、
「陽ちゃん」の評論に心を動かされたことを思い出した みなさま、
現在、合唱、オペラ、作曲など…音楽に携わっている みなさま、
全てのみなさまに是非ともご一読をお奨めしたいと思い、このページを作成しました。(正木一弘) 【陽ちゃんMemorial】へ
Copyright (c)2010 Kazuhiro Masaki. All rights reserved.