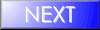
|
道成寺説話の変遷の系譜は、大別して三期にわけることが出来るだろう。 但し、道成寺説話の芸能化によって生まれた、第一伝説・第二伝説を考えに入れてのことである。 第一伝説とは、法華経の霊験を称えた鐘巻誕であり、後世、安珍清姫の物語として有名になったもの。 第二伝説とは、第一伝説の後日譚のごとく言われている、鐘供養における怪異の物語。 この二つの伝説を一つの道成寺説話の中にまとめ、次に三期に割けた時期ごとの時期的様相の概略を述べたい。 第1期は、 『古事記』に記載された原道成寺説話から、『大日本国法華経験記』巻下、第129、『今昔物語集』第十四、 『元亨釈書』巻第十九、などの文献に表わされた、 第一伝説中心の時期であり、記述の多少の変化を見ながらも、説教教化的指向の強い時期である。 第2期は、 能などの芸能による第二伝説の登場によって、第一伝説の広範囲な流布を証明する時期である。 またこの期の芸能には、第一伝説が、第二伝説の説明的な役割を果すがごとくに用いられる折、 安珍清姫の物語の形へと、まとまりはじめる時期でもある。 第二伝説の芸能としては、能の謡曲「道成寺」・「鐘巻」、黒川能の「錘巻」・「道成寺」、壬生大念仏の『道成寺』など 種々なものが上げられるであろう。 また同じ「金巻」の名でありながらも山伏神楽・番楽に伝承されている「金巻」は、 表現の演出的な面からも、内容、詞章からも、能の「鐘巻」と別の系譜を持つモノなのかも知れない。 また、沖縄の「執心鍾入」(沖縄組踊)は演目として作られた時期がこの第二期より二百年程度後になるが、 内容的には、鐘巻譚と錘供養譚の中間に位置する変動期の芸能作品と言えるだろう。 「執心錘入」については、次のような論考がある。 「いまは歿くなった沖縄の学者、伊波普猷氏の考証によれば、道成寺の伝説は、『執心錘入』の生まれる以前から沖縄にあり、 主人公若松のことは、島のおもろ(古歌謡)の中にも読まれているという。 そして、調べてみるとその種は内地から渡ったものらしいが、島にもたらしたのは、名ある俳優ではなく、 熊野権現の信仰の教導にあたった山伏修験の徒であったと思われる……中略……世に知られる“道成寺芸術”の展開は、 能に始まり、歌舞伎の諸種の所作事に及ぶというが、しかしその陰には、日本国中を南に北に渡り歩いた山伏修験道の強力な 道成寺文芸伝播の足跡のあった事実を、我々はまず知っておかなければならない。……後略……。」 (三隅治雄著『日本舞踊史の研究』道成寺の由来より)。 第3期には、長歌古今集や松の葉などに見られるように、第一伝説・第二伝説ともに定着して、 民間の歌謡・都市の流り歌にまで歌われるようになる。 道成寺説話は、歌舞伎に登場する事によって、芸能としての確固たる位置を占め、より様々な形に利用されてゆくのだ。 |
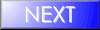 |
[次へ] |
| 【道成寺攷 参考資料一覧】 |
| TOPへもどる |
| 隠居部屋あれこれ |
| 伝統芸能 |