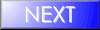
|
道成寺説話の伝承が、第二期から芸能によって受けつがれて来たとするならば、その主体となったものは能であると言える。 そしてその伝承を支えていたのは、第一期から連綿と続く様々な伝承者達の素朴な芸能である。 仮りに、その「芸能による伝承」の総体を「道成寺芸能」とし、第三期までの伝承の過程を顧みると、 第二期までは第一伝説の形が決して崩されることなく伝承されていることがわかる。 それは、能についても同じであると言えるであろう。 しかし、謡曲「道成寺」の詞章を見ると、『法華験記』などに見られる道成寺説話と比較して、 単純で明確な語りによる力強さ、怖ろしさなどの点において劣っていると考えられる。 その原因として考えられることは、能によって道成寺説話が芸能化される時に、演劇的な構成が行なわれて、 道成寺説話の持っていた主題が、はぐらかされているのではないかということである。 その主題とは、能以前の伝承者達が守って来た「道成寺説話の心髄」であり、蛇に変身しなければならなかった女の怒り、怨念の魂である。 その主題をはぐらかしている能は、道成寺説話の伝承を担うものとは言えないのかもしれない。 しかし、能は道成寺芸能の伝承の上に、自らの「道成寺芸能」を築き上げたのだ。 では何故主題をはぐらかさねばならなかったのだろう。 それは一体何に起因するのであろうか。 また、能に携わった能楽者と呼ばれる人々と、道成寺説話の伝承の主流を担ってきた熊野遊行者などとは、全く異なった出自なのであろうか。 能楽者の出自について林屋辰三郎によれば次のごとく論じられている。 「やがて南北朝の内乱期をむかえると、畿内農村には大きな変動がおとずれた。 ……中略……村の鎮守の猿楽もまた、鎌倉のままではあり得なかったのであって、……中略……農村から京都へもち出され、 或は能に、或は狂言にその内容を発展させていったのである。 ……中略……こうして能は、猿楽のなかの象徴的な歌舞的要素を中心とした劇として誕生した。」 (『歌舞伎以前』五章、能と狂言より)。 能の前身である鎮守の猿楽についてもさらに、「すなわち鎌倉の猿楽は、鎮守社の神事猿楽が主体であったが、 当時の信仰じしんが神仏習合の風潮にあったから、 そのなかには仏教寺院に従属した呪師の寓意的歌舞が、多分にとりいれられて、いちじるしく歌舞的要素を加えることになった。」 (前出、同章)と論じられている。 また折口信夫も、次のごとく考察している。 「平安期末から鎌倉になると、諸種のほかひびと、くぐつは、皆互に特徴をとり込みあうて、いよいよ複雑になった。 ちょっと見には、どれが或種の芸人の本色か分らなくなった。 『新猿楽記』を見ると、此猿楽は恐らく皆、千秋万歳の徒の演芸種目らしく思はれる。 ……中略……、此が、田遊び・踊躍念仏を除いた田楽の全容にもなった。 今、能楽と言う猿楽も、初めはやはり、此であったであらう。……中略……けれども、元は唱門師同様の祝言もする賎民の一種であって、 将軍の恩顧を得たのも、容色を表とする芸妓であったからである。」(前掲書、「国文学の発生」、第四編186頁)。 以上の論考を基とすると、能楽者と熊野遊行者とは、同一の芸能者の発展の上に生まれて来たものであると言えるだろう。 そして、能楽者と熊野遊行者の精神的基盤は、何ら変化を見せずほぼ同一であると言えないであろうか。 では、なにゆえに熊野遊行者などが伝承し守ってきた道成寺説話の心髄が、能楽者によって伝承される時に、 はぐらかされなければならなかったのであろうか。 それは、或る意味では熊野遊行者などと比較して同じ発生基盤を持つと思われる能楽者達が、一方は完全な非定住であるのに対し、 都市という一つのカオスの中で不完全な定住の形を取るために、 ほかひびとの持っていた「おとない人」あるいは「まれびと」としての神性を失い、自らの宗教的基盤を失って、 生計の全てを自らの演じる"わざ"によって得なければならなかった結果生じた現象かも知れない。 また、道成寺説話の主題は、遊行者の祝言としては威力があっても、芸能とするにはあまりに不気味なものであったために、 その主題を、芸能の中心にはおけなかったのであろう。 能楽者の宗教的な基盤の変化について戸井田道三によれば、次のような論考がある。 「『翁をば、むかしを宿老次第に舞けるを今熊野の田楽のとき、将軍家、はじめておなりなれば、一番にいづべきものを御たづね有べきに、 大夫にてなくてはとて、南阿弥陀仏一言によりて、清次出仕し、せられしより、是よりはじめとす。 よってやまと猿楽是を本とす。』と『談儀』に見えている。……中略……、つまり、『今熊野の能』以後、 神事としての『翁』の申楽が、役の担当者を神事以外の理由によって変えられたのであるから、 この一事は能のありかたが社会的に変化する一指標としての意味をもっていたと考えていいのである。」(『観阿弥と世阿弥』57頁)。 この論より、能楽者達が、足利将軍家をはじめとする都市の観客の支持を得ていく過程に能楽者達自身の中で、 彼らの宗教的な束縛が解けていったことが推測出来る。 能楽者によって、道成寺説話の伝承が行なわれていく時にその本質が変化して行ったことは、 上述した論考によって説明出来るのではなかろうか。 つまり、道成寺説話を宗教的な祝言のように用いて伝承する必要のなかったことと、彼ら自身が神としての"わざおぎ〃ではなくなって、 「人間」の芸能者に変化していったことの二点によって、道成寺説話の伝承の主体が、 その秘めている怨念の伝承ではなく、劇的構成としての利用価値に変ずるのであると考えられよう。 だが、能における道成寺芸能の発展が、謡曲「鐘巻」から「道成寺」へとなっただけで止まってしまった背景には、 能という芸能それ自身が、未だ宗教的意義を携えていたことを推測出来る。 前出の戸井田道三によれば、次のような論考がある。 「観世座の規定のなかに、『多武峯ノ役ノ事』というのがあって、たいへん厳重に参勤の義務をきめている。 そこに『大和の国は申すに及ばず、伊賀・山城・近江・和泉・河内・紀の国・津の国のうちにいながら参勤しなければ、座を永久追放する。 このほかの国々にいて参勤しないのならゆるす」と書いてある。 つまり、座員はいつも一ケ所に集団をくんで定住していたのではなかった。 多武峯の八講、春日若宮の御祭り、興福寺薪の神事などのほかは、小集団にわかれて地方巡業をしていたと解される。」(前出、82頁)。 この一文より、熊野遊行者などの生活基盤と、能楽者の生活基盤が、さほど隔っていないことが推測出来るであろう。 そして、能楽者自身の宗教的意義が薄れて行くにもかかわらず、能が、従来の遊行者の職分をしっかりと受けついでいることがわかるのである。 道成寺説話の伝承の変化は、説話の秘めている怨念の伝承ではなく説話の劇的構成の伝承に変ったと言える。 その結果生まれてくるものが、一つのパターンとしての「道成寺芸能」の姿である。 それは、前節で述べた「日高踊」などのように、手猿楽や風流踊りの中にも織り込まれていったのであろうと思われる。 第三期に入ると、「道成寺芸能」伝承の主流は、「人形浄瑠璃」・「歌舞伎」の手へ受けつがれて行くと言えよう。 人形浄瑠璃は、その出自を説経節と浄瑠璃に求められると言う。 前出の折口信夫によれば、次のごとく論じられている。 「説教は本地を説き、人間苦の試練を説いて現世利益の方面は、閑却していた。 其で、薬師如来の功徳を述べる、女の語り物の説経が出来た。 女には、正式な説経は許されていなかった為もあろう、浄瑠璃と言う様になった。 薬師如来は浄瑠璃国王だから、幾種もの女説経を、浄瑠璃物語と称する様になった。」(前出書、205頁)。 この論考から推測し得るものは、猿楽を基として発達した能のように、人形浄瑠璃もまた、歴史を遥かに遡って、 「ほかひびと」などからはじまる、日本の古くからの芸能の流れにつながるものであるということである。 歌舞伎もまた、同書によれば、次のごとく論じられている。 「江戸歌舞伎の本筋は、まづ幸若舞で、上方のものは念仏踊りを基礎として浮世物まねや組み踊りを混へている。」(前出、207頁)。 この論考は、大まかではあるが歌舞伎もまた人形浄瑠璃と同じように、連綿と続く芸能の伝承の中で、 やっと花を咲かせて来たものであることがわかる。 だが、歌舞伎によっても人形浄瑠璃によっても、道成寺説話の伝承における能によって生じて来た現象を止めることは出来なかった。 むしろ、一つの劇的構成方法としての「道成寺芸能」の伝承をより発展させて、 「京鹿子娘道成寺」のような、「道成寺芸能」の傑作を生み出すのである。 初期の歌舞伎に見られる「道成寺芸能」は、山伏神楽や能などにおける「道成寺芸能」の演じられる形態と比較すると、 さほど掛け離れていたものではなかったようである。 歌舞伎年表によれば、次の一文が記載されている。 「寛永十六年禰宜町に芝居ありし時の古図を見るに、 芸をなす場のみ板を葺て、四方は竹矢来を引廻し、中に莚を覆い、見物所は土間にて莚を敷き見物せし体也。 桟敷はなし屋上のよし簀の上をむしろをのせ、小雨くらいの時は興行せり。 舞台は板を横にならべ、正面に高き所あって爰に唄い鳴物師ら居並び此前にて役者所作を演ず……後略……。 正保三年の図には、屋根は元の如くなれども、竹矢来を取って板がこいとし、舞台の後に幕を張、狂言所作竝道成寺を仕組し体也」。 これによって、本田安次の『山伏神楽・番楽」に論じられている舞台の有様と比べて、初期の歌舞伎の舞台がほぼ同じようであることがわかる。 また元禄七年三月の大坂にて、岩井半四郎座の坂東又太郎の劇中能の道成寺大当り、 元禄十四年七月、江戸森田座にて「三世道成寺」が上演された記録がある。 前者は能そのものを舞台に上げ、後者は水カラクリなどの軽業芸であったという(『歌舞伎年表』による)。 そして、同じ元禄時代に、榊山小四郎が踊ったという曲に、道成寺説話の伝承の名残りを留めているかのようなものがある。 今日、上方唄の三下り物として残されている『古道成寺』あるいは『語り道成寺』といわれ、作曲は名人岸野次郎三であると伝わっている。 (『歌舞伎年表』・『邦楽舞踊辞典』等に拠る)。 この『語り道成寺』の詞章は、高野辰之の『日本歌謡集成』巻七に、『第八・琴線和歌の糸』五十二・道成寺として記載されている。 それによれば、この曲が詞章としてくだけてはいるが、説話の内容を確実に伝えているものであると言える。 これは、操りの説経節などの影響を受けているものかも知れない。 そしてそれ以後の歌舞伎には、四十種もの「道成寺所作」と呼ばれる道成寺芸能が生まれ、人形浄瑠璃においても、 『用明天皇職人鑑』(近松門左衛門作・宝永二年三月) 『道成寺現在蛇鱗』(浅田一鳥・並木宗輔合作、寛保二年八月) 『日高川入相花王』(近松半二・竹田出雲・竹本三郎兵衛等合作、宝暦九年二月)。 などを生み出した。 しかし、能によってはじまった道成寺説話の伝承における主体の変化は、第一伝説という怨念の叙事詩の伝承の崩壊をうながし、 歌舞伎・人形浄瑠璃の伝承によって、完全に消滅したのである。 第三期における最大の特徴は、道成寺説話の伝承によって守られ受けつながれてきた「怨念の叙事詩」が、伝承者自身の手によって消滅し、 その形骸だけが、「美しく」伝え残されて行くことである。 その形骸が、いかによく当時の観客に愛され好まれていたかは、「道成寺芸能」のパターンが、実によく利用され使われていたことによって推測出来る。 そしてそれが、周期的な<流り>のようにくりかえしくりかえし、盛んになることが歌舞伎の記録の中に見られる(『歌舞伎年表』などに拠る)。 そのような現象の根底にながれる精神性と道成寺説話の怨念の伝承の魂は、どこかでつながっているのではなかろうか。 このつながりの研究は、後に期待する。 歌舞伎を包んでいた社会的風潮の変化と、その変化に則して工夫されていったと思われる歌舞伎の演目のつながりを、 歌舞伎の精神史として解明する必要があるだろう。 |
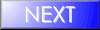 |
[次へ] |
| 【道成寺攷 参考資料一覧】 |
| TOPへもどる |
| 隠居部屋あれこれ |
| 伝統芸能 |