
|
賊(あた)まもる鎮(おさ)への城(き)ぞと...
(巻二十 4331)「大君の遠の朝廷」と讃えられた大宰府は、その起源を遠く宣化元年(西暦536年)に設置された那津官家にまで遡ることが出来、『日本書紀』推古天皇代(在位592〜628年)には「筑紫大宰」の名が見えるようになります。当初は内外使節の送迎を主な任務とする外交府としての性格が濃厚でしたが、白村江での敗戦後、664(天智3)年、対馬・壱岐に防人と烽(とぶひ)が配備され、さらに博多湾から上陸した外敵の南進を防ぐための施設として水城(みずき)が着工されており、同じ頃対外防衛拠点としての大宰府が確立されたものと考えられています。

|
同時に大宰府は西海道(九州)諸国を統括する内政の府でもあり、8世紀頃には西国の政治・経済・文化・宗教の中心として都市的な繁栄を見るようになりました。左右各12坊、南北22条の広大な条坊制に基づく都城をなし、その中枢である政庁には、平城宮朝堂院を模した壮麗な殿舎が建ち並んでいたと想定されています。府の長官たる帥(そち。そつとも)は、中央官庁の各省の卿より高い地位にあり、代々皇親もしくは中納言以上がその任にあてられました。

|
中納言大伴旅人が帥として大宰府に赴任したのは、727(神亀4)年冬頃のことでした。同年10月には、聖武天皇と夫人安宿媛の間に待望の男子(基親王)が生まれ、翌月にはその立太子が朝堂で盛大に祝われています。皇太子の誕生に湧き立つ都を後に、旅人は筑紫の地へ旅立ったことになります。当時10歳の少年だった家持も父に同行したものと思われ、遅くとも730(天平2)年夏に家持が大宰府にいたことは、万葉集の記事から確かめることが出来ます(巻四 567左注)。
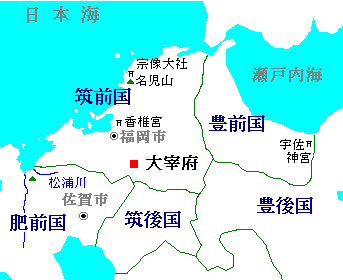
|
時はまさに天平の盛期、728(神亀5)年春に大宰少弐として赴任してきた小野老(おゆ)は、大宰府での歓迎の宴で奈良を偲び、名高い一首を詠みました。
青丹吉し寧楽の京師は咲く花の薫ふが如く今盛りなり(巻三 328)
ところが、この歌が詠まれた同じ年の秋、都では、生後一年に満たない皇太子が薨去し、政局は思いもかけなかった混迷に陥ります。この年、聖武天皇のもう一人の夫人である県犬養広刀自が安積親王(あさかのみこ)を出産し、外戚としての立場に危機を迎えた藤原氏は、光明子を皇后に立てる工作に奔走し始め、左大臣長屋王らとの対立を深めてゆきました。
旅人もまた大宰府にあって悲運に見舞われます。着任して初めて迎えた夏、筑紫に伴って来た正妻大伴郎女を亡くし、これに前後して弟宿奈麻呂逝去の報が大宰府に齋されたのです。
「独り断腸の泣(なみた)を流す」(巻五 793序文) 旅人に対し、筑前守として側にいた山上憶良は「日本挽歌」を捧げ、帥の悲嘆を自らの痛みとして詠いました。
大野山霧立ち渡るわが嘆く息嘯(おきそ)の風に霧立ち渡る(巻五 799)

|
以後、旅人と憶良は競い合うかのように詩作に励み、「嘉摩三部作」「松浦川に遊ぶ」といった、従来の倭歌(やまとうた)の範疇を大きく逸脱した文芸作品が次々に生み出されます。それらは中国の哲学や文芸をよく消化した上で、借り物でない士大夫文芸(近代風の言い方をすれば「知識人文学」)を日本の詩歌において初めて実現したものでした。
やがて夫宿奈麻呂に去られた坂上郎女が刀自の代役として筑紫へ下って来ました。暗澹たる大宰府生活の始まりにも、こうして次第に光明が射し込み始めたかのようでした。

|
神亀6年の年が明けた都では、武智麻呂を主導とする藤原氏の謀略が、ついに長屋王を追い詰めるにまで至っていました。2月、王の謀反が発覚したとして、不比等の第三子宇合(うまかい)が兵を率いて長屋王の邸を囲み、武智麻呂は「左道を学び国家を傾けんと..」の罪状を以て王を窮問しました。長屋王は権力の絶頂で自害、正室の吉備内親王とその子四王も死に至らしめられました。同年8月には天平と改元され、安宿媛が臣下として異例の立后を果たします。
都でのこうした政界の激動を、遠く筑紫の地にあった旅人は如何なる思いで受け止めたのでしょうか。その文人気質や皇親派としての政治的志向において、旅人と長屋王の間には共通するものがあり、当然旅人は武智麻呂より長屋王に親近感を抱いていたものと想像されますが、とはいえこの二人の親交を示す史料は一つもありません。
当時の旅人の心境を辛うじて暗示する作品として、変の8か月後、彼が京の藤原房前に宛てた書簡が万葉に残されています(巻五 810〜811)。旅人は房前に対し、倭琴一面と共に殆ど小説と呼んでもいいような一編の虚構作品を贈っています。さまざまな解釈を可能にする小品ですが、文選の「琴賦」などを思想的な下地として、「政権掌握をめぐる抗争や、音楽をも統治の方途とするような在り方に距離を置き、心情的には『方外の士』たろうとする私的な感懐を込めたもの」とする解釈(増尾伸一郎『万葉歌人と中国思想』)が最も行き届いたものと思われます(旅人略伝の注1を参照下さい)。

|
翌天平2年正月には、大宰府の旅人邸で梅花の宴が開かれ、筑紫諸国から参集した32名に及ぶ参席者によって32首の梅の歌が披露されました。万葉全巻を通じても、これほど盛大にして花やかな宴歌群は他に見つかりません。家持も末席に連なったと思われるこの宴は、その後も永く家持らによって追想されることになります。
我が園に梅の花散るひさかたの天より雪の流れ来るかも(巻五 822 旅人)
春の裏(うち)の楽しき終へは梅の花手折り招(を)きつつ遊ぶにあるべし(巻十九 4174 家持)
また、有名な讃酒歌(巻三 338〜350)も、大宰府時代の旅人の作品にほかなりません。
この代にし楽しくあらば来む生(よ)には虫に鳥にも吾は成りなむ
生ける者遂にも死ぬる物にあればこの生(よ)なる間は楽しくを有らな
苦悩に満ちた世俗生活からの超脱を志向しつつも、現世を穢土として厭離するのでなく、大君の支配する楽土として謳歌する浪曼的イロニーとしての「天平の精神」は、大宰府時代の旅人によって最も典型的な文芸表現を得たと言えます。家持は父旅人からこの「天平の精神」を継承しつつ、人麻呂に極まる白鳳の伝統に自らの文芸をつなげることで、やがて「万葉集の精神」を体現する唯独りの人としての道を歩み始めることになるのです。
梅花の宴の翌年、天平2年夏6月、旅人は突然脚に瘡を拵える病に臥し、一時は危篤に陥ります。遺言を伝えるため庶弟稲公と甥古麻呂が京から呼び寄せられました。幸い大事には至らず、稲公らが帰京する折、駅家で設けられた送別の宴には、家持が父の代役を務めて出席しました。
冬10月、旅人は先に逝去した多治比池守の後任として大納言を拝命し、武智麻呂と太政官の最上位を分かち合うこととなりました。
天平2年の暮れ、一家は約3年ぶりに佐保の自宅に落ち着きましたが、翌年7月には、前年の病の余燼に旅の疲れも重なってか、旅人は67歳の生涯を閉じました。旅人が最後に残した歌は、故郷の飛鳥で萩の花が散る頃、ささやかな神祭りをしたいと願う、次のような一首です。
指進(さしずみ)の栗栖の小野の萩の花散らむ時にし行きて手向けむ(巻六 970)

|
この年、家持は14歳になっていました。