生まれた年が1年や2年違うからってどうだと言うのか? という思いがある一方、やはり敬愛する人物の誕生年くらいはハッキリしておきたい、ということで、自分なりに家持の生年を考証してみました。数年前のノートがもとになっていますので、これを叩き台にして考察を深めてゆきたいと思っています。『続日本紀』には大伴家持の年齢についての記載がなく、『公卿補任』と「大伴系図」の記事から、その生年は従来養老二年(西暦718年)を通説としてきた。すなわち、『公卿補任』は天応元年(781年)の条に家持の年齢を六十四歳と記載し、大伴系図(『続群書類従』巻一八二)は享年六十八としている。いずれも逆算すれば、養老二年(718年)生まれとなるのである。しかし、これでは説明しがたい矛盾が生じるとして、霊亀二年、養老元年、同四年など異説が唱えられ、現在では養老元年説も有力視されているらしい(注1)。家持の年齢考証の最も有力な手がかりとされているのは、彼が内舎人に任官した年がいつかということである。軍防令によれば、内舎人は毎年十二月一日までに、二十一歳(数え年)以上の蔭子孫(五位以上の官位を持つ者の子孫)を式部省に登録し、太政官において選考の上これを任ずるとされる。親が三位以上の場合は検査を経ず無条件で選任されるが、家持はこの例で、おそらく二十一歳に至ると(病や喪など、特別の事情がない限りは)即座に選任されただろう。正式の就任はおそらく選考の翌年の初頭であり、このときの年齢は二十二歳以上ということになる(注2)。内舎人就任の年が判明すれば、そこから逆算して生年がほぼ確定できるというわけである。
さて、万葉集で家持の肩書に「内舎人」の語が見える最初の例は、普通、巻八・1591番歌の左注であるとされる。
これを最初の例とするのは、十一首全体を括る左注の「冬」を、天平十年(738年)冬と推定しての上である。というのも、巻八は季節毎に部立を立てる編集をとっているが、各部立内の排列はほぼ年代順の原則が守られており、一連の歌の直前には「天平十年戊寅八月二十日」の左注を持つ「右大臣橘家の宴の歌七首」が置かれ、直後には「天平十一年己卯秋九月」の左注を持つ「大伴坂上郎女の竹田庄にして作る歌二首」が置かれているからである。橘朝臣奈良麻呂の集宴を結ぶ歌十一首(中略)黄葉の過ぎまく惜しみ思ふどち遊ぶ今夜は明けずもあらぬか(08/1591)
右一首、内舎人大伴宿禰家持。
以前(さき)は、冬十月十七日に、右大臣橘卿の旧宅に集ひて宴飲しき。家持が天平十年十月の時点で内舎人であるためには、天平九年(737年)中に選任されていなければならず、ここから逆算すると生年は養老元年(717年)以前ということになる。『公卿補任』「大伴系図」記載の年齢とは相容れないのである。
ところで、内舎人の任期は当初最長6年とされていたが(注3)、慶雲三年(706年)二月十六日の格(律令の追加法令)に注目して、家持の頃の任期が4年以内であったことを論じたのは藤田寛海氏であった(「大伴家持」『講座日本文学』上代編2)。当日の『続日本紀』には、
諸の長上官(引用者注:毎日出勤を原則とする官)の遷り代らむ(卑官より高官に遷ること)は、皆六考(勤務評定期間六年)を以て限とす。……百官、選(昇叙の審査)を得る限太だ遠し。色別に(官職の種類毎に)二考を減して、各選限(選の資格を得るに要する考の数)を定むべし(慶雲三年二月庚寅条)とあり、「長上官」にあたる内舎人についても、このとき選限(任期)が最長6考から最長4考に減じられたことが知られるのである。そこで家持に「内舎人」の肩書が見える最後を探すと、巻三・475番以下六首の題詞「(天平)十六年甲申春二月…内舎人大伴宿祢家持…」がそれにあたる。天平十年十月から既に6年目の春となり、当時の内舎人の任期と矛盾を生じてしまう。これによって、藤田氏は上記「奈良麻呂結集宴歌」の「冬」を天平十年冬とする定説に疑義を挟み、天平十二年内舎人任官説を主張したのであった。
これに対し、伊藤博氏は、慶雲三年の格は忠実に守られなかったのであり、家持は旧来通り6年の任期を果たしたのであろう、と論じた(『萬葉集の歌人と作品』第九章第一節「内舎人の文学」)。その根拠として伊藤氏は、延暦十四年(795年)十月八日の官符「三位以上の子孫、及び四位五位の子、出身の後、六考に足るを待ちて、乃ち選例に預かる。既に令条に乖くも、因循を易へず云々」(令集解選叙令「授位条」)を挙げている。しかし、この条文は、二十一歳に達すれば必ず蔭位を授けられるはずの蔭子孫が、出身後六年を待って初めて選例(昇進の審査)に預かる点で「令条に乖く」と指摘している、と取るべき文であろう(岩波日本思想大系『律令』選叙令補注)。すなわちここに言う「令条」とは慶雲三年の格を指しているのではなく、選叙令の「凡そ位授けむは、皆年廿五以上を限れ。但し蔭を以て出身せむは、皆年廿一以上を限れ」(訓読は岩波日本思想大系本による。以下同)を指していると考えるべきである。
伊藤氏はまた、家持の越中守在任が満5年(足掛け6年)に及んだことを挙げて、慶雲三年の格が守られなかった実例としている。確かにそのような実例が「少なくない」ことは事実であるが、あくまでも例外的なケースであったこともまた事実である。続紀と万葉集から知り得る限りで、家持の官職推移を以下の表に掲げよう(内舎人を除く)。
官職名 就任年月 離任年月 宮内少輔 746(天平18)3 同年7 越中守 746(天平18)7 751(勝宝3)7 少納言 751(勝宝3)7 754(勝宝6)4 兵部少輔 754(勝宝6)4 757(宝字1)6 兵部大輔 757(宝字1)6 757(宝字1)12以前 右中弁 757(宝字1)12以前 758(宝字2)6 因幡守 758(宝字2)6 762(宝字6)1 信部大輔 762(宝字6)1 764(宝字8)1 薩摩守 764(宝字8)1 765(天平神護1)2 大宰少弐 767(神護景雲1)8 770(宝亀1)6 民部大輔 770(宝亀1)6 同年9 左中弁 770(宝亀1)9 774(宝亀5)3 中務大輔(兼職) 770(宝亀1)9 772(宝亀3)2 式部員外大輔(兼職) 772(宝亀3)2 774(宝亀5)3? 相模守 774(宝亀5)3 同年9 左京大夫 774(宝亀5)9 775(宝亀6)11 上総守(兼職) 774(宝亀5)9 775(宝亀6)11 衛門督 775(宝亀6)11 776(宝亀7)3 伊勢守 776(宝亀7)3 780(宝亀11)2 参議 780(宝亀11)2 783(延暦2)7 右大弁(兼職) 780(宝亀11)2 781(天応1)4 右京大夫(兼職) ? 781(天応1)5 春宮大夫(兼職) 781(天応1)5 785(延暦4)8 左大弁(兼職) 781(天応1)5 782(延暦1)6 陸奥按察使鎮守将軍(兼職) 782(延暦1)6 784(延暦3)2? 中納言 783(延暦2)7 785(延暦4)8 持節征東将軍(兼職) 784(延暦3)2 785(延暦4)8 このように、知られる27の官職のうち、満4年を超えて在任した例は越中守と春宮大夫の2例あるのみなのである。このうち春宮大夫は従四位下相当官であり、しかも皇太子個人に親しく接するという特殊な職務柄、容易に代任者を見出せない官であるから、参考にはなるまい。また越中守にしても、家持は離任の際つぎのような歌を詠んでいる。
しなざかる越に五年(いつとせ)住み住みて立ち別れまく惜しき宵かも(19/4250)これが憶良の天平二年作「天離る鄙に五年住まひつつ都の手ぶり忘らえにけり」(05/880)を意識した作であることは度々指摘されている通りであるが、この二首から推測されるのは、当時国守の任期を5年(足掛け5年=満4年)と考えるのが常識であったらしいことである。このことからも、当時長上官の任期が満4年であったこと、そして家持の越中守在任期間が違例のものであったことが知られるのである。ましてや、内舎人は毎年定員が補充される官職であり、エリートコースとはいえ所詮見習い修業的な官職である。そのような地位に、若い有為な人材を任期を超えて足掛け7年にわたり留めておくとは、どうにも納得がゆかないではないか(たとえ最初の2年間が「自進仕人」だとしても)。しかも、当時は親大伴的な橘諸兄がもっとも強力な人事権を有していた時代なのである。
それでは、万葉集に見られる家持の内舎人6年間在任をどう見ればよいか。
藤田氏は上記論文で、先に引用した「橘朝臣奈良麻呂結集宴歌十一首」を天平十年作と断定できない消極的な理由として、巻八は歌作の年次を重視したものでないこと、一連の歌群は家持の手控えからの所引であろうと推測されること等を挙げているが、より積極的に「冬十月」が天平十年十月ではないことを示す根拠はないであろうか。
まず注意したいのは、巻八においては左注に制作年月を表記する際、常に年号を略さず記載する原則を取っていることである。この原則は同年が続く場合でも守られており、一例を挙げれば、1599左注に「天平十五年癸未八月」とあり、1603左注でも再び「天平十五年癸未八月十六日」と、年号を重複して記載している。
制作事情も月日も詳細に判明しているのに、「奈良麻呂結集宴歌」のみ年号表記を略しているのはどういうわけであろう。かかる異例な表記としたのには、それ相当の事情があったのではないだろうか。
ところで、左注にある「右大臣橘卿之旧宅」は奈良の諸兄宅を指すと見られる(1585・1588に「平山(ならやま)」の語が見える)。なぜ奈良の諸兄宅を「旧宅」と呼んでいるのだろうか。これに関しては、平城京からの遷都後、恭仁京に建てられた「新宅」に対する「旧宅」であろうとする契沖説(万葉代匠記)が最も納得できる考え方であると思われる。同様な例は、巻十七所載の家持の歌の題詞「十六年四月五日、独り平城の旧宅に居て…」(3916〜3921番)にも見られるのである。
また、この宴の参列者たちは奈良山を通って諸兄旧宅に参集したことが歌から窺える。
奈良山の峯のもみち葉取れば散るしぐれの雨し間無く降るらし(08/1585)県犬養吉男の肩書は内舎人とあり、京に在住していたはずである。天平十年であれば平城京に住んでいたはずの吉男が、奈良の諸兄宅に行くのに何故奈良山を通過する必要があったのだろうか。黄葉を手折るためだけに、わざわざ「しぐれの雨」が降る中、奈良山を登って降りてくるという遠回りをする必要があっただろうか。この点からも、上記の宴が、恭仁京から平城旧京に参集して開かれたものであったことは明らかであろう(言うまでもなく、恭仁京を南に下り奈良山を越えれば平城京である)。
右一首、内舎人県犬養宿禰吉男奈良山をにほはす黄葉手折り来て今夜挿頭しつ散らば散るとも(08/1588)
右一首、三手代人名
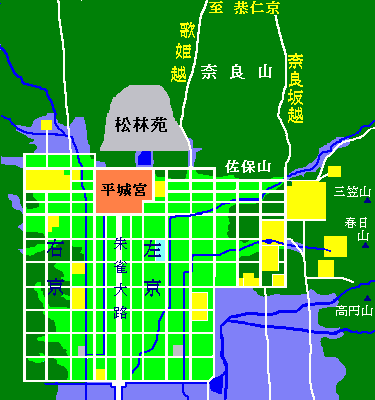
平城京と奈良山 京北郊の丘陵地を概して奈良山と呼んだ 逆に、平城還都(天平十七年)以後、平城京から恭仁京の旧宅に集まった、と見ることは無論不可能である。諸兄は天平十五年に左大臣に就任しており、左注の「右大臣橘卿」と矛盾を来すからである。
従って、一連の歌十一首は、恭仁京遷都(天平十二年十二月)以後の作であり、また、下限は諸兄の左大臣就任時(天平十五年五月五日)である。即ち契沖の指摘通り、「冬十月十七日」とは、天平十三年か十四年の十月十七日でしかあり得ない、という結論が導かれるのである。
そこで考えられるのは、天平十四年に作られたと明記された歌が、万葉集には一首として存在しないことである。これは、天災が打ち続いた天平十四年を不吉な一年として忌避した結果と見られ、おそらく万葉の編集者はこの歌が十四年作であることを知りつつ、敢えて制作年をぼかしたものではないだろうか(注4)。
もっとも、天平十四年十月十四日には参議県犬養石次が卒しており、三日後の十七日に同族の県犬養吉男・持男がこの宴に参加していることにはやや疑問が残る。しかし、言うまでもなく県犬養氏は古来からの大族であり、氏族名を同じくするからと言って近親であるとは限らない。特に問題とはならないであろう。
もし万葉巻第八の編者が、この宴が天平十四年十月に行われたことを知っていたとするなら、一連の歌を天平十五年の歌の前に置いたはずではないか? そうした疑問が湧くのは当然である。しかしこの「橘朝臣奈良麻呂結集宴歌十一首」の直前には「右大臣橘卿宴歌七首」が置かれており、ここでは年代順排列の原則より作歌事情別の排列を優先させたものであろう。あるいは、「橘朝臣」との誤記(当時正しくは宿禰)や「奈良丸」との表記(廣瀬本)から、これらの歌が後世の補遺であったことも推測される。年号の記されていないこの宴の歌稿が巻八編集後に発見され、同じ橘家の宴歌としてこの位置に挿入されたのかも知れない。
巻八・1591番歌の左注を除外すれば、家持の肩書に最も早く「内舎人」の語が現れるのは、天平十二年十月と明記された、巻六・1029番の題詞においてである。
天平十二年から十六年までなら、ちょうど満4年間内舎人の職にあったことになり、4考満ちた家持は翌天平十七年正月、晴れて従五位下に叙せられている。ぴたりと慶雲三年の格に一致するのである。十二年庚辰冬十月、大宰少弐藤原朝臣広嗣謀反して軍を発せるによりて、伊勢国に幸しし時に、河口の行宮にして内舎人大伴宿禰家持の作る歌一首河口の野辺に廬りて夜の歴れば妹が手本し念ほゆるかも(06/1029)すなわち、家持は天平十一年の暮れまでに内舎人に選ばれ、翌十二年から正式に任官したのであろう。この点で私は藤田氏の結論に賛同するのである。
さて、天平十一年(739年)十二月の時点で数え齢二十一歳であるとすれば、家持の生年は養老三年(719年)に当たり、これまた養老二年説とは合致しない。ところが、彼は天平十一年夏から秋にかけて、「亡妾」を悲傷する長短歌十三首(うち一首は書持作)を詠んでいる。
これらの創作が事実にもとづくとすれば、同年夏六月以前に傍妻を失ったことになる。服喪(妻の死の服期は3か月)により、天平十一年中に予定されていた着任の機会を逸し、翌年に持ち越したのではないだろうか。或いは、十一年に着任はしたものの、喪により一旦解任され、この結果1考を減じられたと考えてもよい。十一年己卯夏六月、大伴宿禰家持の、亡妾を悲しび傷みて作る歌一首今よりは秋風寒く吹きなむを如何にか独り長き夜を寝む(03/0462)「妾」が亡くなったのをもっと早く、前年の天平十年末に想定しても構わない。その場合、本来なら十年中に選任されるはずが、服喪により翌年に延期され、着任はやはり翌々年の十二年にまで持ち越されたことになる。
いずれにしても、家持が内舎人に選任されるべき年は天平十年(738年)であったと考えることが可能であり、ここから逆算して得られる家持の生年は、公卿補任・大伴系図が伝える養老二年(718年)に合致するのである。
自進仕人説(山本健吉『大伴家持』に紹介されている林田正男氏説など)を持ち出さずとも、家持養老二年生誕説はじゅうぶん成り立ちうると考える所以である。
(注1)一例として、岩波新日本古典文学大系『八代集索引』『袋草紙』の人名索引の家持の項は養老元年生誕説をとり、養老二年説は異説として提示されている。
(注2)軍防令で内舎人について規定している条文はつぎの通り。
凡そ五位以上の子孫、年廿一以上にして、見(げん)に役任無くは、年毎に京国の官司、勘検して実を知れ。十二月一日を限りて、并せて身さへに式部に送りて、太政官に申して、性識聡敏にして、儀容取りつべきを検(かむが)へ簡(えら)びて、内舎人(ないしゃにん)に充てよ。三位以上の子は、簡ぶ限に在らず。条文に「限十二月一日」とあるのは、式部省に名を登録する締め切りが十二月一日であることを意味するのであろう。「并」という語から、対象者のリストは一まとめにして式部省に送られたものと判る。実際に選考を行うのは太政官の官人であり、審査は十二月一日以降にまとめて行われたことになる。したがって合格者が実際に内舎人に着任するのは翌年になったはずである。無審査の場合も太政官の承認を得るのは十二月中になるので、やはり着任は翌年からであろうと思われる。なお、続紀薨伝によれば藤原豊成は養老七年(723年)内舎人に兵部大丞を兼ねたとあり、この年20歳にあたる。内舎人の年齢規定が必ずしも守られなかった実例であるが、贈太政大臣正一位の嫡孫ゆえの特例と考えられる。豊成は翌年21歳にして正六位下から従五位下に昇叙されているが、これも特別な優遇の例である。奈良時代において叙位任官上のかかる特例(令の規定より若年での叙位任官)が確認できるのは、臣下では藤原氏・橘氏の子弟に限られる。
(注3)「凡そ初位以上の長上の官の遷り代らむことは、皆六考を以て限りとせよ」(選叙令)。
(注4)続日本紀より、天平十四年における天変地異に関する記事を以下に挙げる。
- 一月二十三日、陸奥国より赤雪が降ったとの報告。
- 三月二十四日、地震。
- 五月三日、洪水の被害に遭った畿内各地に使を派遣。
- 五月十日、越智山陵(皇極陵)崩壊。
- 六月五日夜、京中に飯雨。
- 七月一日、日蝕(食分九)。
- 九月十二日、大風吹き雨ふる。宮中の建物や墻、人民の住居が壊れる。
- 十一月十一日、大隅国司より「空の中に音有り…地大いに震動せり」と報告(桜島の火山活動と関連あるか)。
- 十二月十六日、地震。