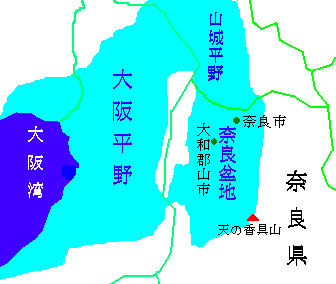折節の記
―天の香具山と「海原」―
 |
| 天の香具山 奈良県橿原市・桜井市 |
万葉集を開くと、最初に詠まれている地名がほかならぬ「大和」です。次に出て来るのが「天の香具山」。舒明天皇の国見歌と呼ばれる歌です。
大和には 群山あれど
とりよろふ 天の香具山
登り立ち 国見をすれば
国原は 煙立ち立つ
海原は 鴎立ち立つ
うまし国ぞ 蜻蛉島 大和の国は
天の香具山は現在アマノカグヤマとよみならわしていますが、万葉集ではアメノカグヤマとよむのが通説です。『古事記』の倭建命の歌に「阿米能迦具夜麻(あめのかぐやま)」と万葉仮名で記されているので、上代はそう読んだのだろうと推測されるからです。
アメノにせよアマノにせよ、万葉集で「天の」という修飾句のつく地名は香具山だけで、いかにこの山が特別視されたかわかります。
「天」が付くのは、この山が天から降って来たという伝承があったためで、『釋日本紀』の伊予国風土記逸文は、次のような地名説話を伝えています。
伊予の郡。郡家より東北のかたに天山(あめやま)あり。天山と名づくる由は、倭(やまと)に天加具山あり。天より天降(あも)りし時、二つに分れて、片端(かたはし)は倭の国に天降(あまくだ)り、片端は此の土(くに)に天降りき。因りて天山と謂ふ、本(このもと)なり。
天上界にあった山が落ちて来て、その片割れが天の香具山になり、もう片方は伊予の国の「天山(あめやま)」になった、というわけです。この「天山」は、愛媛県に今も地名が残っていて、温泉郡石井村にある孤立丘がその山なのだそうです。
この起源説話からすると、天の香具山の語源は天の欠け山、ってことになりそうですが、たぶんカグはカグツチの神のカグ、かぐや姫のカグに通ずるもので、「光輝く」といった意味をもつと思われます。天から降って来た輝く山、それが天の香具山だったでしょう。
さて、舒明天皇の御製は、国ぼめ歌とよばれるパターンに属するもので、春、大王が聖山に登って領土を眺望した、いわゆる「国見の儀礼」と関係のある歌だろうと言われています。
そういった解説はいろんな本に書いてあると思うので、ここではちょっと違う点に目を付けてみましょう。
私がこの歌で前から不思議だったのは、
海原は かまめ立ち立つ
と詠まれている部分です。香具山から海が見える、とはどういうことでしょうか。江戸初期の学者契沖(けいちゅう)も、「和州には海なきを、かくよませ給ふは、彼山より難波の方などの見ゆるにや」と訝しがっています。標高150メートル前後の香具山から、大阪湾が見えるなんてことがあるのでしょうか。
契沖の疑問に対し、少し後の時代の国学者たちは、香具山の麓にある埴安(はにやす)の池を海といったのだ、と解答しました。この説は広く受け入れられ、以来、この「海」は埴安の池ということにほぼ落ち着いているようです。
最も新しい個人万葉全注釈である伊藤博氏の『萬葉集釋注』でも、この句について次のように注記しています。
香具山の周辺には、埴安、磐余など、多くの池があった。「海原」はそれを海とみなしたものであろう。「かまめ」は「かもめ」の古形で、その池のあたりを飛ぶ白い水鳥をかもめと見なしたのか。
そして、舒明天皇の国見歌は、「海と陸によって成る"日本国"全体の映像を」大和にになわせたもの、と見ています。奈良盆地の小風景に日本国全体を幻視している、というわけです。
なるほど、そういう読み方も出来そうです。
しかし、下の写真を見てください。埴安の池の名残りと考えられる、香具山山麓の古池を最近写したものです。
埴安の池? 香具山山麓の古池
「大雨で校庭にできた水たまり」といった程度ではないでしょうか? もっとも、昔の埴安の池が今よりかなり広い水面を湛えていたらしいことは、周辺の地名(南浦など)から推測されるところで、犬養孝氏の『万葉の旅』にも指摘されている通りです。それにしても、校庭がサッカー場に変わるのが関の山でしょう。その程度の池を「海原」にしてしまうとは、針小棒大、誇大妄想の譏りを免れないのでは?
「国原は」「海原は」と詠み上げる順序にも、山の麓の池では合いません。舒明天皇の御製は、まず眼下の国原の煙(人家の炊煙、または陽炎や水蒸気)を眺め、ついで視線を移すと、海原が広がってカモメが次々に水面を飛び立つ――こう読んでこそ、国見歌としての格調があるわけで、この海を山麓の水たまりと解釈してしまっては、歌が台無しになってしまいます。
上に見たような国文学者の説に対し、意想外の着眼点から反論が為されていたことを、私は万葉集とはあまり関係のない本を読んでいて知りました。吉本隆明氏の『ハイ・イメージ論1』(福武文庫 1994年刊)という本に、地質学と考古地理学の最近の成果を取り入れた、考古学者樋口清之氏の論考が紹介されていたのです。
以下は吉本氏の本からの孫引きになりますが、樋口氏は、地下の地質調査から判明した事実として「ほぼ長方形をしている現在の大和平野は、今から約一万年余り前、即ち洪積期の最終末の頃、山城平野に口を開いている海湾であった」ことを指摘しています。同書に載っていたランドサット映像からの想像図をたよりに、約1万年前の畿内地方の概念図を作ってみました。
1万年前の畿内地方中心部
参考:吉本隆明『ハイ・イメージ論1』(福武書店)
上の図の水色の部分が、当時海湾であったと推定される領域です。樋口氏の説をさらに聞きましょう。
海の塩水は大阪湾を満し、山城平野を満し、現在の奈良市の北にある奈良山の丘陵はなくて、それを越えて大和湾に北から南へ湾入していた。後に紀伊半島の地盤隆起に従って、大和平野の地盤は次第に海面から離れて行くことになった。(中略)つまり、大和盆地はもと湖であったが、地盤の隆起につれて排水が進行すると湖面が次第に低下し、最後には干上がって浅い摺鉢状の盆地になったと理解されます。(樋口清之「日本古典の信憑性」『国学院大学日本文化研究所紀要』第十七輯)
簡単にまとめると、洪積世末期から沖積世にかけて、大和(奈良)盆地は、
海湾→海水湖→淡水湖→盆地
と移り変わったことになります。
奈良盆地の標高45メートル線以下には、奈良時代以前の住居跡や遺物は発見されておらず、それ以下の低地は大和盆地湖の名残りで、湖水や湿潤地であった、と樋口氏はいいます。そして舒明天皇の国見歌に言及し、何十回も香具山に登ってみたが、埴安の池は見えなかった、とのべ、「むしろここから見える海原は、国原に対して海原と表現したもので、かつての盆地湖の名残りとして、丁度今の郡山の東の方が奈良朝まで湿潤の地であり、香具山からはこれが見え、また鴎の立つ姿も見えたと思う」と論じます。
湖水の干上がった後に出来た肥沃な「国原」と、その向うに広がる、いくつかの海跡湖を湛えた湿原地帯である「海原」――私はこの説を知って、箱庭的な大和盆地の風景が、突然海と陸の織り成す壮大な光景に変容するのをおぼえ、驚き興奮したものでした。
天の香具山 撮影時、ちょうど山の真上から陽が差し込んだ。
香具山は、奈良盆地の東南角にあたり、『万葉の旅』の犬養孝氏のみごとな描写を借りれば「多武峰の山つづきの端山が、西北でぐっと低くなって、そのまた端山が平野になだらかにつき出たような位置」にあります。奈良盆地が入江だった時には、おそらく海に突き出た岬を成していたことでしょう(畝傍山や耳成山は海中の小島です)。縄文人や弥生人たちは、この岬に立って入江(あるいは湖)を遥か彼方まで見渡すことができたでしょう。
吉本氏も示唆する通り、上代文学の地理的・風土的研究は、よりスケールを大きくとった考古地理学や地質学の観点から、もう一度見直してみる必要があるように思えます。
*
万葉集の歌には、思った以上に分厚い時の重なりが堆積しているのかも知れません。万葉の地下水として湛えられた、太古にまでさかのぼる豊饒な記憶は、もちろん地名という「言葉の化石」にも、しっかりと刻印されているはずです。
和歌雑記もくじ やまとうた表紙
©水垣 久 最終更新日:平成13-06-14