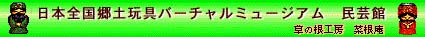
----兵庫県篇(1)ー1----
----HYOGO----
■兵庫県の郷土玩具ガイド■(掲載されていないもの、廃絶品を含みます)
神戸市:神戸人形。雀の巣ごもり。神鶏。ポッペン。 あかえいの絵馬。 尼崎市:厄よけだるま。 西宮市:絵ろうそく。 有馬温泉:人形筆。 淡路島:だんじり(廃絶)。舟(廃絶)。 城崎温泉:麦わら細工。 姫路市:姫路のこま。姫路張り子。 大塩町:七夕人形。 加西市:北条の布団屋台。大羽子板。 氷上町稲畑:稲畑土人形。 養父(やぶ)郡関宮町葛畑(かずらはた):葛畑土人形(廃絶)。 佐用郡上月村:早瀬土人形(廃絶)。 ■施設■ 日本玩具博物館 神崎郡香寺中仁野671-3 TEL:0792-32-4388 世界の貯金箱博物館 尼崎市西本町北通3-93 尼崎信用金庫本店別館内 TEL:06-413-1163 ひょうごふるさと館 神戸市中央区御幸8-1-25 ケイ・エスビル2階(そごう百貨店新館2F) イベントコーナー TEL:078-252-0686 |

|
■神戸人形■ 神戸人形は、兵庫県の代表的な郷土玩具です。この「からくり人形」は、明治の中期頃から作り始められたと云われています。 当時は「黒人人形」とか「お化け人形」などと呼ばれていました。初代の製作者は、淡路人形師の中村某であるとか、永田村で芝居の小道具を作っていた春さんなどと伝えられていますが、確認できるものは残っていません。 明治後期。出崎房松氏、からくりの改良。 これを引き継いだのが、小田太四郎氏で、制作技術は名人といわれました。昭和25年66才で亡くなります。 その後、3、4年後、廃絶を惜しむ人達の声を受けて、数岡雅数氏が研究をはじめ、昭和34年頃に制作を軌道にのせます。平成元年、60才で、亡くなりました。 現在の、松岡達さんは、数岡氏の初期の作品を取り扱っていた関係から、生産の数も少ないので、自分で制作に乗り出ました。神戸人形の伝統的な技術は、むしろ松井さんに色濃く残っているのかもしれないと思われます。 制作者:松井駿侍(キヨシマ屋):神戸市中央区元町2-5-14..TEL:078-392-2471 入手先:上記の「キヨシマ屋」 神戸センター(三宮センター街):中央区三宮町1-5-27..TEL:078-321-0161 ---制作者・入手先は、阪神大震災以前の資料によります。--- ■(有馬温泉)人形筆■ 人形筆は、穂先を下にむけると、豆人形が上の筒先からピョコッと顔を出し、筆を寝かすと人形は姿をかくす仕掛けになっています。 この人形筆の歴史は古く、天和2年(1682)刊の「有馬名所鑑」にも載っていて、江戸初期には作られいたことがわかっています。 明治・大正の頃は、この地域に人形筆をつくる家が4、5軒ありましたが、今は1軒となりました。 制作者:「灰吹屋」(三代目)西田光子。(子息)西田健一郎: 神戸市北区有馬町1160..TEL:078-904-0761 ■雀の巣ごもり(花)■ 聖徳太子開基と伝えられる「太福寺」で祭礼の日に授与されている、珍しい形のお守りです。 これは、檀家の青年達による手作りのお守りで、農具の鎌一丁により、削りかけの手法でつくられています。 お守りは、毎年2月11日の祭礼に授与されるもので、当日は子供連れの人達で賑わいます。特に新生児には太子のご威徳にあやかり、無病息災、知能生育が授かるといわれています。 昼すぎ、大般若経が上げられた後、檀家の人達により、2羽の雀と巣がばらばらにして撒かれます。参拝者は、お互いに拾った雀の雌雄や巣を交換して1組にして持ち帰ります。 ---太福寺:神戸市北区道場町生野148 TEL:0795-62-4163 |

|
(1998.9.22掲載)