|
しかし、小協奏曲とピアノ協奏曲の二曲をアントニオーリというスイスの若手ピアニストがローレンス・フォスター指揮ローザンヌ室内管弦楽団と共に録音したものがスイス・クラヴェースから出ているものを聞いて感じ、考えたことと、ピアノ協奏曲だけですが、スイスのエアージンゲン生まれの中堅指揮者マティアス・バーメルト指揮のバーゼル放送交響楽団がベーター・アロンスキーと共演した録音したCDがあるので、それらを紹介しながら話を進めていきたいと思います。
ジャン=フランソワ・アントニオーリは一九五九年ローザンヌの生まれだそうですから、今年一九九九年には四〇才になるピアニストです。ローザンヌ音楽院卒業で、パリでサンカン教授に更に三年間師事したということですから、正統的なピアノ・テクニックを身につけた若手(中堅かな?)ピアニストだといえます。
録音は一九八八年ですからアントニオーリが29才の時であります。
さて、小協奏曲「春への賛歌」Op.76は一八五七年、ラフ35才の時にヴィスバーデンで書かれた作品です。ショパンのピアノ協奏曲の二楽章などを思い起こさせるかのような、うっとりさせる楽想であふれています。ラルゲットという指示もショパンの同じ楽章を思い起こさせますが、ショパンよりもずっと管弦楽が充実していて、ピアニスティックな聞き所にも事欠かないこの作品は、もっと有名になってもおかしくないと思うのですが、いかがでしょう。
後半のプレストは、更に充実した書法で書かれ、展開の入念さはいつもの通りながら、更にスケルツァンドな性格と、叙情的な楽想との少々水と油のような性格を統合していくという困難な課題に見事に答えているのであります。リストの音楽の影響は明らかではありますが、ピアノよりもオーケストラへの重心の方が勝っているようで、小協奏曲というより、ピアノ入りの交響詩といった感じに仕上がっています。
様々な転調、変遷を経て、最初の叙情的な旋律に回帰していく様子は感動的であります。
アントニオーリの演奏は堅実で、共演のオケがとてもしっかりしているので、実に聞き易い美しい演奏に仕上がっています。ただ、プレストの所での音が軽量なので、全体に音が硬質で浮いてしまい、作品を実際以上に小さな音楽にしてしまっているところが残念です。
昔、ヴォックスだったと思うのですが、出ていた「ロマン派の知られざるピアノ協奏曲」のシリーズで、聞いたように思うのですが(ポンティのピアノだったと思います)もう少し、スケールの大きい作品に聞こえたと思うのですが…。
もう一つ、ラフのピアノ作品の代表作と言われる唯一のピアノ協奏曲ハ短調は、三楽章制に則っている古典的な枠組みの中の作品です。
一八七三年、ヴィスバーデンで書かれたこの作品は、ラフが五〇才を過ぎてやっと作った本格的なピアノ協奏曲です。リストに近い、この作曲家の位置づけで、ピアノ協奏曲がたった一曲というのは、ちょっとしたミステリーのようにも思えますが、それにしてもこの協奏曲は、充実した作品に仕上がっています。
初演は、ハンス・フォン・ビューローのピアノ、ラフ自身の指揮で行われたそうです。
第一楽章は、伝統的なソナタ・アレグロ形式で書かれ、冒頭からいきなりオケのトゥッティ(総奏)とピアノ・ソロの掛け合いではじまるのですが、この辺りはリストのピアノ協奏曲第一番を思い起こす部分でもあります。いやそれよりもずっと古典的な枠組みを守りながらの作曲であるところが、ラフの教育者としてのアカデミズムの特徴のようにも思えます。
第二主題はとても伸びやかなベルカント風のメロディーが置かれていて、このロマン派の時代の特徴をよく現している楽章であるといってよいでしょうね。
ピアノの分散和音の扱いなどは、明らかにラフマニノフのピアノ協奏曲第三番の先取りのようにも思えますし、決してこの作曲者が、色々な作曲家の真似事で終わっていたのではないことは明白な事実であります。
アントニオーリの演奏はこのあたりになるとオケの軽量ぶり(室内管弦楽団だからかどうかわかりませんが、響きそのものの薄さが気になります。
またそのせいでもないのでしょうが、アントニオーリのピアノの音も随分軽量で、やや不満が残るのも事実であります。
私は、ベーター・アロンスキーとバーメルト指揮のバーゼル放送交響楽団の演奏の方が、随分優れていると思います。特にラフマニノフ調のスケール感を出して盛り上がる場面では、アロンスキーは実に重心の低い、ノビのあるフォルテを出すことが出来、フル編成のオケとの協奏という面でも全く不満を感じさせません。
さて、第二楽章ですが、アンダンテ・クワジ・ラルゲットという指示のある音楽で、ラルゲットのようなアンダンテでとでも訳すといいのでしょうか?
心に滲み入るメロディーが木管のハーモニーに支えられてオーボエによって提示されます。弦の扱いなどはベートーヴェンの第三ピアノ協奏曲の第二楽章のようで、美しいハーモニーに支えられて、ピアノが自由に装飾していくといった形で音楽が進んで行きます。
アントニオーリも健闘はしていますが、ここでもアロンスキーの演奏は、小綺麗なだけに終わることなく、大きく呼吸をしての深く歌う演奏となっていて、深く印象に残ります。
第三楽章(終楽章)のアレグロは、恐らくはラフが終生深い尊敬を捧げたベートーヴェンの「皇帝」の三楽章にも似て、華麗で技巧的で、ピアノのまさに名人芸を要求する音楽となっていることは間違いありません。
古典的な協奏曲なら、ここでロンド・テーマが出てくるのですが、ラフはヒロイックな(英雄的な)行進曲をピアノ協奏曲のフィナーレに持って来ています。
一年程前に作った傑作、交響曲第五番「レノール(またはレオノーレ)」の第二楽章の主題にも似た、大変力強いもので、この楽章もアロンスキーの演奏は、作品が要求するものを充分に表現した、実に力強い演奏であると考えます。
全体にアントニオーリの演奏は室内楽的で、やや軽量で硬質な響きが特徴ですが、アロンスキーの演奏はオケ共々、重心の低い、スケールの豊かな、そしてピアノの響きの大変良い演奏であると言えます。
アントニオーリの演奏はスイス・クラヴェースから、アロンスキーの演奏はスイス、チューダーからCDで発売されています。
演奏だけなら、アロンスキーで決まりなのですが、名曲「春への賛歌」はアントニオーリのCDにしか入っていないし、で欲しい人は両方買いましょうね。
スイスの作曲家、ラフ。ぜひ多くの方に知って貰いたいと思います。
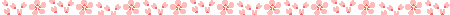
|
