|
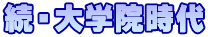
これは「大学院時代」の続きです。
千葉大学で第一外科(現在の臓器制御外科学)から第二病理(病態病理学)に出向して戸惑っていた大学院生活も、2年目となれば仕事にも慣れて勝手も分かり、病理を学ぶことがだんだんと楽しくなってきた。
教室でも、夜型の人が午前3時に研究を終えて灯りを消して帰ると、朝型の人が午前4時にやって来て灯りをつけるといった調子で、いつも誰かが熱心に研究をしていた。
学位論文に関しては、私は肝臓を研究する予定だったこともあり、まずは見習いということで、第二病理教授のK先生が研究されていた偽腺管型肝細胞癌のお手伝いをさせてもらった。
これは、肝細胞癌の組織像は索状型が一般的なのだが、一部に腺管様構造を示すものがあり、胆管癌と類似しているため鑑別を要するといった内容のものだった。日本病理学会においてポスターセッションへのデビューも飾らせてもらった。
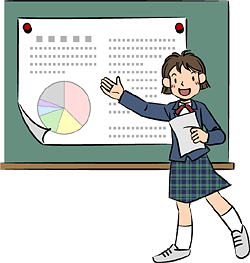
このとき比較するために肝内胆管癌の組織像を調べているうちに、まだあまり研究されていない分野であることに気づき、それなら自分でやってみようということで、「肝内胆管癌の病理組織学的検討」というテーマが見つかった。
幸いなことに、臓器制御外科学教授であったM先生が、当時ちょうど積極的に肝内胆管癌の手術を始めた時期だったこともあり、ご厚意から研究の対象となる多くの手術症例をいただくことができた。
また、病理学教室の解剖例の中にも、興味ある肝内胆管癌の症例が多々あり、そのうえ関連病院からも症例を提供してもらう機会もあって、最終的に研究の対象として合計102例での検討が可能となった。
千葉大学における臨床と基礎の両教室の奥深さに感嘆すると共に、そのような伝統のある母校を誇りに思えたのだった。

一方、病理を学びたいと思ったもう一つの目的として、生検診断をはじめとした実地診療に活用できる外科病理学を習得したいということがあった。
千葉大学付属病院の各科から毎日送られてくる生検材料や手術臓器は、日替わりで当番の病理専門医が担当して診断していた。
その標本は前日の夕方に届けられるので、事前に下見をして、AckermanのSurgical Pathologyなどの教科書や、AFIPやWHOから出版されている腫瘍病理アトラスとかを参考にしながら、自分なりの診断を下しておいた。
翌日に担当病理医が診断するときに、ティーチングスコープ(ひとつの顕微鏡に接眼レンズがいくつも連結され、複数の人が同時に検鏡できる装置)で一緒に覗かせてもらい、診断過程をリアルに学ぶといったことを繰り返した。

初めのうちは、胃癌ひとつをとってみても、異型を示す腺管を見たときに、それが炎症性変化によって修飾された良性のものなのか、あるいは腫瘍性変化による悪性のものなのか、判断に迷うことが多かった。
しかし門前の小僧ではないが、先輩の病理医の診断過程を同時体験させてもらっているうちに、少しずつではあるが、良悪性の鑑別がなんとなく分かるようになってきた。
こればかりはいくら教科書を読んで頭に知識だけを入れていても、実践を踏んでいなければ身につけることはできない、微妙なフィーリングの領域なのだ。
こうして各臓器の病理組織像のいろいろなパターンを頭の引き出しに整理し、診断時に目の前の症例に当てはめていくということが、徐々にできるようになっていった。

自ら臨床診断をして、手術を行い、病理診断も下せる医師になるという理想に向けて頑張っていた大学院時代だったが、学生ならではのお楽しみもあった。
休憩室ではK教授自らが、料理の腕前を披露してカレーライスを作り、教室員に振る舞うという、臨床ではあまり考えられないような一幕もあった。
午後5時を過ぎると酒盛りが始まり、一人また一人と教室員が集まって来るにつれ、談笑の輪が広がることもよくあり、終始和やかな雰囲気に満ちていた。
教室行事としては、ゐのはなキャンパスでの春のお花見、夏のバーベキュー大会、秋の一泊旅行、冬の志賀高原へのスキーと、いろいろな催し物があった。

また、東京大学、慶応大学、東京医科歯科大学、千葉大学の病理医からなるチーム同士の4大学対抗野球大会が毎年開かれ、いつも熱戦を繰り広げていた。
それに続く夜の宴会では、これまた大学ごとに隠し芸を競う対抗戦(ナイターと称していた)もあった。
普段は真面目な大学院生たちが、いかに馬鹿になってお笑いをとるか、数週間前から集まって皆で真剣に出し物の稽古をしていたのも、今では懐かしい思い出である。

エッセイ集に
|