
ハーフムーンの夜には心苦しい気持ちが湧き起こる・・・
その発端となったのはだいぶ昔の話だが、Pという我が家の犬が晩御飯を残すようになったことからだ。
ちなみに現在と違って当時の犬は外飼いが普通で、室内で飼われている犬は座敷犬と呼ばれて珍重されていた。
食事も今でこそ犬の健康を考えて作られているドッグフードを与えるのが常識だが、当時のたいがいの犬は米と人間の食べるおかずを混ぜて与えられていたものだった。
それでもPは完食が常だったし、健康上も特に支障はなく獣医さんのお世話になることもなかった。
異変は突然に起きた。
このところ犬用の丸い食器に、晩ご飯がちょうど半分残されるようになったのだ。
それはまるで計ったように───我々が饅頭やせんべいを半分にして互いに分け合うみたいに───きっちりと二等分されて食器内に残されていた。
最初は具合が悪くて食欲が落ちたのではないかと心配したが、朝になるときれいになくなっているので、夜の間に残りを食べたのだと思っていた。
だがある夜、どこからか見知らぬ犬がやってきて、Pの残したご飯を食べていることに母が気づいた。
一体どこの犬なのかと不思議に思っていたところ、再び母がある噂を聞きつけてきた。
なんでも近所のおばあさんが、足が衰えて散歩ができなくなったため、飼い犬を夜の間だけ外に放しているというのだ。
今と違って当時は夜になると人や車の往来もまばらになり、犬を放しても交通事故などの危険は少なかったのだろう。
犬も心得ているもので、外を少しうろついて気が済むときちんと家に帰っているとのことだった。
半分に残されていた晩ご飯は、たまたま我が家の庭を訪れた犬への、Pからのプレゼントだったのだ。

おまえすごいな、友達のためにご飯を分けてあげるなんて、と思わず話しかけた。
確かにPにとって与えることができるものは他には何もなかったのだ。
しかしPはそれがどうかしたのかといった風に泰然としていた。
つらつら考えてみるに、子供のころ弟とおやつを分け合うとき、兄は体が大きいのだからと宣言し、余分にもらおうとしていた私の行いは、犬にも劣るものであり恥ずかしい限りだ。
犬が訪れるのは夜遅くだったので姿を見たことはなかった。
でもある夜たまたま外に出たときに見知らぬ犬が来ていて、Pの見守る中でご飯を食べている場面に出くわした。
これが例の犬かと思ったが、月明りしかないため姿かたちがよくわからない。
そこでそろりそろりと近寄って、どんな犬かを確かめようとした。
犬は最初のうちは気にも留めずにひたすら食べていたが、私が接近してきていることが分かったのか、食べるのをやめてこちらを見た。
私は驚かさないように口笛を吹いたり手を振ったりして、精一杯の友好的態度を示しながら注意深くさらに近づいてみた。
だが犬は急に逃げだしてしまった。

いや、悪意はない、どんな犬か見たかっただけだよ、焦った私は思わず犬の逃げる方向に歩を向けた。
すると犬は追いかけられていると思ったのか、猛スピードで走り去っていった。
その間ずっとPはワンワンと吠え続けていた。
相手の犬に対して吠えているのかと思っていたが、後から考えると私に向かって行動を差し控えてほしいと訴えていたのかもしれない。
犬がいなくなった後にPと顔を見合わせた。
言葉は交わせなくても、何となく気まずい空気が流れているのを感じる。
子供の頃にいたずらがばれて叱られる直前の、後悔しているときと同じ気持ちだ。
怒ってる? かんにんね、でもあの犬はきっと明日の夜になれば、ご飯を食べにまたやってくるから心配ないよ、と言い訳をした。
ため息交じりに夜空を見上げると、ハーフムーンが出ていた。
それはあたかも二等分されて食器に残っている白いご飯のように思えた。
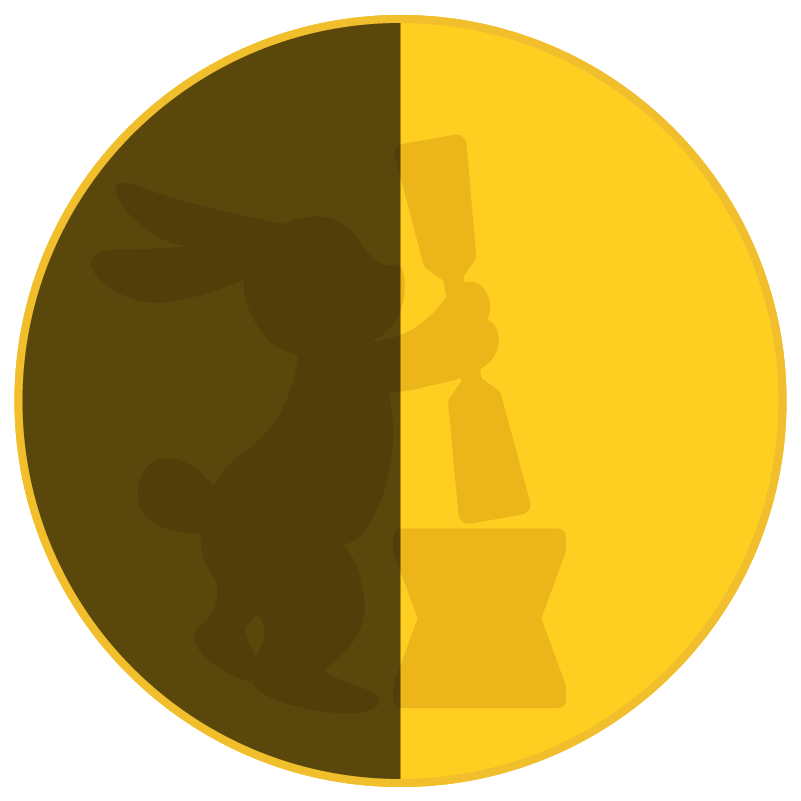
しかし私の楽観的な予想とは裏腹に、翌日になっても、その次の日になっても犬は現れなかった。
しばらくの間は食器に半月の形をしたご飯が残されていたが、犬の訪れはなかったのか、朝になるとPはひっそりと残りを食べていた。
やがてPはとうとうご飯を残さないようになった。
事ここに至って私は自分のした事の深刻さを思い知った。
私のほんの一瞬の興味本位の行動のせいで、2匹の犬の交流が断たれてしまったのだ。
相手の犬からあの家は危ない、近づいてはいけない、とスティグマが押されたのに違いない。
Pは相変わらず飄々としていたので胸の内はわからないが、がっかりしていたことは想像に難くない。
それからはせめてもの罪滅ぼしに、いつもより遠くまで散歩に連れて行ったり、おやつを多くあげたりもした。
その後何年かしてPは永遠の眠りにつき、一連の事件のことは時の流れとともに、しだいに遠い記憶となっていった。
でも夜空を見上げた時にハーフムーンが出ていたりすると、今でも不意に思い出してしまう。
すると時はあっという間に当時へと遡り、月夜の2匹の犬の姿があぶり出しを見ているように、じんわりと浮かんでくるのだ。
