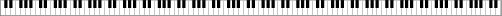
楽器のお話
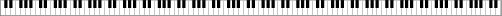

マンドリンです。
長年弾いているにもかかわらず、あらためてマンドリンについて
書こうとすると、記憶や知識がいい加減だと痛感しました。(^^;
マンドリンはイタリアの楽器です。
その大部分が木でできています。
表面板はスプルース(松)、胴はメイプル(楓)やローズウッド(紫檀)等々。
実はこの材質は、ヴァイオリンと同じだったりします。
左手でギター同様金属製のフレットを押さえ、右手にべっ甲製やナイロン製のピックを持って
弦をはじいて演奏します。
弦はスチール製で高いほうから「ミ」「ラ」「レ」「ソ」(これもヴァイオリンと同じ)、それぞれ2本ずつ
4対8本あります。「2本ずつ」あるのは、連続的に弾く「トレモロ奏法」のためといわれています。
ヴァイオリンの仲間に、ヴィオラ、チェロ、コントラバスとあるように、マンドリンにも仲間があります。
マンドラ、マンドチェロ、マンドローネ。必ずしもバイオリン属と同様の調弦や役目ではありませんが
これらの楽器にギターとコントラバスを加えて、「マンドリン・オーケストラ」を編成して演奏します。
曲によっては、打楽器や管楽器を加える場合もあります。
*私のマンドリン歴
中学に入学して、なにか部活動をと考え、「ブラスバンドがカッコイイな」と思ったんですが、
なんと音楽系は「マンドリン部」しかなかったのです。
田舎の学校なのに、コーラスもブラバンもなく、なぜマンドリンなのか未だに不明です(笑)。
少し迷って、1週間ほど遅れて入部したところ、どのパートもいっぱいで、先輩から
「マンドチェロやりな」と言われました。そもそも、マンドリン自体、見たことも、聞いたことも
なかったので、チェロといわれて「はい」と答えるしかありませんでした。(笑)
渡されたのは、鈴木マンドリン製のマンドチェロ(当時は「マンドセロ」と言ってた気がする)。
一番低い弦を強く引くと、駒から弦が外れて、同じ音の2弦がくっついてしまう楽器でした(笑)。
中学校の備品なので、文句も言えませんでしたけど。
合奏をしているうちに、マンドリンが弾きたいなぁ、と思うようになって、3年生が引退した後、
2年の3学期からマンドリンパートにコンバートしてもらいました。
親に買ってもらった木曽鈴木製のマンドリンを使っていましたが、コンサートマスターになった時、
練習を見に来てくださっていたコーチが、渡辺精次製の楽器を貸してくださって、引退まで使って
いました。鈴木製に比べて、音量も豊富で、甘く柔らかい音が特徴的な楽器でした。
すっかり気に入ってしまって、高校合格を条件に(爆笑)、渡辺精次製のマンドリンを買って
もらいました。モデルは中学時代に借りていたものと同じでしたが、予算の都合もあってで胴が
ローズウッドのものでした。借りていたメイプルよりは、輪郭のハッキリとした明るい音だったよう
に思います。
楽器のお話part2へ
Home

