|
|
□はみ出し目次へ ■三国志関連へ■ホームへ |
|
|
□はみ出し目次へ ■三国志関連へ■ホームへ |
まあ、演義のお話の世界ですけど、やっぱり星が出てくると気になります(^^;)諸葛亮の最後の北伐。星を見、自分の寿命がまさに尽きんとしている事を知り、 延命の祈りを北斗にささげますが、魏延がうっかり主灯を消してしまい、儀式に失敗します。
そして孔明は「あの星が私である。今落ちるであろう」と、その時星が落ち、 皆が孔明を見ると事切れていました。
敵の総大将司馬懿もこの流れ星を見て、孔明が陣没した事に気がつきます。
えい!これをなんかの現象に無理やりこじつけてやれと言うわけです(^^;)
北斗は死を司りますので、北斗に願い事をするのはわかりますね。 七つのロウソクも北斗七星の七でしょう。まあこれは問題ないですね。
蜀漢を正統と見れば、丞相の星は北斗七星にある輔星{ほせい(アルコル)}だと想像はつきます。 でも、まだあるので落ちてはいないですよね・・・もう苦しい(^^;)
輔星は武曲(ムコク)と肉眼二重星になっておりまして、帝を補佐する星を表していると されておりました。
くるちい。もう、流星群しかないか・・・(^^;)
諸葛亮が陣没したのは建興12年10月3日甲寅。これは蜀漢の四分暦ですから俗に言う西暦に直すと 234年11月11日火曜日。これはユリウス暦ですが200年代ならば現行のグレゴリオ暦とは さほどの差は無いですね。
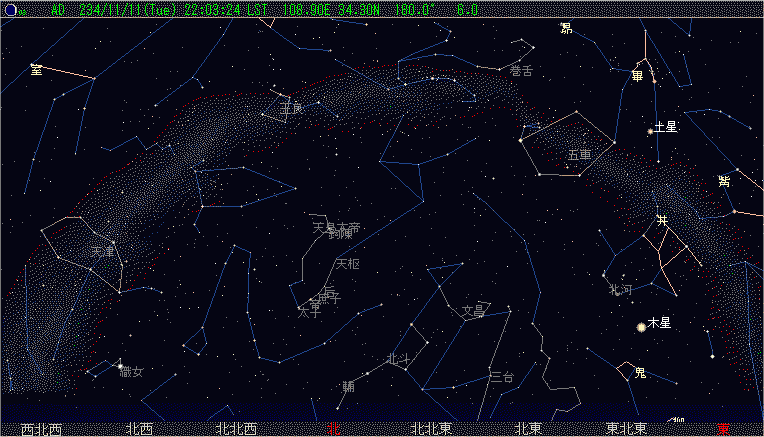
夜の10時で輔星がようやく見えるようになるみたいですね。ベガが沈んでいく。 夜の10時でオリオンが昇って来ているから・・・確かに秋だ。場所は面倒なので長安で標高400mでシュミレート。木星と土星が見えたんですね。 ・・・これだと・・・おうし座南流星群の頃だな・・・11月3日が極大かな・・・
こんな風に見えたのか・・・アンドロメダは真上か・・・・
こうしてみると孔明が死んだのは、輔星が出ている間とすれば、 「0時から夜明けまで」と「22時頃から24時の間」の二通りがある事になりますね。 まあ、刻限だから多少時間はずれますけどね。・・・天の川が良く見えたでしょうね。
蜀の後主の建興十三年(235)に諸葛亮は、大軍を率いて魏を伐ち、渭南(いなん)に陣をとった。 長星が現れ、亮の陣営に落ちた。三回落ち、二度もとに戻った。流れる時は大きく、 戻る時は小さかった。占いによれば「両軍が退治するときには大流星がある。 それが軍隊の上を飛んだり、軍隊の中に落ちるのは敗戦の象徴である」と。九月に、亮は陣中に死んだ。陣地を焼き払って退却したが、諸将はたがいに私怨を抱き、 殺しあった。(中国の科学・世界の名著12・中央公論社P354より引用)
この場面演義では、赤い色の大きな星が、光の尾を引きながら東北から西南に流れ、 蜀に陣に落ち、落ちては跳ね上がりして3度目に落ちて、陰にこもる音がした。とあります。凄まじいですね・・・もう演義も天文史もありません。なんじゃそれ(^^;)
まず死亡年が違いますね。「光の尾を引きながら東北から西南」・・・つまりおうし座南流星群 とは逆の方向。「赤い色の大きな星が、光の尾を引きながら」からすると、これは 流星というより火球(でっかい流星)ですね。
ただバウンドしたってのがね・・・どんなにでかいんだ(^^;)
通常はクレーターを作るので、よほど進入角度が浅かったでしょうね。すると これは隕石って事になりますね。まあ、考えられない事は無いけど・・・よほどの速度を持っていないと進入角度が浅く 入れないよな。よく大気層でバウンドしなかったよな・・・・普通なら大気層がバリアの 役目をしますからね。
オールトの雲からダイレクトで・・・・え!木星が見えるって事は・・・東北からか・・・ 木星でスイング・バイされたか・・・ううん。でも陰にこもる音って、蒸発する音? 爆発じゃないよね。
陣を焼き払ったって・・・これ爆発じゃないの??ううん。 魏延だけ置き去りにしてゆっくり竈を増やしながら撤退したんだし、 大体魏延は変な夢を見たって話があるんですから、 隕石が爆発していてガ〜ガ〜寝てたのか(^^;)
まさか孔明は隕石の爆発死・・・って事じゃないですよね(^^;)
ううん。ううん。ううん。わかんないや(^^;)
234年8月27日頃地球軌道にジコビニ・ジンナー彗星が近づきます。 彗星自体は7等級が最高ですから見えないですが、その後その彗星の軌道に 地球が最も近づくのは9月27日頃。流星群が起きたとすればこの日か・・・時期が違うな・・・
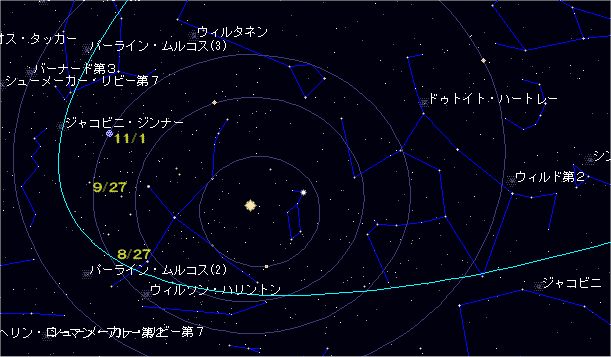
ジコビニ・ジンナー彗星は図では分かりにくいですが図の太陽系の上から下に突き抜けるように 動きます。この太陽系モードは11/1現在のもの。水星より内側にいて明るくなるような 彗星はなし。つまり客星は現在軌道が分かっている彗星の事ではないですね。