イザナギは黄泉の国に行ったけがれを落とすために全身を禊をしました。 その際に神々が生まれました。
禊のなかで、水の底で禊をした時に底津綿津美(そこつわたつみ)の神と 底筒の男の命(そこつつのおのみこと)が成りました。水の中底で禊をした時に中津綿津美(なかつわたつみ)の神と 中筒の男の命(なかつつのおのみこと)が成りました。
水の底で禊をした時に上底津綿津美(うわつわたつみ)の神と 上筒の男の命(うわつつのおのみこと)が成りました。
その後幾つかの禊の最後に左目を洗うと天照大御神 (アマテラスオオミカミ)が成りました。右目を洗うと月読の命 (ツクヨミのミコト)が成りました。
鼻を洗うと建速須佐男の命 (タケハヤスサノヲのミコト)が成りました。
イザナギは最後に一番立派な神を生んだ事を大変喜んで、 アマテラスには天を、ツクヨミには夜を、スサノヲには海を支配するように言いつけました。
- ●住吉神社の三神
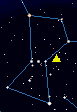 住吉神社の三神は底筒の男の命・中筒の男の命・上筒の男の命の三神であります。
この「筒」は「星」を表す言葉でありまして、具体的にはオリオン座のベルトの部分の「三つ星」
(図左からアルニタク・アルニラム・ミンタカの3星)
を指していると言うのが定説であるようです。
住吉神社の三神は底筒の男の命・中筒の男の命・上筒の男の命の三神であります。
この「筒」は「星」を表す言葉でありまして、具体的にはオリオン座のベルトの部分の「三つ星」
(図左からアルニタク・アルニラム・ミンタカの3星)
を指していると言うのが定説であるようです。
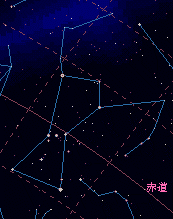 殆ど誰でも1度は見た事のある、特徴があり印象的な「三つ並んだ星」であります。
殆ど誰でも1度は見た事のある、特徴があり印象的な「三つ並んだ星」であります。オリオン座の「三つ星」の部分には丁度赤道が通っているので、太陽が昇った位置と同じ方角から 「三つ星」昇り、太陽の沈んだ位置にと同じ方角に「三つ星」が沈む特徴があります。
- ●天照大御神
 アマテラスはその名の通り、太陽神で女神です。
後に末弟のスサノヲの乱行に怒り「天の岩戸」に隠れてしまう事件がおきます。
アマテラスはその名の通り、太陽神で女神です。
後に末弟のスサノヲの乱行に怒り「天の岩戸」に隠れてしまう事件がおきます。この項目につきましては下記のリンク「卑弥呼の日蝕」にあります。
- ●天の川?
スサノヲが海の支配を解任されたときに、アマテラスの所に暇乞いに行ったとき、 双方「天の安の川」に退治します。う〜んこれは単純に「天の川」と思って良いのでしょうか?
- ●天の川?
- ●月読の命
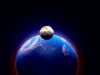 ツクヨミは月神でアマテラスの弟になります。
ツクヨミは月神でアマテラスの弟になります。古事記ではアマテラスとスサノヲの話になっておりますが、日本書記では アマテラスとツクヨミの話となっている「昼と夜の分離及び五穀の起源」の話があります。
- ●昼と夜の分離
アマテラスがツクヨミに「ウケモチという食物神がいるとういので、見てきてください。」 と頼みました。ツクヨミがウケモチの所に行くと、ウケモチが陸を向いて口から飯を吐き出しました。 ウケモチが海を向くと口から魚を吐き出しました。山を向くと獣を口から吐き出しました。
このウケモチはこの吐き出したものをツクヨミに饗したので、ツクヨミは怒り 「汚い。なぜ吐き出したものを食べさせるのだ」とウケモチを斬り殺してしまいました。
事の次第を聞いたアマテラスは「お前は悪い神だ。もう二度と合わない」と怒りました。 そのためアマテラス(太陽)とツクヨミ(月)は昼と夜に別かれて住むことになりました。
- ●五穀の起源
ところが死んだウケモチの「頭に牛馬と粟」「腹に稲」「眉に蚕(かいこ)」「目に稗(ひえ)」 「ほとに麦と大小豆」(別の話もあります)が生じました。
アマテラスは「これは人間が食べるものだ」と喜んだそうであります。
- ●昼と夜の分離
- ●建速須佐男の命
 スサノヲはアマテラスの末弟で嵐の神です。数々の乱行をし、下界に追放されてしまいます。
スサノヲはアマテラスの末弟で嵐の神です。数々の乱行をし、下界に追放されてしまいます。この項目のお話につきましては下記のリンク「卑弥呼の日蝕」にあり、 スサノヲは嵐の神ではなく金星なのではないかというお話は下記のリンク「スサノヲは金星か」 にあります。
- ●国譲り
天神が「葦原中国を征したい。誰を遣わしたら良いか」と神々にただした話の続きに、 悪い星神・アマノカカセヲが出てくるのですが・・・
このお話は七夕の項目にしたいと思います。
- ●神社
- 住吉大明神(筒之男三神)御祭神
- 住吉大明神(筒之男三神)御祭神
- ●あとがき
お話は抜粋なので、詳しくは「古事記」「日本書紀」を読んでね(^^;
あ!古文の本では分からないと思います。ちなみに、これらの本は 「筑紫神話」「大国神話」「天国神話」などの合作で出来ている背景が有りますが、 これは民俗学・考古学などの分野ですので国語の先生に聞いて困らせない出ね(^^;
- ●参考文献
- ★★★古天文の散歩道・斉藤国治著・恒星社
- ★★★古天文学・斉藤国治著・恒星社
- ★新訂古事記・(付現代語訳・武田祐吉訳注)・中村啓信補訂解説・角川文庫ソフィア
- ★古事記物語り・太田善麿著・現代教養文庫717 D101
- ★日本の神話・山田宗睦著・B-1カラーブックス648
- ☆古事記要解・三谷栄一著・有精堂
- ●使用ソフト
- ステラナビゲーターVer3.Ver5