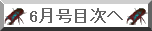「カブ吉」こと塚原 と ポール鈴木

「カブ吉」こと塚原 と ポール鈴木
 |
 |
|
4月10日 更に多くのカブト幼虫が欲しいと思いポール鈴木氏に要望し、あと2匹を貰う事となった。 「わくわくランド」で菌床瓶の使い古しの900CCのガラス瓶が100円で売っていたので、汚れていたがあるだけ買った。その瓶はネスレーの中瓶よりも遥かに大きく、カブト幼虫にはもってこいなので早速移し替える事とした。まるでクワガタマニアが毎日菌床瓶をじーっと見るがごとく、動き回るカブト幼虫をよく眺めていた。 ポール鈴木氏が持ってきたカブト3号と4号は自信作らしく、特に3号は普通の幼虫の2倍ぐらいの大きさがあった。鈴木氏所有の超過密状態の劣悪な餌の中で育てられた幼虫が、どうしたらこの大きさに育つことができるのかは明白であろう。何匹もの兄弟を飲み込んできた「人食い」ならぬ狂暴な「カブト食い」幼虫に違いなかった。「こいつは70mmオーバーは確実だ」心のなかでそう叫んだ。(もしメスだったらどうしよう)。 更にポール鈴木氏はそれらの幼虫とともに菌床瓶を取り出し、密かに隠し持っていたちょっと小ぶりなカブト5号を取りだし「塚原君も菌床瓶を使って70mmオーバーのカブトムシを作らないと」と無謀な提案をしてきた。彼はその小ぶりな幼虫を菌床瓶で育てて、巨大カブトを作り出す気でいるらしい。カブトムシを菌床瓶で飼うなど聞いた事がないし、果たして菌床瓶の中でも生きていられるのかが心配であったので、私は激しく拒否し、そのカブト5号を勝手に持ち帰ると、翌日ポール鈴木氏はカブト6号を持ってきて無謀にもその菌床瓶の中に投入してしまった。 その900ccの菌床瓶は鳳凰茸と名づけられ、表面が真っ白で激しくきのこの根が生えていた。同氏曰くこの菌床瓶はさる有名な業者から取り寄せた再高級の菌床瓶で2、000円もしたとのことである。初めて菌床瓶というものをじっくりと見たが、鈴木氏が「最高級」とうそぶくほどの物とは思えなかった。きのこの根が瓶じゅうにのたうち回っており、本当にこれが幼虫にいいのか心配であった。 数日後、幼虫がその半透明のプラ瓶の隙間から見えたときはほっとしたが、ある日を境に、姿が見えないので心配になってしまい、「雑菌が入るので決して開けてはいけない」とポール鈴木氏には言われていたが蓋を開けてしまった。なんと幼虫は蓋の真下に丸くなって寝転がっていた。温度が高すぎるのか、菌床が口に合わないのか幼虫はほとんど潜る事はなく、蓋の下に寝転がってばかりいた。このままではいけないと思い鈴木氏の反対を押し切り、昆虫飼料研究所のマット入り瓶に移し替える事とした。 その菌床瓶を掘り返してみたが、スポンジ状態の固い菌床が瓶全体の60%近くを占めており、木屑らしきものも粒が粗く、どう見てもクヌギではないようであった。鈴木氏にこの菌床瓶の出所を激しく問いただしたところ、クワガタ専門業者ではなく、名もない田舎のきのこ栽培農園とのことであった。クワガタ飼育本の伝言板で紹介されていた「きのこ専門農園の菌床瓶が幼虫に最適かもしれない」との噂話をうのみにして、菌床専門(きのこ専門)業者製造の菌床瓶が最高級品と勘違いして10本もまとめ買いしたとの事である。そのきのこ栽培農園では木屑の成分についても企業秘密であるとして公開せず、よく見てみたらぐんぐんときのこは成長し、とてもおいしそうであった。まさに、きのこを栽培するための菌床瓶であり、幼虫用では決してなかった。 ポール鈴木氏にこの話をして、現在この菌床瓶の中に入っている全ての幼虫を救出する事を提案した。同氏によるとこの菌床瓶に入った幼虫は最近全く姿を見せないという。もしかしたらきのこの養分になってしまったのか。 ポール鈴木氏はこの最高級と思い込んでいた菌床瓶の中に、自分の幼虫のなかでもっとも大事な、台湾オオクワ、大王ヒラタ、国産オオクワなどを入れていたらしいので、顔が蒼ざめていた。 早速、二人でワクワクランドに走り、急いで別の菌床瓶を買って鈴木邸にてその不明瞭な菌床瓶を掘り出してみた。なんと全ての幼虫がかなり大きく成長していた(もしかしたら幼虫によいのかも、少なくともクワガタには)。しかし、菌床は瓶の70%ぐらいに充満していたので幼虫はいまにも巻かれそうになっていたのでちょうどいい替え時であったかもしれない。 その瓶替えのときに鈴木氏は子供のように台湾オオクワと日本産オオクワの大きさを見比べようとして並べたが、そのうちにどっちが台湾オオクワかわからなくなってしまった…。 はたしたこの世にこの2匹を見分ける方法があるのでしょうか。 |

会社での飼育風景
|
4月14日 ポール鈴木氏の激しい薦めにより、クワガタ虫にも手を広げようと考えていた。そこで彼が最も愛している大王ヒラタクワガタを買ってみようと思った。 去年の2月頃、鈴木氏はある業者から計4万円で大王ヒラタクワガタ幼虫ペア(♂・♀)を購入し、5月ごろ羽化した。初めて羽化した巨大クワガタに鈴木氏は歓喜し、どうしてもすぐに触ってみたくなってしまったらしい。彼は羽化したてのオスの新生虫を羽化後1週間しかたっていないうちにほじくりだし、もてあそんでいた。そのうち彼の長男にも見せてやりたくなり、隣の部屋に移動しようとしたその瞬間、手足のまだ満足に機能していない78mmの新成虫は、鈴木氏の手から滑り落ち、固い床に叩き付けられてしまった。この衝撃により、まだ体の固まっていない新成虫の内臓は破裂しぶらぶらと体外に出てきてしまった。このため、羽化したての78mmの大王ヒラタはわずか1週間でその一生を終えてしまった。 自分のしたことのあまりの不用意さと愚かさに、ポール鈴木氏は激しく後悔し、なんとそのまま業者に電話し「お宅から買った大王の幼虫、羽化したと思ったら、すぐに死んでしまったよ。交換してくれますよね?」と強烈に交渉したらしい。もちろん業者には激しく断絶され「じゃーそのかわり新成虫はどうですか、安くしておきますよ」と逆にオファーされ、普通ならそこであきらめるが、「大王ヒラタの83mmの新成虫がいますが、今回のこともあるし、特別に5万円でいいですよ」と言われ、「3万円なら…。」と応えたらしい。常人であるなら5万円と聞いただけで電話を叩き切るが、鈴木氏は3万円でその83mmのオスの新成虫を奥さんには内緒でカードで買ってしまった。なぜそこまでするのか常人には理解できないが、それがマニアなのかもしれない。その後、この83mmの成虫は何日間生きたと御想像なさるだろうか? 答えは10日間である。 その元気な成虫は1日中狭いケース(中プラケ)の中を動き回り、9日目のある日、上部の蓋に大顎を突き刺し、破ろうと試みているうちに顎が外れなくなり、そのまま宙ずりになってしまった。その状態に、不覚にもポール鈴木氏は全く気付かず、激しくじたばたしているうちに成虫は体力を消耗し、ついには力尽き、生き絶えてしまった。酔っ払って帰ってきた鈴木氏が発見した時には、すでに事切れており、そのまま彼はまたもや業者にクレームの電話をしたが、やはり一蹴されてしまった。 この文章を読んだ方は、この話は嘘臭いと思っているかもしれませんが、まぎれもない事実です。また、いったいポール鈴木という人は何をしているんだと歯がゆい思いをされているかもしれませんが、ポール鈴木氏はいたって真剣にクワガタに取り組んでいます。 幸いこの短い10日間のうちにペアリングには成功し、メスの大王ヒラタが卵を生んだ。死んだ83mmオス成虫は太く短く生きた。 大王ヒラタの幼虫は20匹ほど生まれ、そのうち4匹だけを残し、10頭を里子に出したり交換した後、残りの6頭はある業者に1匹1000円で売却してしまった。4匹もいれば十分だとあさはかにも思ったらしいが、その後なんと全部死んでしまったらしい…。 そこで今年の4月14日、鈴木氏が幼虫を売った業者に大王ヒラタを売って下さい(返してください?)と注文したところ、4匹合計10、000円(菌床瓶入り)で売ってくれる(返してくれる)ことになった。届いた幼虫は巨大化しており、なぜ業者にはこんなに大きく育てられて、自分のは全滅したのか不思議だと鈴木氏はぼやいた。 この業者は非常に良心的であり、1000円で鈴木氏から買った幼虫を売価900円の菌床瓶にいれて2500円で売ってくれた。つまり600円で半年間ここまで大きく育ててくれたのである。 付き合いのある業者とはいえ、この業者は本当にいい人だ。 大王ヒラタの10mm位はある巨大幼虫を手にいれ、新たな試練は続く…。 別冊 カブ馬鹿日誌 第二話 完 |