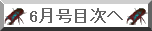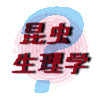 |
科学される昆虫たち! by 大外一気 第4回 消化と吸収 〜なぜマットを発酵させるのか?〜 |
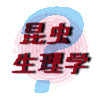 |
科学される昆虫たち! by 大外一気 第4回 消化と吸収 〜なぜマットを発酵させるのか?〜 |
|
はじめに 先日、”マットの発酵に関する議論”がまちかね掲示板でなされました。 何故マットを発酵させるのか? 何故マットを発酵させるのか?2 発酵というのは微生物の作用なのでよく解らないし、解明しようにも長い時間を必要とするし・・・という先入観たっぷりの大外はROMをきめこむことに(いつものことですが)しようと思ったのですが,えりーさんからこんなんで次回の昆虫生理学の講義はできませんか?との発言がありました. ”ええい,えりーさんのリクエストなら仕方なし”ということで快く要望を承け,知っている範囲で書くことにしました。
えりーさんが持ち出したテーマは
”クワの葉っぱを食べているカイコがどのようにして絹糸をつくるのか?”
|
|
栄養素か安定化か?
”何故マットを発酵させるのか”という、K-sugano 氏のポストに対するコメントを少しまとめてみましょう. まちかねBBS では多様ですばらしい意見がでていましたが、えりーさんがコメントしているように、 体をつくるうえでなくてはならない蛋白質、つまり窒素源は何かということが不明瞭である以上,発酵イコール栄養価の上昇という発想を支持するだけの説得力に乏しいのです。 確かに、発酵にはアミノ酸発酵や核酸発酵というものがあり、蛋白質の構成単位であるアミノ酸と遺伝情報を担う物質である核酸をつくりますので発酵後のマットにたくさん蓄積されたため栄養価が上昇すると考えることもできます。 しかし、実際にみなさんがやっておられるマット発酵というプロセスを通して,本当にマットにアミノ酸や核酸が蓄積されているでしょうか? 私がこのように思うのは、皆さんが結構いい加減に(このいい加減さが良い結果を生むとされていますよね)水やら小麦粉を入れているからです。 発酵はある一定の条件(温度、時間、栄養状態及び水分など)を満たした場合にのみ行なわれる生化学的な反応のことです。 しかし一方で、皆さんの行なっている"いい加減発酵"の条件はかなりは幅広いものと考えるのが自然ではないでしょうか? 日本の各地で、同一ではない小麦粉、マット及び水を使用しているにもかかわらず、"いい加減に"という言葉のもとに行なわれている発酵条件が偶然にも全てが至適であったと考えられますか? それゆえ,都合よく栄養価があがっているとは考えられないのです。 また,大型個体を育てることができた=マットの栄養価が上がったという考えは短絡的です. さあ,反論ばかりでは仕方ありませんので,昆虫が生命活動を展開する上で必要な蛋白を得る方法について少し考えてみましょう. それは昆虫の共生体(微生物)です。 人間にもありますし,多くの昆虫の消化管の中には共生体がいますので、クワガタの幼虫にもおそらくいると思います。 ここで,クワガタの幼虫と同じように木を食べる虫、シロアリを例にとってみましょいう。 シロアリは木をばりばり食べて下手をすると木造家屋をぼろぼろにしてしまいますが、シロアリそのものはあまり効率よく木を分解できません。 しかし、シロアリは共生体として細菌や原生動物をおなかに飼っていてそれらが上手く代謝してくれているのです。 すなわち,シロアリは木を食べますが,木を直接栄養として消化吸収するわけではないのです. シロアリが木を食べると,砕かれた木片は成分としてはほとんどそのままの状態でおなかに流れてきます。 そして,おなかの中には木を餌とする生物が住んでいてムシャムシャとそれを食べて分解してくれるのです。 すなわち,この共生体は明らかに栄養的に偏っている木から有機窒素(アミノ酸:窒素源で蛋白質のもと)を生合成してくれます。 このようにして,共生体の分解作用により生じた副産物=窒素源つまり蛋白質の素がシロアリに還元されるのです。 さらに,おなかの中にいる微生物により生合成される栄養素は窒素源のみならず、炭素源、ステロール類、ビタミンと多種多様なのです。 ここで,私が何を言いたいかというとをまとめると次のようになります。
|
|
と、つながっていくのではないかと考えます。
もう一度言い直しますと事前にマットを発酵(培養)するということは,幼虫にとって有益な細菌類をマ
ットの中に十分に増やしておくということに他ならない、ということです。
しかし、このときマットの中にクワガタ虫の幼虫が直接餌とする栄養素が蓄積する可能性は極めて少ないのではないでしょうか。 |
|
共生体の正体
まず、どうしたら手にはいるのか?
2つめの例としては、K-sugano さんマットの作り方です。
K-sugano さんはマットを作るとき幼虫の糞を溶いた水を使用するそうです。
これは幼虫の排泄した糞の中には有益な菌がいることを知っており、それらを新
しいマットに継代し,利用するということは明白であります.
次に、細菌はどんな菌?についてです.
これは非常に難しい問題です。
昆虫と細菌というこの地球上でもっとも繁栄している生物の組み合わせを論じなくてはならないし、これら2つの生物の「生物学的依存度」にもよるからです。
生物学的依存度が高いということは宿主(昆虫)と細菌の関係が非常に密接で細菌がいなければ昆虫が生きていけない状態のことを指します。
まず,可能性が膨大すぎるので組み合わせの問題はコメントのしようがありません。
しかし,依存度の違いにより細菌の種類をある程度絞り込むことができるかもしれません。
ただ,おなかの中の細菌を取り出して人工的に培養し調べることは非常に困難です.
なぜなら、関係が密接ゆえにこれらの細菌が特殊化しているからです.
簡単な例を挙げます。
映画"パラサイトイヴ"で主役となったミトコンドリアは宿主の真核細胞の中で特殊化しています。
その昔、宿主の真核細胞(の祖先)とミトコンドリア(の祖先)は別々の生き物でした。
もともと仲良くお互い共存しながら良い関係を保ってきたのですが,生活環境の変遷により、ミトコンドリアは宿主細胞の中に取り込まれ細胞のなかで生活する(共生)ようになりました。
この方が、別々に寄り添っていきるくらいならいっそのこと一緒になってしまったほうが都合がよかったのでしょう.
長い年月の中でミトコンドリアはもともと自分の持っていた情報の一部を宿主細胞に渡し(もしくは捨てて)、宿主細胞の中での役割(エネルギー産生)を担うよう機能的に特殊化しました.
その結果、ミトコンドリアと宿主細胞は切っても切れない関係になったのです。
このミトコンドリアと同じようなことが昆虫共生体にも起きており、特殊化する事で昆虫体外では生活できないように成ってしまっているのです。
すなわち、菌を取り出して培養することが難しい(出来ないかもしれない)のです。
しかし、依存度が高いゆえ、共生体の有する機能から推測することは出来ます。
また、依存度の低い菌であれば培養が可能であることから同定出来るでしょう。 |
|
消化・吸収と共生体 |
|
古いマットほど良い?
共生体が消化・吸収に直接関与するかもしれない事例をひとつあげましょう.
拒食症・・・みなさんのところでも一度くらいは経験があるのではないでしょうか?
元気に摂食,排泄をしていた幼虫が何故か元気がなくなってきて,餌を食べなくなる.
食べないどころか糞もでなくなってからだがだんだん透明になってゆく.
こうなるともうおしまいです.
ほとんどの場合,成長するどころかどんどん縮んでしまって,さいごにはひっそりと亡くなります.
この病気(?)は共生体との関係不和が原因ではないかと私は考えています.
マット交換後あるいは温度変化など環境の変化で起こるようです.
もしかしたら共生体が死滅してしまって吸収阻害をおこしているのかも知れません.
あるいは消化管に悪い菌が住み着いて,あるいは体内に入り込んで(感染して)消化阻害をおこしているのかもしれません.
人間は人間が食べる食物の消化に関わる分解酵素をほとんど持っています.
胃では消化酵素(ペプシン)が胃底腺から外分泌され,肝臓や膵臓で作られた消化酵素は十二指腸に分泌されます.しかも,我々は雑食性で肉(タンパク質,ビタミン),野菜(ビタミン,炭水化物),米(炭水化物),魚貝海藻類(タンパク質,各種ミネラル,ヨウ素)など様々な種類の食物を摂取し,タンパ
ク質はアミノ酸まで分解し,炭水化物はグルコース(糖)として小腸の粘膜から吸収します.
クワガタ虫は朽ち木しか食べれません.
肉や野菜はいうにおよばず,腐葉土,生木でもいきてゆけないのです.
このように共生体の存在はクワガタ虫のような食性の偏った生物には欠かせないものなのです. |
|
共生体と大型化 |
|
発酵マットと菌糸ビン
実はキノコと共生体の関係は、えりーさんからのリクエストなのですが、それを頂いたときは、何ともコメントしがたいブレインストーム状態でした。
”何かうまい具体例でもあればなァ”と思いながら幼虫の飼育ビンをながめていたら、あったんですよ、ヒントが。
皆さんはクワガタを飼っているときにカビやキノコが生えちゃったことありますよね。
大外のクワガタキャリアはまだ短いのですが、生えまくっています。
何だかウスキミ悪いのですが生えちゃったモノは仕方ありません。
でも、よーく見ると生えてるモノが違ったんですよ、クワガタの種類で。これは、国産同士でも見られるのですが、
国産と外産との間の方が顕著でした。
”ほほー、これなら説明がつくかな?”
|
|
と、結論する事が出来ると思います。
もしこの仮説のように関わり合いが大きいなら、理論的に菌糸ビンは効果的といえます。
事実、菌糸ビンは高い再現性でもって大きな個体を生育させる効果を示しています。
つまり菌糸ビンのなかで活きているキノコ(=真菌)は共生有用菌のひとつで,しかも消化吸収に関して重要な役割を果たしているものであると考えることはできないでしょうか?
共生体の働きは多岐にわたりますが,真菌と幼虫との関わりについては先に書きましたように、栄養学的な面が多いと思います。
ヒラタケなどのキノコの菌体そのものがクワガタ虫の共生体かどうかはまだ直接証明されたわけではありません.
キノコと同居している他の微生物かもしれません.
しかし,菌体(=餌)を食べるということではなく「活きている共生体」を取り込むということの方が積極的に重要な意味を持つという仮説はあながち間違ったものではないのではないと考えています.
なぜなら,劣化した菌床,すなわち菌が死んでしまって別の共生作用のない悪玉真菌(カビ)が生えると大抵の場合幼虫は死んでしまいます.
もし,菌糸ビンがマット中に栄養物質(菌体のタンパク質)の供給を目的とするならば,キノコそのものの生き死に関わらず,同じように大きく成長するでしょう.
さて,みなさんはどう思いますか? |
|
さいごに
それにしても実際のマット発酵の過程では一体何がおこっているのでしょう?
大外と同じ考えの方もいるかもしれません。
発酵中に栄養素が蓄積されると考える方だっています。
答えはどちらでもいいと思っています。
結論はクワガタを飼っている皆様が自らの経験の中で見いだしてください。
実験動物ではなく、系統が確立されていないクワガタで極めて精巧な再現性を追求するのは難しすぎます。
どうすれば健康なクワガタが育つか、試行錯誤してみてください。
奇形や不全による死亡を少なくし,健康なクワガタを育てることこそ大切なことと思いませんか?
発酵とは話がずれましたが大外はそう思います。 |