| ホーム > サイトマップ > 言葉 > 生き方エッセイ > 私にとっての死 |
私にとっての死
|
2006.02.22. 掲載
このページの最後へ |
目次
はじめに
死は生の終わり
望ましい死
親しい者の死、他人の死
病死、自然死
死にたくなる病気
死後の世界
自然の摂理
価値の基準
死ぬ前の苦しみ
死の儀式
死が関わる他への迷惑
あとがき
はじめに
少し前に「死期を想定して生きる」というタイトルで、私の生き方を紹介した。ここでは、死を意識するからよく生きることができる、という私の死生観を基にして、自分にとって大切な「生きる意味」「生きがい」を書いた。これを書き終えた時、私の「死」に対する気持や考え方も、世間の常識と違っているかもしれないと思った。
そこで、この機会に、今度は、「死」を中心とした私の死生観を、書いておくことにする。生き方がいろいろあるように、死に対する気持や考え方も、人それぞれで違って当然である。何が良い、どれが正しいという問題ではない。これは古希の齢となった一人の人間が、「死」をどのように思い、考えているかを書き留めたものである。
死は生の終わり
「死」について、分からないことや、分かることができないことがある。その一方で、誰にも分かることがある。その第1は「命には必ず終わりがある」ということ、第2は「命の終わる時が、いつなのかは分からない」こと、第3は「世代の交代は、人の存続に必須である」ことだ。
分からないことや、分かることができないことについて、いろいろ考えるのはその人の自由である。そのことが良く生きることに役立つのなら、望ましいかもしれない。しかし、はっきり分かることについて、それから目をそらしたり、考えようとしないのはおかしいのではないか、と私は思ってきた。
第1の「命には必ず終わりがある」ことを否定する者はいないだろう。それが分かるのは、生き物の中で、恐らく人間だけだ。この命に限りがあることに目をつぶって生きる人がいる。また、生に限りがあることを知って自暴自棄的になり、虚無的で自堕落に生きることを選ぶ人もいるだろう。しかし、多くの人は、生に限りがあることをはっきり認識すると、生きている意味を考え、生きている間を精一杯生きようと思うのではなかろうか?
第2の「命の終わる時がいつなのかは分からない」も、間違いのない事実であるが、これを認識する程度に大きな個人差がある。近親者の死を早くから多く経験した者と、その経験のない者とでは、これを実感として認識する程度がまったく異なることが多い。その一例として、私の場合、11歳の時に可愛い8歳の妹をわずか3日で亡くしたことが、人の命の明日が分からないことを、私の心に強く刻みつける結果をもたらした。いつ死ぬかが分からないことを深く認識すれば、一日一日を大切に生きようとするであろうし、生きている時間を予測して、その間に達成できる目標を立てて、その成就に努める者もいるだろう。
第3の「世代の交代は人の存続に必須である」については説明がいるかもしれない。これについては、世代の交代がなく、人類が生き続け、増え続け、高齢者が多数を占める状況を想像すれば、そのような状況では人類は滅ばざるを得ないことが、理解できるだろう。人が、ただ生きているだけでは価値は低く、思いっきり自分の命を発揮させようとする時に、価値は高まると考えるべきだろう。
2000年の日本の老年人口(65歳以上)は18%となり、年少人口(15歳未満)の15%を初めて上回った。一方、世界全体で見ると、老年人口は7%、年少人口は30%であり、日本はこどもよりも年寄りが多いという老人国に変貌してしまった。
今から60年前の平均寿命は、男50歳、女54歳であった。それが急速に伸び、2002年の平均寿命は、男78歳、女85歳、男女合わせると82歳で、いずれも世界第1位である。しかし、同じ2002年のアフリカのシエラレオーネでは34歳、レソト36歳、ジンバウエ38歳で、日本の半分にも満たない。同じ日本人でありながら、60年前には、今より30歳も平均寿命が短かった。また、同じ時を生きながら、アフリカには、日本よりも平均寿命の4〜50歳短い国がある。
人間の寿命が延びることは、それ自体価値のあることであろう。しかし、寿命が延びれば延びるほど良い、とは言えまい。命永らえたが、ただ生きているだけの状態の者が、若い者の生きることを妨げているとしたら、さらには、資源の枯渇に働き、環境を破壊し、子孫の生きる妨げになるとしたら、それは、負の価値の方が大きいと言わざるを得ないだろう。
現在に生きる人間は、自分が、自分の仲間が、自分の年代が、自分の地域が良ければ良く、後の世代や他の地域を考えない利己的な生き方をしているように思えて仕方がない。貪欲、強欲は、人間の本来持っている特性で、如何ともし難いのだろうか? この傾向が続き、増せば、いずれ人類は滅亡するかもしれないと思うのも、あながち間違いとは言えないだろう。
望ましい死
望ましい死については、人それぞれに思うことが違っていて当然であり、議論も多いことだろう。ここでは、私にとっての良き死、望ましい死を述べたい。
私は30歳頃から、死ぬ時に悔いのないように生きたいと思ってきた。悔いのない、実際的に言えば悔いの少ないというのは、精一杯生きたと同じ意味である。私の場合は、したいことを充分にしたということが、ほぼそれに相当する。
人は独りで生きていくことはできず、多くの人の恩恵を受けて生きている。だから、したいことをするには、それ相応の、しなければならないことを果たさなければならない。だから、私にとっての望ましい死は、「しなければならないことを済ませ、したいことをすることができた」と思って死ねることだ。つまり、私の死は、私の生の総括であり、望ましい死とは、望ましい生と同じことになる。
望ましい死として、苦しまずに死ねることを思う人もいるだろうが、私はそれについてほとんど気にしていない。また、人間にふさわしく死にたいという尊厳死についても、私はほとんど気にしていない。そのどちらも、「望ましい死」にとって、本質的なものではないと思えるからだ。
親しい者の死、他人の死
私が最初に「死」を強烈に体験したのは、11歳の時の8歳妹の死だった。麻疹に罹り、3日目に突然亡くなった。この頃の私はものごころがつき始め、多感であった。近親者や友人など親しい者の死は、亡くなった者と結ばれた他の人たちにも、大きな影響を与える。人は、親しい者の死を体験することで、生きる者は死ぬということと、その死がいつ訪れるか分からないことを覚り、自分の死についても考えるようになるのだろう。
それに対して、三人称の死と呼ばれる他人の死は、多くの場合客観的に受け止められ、親しい者の死のような強い衝撃や悲しみをもたらすことは少ない。私の世代までは、人の寿命が短く、多くは家庭で、親しい者の臨終に立ち会って来た。しかし、現在では、人の寿命が延びた上、家庭ではなくて、病院で死を迎えることが多くなり、昔のように死んでいく人の傍で、長い時間を過ごすことが難しくなっている。
このように、現在に生きる者は、親しい者の死を経験する機会が極端に少なくなっている。このことは、幸せに思えるかもしれないが、実際は、非常に不幸なことである。身近な死を体験して死を意識するから、良く生きようとするのであり、親しい者の死を自分の死のように受け止めるから、死ぬ準備や死ぬ覚悟ができてくるのだと思う。死を身近なものとして体験することなく、人生のある時期に突然、死と直面することになった時、人は狼狽し、不安におののかざるを得ないだろう。
私は11歳で妹の死に居合わせ、29歳で母の臨終に立ち会った。それは悲しいできごとであったが、二人の死から教えてもらったことは非常に大きかった。今は、悲しかった運命に感謝さえしている。親しい者の死が、自分の死を考える強い動機となると書いたが、「自分自身の死」というものは、直面することのできない死であり、「親しい者の死」「他人の死」を通して、類推するより仕方がない。
病死、自然死
死の原因をいろいろ分類することができるが、死亡診断書の分類に従うのが、客観的で普遍性があると考えられる。死の原因は、大きく内因死と外因死に分類される。外因死には、事故死、自殺、中毒死などが含まれ、通常の死に方ではない。だから、ほとんどの人間の死因は内因死である。内因死は、病死と自然死(老衰死)に分けられる。
老化に関係すると考えられる、悪性新生物(がん)、心疾患(心筋梗塞など)、脳血管疾患(脳卒中など)、肺炎の4疾患について、人口10万人当りの年間死亡数をグラフで表してみた。データは2004年の厚生労働省の人口動態統計を使用した。これで見ると心疾患、脳血管疾患、肺炎による死亡者数は70歳あたりから非常に急峻に増加していて、これらの疾病が老化現象、加齢現象と密接に結びついていることが分かる。心疾患と脳血管疾患は、その基礎に、加齢による動脈硬化があり、肺炎は、加齢による抵抗力の低下がその基礎にある。悪性新生物も、60歳頃から急激に増加していて、老化現象と密接に結びついていることが分かるが、その増加のカーブは、心疾患、脳血管疾患、肺炎よりややゆるやかで、老化以外の因子も関係していることが推測される。
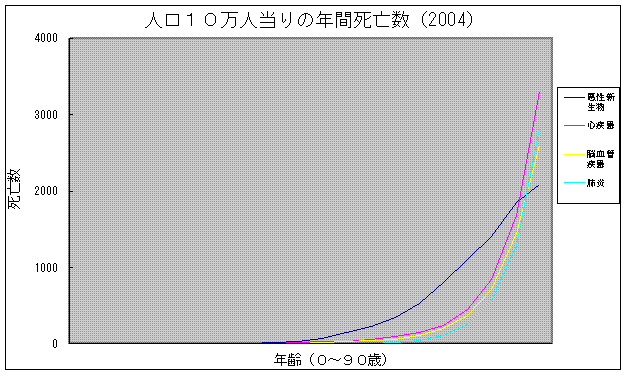
厚生労働省人口動態統計によると、下表のように、老化に関係する5死因の割合が50年ほどの間で急速に増加し、1955年に54%だったのが、2004年では71%を占めるまでに至っている。その理由は、平均寿命が男は15歳、女は18歳も延びたことによる。老衰死(自然死)が11%から2%に減少したことは、医学の進歩により、かっては、老衰死とされていた症例に対して、疾病の診断がつけられるようになったためと考えられる。
| 1955年 | 2000年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|
| 死亡者総数 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 悪性新生物 | 11.2% | 30.7% | 31.1% |
| 心疾患 | 7.8% | 15.3% | 15.5% |
| 脳血管疾患 | 17.5% | 13.8% | 12.5% |
| 肺炎 | 6.2% | 9.0% | 9.3% |
| 老衰 | 11.2% | 2.3% | 2.3% |
| (小計) | 53.9% | 71.1% | 70.7% |
| 平均寿命 男 | 64歳 | 78歳 | 79歳 |
| 平均寿命 女 | 68歳 | 85歳 | 86歳 |
死因のほぼ7割が、老化現象に大きく関係している病気であるということは、5〜60年前までは老衰死(自然死)とされていたものが、多く含まれていると考えて良いだろう。つまり、青年や壮年の死因となる病気と老年のそれとでは、病名は同じだとしても、内容はかなり異なり、老年の病死は自然死(老衰死)の要素が大きいと考えられる。悪性新生物(がん)についても、幼年・青年・壮年の場合と老年とでは、その経過がかなり違うが、これにも老化現象という要素が加わっていると考えられる。
死にたくなる病気
厚生労働省の2004年の人口動態統計によれば、外因死の一つである「不慮の事故死」は、死因の第5位で3.7%、「自殺」は第6位で2.9%、3万人が亡くなっている。「自殺」というのは、私の単純な「価値の基準=生命の発揮」からも、また、おそらくは、世の中のあらゆる宗教、倫理、哲学からも、肯定されるものではあるまい。
しかし、これが病気であるとしたら、そして多くは治すことができるとしたら、この病気による死は、悪性新生物や心疾患による病死と変わることはない。自殺の原因の大部分が「うつ病」であり、誰もが「うつ病」になる可能性があり、多くは薬剤により治る病気であることが分かった現在、これを外因死とするよりも、内因死である病死に分類すべきだろう。また、「自殺」という罪の意識を持たせる用語を改め、「自死」とすべきではなかろうか?
私のこころに残る最初の「自殺」は、高校3年のときの通学友達の死だった。「忘れな草をあなたに」の歌を愛した弟の友人が、それに続いた。そして、開業する前の年に、学生時代からの親友がこの世を去った。今、彼が生きていたらどんなに楽しいだろうと思うことがある。何かにつけ、彼と過ごした日々を思い出す。彼は私の記憶の中にずっと生きている。開業して間もなく、若い女性が同じ病気で亡くなり、ショックを受けた。その頃から「うつ病」の病態や治療法の解明がどんどん進み、治療薬はめざましい進歩を遂げて来た。今では「自殺」の90%は、防ぐことができるとまで言われている。
死後の世界
「生あるものは必ず死ぬ」ことについては誰もが知っている。しかし、「死んだらどうなるか、どこへ行くのか、まったく無になるのか」ということは、人間にとって最大の関心ごとでありながら、誰も知らない、というより知ることができない。それは、自分で経験できないことであり、いくら考えても分からないことだからである。自然科学の発展は目覚しいが、死後の世界については教えてくれない。それでも、人間は、古今東西、死後の世界についていろいろ考え、そこから多くの哲学や宗教が生まれた。
それを私なりにまとめてみると、1)死んだ後も何かにかたちを変えて残ると思うか、2)無になると思うかに大別される。その内で、無になると思う人は少数だろう。何にかたちを変えるかについては、人間とか人間にに近いもの、動物、自然、霊魂、生きている者の記憶、などいろいろある。また、そのかたちを変えたものが、どこへ行くかについてもいろいろあり、来世、天国、極楽、極楽浄土、冥土、地獄、煉獄や、宇宙に帰る、自然に帰る、風になる、星になる、生きている者の記憶の中に留まるなどのことばが、それを表している。
それらについて、本当はいくら考えても分からないことだから、自分が良く生きて、安らかに死を迎えることの支えとなるものがあれば、自分の好みで選べば良い。それは真理ではなく、信じるより仕方がないことである。優れた宗教は、多くの人の「良く生き、良く死ぬ」こと、つまりは「生命の発揮」を助けることに役立つのだと思う。
BC3500年のエジプトの時代から、現代に至るまで、全世界に来世信仰があったことは知っている。また、ゆるぎない来世信仰を持っている人は、死に臨んでも見事に生き切ることが多いことも知っている。そういう意味で、来世信仰を持つことができる人は、幸せだと思う。来世信仰は、その人の生命を精一杯発揮させることに有効である場合には、価値があると思う。
しかし、私には来世信仰はない。来世を信じられないし、必要ではない。「諸行無常の法則」「万物流転の法則」にしたがって、生まれ、生き、死んで行く。生きている間に生命を精一杯発揮させる。それ以上を望まないし、望むものではないと思っている。このような人間は、変わり者かもしれない。
私は「しなければならないことを済まし、したいことをしてきた」と思って死ねたら言うことはない。それが自然の理に適っていると思って、ためらうことなく、死を受容するだろう。しかし、これもまた信仰である。私には死ねば無になるという考え方が一番納得できるが、それにこだわるわけではない。高村光太郎の「死ねば死にきり」、あるいは良寛の「死ぬ時節には死ぬがよく候」のように、自然に任せるのが、自分にはよく合っている。その上で、短い間でも、「生きている者の記憶に留まる」ことがあれば嬉しい。
ここで、臨死体験についても触れておく。数年前にTVなどのマスコミで臨死体験が報道され、書物も出版されて話題になったことがあった。私は病院勤務中、二人の患者に対して蘇生術で生き返った直後に尋ねてみたが、眠りから覚めたのと同じで何も覚えていないとの答えが返ってきた。遊泳中溺死しかけた哲学者吉本隆明さんは、「遺書」という著書の中で、自分の臨死体験について、「残念ながら、期待したような体験はまったくありませんでした」と書いている。また、くも膜下出血で「死のリハーサル」を行なう羽目になった、作家の服部眞澄さんは、「何も見ず、何も聞かず、一切が無だった」と読売新聞に書いていた。
そこから考えて、臨死体験というのは、生命がかろうじて保たれている状態の脳が作り出す、夢のようなものではないかと考える。人間の五感の中で一番最後まで残るのが聴覚であることが分かっている。そうすると、耳から入ってくる情報を基にして、脳が夢、幻を作り出していると考えれば、蘇生された人の中の、ごく限られた人にしか、臨死体験がないことの説明がつく。
自然の摂理
私の母は、妹が麻疹で突然亡くなって間もなく肺結核となり、18年間の療養生活の後に亡くなった。最後の2〜3年は息切れが激しく、ほとんど寝たきりだった。そのような状態でありながら、愚痴や不安をもらさず、家族の中で一番明るくふるまい、讃美歌を歌ってくれと私に頼むのだった。私が母に教えられた一番大きなことは、人生の最後をどのように過ごすかと言うことだったと思う。
母は結婚する前に洗礼を受けていたので、神を信じない私のことを恐いと言った。確かに私は、今も宗教が言う神を信じることができない。そう言う意味では、無宗教であるが、宇宙自然の根源にあるものの存在、自然の摂理、を常に感じている。生きる価値の基準を「生命の発揮」とするのも、自然の摂理の中の一つと考えるからで、この自然の摂理を神と呼ぶのなら、私にも神はある。
価値の基準
20代半ばの頃、「人間は、何を価値判断のよりどころにすればよいのか?」という問いが頭から離れず、考え続けたことがあった。これが分からなければ、生きる意味が分からないと思った。ある時、生き物が与えられた命を精一杯発揮して生きること、「生命の発揮」を、生きる価値の基準と考えると、これまで漠然と自分の頭にあった生きる価値を、体系的に説明することができるという考えが閃いた。
満足できる答えを得た私は、嬉しくなって、それ以上考えることを止めたが、「価値の基準=生命の発揮」は、そのまま私の頭に居座り続けてきた。自然の摂理と思うものの一つが、この「生命の発揮」である。「価値の基準=生命の発揮」に理由はなく、公理であり、直感であり、信仰である。これは私にとっての価値の基準であって、声高に他人に勧める気持はないが、普遍性はあると思っている。
個人の「生命の発揮」は価値があるが、共に生きる者の「生命の発揮」に役立つことも、また、あとから生まれてくる人間の「生命の発揮」にプラスに働くことも、同様に価値がある。逆に、共に生きる者の「生命の発揮」を妨げたり、あとから生まれて来る者の「生命の発揮」にマイナスに働くことは、負の価値があることになる。正の価値を善とすれば、負の価値は悪である。
このように単純に考えれば、何も問題はないが、実際は正の価値のあるものが、他には負の価値を持つことがあり、負の価値も他に対しては正の価値を持つことがあるなど、簡単ではない。それでも、このような価値の基準を持つことができたことは、私とって幸いであった。
死ぬ前の苦しみ
多くの人は「死」を恐く思うようだ。その理由の一つが、死ぬ時に苦しむのではないかという肉体的苦痛で、もう一つが、死後の世界に対する精神的な不安であろう。死後の世界については分からないことなので、何も言えないが、死ぬ際の肉体的苦痛については、43年間を医師として生きてきたので、知っていることを伝えたい。
死の現場を知らない者の中には、人は死ぬ時に悶え苦しみ七転八倒する、などと思い込んでいる者もいるようだ。しかし、そのような死に方は極めて稀である。私は3人の肉親の死、開業してからは155人の死に立ち会った。勤務医時代にも3〜40名の死亡現場に立ち会っている。
その中で、苦しみ悶えて死んだ人は極めてわずかであり、ほとんどが安らかな死か、あっけない死、あるいは、朝起きたら亡くなっていたなどだった。不慮の事故、殺人、拷問死などでは断末魔の苦しみを見せることもあるだろうが、通常の病死や老衰による自然死などでは、苦しみを伴うことは極めて少ない。また高齢者であればあるほど、穏やかに死を迎えるようだ。死亡診断書を書いた155名の平均年齢は79歳だったが、ほとんどが安らかな死であった。老人では心筋梗塞であっても、強烈な痛みがなく、心電図や血液検査の結果で、心筋梗塞だったと分かることも珍しくはない。老人の病死には、老衰死の要素が大きく関わっていることも影響しているのだろう。
勤務医時代には、疼痛に苦しむ肺癌末期の患者を見たことがあるが、それは30年以上前のことで、現在ではWHO方式癌性疼痛治療法が普及し、疼痛緩和ケアが広く行なわれ始めている。だから、苦しみながら死ぬということは非常に少なくなっている。
死の儀式
死にまつわる葬儀などの一連の儀式や墓は、残された者の問題であると私は思う。私が死んだ場合、故人の私が望んでいたように行いたいが、それが分からなくて困るというのであれば、プランを組み立てるのは好きだから、書き残しておいても良い。しかし、死んでしまえば、そのようなことはどちらでも良く、残った者のしたいようにしてもらって、まったく構わない。ただし、そのことが、他の人の「生命の発揮」にとって大きくマイナスに働くようなこと、例えば極寒の外気の中、炎天下での長時間の葬儀などは、避けるべきだと思う。
死が関わる他への迷惑
人が死ぬと、そこから発生する死後処理や手続き、そのほか諸々の面倒が生じる。人は独りでは生きることはできず、多くの人の助け合いの中で生きている。だから、生の終わりである死も同じで、多くの人の助け合いの中で死んで行くより仕方がない。生きている者は、それを義務として引き受けなければならないと思う。
また、死んだ人がどのような生き方をしてきたとしても、生きてきたということだけの価値はあり、どのような死者に対しても、生きてきた価値を認めなければならないと思う。死んだ人を非難し貶めることは、「生命の発揮」という価値に対する冒涜であると私は思う。「生き恥かいても死に恥さらすな」ということばがある。これは、生きている者に対しては、良い生き方を助ける価値があるかもしれない。しかし、死者に対して「死に恥をさらした」と非難するのは、何の価値もなく、逆に、死者が生きてきた価値を否定していることになる。死者を冒涜する者に組することを私はしない。
あとがき
今から3年前に、「心に生きることば」のタイトルで、自分の心に残って生きていることばをまとめ、Webサイトに掲示した。それは全部で442篇という膨大なものになってしまった。その内の第9章:価値の中で「生」に連なることばを紹介したが、「生」を中心とした私の死生観をまとめ直して、「死期を想定して生きる」のタイトルでWebサイトに掲載した。
また、「心に生きることば」の第8章:運命の中で「死」に関することばを紹介したが、今回は、「死」を中心とした死生観を、「私にとっての死」というタイトルでまとめてみた。この二つを以て死生観シリーズを終えることにする。古希の男の死生観だから、もう大きく変わることはあるまい。
<2006.2.22.>
| ホーム > サイトマップ > 言葉 > 生き方エッセイ > 私にとっての死 このページのトップへ |