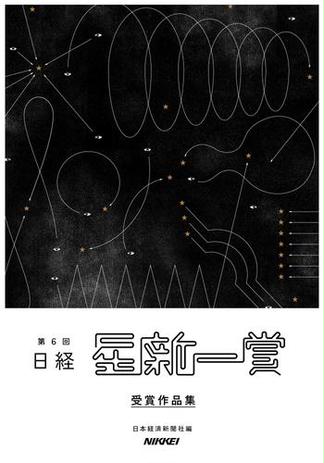内 輪 第343回
大野万紀
映画「移動都市 モータル・エンジン」を見ました。
原作はフィリップ・リーヴの『移動都市』ですね。読んだのはずいぶん前なので、ストーリーはおぼろげにしか覚えていなかったのですが、映画はハラハラドキドキのサスペンスとアクション満載で楽しめました。ただ面白かったけれど、本来の移動都市の面白さは最初の方に少し出てきただけで、以後はまるでデススターによる惑星破壊をいかに止めるかみたいな、悪の移動都市ロンドンと善の反移動都市同盟みたいな構図となっていました。原作では超凶悪なヒロインのへスターが、何か大人しい、普通のヒロインみたいだったし。移動都市そのものよりも、様々な形の飛行機械が活躍するのが良くて。そっちの描写の方が生き生きとしていたように思います。
編集後記でも書きましたが、ヴォンダ・マッキンタイアが亡くなりました。ぼくにとってとても大事な作家の一人でした。ハヤカワ版の『夢の蛇』に書いたぼくの解説はここにあります。
それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。
 『セミオーシス』 スー・バーク ハヤカワ文庫SF
『セミオーシス』 スー・バーク ハヤカワ文庫SF
アメリカでスペイン文学を翻訳している作者の、2018年に出たばかりの第一長編である。帯に「惑星植民者と知性を持つ植物との、7世代100年にわたるファーストコンタクト年代記」とあり、100年にわたるファーストコンタクトって、どういうの? と思ったが、まあ確かにそういう話だった。
環境破壊と不平等のはびこる地球を逃れて、惑星パックスに移住した理想主義的な数十人の人々の、小規模なコロニーが、やがてテクノロジーを失い、活動方針や世代間の対立を引き起こしながら、この地の生態系の中で生き延びていこうとする物語である。各章で話者の世代が異なる年代記ものなのだが、本書の半分以上を占める第4章から終章までは、コロニー最大の危機をめぐる連続した一つの物語となっている。
本書では惑星パックスの植物が大きな役割を果たしている。特に「竹」と呼ばれる植物は、明らかに知性をもっているのだ。100年にわたるファーストコンタクトというのは、人々がその知性に気づき、敵か味方かわからないが、とにかく意思疎通のできる相手として対することができるようになるまでのことを示している。
そしてもうひとつ、この惑星には人類より先に宇宙から来た〈ガラスメーカー〉と名付けられた別の異星人の遺跡がある。彼らは滅んでしまったのか、まだどこかに生き残っているのか。
各章はそれぞれ観点も異なり、スタイルも違っていて(ミステリ仕立ての章もある)、それがなかなか面白い。理想と現実との乖離がひとつのテーマとなっているが、そこを少しでも理想の側に近づけたいという描き方には好感がもてる。とはいえ、異星の知性体の描き方があまりにもステレオタイプに擬人化されていて、それはそういう小説なのだと思って読む必要があるだろう。
舞台が異星で、相手は植物だったり昆虫的なやつだったりするのだけれど、物語のスタイルは、これはもう大航海時代の異民族との接触や、開拓初期の時代のアメリカ植民地を描いた作品のようにしか読めない。また「竹」が生態系へのコミュニケーションに化学物質を使うのだが、それをいちいち人間の化学用語で語るのにも違和感がある。まあそれはそれとして、特に後半は、いかにもステレオタイプではあるが、緊迫感と迫力があって面白く読めた。きっとこの続きもあるんだろうなあ。
 『東京の子』 藤井太洋 角川書店
『東京の子』 藤井太洋 角川書店
これはかっこいい小説だ。
2023年の東京のストリートを、鍛えられた少年の肉体が、パルクールの超絶な技を駆使して疾走し、宙を舞う。そのスピード感。リングもなく競技場もなくルールもなく、スポーツというより個人のパフォーマンスの世界(後でそれがパフォーマンスだけでないことが示されるのだが)。都会の道路や壁や、建築のインフラがクールな舞台となって、そこにただ筋肉と神経だけの、華麗すぎてほとんどわからないほどの技が炸裂する。街の中を駆け抜け、宙を跳ぶ。格闘技じゃないから相手はいらない。ただ都会の無機的なインフラを相手に自分自身を向かわせるのだ。
正直言ってこの本を読むまでパルクールという言葉は知らなかった。でもYouTubeで動画は見たことがあった。とても危険でとてもかっこいい技。本書はまず第一に、そのパルクールを見せ場とした小説である。いやもうこのかっこよさはぜひ映像化してほしいなあ。この目くるめくスピード感を、ぜひ味わって欲しい。
そしてもちろん、作者の得意とする、近未来(というか東京オリンピック後の、すぐ明日の)日本、変貌する東京の姿を想像し、描こうとするSF小説である。それは「今」の延長線上にあるものだが、「今」とは大きく変わっていく、変わらざるを得ない社会の姿なのである。
ひとつは移民により多民族社会となった東京。そしてもうひとつは人々の働き方を大きく変えてしまうかも知れない産学協同の「理想の大学校」の姿。さらにもうひとついうなら、様々な理由で「過去」を捨てた人々が、それが何であれ、新しい未来へと向かって生きていく姿である。
主人公はかつてパルクールのパフォーマンスで世界から「東京の子」と呼ばれていたが、15歳で引退し、今は名前を変えて何でも屋として働く青年、船津怜。彼は、博士号をもちながら東京のベトナム料理屋で働いていたベトナム人の女性、ファム・チ=リンの捜索を依頼され、オリンピック跡地に建てられた「理想の大学校」東京デュアルの内部へと入り込んでいく。
この東京デュアル(のシステム)が本書のもうひとつの主役といっていい。形としては職業に直結する知識を教える職業訓練校(ポリテクニック)であり、広大なキャンパスの中で学生が働く職場であり(学生ながら各種企業に雇用されてOJTを受ける)、彼ら数万人(将来は数十万人)がその中で暮らすひとつの街であり、日本の法律が一部適用除外される特区である。こんな形で実現するかどうかはともかく、確かにあり得る学習と働き方の現実的なモデルであり、国内法との齟齬が本当に調整できるのなら、将来実現するものかも知れない。だがそこには危うさもあり、矛盾もある。
本書に登場する人々は基本的に悪意のない(ちょっと拗れた者もいるが)善意の人たちばかりなので、この矛盾は本書の中では前向きに解消されるのだけれど、そこに悪意や政治的思惑やらが入ってくれば、とんでもないことになりかねない。トップダウンに設計された理想を目指すシステムは、悪意ある運用によって硬直したディストピアの装置となる。もっとボトムアップで多様な、柔軟性と冗長性のある制度設計が必要なのだ。確かに社会は変わらなければいけないし、いつまでも過去のやり方を良しとするわれわれの保守性も乗り越えられねばならない。でも、それがトップダウンな制度改革によってなされるのなら、それは本質的には何も変わらないままとなってしまうのではないだろうか。
本書では、その矛盾を突く形で、大学の労組(やってることは普通の自治会みたい)に、外部からの侵入がある。学内の労働者=学生に大規模なストライキがオルグされるのだ。そんな一点突破によって揺るがされるのも、このシステムに脆弱性があるからだといえるだろう。主人公もそれに巻き込まれていく。しかし主人公は別の原理によって自立しているので、簡単に揺るがされることはない。その原理とは作者がこれまでも描き続けてきた、日本という国を超える、多様な階層、多様な民族、多様な出自の中で共生していく知恵、その中で自己を確立していくための原理である。それが本書のもうひとつの柱、多民族共生社会としての日本の姿である。
本書のキャラクターたちはみんな魅力的だが、その中で、ぼくが一番とまどったのは、東京デュアルの学長である三橋である。善意の理想家のようでもあるが、決してそれだけではないはずだ。従来の日本社会と対立するような特区を国の戦略と共同歩調で作り上げてきた男なのだから。でもその裏の姿が見えてこない。うっかりたらし込まれそうになるではないか。きっと超やばいヤツに違いないのに。
 『日本人の起源 人類誕生から縄文・弥生へ』 中橋孝博 講談社学術文庫
『日本人の起源 人類誕生から縄文・弥生へ』 中橋孝博 講談社学術文庫
2005年に出た本の文庫改訂版。遺跡から出た骨(縄文時代なら化石とはいわないんだろうな)の研究やDNA分析などから、日本人はどこから来たのかという謎を人類学の立場から解き明かそうとする本である。
一般向けなのでそんなに難しくはなく、研究史の部分も面白い。あの旧石器捏造事件がどれだけ大きなインパクトを与えたか、そして近年の弥生時代の開始年代の見直しがどれほどの影響があるか(まだ決着はしていないようだが)についても大きく扱われている。
日本人(これは日本列島に定住している人という意味で、もちろん「日本」人のことではない)の歴史を探りながらも、大きく人類全体の起源と進化についても一章がさかれていて、他の本で読んだ内容とも重複するのだけれど、ホモサピエンスについて、アフリカ単一起源とは異なる視点が重視されている。
日本列島の人々については、様々なデータから、縄文人と呼ばれる人々が現代日本人や近隣諸国の人々とはかなりかけ離れた特徴を持っていたことが示される。それと弥生人との対比で、渡来があったことは明らかなのだが、それがどのくらいの規模だったかについては論争があり、どうやら渡来はあったが、置き換わってしまうような規模ではなかったということのようだ。
後半で、文化的な影響が骨の形質にも大きな違いをもたらすことが書かれている。明治以後のことを考えれば明らかだが、とりわけ中世の、鎌倉時代の人骨が他の時代と比べても異常だという話は面白かった。
もっとも著者はこれが結論というように決めつけてはいない。そこは科学者として、まだ決定的な証拠が掘り出されるまでは保留としているところが多い。というのも弥生時代は骨が残りにくく、また宇宙線の影響などから放射線による年代決定がとても難しい時代なのだそうだ。これはタイムマシンが必要だなあ。
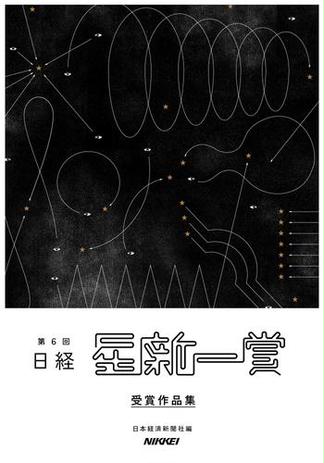 『第六回 日経星新一賞受賞作品集』 日本経済新聞社編 日本経済新聞社
『第六回 日経星新一賞受賞作品集』 日本経済新聞社編 日本経済新聞社
2018年度の星新一賞の受賞作を集めた電子書籍である。一般部門のグランプリと優秀賞、ジュニア部門のグランプリ、準グランプリと優秀賞、学生部門のグランプリ、準グランプリと優秀賞の、計15編が収録され、それに選者の評がついている。
一般部門のグランプリ(星新一賞)は梅津高重「SING X(シンクロ)レインボー」。人間の意識を失わせる眠り草によって世界は崩壊の瀬戸際にある。そんな中で人々は小さな村に分散し、たまたま生き残っていた衛星に搭載されたスマホの音ゲーを使って、コミュニケーションの手段としている。このスマホのしょーもない音ゲーにいかに通信文をエンコードし、その情報がどのように世界をつなぐかというディテールが描かれていて、なるほどこれはこの賞にふさわしい、技術者らしくユニークな作品だと思った。その昔、出てきたばかりの貧弱なマイコンでプログラムに知恵を絞っていたころのことを思い出した。
優秀賞は安野貴博「コンティニュアス・インテグレーション」。未来の冬季オリンピックと、仮想現実を使っての選手強化を扱っているのだけれど、それ自体は特別目新しくはなく、テーマもティプトリーまでさかのぼるものだといえる。でも切り口が素晴らしく、これは傑作だ。現実と仮想現実の乖離を描く話は数あれど、このような観点から心にずっしりと響く物語を描いて見せたのは称賛に値する。とても新人とは思えない完成度だ。CIで選手強化というのはちょっと無理があると感じたが、まあ許容範囲。
優秀賞は他にも、寿司職人と科学の結合を絶妙な江戸っ子の語り口で語った竹内正人「KANIKAMA」、宇宙から来た脂肪を食べる細菌による騒動を描く揚羽はな「Meteobacteria」、希望条件を聞かずにビッグデータによるマッチングで結婚相手を紹介するサービスの顛末を語る神谷敦史「アルティメットパッション」、体に取り付けて健康状態を報告する装置がかえって混乱を引き起こすマウチ「不安」、巣から落ちたツバメとAIでコミュニケーションを取るという代哲安「ピピの物語」がある。この中では「ピピの物語」が可愛らしくて良かったが、選評にもあるとおり、後半がもう一つ。やはり「コンティニュアス・インテグレーション」が抜きんでている。グランプリも個人的には好きな作品ではあるのだが。
中学生と小学生が中心のジュニア部門。グランプリは中学生の岩井太佑「クローン」。キリストやブッダのクローンが作られて、というコミカルなショートショートだ。
準グランプリのこれまた中学生岡本優美「ゆりちゃんの友達」は、人と接するのが苦手な小学生の女の子にお父さんが、人形にかけると心が生じて友達になってくれるという香水をくれるのだが……という話。一見可愛らしいお話なのだが、よく考えると実に恐ろしいという傑作だ。こちらがグランプリでも良かったのではないかと思う。
優秀賞は小学生の奏太郎「決められた未来」。これもよく出来た話で、優秀な人材のクローンとして生まれた少年が、求められるオリジナルの才能を開花させられなくて……というお話。これまた選者の多くが言っているように、よけいなオチさえなければ傑作だった。本人としてはこのオチでつじつまも合って決まった、と思ったんだろうな。
こちらも優秀賞の山沢智知「商店街に挟まった日」は言葉を話す巨大な兎が商店街に挟まっていたという奇想天外なお話。オチはもう一つだが、語り口がとてもいい。
優秀賞はもう一編、岡田萌花「素晴らしきAI社会」。AIが人間の蘇生術を発明し、善意からそれを使うというショートショート。ある意味すごくストレートで、ジュニアだから書ける作品かも知れない。
大学、高専、専門学校の学生による学生部門。グランプリは藤田健太郎「創訳する少女」で、これも素晴らしく完成度の高い傑作だ。日本で育ったクローンの少女とそのオリジナルの米国人の女性が、単なる翻訳機ではなく、心の動きを解釈して〈創訳〉してくれる機械を通じ、会話する。そこから言語、コミュニケーション、意識と情動の問題を、わかりやすく浮き彫りにしていく。
準グランプリは大貫瑠香「ゼロ体温とオリーブオイル」。大阪弁をしゃべる冷蔵庫と一人暮らしの女性とのかけあい漫才から、ほろりとする機械と人間の恋愛ものになる。
優秀賞は関﨑歩「良心の種」。良心の種を植え付け、発芽するとその人は犯罪を犯さない。だが主人公の少年はそれがなぜか発芽しなかった、というところから始まる物語。ディストピアへの道は善意からできているのだなあと思わせる。
全体に多少の出来不出来はあるが、年間傑作選級の作品が何編もあり、非常にレベルが高い作品集だった。
 『生まれ変わり』 ケン・リュウ 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ
『生まれ変わり』 ケン・リュウ 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ
『紙の動物園』『母の記憶に』に続くケン・リュウの日本オリジナル短篇集。2002年の商業誌デビュー作「カルタゴの薔薇」も含まれているが、主に2011年から2018年の最新作まで、20編が収録されている。
表題柞「生まれ変わり」は傑作。異星人に占領された地球が舞台だが、この異星人の考えでは人の意識とは唯一のものではなく、複数の自分が混在している。だから罪を犯した人間は、その罪を犯した自分のみを消去して新しい自分として生まれ変わらせることができる。とはいうものの……という話。主人公は異星人と結婚しており、その性生活まで描かれるのが面白い。
「介護士」はちょっと変わった介護ロボットの話……というか、やはり現代の社会問題とリンクしていて、とても切ない気分になる。
「ランニング・シューズ」は短いが、劣悪な環境の工場でランニング・シューズを作っていた少女の見るファンタジー。これまた重いテーマを見つめる作者の目に優しさがある。
うって変わって楽しいのが「化学調味料ゴーレム」。はるか昔にユダヤ人の御先祖様がいたという中国人の少女が、宇宙船の中で神の声を聞き、ゴーレムを使ったネズミ退治を命じられる。彼女が頭のいい現代っ子で、すべてがアメリカのコメディ番組のようになってしまう。つまり裏で観客の笑い声が聞こえるような。でもウィットが効いていて面白い。
「ホモ・フローレシエンシス」はインドネシアで古人類の化石を巡り、現地の人間の価値観とアメリカ人の科学者の価値観がぶつかる。分断とコレクトネス。そして科学者は、発見された未知の人類に対し、より重い決断を迫られることになる。
「訪問者」もファーストコンタクトの話。しかし異星人は姿を表さず、ただ無数の探査機が人々の生活をじっと観察するばかり。他者の目があることにより、人間性は変わるものなのか。
「悪疫」はショートショートだが、悪疫にさらされ、ドームの中でしか生きられなくなった人々と、外の世界で生き残った人々の、互いに理解されることのない関係が描かれる。
「生きている本の起源に関する、短くて不確かだが本当の話」という長いタイトルの短篇は、本と読書についての寓話かと思いきや、自動生成される物語についてのわりとリアルな問題意識がテーマとなっている。でもそれだけではなく、読書というものの本質についても触れられている。ちょっと円城塔。
「ペレの住民」は本格SF。地球から遠く離れた異星の惑星に降り立った宇宙飛行士たちが、奇妙で異質な生命と出会う。ケン・リュウのこういうストレートなSF作品も好きだ。
「揺り籠からの特報:隠遁者――マサチューセッツ海での四十八時間」も長いタイトルの短篇だが、温暖化で海に沈んだハーバード大学に戻ってきた、元金星出身のエグゼクティブで、今は地球を旅する著名な隠遁者の物語。彼女の行為を難民ツーリズムと非難する人々もいる。ここにも分断とコレクトネスのテーマがある。
「七度の誕生日」は遠未来へとつながる遙かな時の流れを、電脳空間にアップロードされた一個人の視点から描く、これまたぼくの好きなタイプのSFだ。壮大な物語でありながら、母と娘、家族の物語でもある。傑作。
「数えられるもの」はカントールの対角線論法が扱われ、無限の意味について語られているので、数学小説だともいえるが、むしろ対比させられる自閉症と児童虐待や家庭崩壊のテーマが重い。
「カルタゴの薔薇」は作者のデビュー作だが、意識アップロードと肉体の死、そしていわゆるクオリアの重要さというテーマがこの時からずっと絶えることなく作者の脳裏にあることがわかる。
「神々は鎖に繋がれてはいない」「神々は殺されはしない」「神々は犬死にはしない」の連作は2014年と15年に発表されたものだが、「カルタゴの薔薇」からつながっている話である。神々とはもちろんネット上にアップロードされたポストヒューマンたち。その人間との会話に絵文字を多用したチャットが使われていて、言語とコミュニケーションについても考えさせられる。とにかく神々に肉体はないのだ。人間の世界と神々の世界で、悲惨な戦いが繰り広げられるが、しかし家族の絆がここでも重要視されている。なお、原文を見ていないのでわからないが「NP-完成問題」とあるのは普通は「NP完全問題」と訳されるものだろう。
「闇に響くこだま」は太平天国の乱の上海を舞台にした短篇だが、科学的な謎解きが中心で、サイエンス・ミステリーとでもいうべき作品。ワンアイデアだが、面白い。
「ゴースト・デイズ」は24世紀の、人類とは姿形も異なったものに変異した遠い惑星の子供たちの教育風景から始まるが、そこから20世紀後半のアメリカ、20世紀始めの香港へとさかのぼっていく。それをつなぐのは古代中国で作られた青銅の布幣である。そこには過去の再帰的な積み重ねが未来を作るという考えが込められている。
「隠娘(いんじょう)」は中華ファンタジーにSF的な要素を加えたかっこいいキャラクターとアクションが魅力の傑作。唐の時代の、秘密の超能力を駆使する暗殺者となった娘が、師匠たちへの恩と正義との狭間で悩みつつ、激しい異能バトルを戦う。ケン・リュウのこの手の超人バトルものはとにかくかっこいいのだ。
本書のトリが、最新作の「ビザンチン・エンパシー」で、これは仮想通貨を武器に、ボトムアップで悲惨な境遇にある人々を救おうとする民間人と、目的は同じでも国家戦略のもとトップダウンに動こうとする公的機関のエリートとの相剋を扱った(しかも二人は友人だった)、藤井太洋を思わす、すぐそこにある未来のリアルを描いた傑作SFである。中国とミャンマーの国境付近の少数民族たちに虐殺の危機が迫る。互いに矛盾する二つのアプローチはそこで激突する。作者は結論は示さない。ただその目は銃撃に逃げ惑う人々と共にある。話は違うがたまたま今の舞台が同じなので、ぼくは志村裕吏原作のコミック「マージナル・オペレーション」を思い起こした。
さてこうして全体を見ると、ケン・リュウの一番のテーマが現代における「倫理」の問題にあるのだとわかる。そこに誰もが合意する結論はないし(そもそも多数決で決まる話ではない)、一人一人が自分の問題としてとらえ、結論を出し、その責任を引き受けなければならない。昔は「神」にその判断をまかせることができたかも知れない。そんな全能の神を信じることのできない(ローカルで限定的な、小さな神々は信じるかも知れないけど)人間には、仮想的な神々を呼び出すしかないのだろう。そんな仮想の神々がこの短篇集には数多く描かれているように思った。
THATTA 371号へ戻る
トップページへ戻る
 『セミオーシス』 スー・バーク ハヤカワ文庫SF
『セミオーシス』 スー・バーク ハヤカワ文庫SF