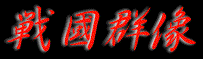186「感状ふたたび還らず」
清田正成(?―?)
岡村又兵衛。立花宗茂の家臣。はじめ大友宗麟に仕えるが、主家没落後、「大友家御客分」として宗茂に従う。慶長五年(一六〇〇)、大津城攻めで奮戦、「清田が兜割り」の異名をとり、感状を受ける。立花家改易後、肥後の加藤清正に預けられていたが、宗茂が奥羽棚倉に領地を拝領すると肥後から移った。後年、宗茂が柳川に復帰する際にも従った。
◆夜の静寂を破って、突然サイレンが鳴り響いた。西の空が真っ赤だ。
「火災発生。火災発生。建物火災。目標、清田屋敷。第一分団、第二分団、第三分団出動・・・・・・」
◆炎上する屋敷の前で、パジャマ姿の清田正成は家族や郎党に羽交い締めにされて、もがき叫んでいた。
正成「うおお。はなせェ。はなせェ! おれの感状!おれの感状が燃えるぅー!うおおー!殿からもらったカンジョーが、カンジョーがぁぁぁぁ!」
◆筑後柳川を隔てること、数百里。奥州棚倉。この地をおさめるのは前柳川侍従・立花宗茂である。関ヶ原合戦で西軍に与して、今は敗残の身をこの北国の一隅に置いている。わずか一万石とはいえ、浪人時代に比べれば寝床や食うものには困らなかった。宗茂はふと国許から届けられた書状を読むのをやめ、大ぶりの頭を仰角四十五度まで動かして天井を睨んだ。そして、背後に控えている家臣由布雪下に話しかけた。
宗茂「雪下」
雪下「はい」
宗茂「今、何か申したか。カンジョー、とか」
雪下「はて。なにも申しませんが」
◆棚倉には故郷柳川からも折々通信が送られてくる。その中に、清田正成からの嘆願書があった。要件は簡潔であった。火事で家屋が焼けた。家宝ともいうべき代々の当主が室町将軍家や大友氏から賜った感状を失ってしまった。殿から賜った大切な感状も燃えてしまった。大津での戦功は一族郎党とも粉骨砕身したもので、何とも口惜しい。ついては、同じ文面で再度発給願いたい、といった意味のことが書かれていた。
◆宗茂は清田正成に与えた感状のことをよく覚えていた。あれは慶長五年の大津城攻めでのこと。清田正成が城中へ攻めこみ、敵を真っ向から胸まで斬撃して「清田の兜割り」と賞賛された合戦でのことである。
◆大津の城攻めを思い出すのはつらかった。同日、隣国美濃関ヶ原では天下分け目の戦いが決着していたのである。あと一日落城が早ければ、と立花勢は臍を噛んだ。士気高い味方を関ヶ原へ転進させ、決戦に間に合わせたものを。それにしても感状の再発行など聞いたことがない。これを許せば、与えていないのに「なくしたから寄越せ」と申し出る不逞の輩も出てくるであろう。
宗茂「死んでしまった人間に感状を乞うのは無理だが、わしが与えた分は、ちゃっかり再発行してほしいと泣きついてきおった。感状が無くなったら、わしが家臣どもの働きまで忘れてしまうとでも思ったか。なさけないことである」
雪下「清田も大津の感状だけは、あきらめきれないのでしょう。立花家もこんな有様ですから、誰を憚るということもないでしょう。おまけしてやったらどうですか?」
宗茂「ばかな」
雪下「しかし、このままでは偽文書作成に走るかもしれませんぞ」
◆宗茂としても、できれば、立花勢の勇猛さの証明として発行しなおしてやりたい。だが、先例にないことを許可するわけにはいかない。
◆その頃、日本列島を東へ、ひとりの男がカンジョー、カンジョーとブツブツつぶやきながら猛進しつつあることを、宗茂主従は知るよしもなかった・・・・・・。
◆棚倉の朝は冷えた。柳川とは違う。おはようございます、と雪下が挨拶に来た。早起きの宗茂はすでに心身の鍛錬でひと汗流し、朝の書見を終えようとしているところであった。
雪下「殿。お顔の色がすぐれませんな?」
宗茂「夢見のせいだ。おそろしい化け物につまみあげられ、何やら懇願された」
雪下「お疲れのようですが」
宗茂「雪下。国許の清田に言っておけ。感状の再発行はできないということをよくよく言い聞かせよ」
雪下「仰せうけたまわりました」
◆宗茂は書見をやめ、大ぶりの頭を仰角四十五度まで動かして天井を睨んだ。そして、背後に控えている由布雪下に話しかけた。
宗茂「雪下」
雪下「はい」
宗茂「今度こそ聞えたぞ。カンジョー、と。それほど再発行させたいのか」
雪下「いいえ。ですから、なにも言ってないですってば」
 XFILE・MENU
XFILE・MENU