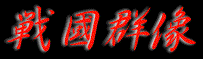177「加藤清正と喧嘩の名人」
谷衛友(1563―1627)
甚太郎、従五位下出羽守。衛好の子。山家藩初代藩主。豊臣秀吉に仕え、播州三木城攻めに参加。攻城戦で討死した父の仇を報じ、六千二百石を加増されたという。のち、丹波国内で一万六千石を領す。慶長五年(一六〇〇)、関ヶ原の合戦では西軍に属し、細川幽斎が籠る丹後田辺城を攻めたが、城内と内通していたため、戦後、本領を安堵された。
◆名人には二種類があるだろう。たとえば、道場で竹刀をもって立ち会う形式に秀でた者。そして、野外で真剣をとって命のやり取りをする豪の者。江戸時代の軍学者と戦国時代の軍師の対比であり、ウルフ金串とゴロマキ権藤の対比である。前者は「道場剣法」とか呼ばれて、死線をくぐってきた者たちから蔑視されもする。
◆加藤清正の戦闘指揮能力は、多士済々の豊臣秀吉の家臣の中でも、五指に入るほどのものであったろう。巨躯を有し、戦功比類ない、その清正が実は「喧嘩下手」であるという。本当だろうか。
◆武家には「奉公構(ほうこうかまい・ほうこうかまえ)」ということがあった。主家にとって憚りのある者を他家に仕官できないようにするもので、プロ野球で言えば自由契約ではなく、永久追放に近い。奉公構に遭った武士はどこにも仕官することができず、浪人の境遇に堕ちたりする。後藤又兵衛が黒田長政によって奉公構にされた例は有名だ。
◆さて、加藤清正もかつての家臣を奉公構にしたことがあった。浪人となったその男は、清正の友人である細川忠興にすがって、主人の怒りを解いてもらおうと考えた。義侠心というよりも、こういう揉め事の仲裁・周旋が三度の飯より大好きな忠興である。さっそく加藤家へ乗り込もうと考えた。が、清正がちょっとコワイ。
◆そこで、助っ人を頼むことにした。友人の谷出羽守衛友である。両名は加藤家へ向かった。座敷では、脇差だけを手挟んだ清正が、風呂上りの直後らしく全身からブワッと発汗し、そこから湯気をたてている。忠興は床に刀を置き、清正と対座。衛友は次の間に控えた。
清正「ふたり揃って、今日は何の用じゃ」
忠興「実はカクカクシカジカ。なにとぞ彼の者の帰参をお許しねがいたい」
衛友「それがしからもお頼みいたす」
清正「どんな用向きかと申せば。あのような馬鹿者のことなど、捨て置け!」
◆これを聞いてカッとなった短気者の谷衛友。やおら立ち上がって、次の間からズカズカと清正のそばへ歩み寄り、その膝をおさえ、脇差に手をかけてその動きを封じた。
衛友「いかに肥後守。それがしを誰だと思って悪言をはくのか!?」
衛友は怪力である。清正をもってしても、膝をおさえられているだけで身動きがとれなくなった。もっとも、清正も百戦錬磨の男。ジタバタと騒いだりはしない。動きを封じられて苦笑いしながら、
清正「出羽守の悪いクセじゃ。これ、三斎。この男をなんとかせんか」
忠興「われらの願い、お聞き届けいただけようか」
清正「まず出羽守をわしから引き剥がせ。話はそれからじゃ」
◆この事件以来、清正の喧嘩下手がひろまった。喧嘩といっても口喧嘩や殴り合いを指すのではなく、平時に一対一で臨んだ場面を称して言ったものであろう。恐らくは細川忠興あたりが同時代の人物を評した際に言ったのであろうか。だが、喧嘩上手の谷衛友を褒めちぎることもしなかった。清正の「勇」は匹夫の勇ではなく、大軍を動かす大勇である。喧嘩の優劣は武功にもつながらない。清正とて、戦陣においては自ら太刀打ち、鑓働きをしたこともある。尋常な勝負であれば負けなかったろう。もっとも、衛友が清正の動きを封じたのも、喧嘩というよりは兵法の心得を思わせる。兵法というものが戦場働きよりも軽んじられていた風潮が、喧嘩という記述になったのだろうか。
◆加藤家では、物見にも清正自身が出たという。陣を布く際に、小屋をかけるのも、その小屋へ家臣たちを割り当てるのも、清正自身が奉行する。一事が万事、こういった具合であったため、次第に「その家来にすぐれたる功者、さほどに出で来らず候由」という状況になったという。そう考えると、谷家の場合は、主人衛友が喧嘩上手なこと以外、頼りにならなかったのであろうか。これをもりたてる家臣たちが谷家を存続せしめたと言う見方もできよう。
◆上にたつ者、大勇のみではどうもいけないらしい。
*補足調査
たまたま細川家の記録『綿考輯録』を読んでいたら興味深い記述を見つけました。関ヶ原合戦の後、細川忠興が家臣たちに恩賞を与えた際、有吉立行は具足を拝領しているのですが、「頬ハ谷頬とて谷出羽守之面体を御似せ被成候なり」というおもしろいものをもらっています。当時から谷出羽守は勇猛として知られていたのでしょうか。(X-file特別調査官:ぴえーる)
 XFILE・MENU
XFILE・MENU