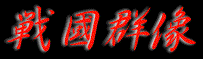110「末森・鳥越城攻防戦(前)」
奥村永福(1542―1624)
家福、助十郎、助右衛門、伊予守。はじめ荒子城主・前田利久に仕えるが、織田信長の命により利久の弟利家の家督継承が決定すると、これに従った。以後、利家の重臣として各地を転戦。利家が豊臣政権下の大名となると、能登末森城を預かる。天正十二年(一五八四)、秀吉に反抗した佐々成政の攻撃を防ぐ。慶長四年(一五九九)、利家の死とともに隠退した。奥村氏は加賀藩八家のうちに数えられる。
◆宿命のライバルというと、謙信と信玄、あるいは秀吉と光秀、三成と家康という具合に互いに雌雄を決した名前を列挙することができる。が、前田利家と佐々成政について指折る人はかなり少ないだろう。先に列挙した人々にくらべて「ライバル」という関係も多くの人々にとってはピンとこないかもしれない。だが、利家は赤母衣衆、成政は黒母衣衆として、ともに信長に仕え、寵を競い、武功を争った愛憎なかばするライバルなのである。
◆二人が真っ向から激突したのは、天正十二年(一五八四)、のちに利家が「末森の後巻き」と喧伝する戦いである。目だった武功はこれしかないという話もある。それはちょっと酷だが、当の利家がこの末森城の攻防ばかりを吹聴するのだから仕方がない。
◆対する佐々政成は主将たる柴田勝家滅亡後、いったんは羽柴秀吉の軍門に降っていたが、やはり肌があわなかったのであろう。ほどなく叛旗を翻した。
◆佐々成政が急襲した末森城を守るのは、利家の部将・奥村伊予守永福の兵五百余。利家が最初に家来にしたという、村井又兵衛とならぶ二大功臣といわれる男だ。この奥村永福を、副将格の千秋範昌、滝沢金右衛門、土肥伊予守が支える。だが、兵力にまさる佐々勢は水の手を断ち、次第に三の丸を占領、二の丸をも脅かしはじめた。
奥村永福「もはやこれまでか。城に火を放ち、潔く自害いたさん」
永福の妻「何をおっしゃいます、なさけない」
◆奥村永福の妻(『太閤記』によると名前はつね)は病床に臥していたが、攻城戦が始まると、寝てはいられぬ、と自ら薙刀を掻い込んで、城中を警護し、時には兵士に粥を振る舞ったり、酒をあたためて馳走したりした。彼女は夫の弱きな言葉を聞くと、大声で叱咤した。
永福の妻「いにしえの楠正成は全国の兵を相手に籠城したとか聞き及んでおります。おまえさまは、たかだか佐々一手の勢に囲まれただけのこと。何を気弱なことを申されまするのか」
◆もともと永福の妻つねは落ち着きはあるが、繊細で病弱な女性であったから、永福も驚いたであろう。病をおして城中を奮励してまわる妻に叱られながら、奥村永福は本丸ばかりとなった守りを厳にして、敵勢を防いでいた。
◆そこへ、これまた正室おまつ(芳春院)に尻を蹴飛ばされるようにして出陣してきた前田利家の後詰が佐々成政の軍勢の背後から襲いかかった。ここに形勢は逆転、佐々勢は落城寸前まで追い込みながらも、末森の囲みを解いて越中へ向かって敗走した。
◆利家にとっても、前田家にとっても、この「末森城の戦い」は特別なものであったらしく、同家にはこの戦いに関する書画や遺品が多い。利家の自画自賛にいたっては、いささか鼻につくほどだ。しかも、利家といい、永福といい、女房にハッパをかけられるのであるからあまり格好のいいものではない。利家の妻も、永福の妻も、いずれもこの末森城の戦いで名をのこすことになった。今ならば「女性が元気な企業は強い」だとか言われるのであろうが。
◆この奥村永福はもともとは、利家の長兄利久に仕えていた。織田信長の命で利家に前田家家督継承が成された際、荒子城を預かってなかなか手渡そうとはしなかった硬骨漢である。利家の入城を頑として断り、兄利久の命令でようやく開城した。きっと救援に駈けつけようと急ぐ利家の脳裏には、かつての振る舞いを思いおこし、「あいつなら、むやみに城を明け渡すまい」と確信していたかもしれない。殊勲の永福に、利家は九月十六日、感状とともに千石を加増している。
◆しかし、佐々成政もただでは転ばない男である。退却に移りつつも、すでに利家に対して大逆襲を用意していた。
 XFILE・MENU
XFILE・MENU