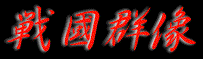087「自腹で人材登用を進言」
由布惟信(1527?―1612)
源兵衛、号雪下。湯布院城主として大友氏に代々仕える。戸次鑑連(立花道雪)が立花城へ封じられた折、嫡子に家督を譲って立花家の家老をつとめた。以後、立花道雪の四天王として勇名を馳せ、その没後は養子宗茂に忠勤をはげむ。関ヶ原戦後、立花家改易の後、浪人となった宗茂に従い、京都、江戸へおもむき、宗茂が奥州棚倉に封じられ立花家が大名として再興するまで見届ける。没年八十六歳といわれている。
◆清冽な生きざまでファンも多い勇将立花宗茂。彼の少年時代にこんなエピソードがある。男子にめぐまれない立花道雪は、高橋家の嫡男・宗茂の将来を嘱望していた。立花・高橋の両家は大友家中でも鎮西のおさえとして親しい間柄だったから、事あるごとに宗茂を城へ呼んで狩りなどに連れ出した。ある日、山道を歩いていた宗茂が栗をふんづけてしまい、イガが足の裏にささってしまった。
宗茂「おい、誰かこのイガを抜いてくれ」
そこへ走りよってきた道雪の家臣がイガを抜くどころか、「どうじゃ、どうじゃ」とぎゃくにグイグイ押しつけてきた。宗茂は「あまりの痛さに驚いたが、道雪どのも見ておったし、痛いとも言えなかった」と述懐している。
◆この逸話は有名だから、宗茂を扱った小説や歴史本には必ずといっていいほど引き合いに出されるので、ご存じの方が多いだろう。道雪主従はわざと栗のイガが転がっているところを宗茂に通らせたのだという。この時、宗茂少年の足に栗のイガをおしつけた男こそ、今回の主人公・由布惟信である。主人道雪の号にちなんで、雪下と称していた。当然、雪下は素手で押しつけたのであろうから、彼の手は尖ったイガも貫通しない分厚い皮膚をもっていたのであろう。
◆この雪下、道雪に従って戦場に出ること六十五回、傷を負うこと六十五回といわれている。毎度負傷していた勘定になる。これほど足萎えの道雪に忠勤を励んだ雪下だが、彼はもともと立花家および戸次家への家臣ではなかった。同じ大友家に仕える湯布院の城主である。いわば同僚だったのだが、道雪が立花城主となった際、城と領地を息子に譲って、このあとについていってしまった。かくして、連年戦場にては陣頭に立ち、感状の数は知えきれず、立花家では十時摂津、安東紀伊介家忠、高野大膳亮とならぶ「道雪四天王」の筆頭の座についたのである。
◆その雪下が大友家からやってきた目付の小野和泉を「頼りになる男・・・・・・」と見込んだ。さっそく主人道雪に推挙する。
雪下「との。小野和泉をお屋形様(大友宗麟)に乞うてもらい受けなされませ。あれはなかなかの人物にござりまする」
道雪「小野和泉がことはわしも気に入っておるが、いかんせん、与える知行がない」
雪下「なさけなや。あれほどの男をほおっておいては立花家の名折れですぞ。では、それがしがとのから戴いております千五〇〇石のうち、五〇〇石を返上しますので、これを和泉に与えてやってくださいませ」
プロ野球でいえば、大物ルーキーのために、ベテラン選手が自分の年俸を三分の一削ってフロントに獲得を進言するようなもの。つまりあり得ない話。
かくして、小野和泉は立花道雪の家臣となり、やがてこれも雪下の推挙によって家老職についた。以来、道雪はこのふたりを立花家の両翼として重用し、「いくさには正道と奇道があり、双方をうまく活用すれば勝利は必ずや掌にある。したがって以後は、雪下が正将をつとめ、和泉は奇将をつとめよ」といいわたした。
◆本来、目付は監視役である。監視されるほうが気に入ることはおろか、自分の禄を削ってまで推挙するケースは皆無といっていい。やはり斜陽の大友氏よりも、鎮西の地で奮闘する道雪のほうが小野和泉には敬服に価したのだろう。その小野和泉の心中というものを雪下がよく汲んだということであろうか。潔い生きざまを見せた立花宗茂は、道雪とこういう家臣たちのつくる立花家の気分というものにひたって育ったのである。
◆立花道雪が龍造寺氏の城を攻囲中、陣没した。雪下はすぐさま腹を切ってお供しようとしたところ、おもだった家臣全員が殉死を希望した。ひとり原尻宮内が「みんなで死んでしまったら若殿はどうなる?」と諌め、雪下は死を思いとどまった。のちに立花宗茂が漂泊の運命に見舞われた時も、雪下の姿がその側にあった。
 XFILE・MENU
XFILE・MENU