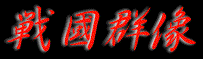

033「釜山より愛をこめて!?」
浅井井頼(?―1615?)
喜八郎、政信、政賢、周防守、作庵。近江小谷城主浅井長政の実子といわれる。母は不詳。異母姉の京極高次室(常高院)に身をよせ、のちに羽柴秀勝・豊臣秀長・秀保に歴仕、禄六百石。文禄三年(1594)、増田長盛の家臣となり、三千石を領す。関ヶ原合戦後、主家没落により浪人。丸亀生駒家に身を寄せ、慶長十九年(1614)、大坂城に入り、翌年の夏の陣で戦死したともいわれたが、生きのびて京極家に客分として仕えた浅井作庵をその後身とする説もある。
◆浅井周防守井頼といえば、関白豊臣秀次の家中にあっても武功の士として聞こえていた。実際の彼は秀長・秀保の大和大納言家に仕えていたらしいことが散見するが、秀次の家臣であった一時期があったのかもしれない。
◆彼は主人の秀次以上に美少年が大好き。
◆ある日、秀次に怒られた寵童のひとりが、罰として部屋に閉じ込められた。座敷牢に主君の愛する美少年が閉じ込められている、と聞いた浅井井頼は、居ても立ってもいられなくなった。なんとか主君の秘蔵する花のかんばせをひとめ見てみたいと思った。
◆あれこれ思い惑うよりも、直接行動に訴えてしまう武人である。夜陰にまぎれて座敷牢にしのびこんだ井頼は、囚われの少年を見、思わず息をのんだ。少女と見紛うような美しさ、上品さ。さすがに聚楽第に美女を数多侍らせている秀次のことだけはある。衆道においても趣味がいい。
◆一方の少年も、いきなり忍んできた相手に身をこわばらせた。一瞬、主人の秀次が宥めにきてくれたのかと期待をしたが、燭台の明かりに映じた相手は秀次の家臣浅井井頼だったので、さらに驚いた。驚いた直後には寵童特有の媚態が自然に出てしまっていた。
◆人の欲はきりがない。しなをつくる美少年を目の当たりにした井頼は、「お〜、おれに気があったんかい」と勘違い。このままおとなしく立ち去ることが惜しくなってきた。かと言って、主君の「お手つき」と通じたならば、自身もただでは済まない。だが、迷っているくらいならば、はじめから少年をのぞき見しようなどとは思わない。井頼は、燭台の火を吹き消し(暗転。きぬずれの音。笑)、とうとう抗う少年をその場へ押し倒して、一気に思いを遂げてしまった。
◆「来た、見た、やった」という金言のおこりである。(うそ)
◆一方、秀次とて寵愛する少年を憎くて折檻したわけではない。嗜虐趣味を楽しんでいた秀次は、ちょっと少年をいたぶってみたくなっただけなので、「どれどれ、泣きべそでもかいておるかな」とニンマリしながら座敷牢に入った。好色ぶりにかけては、叔父太閤秀吉でさえ一目をおくほどの海千山千、両刀づかいの秀次である。少年の様子がおかしい、というのはすぐにピーンときた。秀次は目を血走らせながら、少年に事の次第を問いただす。精一杯の媚態を示す少年は、蛇のような眼に射すくめられ、なくなく昨夜の出来事について語った。
◆果たして、秘蔵の花を散らされたと知った秀次は、怒った。愛する女性を寝取られたよりも数倍悔しいらしい。
秀次「おのれ、誰かあるッ。成敗じゃ、周防守を斬れッ」
しかし、井頼も即座に退散することは癪だった。
井頼「わが武勇の名を得て禄を食み、今おめおめと立ち退きなば、命おしさになど人の誹りも口惜し」
ま、要するに何も言わずに逃げ出したら、臆病者と思われるかもしれない、と思ったのだね。彼の傾奇者の側面であろうか、こういう戦国武士の気位の高さ、やせ我慢的な気分が横溢していた時代である。おのれの武勇をあなどられることは、何よりも恥辱とするところ。相手がそう思うであろう、と自分のほうで一方的に解釈しているのがかわいいというか馬鹿馬鹿しい。
◆城に登った井頼は大声で眼下の朋輩たちに叫んだ、
井頼「わしを殺せ、との殿のご命令じゃ。誰か殿の命を受けてわしを討つ者はおらぬか!?」
ところが、浅井井頼の日頃の武勇におそれをなして、誰も名乗りをあげない。手向かう者がいないと知ると、彼は見得をきって主家を退散した。ここまではカッコよかったが、国内では追っ手がかかるおそれがあったので、はるばる朝鮮まで渡ってしまったというから、案外、小心者なのかもしれない。おりしも秀吉による二度の朝鮮出兵のはざまの時期であったから、彼の地に渡る日本人も大勢いたことであろう。
◆朝鮮にわたった浅井井頼の日課は、毎朝、海岸に出て日本の方角に向かい、刀を振り回しながら、「日本大乱、国家滅亡〜!」と叫ぶことだったという。
◆海の向こうからの思いが届いたのか、そのうちに、秀吉によって豊臣秀次とその一類はことごとく処刑されてしまった。帰国したとしても、もはや彼をとらえようとする者はいない。浅井井頼は日本へ戻り、気ままな浪人暮らしを送っていたが、間もなく大坂冬の陣がおこった。
◆浅井井頼は、最後の働き場所を求めて大坂城へ入城した。城には淀殿とその子秀頼がいる。井頼にとっては秀次失脚・滅亡の一因ともなった母子だし、史書が伝えるように彼が浅井長政の子であるとするならば、まさしく姉と甥にあたる。憎かろうはずがない。
◆結局、浅井周防守井頼は、大坂の陣で戦死した。あるいは若狭国小浜に落ち延び、京極家に仕官したとも伝える。彼のように主人にさからったため、世間から身を隠し、その主人が死んだあと、何食わぬ顔でひょっこり出てきた者が多かったらしい。朝鮮にまで逃げているひまがあったかどうかは疑わしいが、江戸時代の随筆『塩尻』が伝える逸話である。
 XFILE・MENU
XFILE・MENU
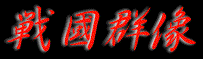

 XFILE・MENU
XFILE・MENU