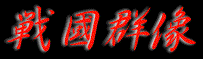

長宗我部信親(1565―1586)
千雄丸、弥三郎。元親の嫡子。母は石谷兵部大輔光政の女という。室は石谷頼辰(美濃斉藤から養子)の女。天正八年(1580)、織田信長の偏諱を受けて信親と名乗る、という。「身の丈六尺一寸、色白くし柔和にして詞寡くて礼譲があって、しかも厳しくはない。戯談しても決して猥がましくはない」と評され、三尺五寸の差料を跳躍しつつ抜刀する技量の持ち主であったという。父元親に従い、阿波攻めに参加。のち、秀吉の四国攻めに際しては、岡豊城を守った。天正十四年、九州征伐に従軍し、戸次川の合戦で戦死。法名天甫寺常舜禅定門。
中にも大将信親は、 唐綾縅の甲を着 蛇皮の冑を戴きて 馬を縦横に馳せめぐらし 四尺三寸の長刀を 閃く稲妻 石撃つ火と 身まがう迄に打ち揮い 敵八人を切り伏せつ
 XFILE・MENU
XFILE・MENU