史跡・スポット
独断と偏見のおすすめ度
★★★★★・・・・・・マニアならば必見スポット。
★★★★・・・・・・・意外と知られていない穴場かも。買い物、名物、温泉を求める人には向かない。
★★★・・・・・・・・観光客うじゃうじゃのおきまりコース。買い物好きも大喜び。
★★・・・・・・・・・時間つぶしか他に予定がなければ。
★・・・・・・・・・・はずれ。話題にしたくもない。
名古屋城★★★
 織田家の居城であった「那古屋城」は現在の名古屋城の二の丸付近にあったという。大永年間に今川氏親が築き、別名柳の丸と呼ばれた。織田信秀が城主今川氏豊を連歌の会にかこつけて奪い取ったという。信長はこの城で生まれた、という説もあり。今は碑が残るのみ。また、西北隅櫓は清洲城小天守の移築という説もある。五層五重の天守閣(昭和三十四年再建)内部も、旧本丸御殿障壁画のほかは藩政時代中心なので、眺望を楽しんだほうがいいかも。左写真は二の丸方向から撮ったもの。
織田家の居城であった「那古屋城」は現在の名古屋城の二の丸付近にあったという。大永年間に今川氏親が築き、別名柳の丸と呼ばれた。織田信秀が城主今川氏豊を連歌の会にかこつけて奪い取ったという。信長はこの城で生まれた、という説もあり。今は碑が残るのみ。また、西北隅櫓は清洲城小天守の移築という説もある。五層五重の天守閣(昭和三十四年再建)内部も、旧本丸御殿障壁画のほかは藩政時代中心なので、眺望を楽しんだほうがいいかも。左写真は二の丸方向から撮ったもの。
熱田神宮★★★★
 永禄三年(1560)、東海の雄今川義元の軍勢が尾張に迫る。清洲城を発した信長は、この熱田神宮に戦勝祈願をし、両面を貼りあわせた通貨で吉凶を占わせたといわれる。その昔、ヤマトタケルが草薙の剣を奉ったという大社。境内には、信長が桶狭間戦勝により寄進したという「信長塀」が残る。水平方向に漆喰を塗り固めていった手の込んだつくりで、三大築地塀の一。その頑丈そうな造りは、合理主義者信長の人柄が出ていそう。また、対今川戦で戦死した佐久間盛重の四男勝之が寄進したといわれる巨大な佐久間灯篭に圧倒。
永禄三年(1560)、東海の雄今川義元の軍勢が尾張に迫る。清洲城を発した信長は、この熱田神宮に戦勝祈願をし、両面を貼りあわせた通貨で吉凶を占わせたといわれる。その昔、ヤマトタケルが草薙の剣を奉ったという大社。境内には、信長が桶狭間戦勝により寄進したという「信長塀」が残る。水平方向に漆喰を塗り固めていった手の込んだつくりで、三大築地塀の一。その頑丈そうな造りは、合理主義者信長の人柄が出ていそう。また、対今川戦で戦死した佐久間盛重の四男勝之が寄進したといわれる巨大な佐久間灯篭に圧倒。
桶狭間古戦場跡★★
周辺は宅地化・公園化されて、古戦場の面影はない。ぽつんと立っている今川義元の墓が哀れをさそう。墓や供養碑はすべて江戸時代以後に建てられたもの。道を隔てて向かい側の高桐院に「今川義元公御本陣」の碑があるが、寺そのものは新しい建築物だ。今川家との関係もない。むしろ、裏手の山を登ると「ここを織田勢は駆け下りて行ったのだろうか」と妄想にひたれる、かも・・・?。
桶狭間古戦場資料館★★
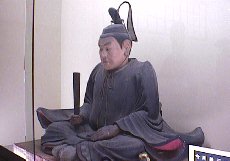 高桐院裏手に新設された資料館。もちろん国宝・重文級は期待しないが、県指定などの逸品はなし。等身大の信長・秀吉・義元らの人形に思わず吹き出してしまった。明治期に書かれた今川義元の肖像などが珍しい。展示品の甲冑などにも「平成○年、どこそこ博物館へ出品」などと札がかかっているのも仰々しい。チラシのようなパンフ(200円!)は必要ない。おまけに記念スタンプが50円とは驚きだ。商売っ気丸出しは鷹揚な義元には似合わないゾ。
高桐院裏手に新設された資料館。もちろん国宝・重文級は期待しないが、県指定などの逸品はなし。等身大の信長・秀吉・義元らの人形に思わず吹き出してしまった。明治期に書かれた今川義元の肖像などが珍しい。展示品の甲冑などにも「平成○年、どこそこ博物館へ出品」などと札がかかっているのも仰々しい。チラシのようなパンフ(200円!)は必要ない。おまけに記念スタンプが50円とは驚きだ。商売っ気丸出しは鷹揚な義元には似合わないゾ。
岐阜城★★★
フロイスいわく「ポルトガル・インドから日本へ来るまでに見た宮殿・家屋の中でもっとも美麗なもの」。おきまりコースとはいっても、誰しもやはりあの金華山山頂へは登ってみたいのではなかろうか。眺めは抜群。麓にあった信長屋敷跡から中腹までロープウェイがある。そこから山頂まで徒歩。信長ではなくてたくさんのリスが迎えてくれる。金華山ロープウェイがリニューアルされた時に訪れた際、プレミア(信長トランプ)つきチケットを入手。岐阜市。
姉川古戦場跡★★
ごぞんじ、織田・徳川連合軍が浅井・朝倉連合軍に勝利した地。大軍を展開するには都合のよいロケーションだ。古戦場碑と血原塚などの故地が散らばっている。滋賀県東浅井郡浅井町。
小谷城跡★★★★
信長の妹お市が嫁いだ浅井長政の居城。国道沿いに「史跡・小谷城址」とあるのに騙されて歩いて登った人はえらいめに遭う。手前の山はごく一部。本丸はさらに奥の奥。桜の名所で大広間と呼ばれた場所には浅井一族の碑が建つ。途中までは車を使うか、さもなければ足回りを強化しておく必要あり。山麓の須賀谷温泉(お市も通った?)もぜひ。露天風呂の赤茶けた湯はいかにも「戦国の秘湯」といった趣だ。滋賀県東浅井郡浅井町。
安土城跡★★★★★
 「山全体が信長公の巨大な墳墓」といわれる戦国時代屈指の名城。周辺の環境もよく、発掘作業が継続しているので期待も大。大手道から上った場合は、天守台、二の丸跡を経て総見寺跡へ至るコースがいい。羽柴秀吉館跡の整備が進んでいる。天守台と二の丸跡の信長廟(写真)はぜひ。秀吉が安置したという烏帽子型の石の意味は謎。ひょっとして信長自身が拝ませたという玉石ではないか、という説もある。森蘭丸ファンは屋敷跡の碑を見逃さぬよう。現在は大手道が復元中である。滋賀県安土町。
「山全体が信長公の巨大な墳墓」といわれる戦国時代屈指の名城。周辺の環境もよく、発掘作業が継続しているので期待も大。大手道から上った場合は、天守台、二の丸跡を経て総見寺跡へ至るコースがいい。羽柴秀吉館跡の整備が進んでいる。天守台と二の丸跡の信長廟(写真)はぜひ。秀吉が安置したという烏帽子型の石の意味は謎。ひょっとして信長自身が拝ませたという玉石ではないか、という説もある。森蘭丸ファンは屋敷跡の碑を見逃さぬよう。現在は大手道が復元中である。滋賀県安土町。
総見寺跡★★★★★
 安土城西側に位置する三重の塔。およびその下方に戦国時代当時の仁王門が遺る。城の上には意外なほどに人が多く、二度ともわたしが訪れた時には、幼稚園児たちがお弁当をひろげていた。滋賀県安土町。
安土城西側に位置する三重の塔。およびその下方に戦国時代当時の仁王門が遺る。城の上には意外なほどに人が多く、二度ともわたしが訪れた時には、幼稚園児たちがお弁当をひろげていた。滋賀県安土町。
信長の館★★★★★
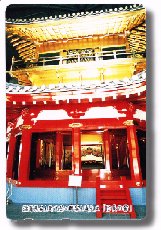 見るべきものはセビリヤ博に出品された原寸大の「安土城天守(五・六階部分)」。これだけで圧倒される。内部の彩色や障壁画も圧巻。黄金の使い方も秀吉より上品な感じがする。撮影禁止だが、「記念撮影する方は申し出てください」という張り紙があったので、頼めば大丈夫なのかもしれない。ここでは、購入したテレカで代用とする。売店ではオリジナル・グッズもある。「右府様」を気どりたい方には「天下布武」印を。資料としては、城郭資料館のパンフレット(\500)がいい。復元安土城の図面がばっちり収録されている。「信長チョコレート」にチャレンジした方はぜひご一報を(笑)。滋賀県安土町。
見るべきものはセビリヤ博に出品された原寸大の「安土城天守(五・六階部分)」。これだけで圧倒される。内部の彩色や障壁画も圧巻。黄金の使い方も秀吉より上品な感じがする。撮影禁止だが、「記念撮影する方は申し出てください」という張り紙があったので、頼めば大丈夫なのかもしれない。ここでは、購入したテレカで代用とする。売店ではオリジナル・グッズもある。「右府様」を気どりたい方には「天下布武」印を。資料としては、城郭資料館のパンフレット(\500)がいい。復元安土城の図面がばっちり収録されている。「信長チョコレート」にチャレンジした方はぜひご一報を(笑)。滋賀県安土町。
安土城考古資料館★★
安土は古くから集落が誕生し、栄えたところ。戦国関連では観音寺城の模型がすごい。これを見て登るのは断念してしまった。ほかに各地の戦国大名の城にスポットをあてた解説、勢揃いした信長肖像画(写真パネル)がある。考古資料館と名づけられているが、戦国ファンはテーマ展示よりも常設展示のほうに目がいってしまうだろう。二階は図書室になっており、歴史関係の書籍が集められている。滋賀県安土町。
安土城城郭資料館★★★★
 原寸大の天守を見たあとではやや物足りないが、二十分の一の安土城模型がある。おまけに内部がのぞけるし、解説ビデオ(必見)もある。新しく描きおこした「安土屏風」もすばらしい。喫茶店を兼ねていて直送のローマ・コーヒーが売り物。ここを起点に予備知識を仕入れ、安土城址で往時をしのび、最後に信長の館(安土城考古資料館隣接)で復元された天守と対面する周回コースがおすすめ。近所には自転車のレンタルもあり。JR安土駅前。
原寸大の天守を見たあとではやや物足りないが、二十分の一の安土城模型がある。おまけに内部がのぞけるし、解説ビデオ(必見)もある。新しく描きおこした「安土屏風」もすばらしい。喫茶店を兼ねていて直送のローマ・コーヒーが売り物。ここを起点に予備知識を仕入れ、安土城址で往時をしのび、最後に信長の館(安土城考古資料館隣接)で復元された天守と対面する周回コースがおすすめ。近所には自転車のレンタルもあり。JR安土駅前。
比叡山延暦寺★★★
 王城鎮護の地、現在は明智光秀の居城があった坂本からケーブルカーで行ける。朝倉勢に味方し、その陣場を提供したため信長の怒りを買って、全山焼き討ちの憂き目になったのは有名だが、当時は僧侶も麓に暮らしており、山上は寂れていたらしい。信長の兵火をまぬがれたといわれる「瑠璃堂」(写真)の枯れた姿は必見。根本中堂付近からバスが便利。今にも燃えそうなので煙草は吸わないように。滋賀県大津市下坂本町。
王城鎮護の地、現在は明智光秀の居城があった坂本からケーブルカーで行ける。朝倉勢に味方し、その陣場を提供したため信長の怒りを買って、全山焼き討ちの憂き目になったのは有名だが、当時は僧侶も麓に暮らしており、山上は寂れていたらしい。信長の兵火をまぬがれたといわれる「瑠璃堂」(写真)の枯れた姿は必見。根本中堂付近からバスが便利。今にも燃えそうなので煙草は吸わないように。滋賀県大津市下坂本町。
奈良国立博物館★★★★★
 「東大寺」という文字を隠した雅名「蘭奢待」で知られる香木黄熟香(長さ1.56m)。写真中の付箋は左から明治天皇、織田信長、足利義政が切り取った痕とされるもの。記録では足利義満、足利義教、徳川家康も切り取った。毎年秋に開催される正倉院展などで公開される。熱帯アジア産の沈香(樹木に樹脂や精油が付着したもの)の一種。鎌倉時代にはすでに中国を経て伝わっていたらしい。ミュージアムで沈香は購入可能(メチャ高い)。奈良県奈良市。
「東大寺」という文字を隠した雅名「蘭奢待」で知られる香木黄熟香(長さ1.56m)。写真中の付箋は左から明治天皇、織田信長、足利義政が切り取った痕とされるもの。記録では足利義満、足利義教、徳川家康も切り取った。毎年秋に開催される正倉院展などで公開される。熱帯アジア産の沈香(樹木に樹脂や精油が付着したもの)の一種。鎌倉時代にはすでに中国を経て伝わっていたらしい。ミュージアムで沈香は購入可能(メチャ高い)。奈良県奈良市。
現・本能寺★★★
 再建後の姿。都市計画のため、豊臣秀吉の命により現在地へ移転。織田信孝が建立した信長廟や森乱丸ら殉死者の供養塔などがある。商店街にあるのはちょっと間が抜けているか。京都市河原町。
再建後の姿。都市計画のため、豊臣秀吉の命により現在地へ移転。織田信孝が建立した信長廟や森乱丸ら殉死者の供養塔などがある。商店街にあるのはちょっと間が抜けているか。京都市河原町。
本能寺跡★★
信長時代の本能寺は現在の場所にはなかった。コンクリート塀の一角に石碑が建つ。しかも「この付近、本能寺跡」という頼りなさ。一見、ゴミ捨て場と間違えてしまいそう。近所には「南蛮寺跡」などといった碑があり、往時をしのばせる。目につかなかっただけかもしれないが、観光者向けの標識などはなかった。現・本能小学校。
京都国立博物館★★★
戦国関係の常設展示は少ないが、織田信長所用の胴丸(紺糸威胴丸具足)と、宗三左文字(いずれも重文)がある。この刀を入手したいきさつは、『信長公記』にも記されている。信長はあまりにうれしかったのか、「なかご」の表に「永禄三年五月十九日義元討捕則彼所持刀」、裏に「織田尾張守信長」と刻ませた。ただし、いずれも常に展示してはいない。京都府京都市東山区茶屋町。
高野山・信長墓★★★
 信長の墓が高野山奥の院にもある。奥の院には錚々たる戦国武将たちが眠っているので、眺めながら散策するのも楽しい。やや奥まった場所にあるが、参道に「織田信長公墓所」という立て札があるのが目印となる。なぜか筒井順慶(画面左)と隣同士。和歌山県高野町。
信長の墓が高野山奥の院にもある。奥の院には錚々たる戦国武将たちが眠っているので、眺めながら散策するのも楽しい。やや奥まった場所にあるが、参道に「織田信長公墓所」という立て札があるのが目印となる。なぜか筒井順慶(画面左)と隣同士。和歌山県高野町。
高野山・柴田勝家墓★★

高野山奥の院には、織田家家老柴田勝家も眠っている。勝家の墓は福井県西光寺にあるが、こちらはお市の方の娘淀の方か、あるいはその姉妹による供養塔であろうか。詳細は不明である。場所が非常にわかりにくい!。和歌山県高野町。
河尻塚★★
 武田氏を滅ぼした織田信長によって甲斐一国をまかされた河尻秀隆。しかし、信長の権力をかさに圧政を布いたため、領民たちは反発。ついに本能寺の変直後、武田遺臣たちの手で殺害されてしまった。写真は河尻秀隆屋敷跡と伝えられる場所で、遺体は逆さまに埋められたため、別名「逆さ塚」ともいわれる。現在はゲートボール場と民家の間に挟まれており、おまけに石碑の正面がそっぽを向き、傾いている。山梨県甲府市。
武田氏を滅ぼした織田信長によって甲斐一国をまかされた河尻秀隆。しかし、信長の権力をかさに圧政を布いたため、領民たちは反発。ついに本能寺の変直後、武田遺臣たちの手で殺害されてしまった。写真は河尻秀隆屋敷跡と伝えられる場所で、遺体は逆さまに埋められたため、別名「逆さ塚」ともいわれる。現在はゲートボール場と民家の間に挟まれており、おまけに石碑の正面がそっぽを向き、傾いている。山梨県甲府市。


 織田家の居城であった「那古屋城」は現在の名古屋城の二の丸付近にあったという。大永年間に今川氏親が築き、別名柳の丸と呼ばれた。織田信秀が城主今川氏豊を連歌の会にかこつけて奪い取ったという。信長はこの城で生まれた、という説もあり。今は碑が残るのみ。また、西北隅櫓は清洲城小天守の移築という説もある。五層五重の天守閣(昭和三十四年再建)内部も、旧本丸御殿障壁画のほかは藩政時代中心なので、眺望を楽しんだほうがいいかも。左写真は二の丸方向から撮ったもの。
織田家の居城であった「那古屋城」は現在の名古屋城の二の丸付近にあったという。大永年間に今川氏親が築き、別名柳の丸と呼ばれた。織田信秀が城主今川氏豊を連歌の会にかこつけて奪い取ったという。信長はこの城で生まれた、という説もあり。今は碑が残るのみ。また、西北隅櫓は清洲城小天守の移築という説もある。五層五重の天守閣(昭和三十四年再建)内部も、旧本丸御殿障壁画のほかは藩政時代中心なので、眺望を楽しんだほうがいいかも。左写真は二の丸方向から撮ったもの。 永禄三年(1560)、東海の雄今川義元の軍勢が尾張に迫る。清洲城を発した信長は、この熱田神宮に戦勝祈願をし、両面を貼りあわせた通貨で吉凶を占わせたといわれる。その昔、ヤマトタケルが草薙の剣を奉ったという大社。境内には、信長が桶狭間戦勝により寄進したという「信長塀」が残る。水平方向に漆喰を塗り固めていった手の込んだつくりで、三大築地塀の一。その頑丈そうな造りは、合理主義者信長の人柄が出ていそう。また、対今川戦で戦死した佐久間盛重の四男勝之が寄進したといわれる巨大な佐久間灯篭に圧倒。
永禄三年(1560)、東海の雄今川義元の軍勢が尾張に迫る。清洲城を発した信長は、この熱田神宮に戦勝祈願をし、両面を貼りあわせた通貨で吉凶を占わせたといわれる。その昔、ヤマトタケルが草薙の剣を奉ったという大社。境内には、信長が桶狭間戦勝により寄進したという「信長塀」が残る。水平方向に漆喰を塗り固めていった手の込んだつくりで、三大築地塀の一。その頑丈そうな造りは、合理主義者信長の人柄が出ていそう。また、対今川戦で戦死した佐久間盛重の四男勝之が寄進したといわれる巨大な佐久間灯篭に圧倒。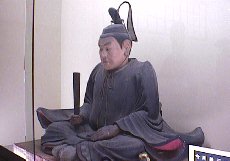 高桐院裏手に新設された資料館。もちろん国宝・重文級は期待しないが、県指定などの逸品はなし。等身大の信長・秀吉・義元らの人形に思わず吹き出してしまった。明治期に書かれた今川義元の肖像などが珍しい。展示品の甲冑などにも「平成○年、どこそこ博物館へ出品」などと札がかかっているのも仰々しい。チラシのようなパンフ(200円!)は必要ない。おまけに記念スタンプが50円とは驚きだ。商売っ気丸出しは鷹揚な義元には似合わないゾ。
高桐院裏手に新設された資料館。もちろん国宝・重文級は期待しないが、県指定などの逸品はなし。等身大の信長・秀吉・義元らの人形に思わず吹き出してしまった。明治期に書かれた今川義元の肖像などが珍しい。展示品の甲冑などにも「平成○年、どこそこ博物館へ出品」などと札がかかっているのも仰々しい。チラシのようなパンフ(200円!)は必要ない。おまけに記念スタンプが50円とは驚きだ。商売っ気丸出しは鷹揚な義元には似合わないゾ。 「山全体が信長公の巨大な墳墓」といわれる戦国時代屈指の名城。周辺の環境もよく、発掘作業が継続しているので期待も大。大手道から上った場合は、天守台、二の丸跡を経て総見寺跡へ至るコースがいい。羽柴秀吉館跡の整備が進んでいる。天守台と二の丸跡の信長廟(写真)はぜひ。秀吉が安置したという烏帽子型の石の意味は謎。ひょっとして信長自身が拝ませたという玉石ではないか、という説もある。森蘭丸ファンは屋敷跡の碑を見逃さぬよう。現在は大手道が復元中である。滋賀県安土町。
「山全体が信長公の巨大な墳墓」といわれる戦国時代屈指の名城。周辺の環境もよく、発掘作業が継続しているので期待も大。大手道から上った場合は、天守台、二の丸跡を経て総見寺跡へ至るコースがいい。羽柴秀吉館跡の整備が進んでいる。天守台と二の丸跡の信長廟(写真)はぜひ。秀吉が安置したという烏帽子型の石の意味は謎。ひょっとして信長自身が拝ませたという玉石ではないか、という説もある。森蘭丸ファンは屋敷跡の碑を見逃さぬよう。現在は大手道が復元中である。滋賀県安土町。 安土城西側に位置する三重の塔。およびその下方に戦国時代当時の仁王門が遺る。城の上には意外なほどに人が多く、二度ともわたしが訪れた時には、幼稚園児たちがお弁当をひろげていた。滋賀県安土町。
安土城西側に位置する三重の塔。およびその下方に戦国時代当時の仁王門が遺る。城の上には意外なほどに人が多く、二度ともわたしが訪れた時には、幼稚園児たちがお弁当をひろげていた。滋賀県安土町。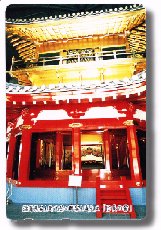 見るべきものはセビリヤ博に出品された原寸大の「安土城天守(五・六階部分)」。これだけで圧倒される。内部の彩色や障壁画も圧巻。黄金の使い方も秀吉より上品な感じがする。撮影禁止だが、「記念撮影する方は申し出てください」という張り紙があったので、頼めば大丈夫なのかもしれない。ここでは、購入したテレカで代用とする。売店ではオリジナル・グッズもある。「右府様」を気どりたい方には「天下布武」印を。資料としては、城郭資料館のパンフレット(\500)がいい。復元安土城の図面がばっちり収録されている。「信長チョコレート」にチャレンジした方はぜひご一報を(笑)。滋賀県安土町。
見るべきものはセビリヤ博に出品された原寸大の「安土城天守(五・六階部分)」。これだけで圧倒される。内部の彩色や障壁画も圧巻。黄金の使い方も秀吉より上品な感じがする。撮影禁止だが、「記念撮影する方は申し出てください」という張り紙があったので、頼めば大丈夫なのかもしれない。ここでは、購入したテレカで代用とする。売店ではオリジナル・グッズもある。「右府様」を気どりたい方には「天下布武」印を。資料としては、城郭資料館のパンフレット(\500)がいい。復元安土城の図面がばっちり収録されている。「信長チョコレート」にチャレンジした方はぜひご一報を(笑)。滋賀県安土町。 原寸大の天守を見たあとではやや物足りないが、二十分の一の安土城模型がある。おまけに内部がのぞけるし、解説ビデオ(必見)もある。新しく描きおこした「安土屏風」もすばらしい。喫茶店を兼ねていて直送のローマ・コーヒーが売り物。ここを起点に予備知識を仕入れ、安土城址で往時をしのび、最後に信長の館(安土城考古資料館隣接)で復元された天守と対面する周回コースがおすすめ。近所には自転車のレンタルもあり。JR安土駅前。
原寸大の天守を見たあとではやや物足りないが、二十分の一の安土城模型がある。おまけに内部がのぞけるし、解説ビデオ(必見)もある。新しく描きおこした「安土屏風」もすばらしい。喫茶店を兼ねていて直送のローマ・コーヒーが売り物。ここを起点に予備知識を仕入れ、安土城址で往時をしのび、最後に信長の館(安土城考古資料館隣接)で復元された天守と対面する周回コースがおすすめ。近所には自転車のレンタルもあり。JR安土駅前。 王城鎮護の地、現在は明智光秀の居城があった坂本からケーブルカーで行ける。朝倉勢に味方し、その陣場を提供したため信長の怒りを買って、全山焼き討ちの憂き目になったのは有名だが、当時は僧侶も麓に暮らしており、山上は寂れていたらしい。信長の兵火をまぬがれたといわれる「瑠璃堂」(写真)の枯れた姿は必見。根本中堂付近からバスが便利。今にも燃えそうなので煙草は吸わないように。滋賀県大津市下坂本町。
王城鎮護の地、現在は明智光秀の居城があった坂本からケーブルカーで行ける。朝倉勢に味方し、その陣場を提供したため信長の怒りを買って、全山焼き討ちの憂き目になったのは有名だが、当時は僧侶も麓に暮らしており、山上は寂れていたらしい。信長の兵火をまぬがれたといわれる「瑠璃堂」(写真)の枯れた姿は必見。根本中堂付近からバスが便利。今にも燃えそうなので煙草は吸わないように。滋賀県大津市下坂本町。 「東大寺」という文字を隠した雅名「蘭奢待」で知られる香木黄熟香(長さ1.56m)。写真中の付箋は左から明治天皇、織田信長、足利義政が切り取った痕とされるもの。記録では足利義満、足利義教、徳川家康も切り取った。毎年秋に開催される正倉院展などで公開される。熱帯アジア産の沈香(樹木に樹脂や精油が付着したもの)の一種。鎌倉時代にはすでに中国を経て伝わっていたらしい。ミュージアムで沈香は購入可能(メチャ高い)。奈良県奈良市。
「東大寺」という文字を隠した雅名「蘭奢待」で知られる香木黄熟香(長さ1.56m)。写真中の付箋は左から明治天皇、織田信長、足利義政が切り取った痕とされるもの。記録では足利義満、足利義教、徳川家康も切り取った。毎年秋に開催される正倉院展などで公開される。熱帯アジア産の沈香(樹木に樹脂や精油が付着したもの)の一種。鎌倉時代にはすでに中国を経て伝わっていたらしい。ミュージアムで沈香は購入可能(メチャ高い)。奈良県奈良市。 再建後の姿。都市計画のため、豊臣秀吉の命により現在地へ移転。織田信孝が建立した信長廟や森乱丸ら殉死者の供養塔などがある。商店街にあるのはちょっと間が抜けているか。京都市河原町。
再建後の姿。都市計画のため、豊臣秀吉の命により現在地へ移転。織田信孝が建立した信長廟や森乱丸ら殉死者の供養塔などがある。商店街にあるのはちょっと間が抜けているか。京都市河原町。 信長の墓が高野山奥の院にもある。奥の院には錚々たる戦国武将たちが眠っているので、眺めながら散策するのも楽しい。やや奥まった場所にあるが、参道に「織田信長公墓所」という立て札があるのが目印となる。なぜか筒井順慶(画面左)と隣同士。和歌山県高野町。
信長の墓が高野山奥の院にもある。奥の院には錚々たる戦国武将たちが眠っているので、眺めながら散策するのも楽しい。やや奥まった場所にあるが、参道に「織田信長公墓所」という立て札があるのが目印となる。なぜか筒井順慶(画面左)と隣同士。和歌山県高野町。
 武田氏を滅ぼした織田信長によって甲斐一国をまかされた河尻秀隆。しかし、信長の権力をかさに圧政を布いたため、領民たちは反発。ついに本能寺の変直後、武田遺臣たちの手で殺害されてしまった。写真は河尻秀隆屋敷跡と伝えられる場所で、遺体は逆さまに埋められたため、別名「逆さ塚」ともいわれる。現在はゲートボール場と民家の間に挟まれており、おまけに石碑の正面がそっぽを向き、傾いている。山梨県甲府市。
武田氏を滅ぼした織田信長によって甲斐一国をまかされた河尻秀隆。しかし、信長の権力をかさに圧政を布いたため、領民たちは反発。ついに本能寺の変直後、武田遺臣たちの手で殺害されてしまった。写真は河尻秀隆屋敷跡と伝えられる場所で、遺体は逆さまに埋められたため、別名「逆さ塚」ともいわれる。現在はゲートボール場と民家の間に挟まれており、おまけに石碑の正面がそっぽを向き、傾いている。山梨県甲府市。