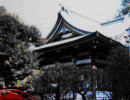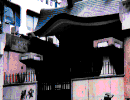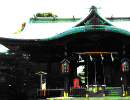新宿御苑

|
新宿御苑は、江戸時代高遠藩主内藤家の下屋敷でした。内藤家では屋敷内の畑で、野菜などを栽培し自給していました。中でも軽くて肥沃な土に適したトウガラシがよくでき、内藤トウガラシと呼ばれて評判でした。今では想像もできませんが、新宿から大久保にかけて盛んに作られていました。菩提寺は太宗寺で内藤家の累代の墓所となっています。
|
明治神宮

|
明治天皇、昭憲皇太后を祀り、12万本の献木が自然の森となっている。
|
成子天神
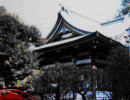
|
成子天神を中心とした地区は、江戸時代マクワウリの特産地でした。幕府は天和年間(1615〜24)に美濃の国、真桑村から農民を呼び寄せ、鳴子と府中の是政村に御用畑を設けて、マクワウリを栽培させました。マクワウリは根が浅く、土の乾燥に弱いので、土に湿気のある神田川流域が適地でした。元禄11年(1698)、新宿に宿場が開設されたため、ウリの栽培は盛んになり、四谷ウリまたは鳴子ウリと呼ばれ、明治に至るまで特産地として栄えました。鳴子ウリの果肉は甘味に富み、甘いものの少ない時代は、水菓子として貴重な野菜でした。
|
花園神社

|
慶安元年(1648)に尾張公の別邸の花園に創建され、その後三光院が別当であったことから、三光稲荷または花園稲荷と呼ばれ、内藤新宿の鎮守として崇敬された。現在の社殿は昭和40年の再建です。
|
歌舞伎町弁天堂
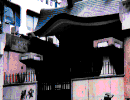
|
明治の始めは歌舞伎町一帯は旧長崎藩主大村家の屋敷があり、大村の森と言われ広大な沼があって、沼には弁財天が祀られていました。
淀橋浄水場の建築に当たり残土で沼は埋め立てられ、尾張銀行頭取峯嶋氏が現在の場所に弁財天を祀りました。大正2年の改築に当たり、不忍弁天堂より現在のご祭神を勧請した。昭和20年の空襲により本堂を焼失し昭和21年復興協力会が峯嶋家に安置しあったご祭神を仮殿に移し、昭和38年に弁天堂を再建しました。現在一帯は歌舞伎町の繁華街の中心です。
|
切支丹灯籠

|
昭和27年(1952)に太宗寺内藤家墓所から出土した織部型灯籠の脚部分で、現在は上部の笠・火袋部分も復元し補われています。江戸時代中期の制作と推定されています。切支丹灯籠は江戸時代、幕府のキリスト教弾圧に対して、隠れ切支丹がひそかに礼拝したとされ、全体の形は十字架を、笠部の彫刻はマリア像を象徴しマリア観音とも呼ばれます。
|
熊野神社
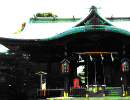
|
十二社の熊野神社は、室町時代の応永年間(1394〜1428)に中野長者と呼ばれた鈴木九朗が、
故郷の紀州熊野権現を勧請したのに始まる。
鈴木家は熊野三山の祀官をつとめる家柄であったが、源義経に従ったため、奥州平泉より敗走し、九朗の代に中野に住むようになった。その後、鈴木家は家運が上昇し、応永10年(1403)には熊野三山の十二所権現を総て祀ったと言われています。
享保年間(1716〜35)に八代将軍吉宗が鷹狩りの機会に参拝し、滝や池を擁した風致は江戸西域の景勝地として賑わった。
氏子町は西新宿並びに新宿駅周辺及び歌舞伎町で新宿の総鎮守となっています。
|