本殿−−−−−御三家銅灯籠−−−−−唐門
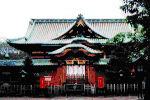
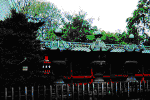

- 唐門(唐破風造り四脚門)
- 慶安4年(1651年)建築。明治40年旧国宝指定。 総金箔の門で、両側上部にある松竹梅と錦鶏鳥の透彫は殊に室町、桃山の技術を集大成したものとして評価されている。柱内外4額面には、不忍池の水を飲みにいったという左甚五郎作の昇り竜、降り竜があり講談などで馴染み深いものである。
- 透塀
- 慶安4年建築。明治40年旧国宝指定。総金箔の門であったが、国の予算がないまま現在下地漆塗りに留めている。上下にある彫刻もすべて極彩色であり、上欄には花木山禽、下欄には水草鳥魚をあしらい、その数約300枚あったが、戦後進駐軍の土産に持ち去られ現在は約250枚程となった。
- 拝殿
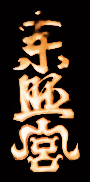
- 慶安4年建築。明治40年旧国宝指定。間口7間、奥行3間で日光に次ぐ結構である。幣殿、本殿と共に銅板葺き屋根であり、日本には二つしかない。(中尊寺光堂)金色殿として有名である。三方の浜縁は総黒漆塗りである。天井は一尺桝目の格天井で、中央正面にある「東照宮」額は後水尾天皇真筆で純金である。壁画は狩野探幽の筆になるもので、桃山期の画風を彷彿させる華麗なものである。
- 幣殿
- 慶安4年建築。明治40年旧国宝指定。将軍家の間で、長押上の松に鷹、鳳凰に牡丹の彫刻や、狩野派の壁画が名高い。
- 本殿
- 慶安4年建築。明治40年旧国宝指定。内部は前後に格桟戸に依って敷切られ、後部は、金梨地の浜縁に巡らされた総金箔の社殿によって占められている。ここに家康公、吉宗公、寒松院(藤堂高虎)、天海僧正の御神体が安置されている。本宮を三所大権現称していたのも、ここから起っている。
- 表参道大石鳥居
- 寛永1010年(1633)酒井忠世建築奉納。昭和17年旧国宝指定。関東大震災の析にも微動だにしなかった程、基礎工事が完全であるというので、建築界の驚異の的となっているものである。
- 池の瑞参道石鳥居
- 寛永3年黒田忠之奉納。江戸城内紅葉山東照宮にあったものを、明治7年5月当宮に移築したものである。
- 水舎門
- 慶安4年阿部重次建築奉納。社前右側にあった御水舎の上屋だけを昭和39年に門として移築した。
- 御水舎
- 明治6年、新門辰五郎奉納。男伊達として江戸市民の崇敬を受けていた辰五郎は、町火消しの棟梁で、特に将軍家の親任が篤かった。娘の芳は徳川慶喜の愛人だった。
- 鋼灯籠
慶安4年諸大名奉納。
 昭和17年旧国宝指定、唐門両側6基は御三家奉献になったもの。このうち社殿向って左側手前の1基だけは寛永5年の銘があり、藤堂高虎(寒松院)が、家康公十三回忌の折に神前に寄進したもので型も南円堂型でおもしろい。
昭和17年旧国宝指定、唐門両側6基は御三家奉献になったもの。このうち社殿向って左側手前の1基だけは寛永5年の銘があり、藤堂高虎(寒松院)が、家康公十三回忌の折に神前に寄進したもので型も南円堂型でおもしろい。

>寄進者に注目<◆◆慶安4年(1651)銅灯篭寄進者名の中には、歴史上の武将名が沢山あり、江戸時代が身近になります。◆◆



