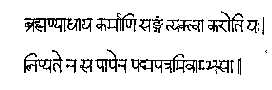
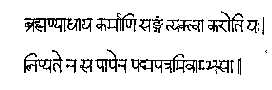
執着を断ち、
行果を梵に献ずるものは、
蓮葉の水におおわるるなきが如くに
罪に汚されず。
以前、生成界のところで、その中に投げ込まれている魂の現状を、対社会的な係わりから見たことがあるのであるが、ここでは、その社会の中における魂の浄化を中心に据えて見てゆくことにする。その生成界の持つ不条理の中で闘う魂がここでの主題である。
前述の所で、この貧しい社会の現状を現出させているのは、個々の魂の物質的欲求に囚われた意欲であることが明らかとなった。即ち、正にその欲求が反省内で増幅され、此の世の一切のものを奪おうとすることから、お互いに手段として規定し、管理し合う状態を現出させてしまうのであった。
その為、個々の魂がより実質的に優れた社会を築き上げようとしても、その社会の外見的な形態のみにかかずらわっている限りは、決して何も変わり得ないと言わねぱならないのである。
問題は、その社会の囚われた意欲を如何にして打ち枠くかにあるのであり、それは取りも直さず、その社会を構成している個々の魂の囚われた意欲に向けられて来るのである。
そして、その問題の解決は、まず初めに、己れ自身が持っているその囚われた意欲を打ち枠くことから手をつけねぱならないのである。己れ自身がまず変わってゆかねぱならないのである。
然しながらここでは、魂の浄化の過程を素描し得るに止まり、己れの変革は、正に己れ自身の闘いの中で掴み取ってゆくしかないことは当然であろう。
ここでは、その闘いの原理的なもののみを示すことにする。
まず、個々の魂が、その置かれている社会の中で、一体如何なるものとして規定され、どのように管理されることになるのかを描き出し、然る後に、それに対する真正な反抗を示してゆくことにする。
下等動物以下のものに関しては、それらの魂が持っている生命力や働きは、因われた意欲の下で、有用な手段・道具として規定され、直接管理され、利用されることになる。
そして、その管理の仕方が、魂本来の意欲にさほど反せず、自然の摂理を破壊しない限り、それは有効なものとなり得るのであるが、然し、因われた意欲の下でそれを無視すると、それらの魂に反逆され、最上位に立つ人間界そのものの存立基盤が崩れ去ることにもなるであろう。
それらの魂は、規定され、管理されていた為に歪んでしまった己れ自身の真正な発現を再び取り戻し、それと同時に、囚われた意欲の為に歪み切ったこの人間界そのものを解消させるのである。
次に、高等動物や人間の段階になると、表象能力の発達の為、その能力に訴えて管理を遂行するようになるので、ここでは、その能力の段階的な働きに従って、その管理の仕組を調べてみることにする。
まず、最初の段階においては、感覚を土台とする実在的な世界の中で、悟性に快い感覚と不快な感覚とを刻み分けさせることから始まる。
その快・不快の感覚は、悟性によって確認される知的な光の戯れとしての性質を持つのであるが、その光の戯れを追い求めさせるように、また避けさせるように馴らすことによって、魂を管理・統制し、本来求めているものを騙し隠す。
即ち、触覚においては、快・不快の感覚を悟性に与え、快楽を求めさせ、苦痛を避けさせることによって、その規定され、鎖につながれた魂を管理・統制する。
味覚においては、本来は、魂そのものが欲しているものに対して、情意の中で〈うまさ〉が覚えられるのであるが、表象能力の発達によって今度は、悟性の知的な光の下でその味が確認されることになり、その為、感覚的な快い味を求めさせ、不快な味を避けさせることによって、魂を管理することも成されるようになる。化学調味料などはその良い例であろう。
また、料理の味も、表象能力が高い者によるほど洗練された味になり得るのであるが、本質的なものから切り離されている限り、行き詰まった状態とならざるを得ないであろう。
同様に、嗅覚においても、単なる知的な光の戯れとしてだけの、快い香りを追い求めさせることがなされている。
次に、聴覚においては、その感覚の知的水準が高く、様々な音からその背後で働きかけている力を写し出すことが出来るほどである為、ここでは、その魂に必要であると見なされるもののみを与え、魂を管理・統制し、さもなければ、情意的なものがほとんど切り捨てられ、または些細な感情(情意の表面的な波の戯れ)のみに持たされる、知的な光の戯れとしての快い音で、魂の本来求めているものを隠し、欺こうとする。
同様に、視覚においても、その知的水準が非常に高いものとして備わっており、その感覚から容易にそこで働きかけている力を写し出すことが出来る為、その能力を利用して、都合の良いもののみを見せ、個々の魂を管理・統制する。
さもなければ、魂に見せてはならないものすべてを隠し、全く差し障りのない画一的なものや、知的な光の戯れとしての快い色・形によって、魂が本来求めているものを欺こうとする。
次に、以上の感覚すべてを含む直観の段階においては、表象内に表されて来る回りのものの振舞・動作が、そのまま魂の発現(思考、行為)を規定し、管理・統制する。
即ち、回りのものの行為・動作によって、共同体の持つ行為規範なり、道徳なり、価値観なり、権力・権威なりが、直接直観内に示され、強要されるのである。
さて、反省の段階においては、その能力が備わると、今まで実在として照し出される世界のみに対して働きかけていた魂は、今度は、反省的な世界に対しても働きかけることになる為、その能力に訴えて、魂を管理・統制することが成されるようになる。
即ち、ここでは、既存の社会的行為規範、道徳、価値観、世界観、そして権力・権威などを合理化し、正当化する為の思想や教義を、何らの深い思考に基づかせずにそのまま飲み込ませ、個々の魂を一つの虚構の中で管理し、統制するのである。
そして、その場合、ある程度の生存的、性的、そして物質的諸欲求を満たしてさえやれぱ、直接暴力を用いずに、群衆に対する家畜並な管理支配が成されることにもなるのである。
その為、そのような虚構がはびこっている社会では、自ら深い思考に基づいて「何故」を発することは忌み嫌われることになる。
また、その反省的な世界に働きかける魂に対して、その判断の根拠または行為の動機としての認識を、都合の良い方へと導こうとすることもなされ、その為、不都合な判断や行為を導き出すような認識の隠蔽、そして都合の良い情報操作がなされることになる。
以上のようにして、表象能力全体に訴えながら、群衆の画一化、白痴化を進め、この人間社会を貧しいものにしてゆくのであるが、然し、それのみによってでは管理は成立し得ず、個々の魂においても、度々浮かび上がって来る「何故」から、その管理・統制の現状を正確に認識することができながらも、己れ自身が利己的な物質的欲求に囚われており、その管理・統制を成さしめている働きと同一な基盤の上に立っている限り、結局その管理・統制の現状を黙認せざるを得ず、そのまま管理を助長させ、完成させてしまうことになるのである。
また、たとえその現体制と敵対する世界観に立って、その管理・統制の現状を打ち破ったとしても、その世界観が如何に理念として立派でありながらも、それを支える個々のものが、その飽くことのない物質的欲求に囚われ続ける限り、やがては、また同じ様な管理支配の体制を築き上げ、様々な確執を続けてゆくことになるのである。
従って、ここにおいて問題は、最初のものに戻らねばならない。
問題の中で、一番初めに手をつけねばならないことは、即ち、己れ自身の持つ囚われた意欲を打ち砕き、魂を浄化させてゆくことなのである。そして、個々の浄化されてゆく魂達によって、初めて、彼の叡知的な世界が此の世に現出するのでなければならないのである。
ところで、以上のような、魂の本来あるべき真正な発現を歪めてしまう社会にあっても、壮健で純粋な魂は、己れ自身を純粋に貫こうとして、強烈に反抗を繰り返すことになるであろう。
一度、真に心から欲する状態を体現すれば、それからは、その徳を追い求めてゆくのである。
そして、その日常的な光の連鎖から逃れ出て、あの燃え上がるような狂気の海ヘ、また、あの純粋に無となり天翔ける天空へと入り込んだ者にとって、再び押し戻され、縛りつけられねぱならないその連鎖とは、常に憎悪の対象であろうが、然し、その徳によって初めて開示された心眼は、常にあの自由性に向けられており、その瞬間が再び訪れるまで彼は、この知的な光の連鎖の中で、闘いながら待つのである。その徳の為に、苦痛などの感覚的に不快なものでも、それが必要であるなら喜んで受け入れてゆくのである。快い洗練された感覚の為に、己れ自身を堕落させるようなことはしないのである。そして、己れ自身の持つ徳によつて、一切の感覚をも否定するにまでなるのである。
ところで、魂に何らの苦闘も与えず、無菌のまま温室の中で発現させようとするのは、最も愚劣なことであろう。大切なことは、魂が傷付かないことなのではなく、傷付きながらも、純粋に己れ自身を貫き通すことなのであり、その為、我々に必要なことは、そのことを厳しく要求し、そして優しく見守ってやることなのである。
五感となつて表れ、魂を脅かし、誘惑するもの、そのものを魂は超克してゆかねばならない。
今、己れが必要とするものは何か、今何を成すべきか、魂はその答えを己れの内奥から聞き取ることが出来るのである。
また、壮健で純粋な魂は、己れに示され、半ば強要されている行為規範・道徳・権力・権威などや、それを正当化する教義・思想に対して疑問を抱き、己れの真正な発現を阻止し、歪める働きをするような一切の世界に対して反抗する。
そして、その植え込まれていた世界の崩壊は、己れの死として引き裂かれるほどの不安を伴うが、然し、そこで死なねばならない自己とは、作り出され強要された己れ自身の影でしか過ぎない。
その《死》の中で初めて、魂は己れの影を打ち砕き、今まで強要されて来た様々な錘から解き放たれることになるのである。
そして、その強要され、背負わされた一切の世界の崩壊の後には、今度は、己れ自身の意欲に基づく一切の世界の創造に導かれるであろう。その強靱な魂は、己れの強烈な意欲の為、一切の事物を追い求め、苦闘することになるであろう。
然し、彼が己れの因われた意欲に基づいて世界を表し、その中で対象を追い求め続ける限り、如何にその世界観が変わろうとも、やはり以前と同じ様に、同じその囚われた意欲に基づいて、様々な目的なり対象なりを追い求め続けるのであると言わねばならない。
だが、彼は求めざるを得ないのである。そして、その強烈に求めていった極点において、己れの追い求めていたものの影としての性質を自覚し、その囚われた意欲すべてが打ち砕かれねばならない。
その崩壊の中で、此の世の一切のものの虚しさを知り、それと同時に初めて、真に解放され、《死》に切れるもののみが持ち得る、満たされた永遠なる喜びを知らねばならないのである。
そして、その《死》の中で真に解放された魂は、それ以降は、たとえ対外的な対象や目的に働きかけ、意欲してゆくとしても、もはやそれらには囚われることなく、消えるにまかせることになる。
己れの内に燈された一点の霊光を頼りに、此の世に対する何らの希望も目的もなく、只闘い続けてゆくことになるのである。
一切のものの虚しさを知りながらも、己れ自身を賭け、己れの浄化の中で、彼の叡知的な世界を現出させようとするのである。
以上のことは、全身を傷だらけにしながらも、闘い続けてゆく魂のみによって成され得、上辺は様々な言葉や行為で着飾ってはいるが、実際には果てしのない眠りに陥入っている魂によってでは決してないのである。
己れの条件の不遇さを挙げつらうのは、己れ自身の無能力を証明することにほかならない。
如何なるものにせよ、頼ろうとするものがある内は、まだ真に己れ自身の闘いを始めているとは言い切れないであろう。
そのようなものが一切影として消え、すべてのものから見捨てられることによって、初めて我々は、己れ自身が自ら光り輝くものとして闘いを始めるのである。
親族、恋人、友人などの、それらすべての関係は、一度徹底的に否定されねばならない。それらの関係を云々する前に、まず我々は、闘う友でなけれぱならないのである。そして、真に己れの実存を賭け、己れ自身の闘いを闘い抜く者達において、初めて真の連帯が、時・空を超えて結ばれることになるのである。
ところで、壮健で純粋な魂は、一切の魂の持つ苦しみが、取りも直さず己れ自身の苦しみであることを直観的に感じ取っており、その苦しみを一身に背負いながら、一切のものの解放を願い、闘い続けるであろう。
そして、その闘いは、認識の程度に応じて、回りのもの、社会、国家、そして最後には、万有の持つ運命にまで向けられることになるであろう。
然し、そこでの闘いは、己れ自身を見失いがちな現象に向けられた闘いであり、その現象に注意が向けられている限り、その闘いには勝ち・負けが、そして最終的には常に負けが、云々されることにならざるを得ないのである。
だが、真なる闘いを、己れ自身の内に見出す者は、その運命に対しても勝つことが出来るのだ。
真に己れを賭け、闘い続けてゆく限り、決して負けることはない。
その極点において栄光を掴むのである。
その《死》において魂を解放し、浄化するのだ。
単なる死ではない、常に勝利が約束された《死》、己れの影を打ち砕く《死》だ!
心穢レナキ阿羅漢ノ赴キシ所ハ
神モ乾闥婆モ人モ能ク知ラズ
我ハ彼ヲ婆羅門ト謂フ
--法句経
最後に、魂の実存を賭けた闘い・反抗を、対社会的な係わりという点から簡単に述べておくことにする。
前述通り、この管理・統制されている貧しい人間社会は、無闇な物質的欲求に因われている為に現出して来ているのであった。
そして、すべての物的・人的要素を己れの有用なるものと規定し、手段として利用することは、即ち、己れの利得の為に、それらのもの一切を奴隷として規定し、有用性の鎖の中に投げ入れ縛りつけることにほかならず、裏返せば、その鎖の輪の中に奴隷を満たす己れの状態こそが、正に、物質的な欲求に因われた奴隷なのであった。
その為、己れの囚われた意欲を打ち砕き、その意欲の下で奴隷として限定されたものを、ありのままの無限定な姿として解放することは、取りも直さず、その奴隷として限定されている己れ自身の影を打ち砕き、その囚われた意欲の下で隠されていた己れ自身を、ありのままの無限定な姿として解放し、取り戻すことにほかならないのである。
日常使用して来たすべての有用な物を火の供犠に掛ける祭りは、その使用されて来たものを、何ら限定されないそのもの自身の姿に解放させると同時に、それを有用なものとして規定し、使用して来た己れ自身をも、その浄化の炎の中で解放し、己れ本来の何ら限定されない姿を取り戻させることを配慮しているのである。
ところで、奴隷制であれ、封建割であれ、または資本主義や共産主義であれ、如何なる体制にあっても、権力というものは、個々の魂を様々な形で規定し、奴隷化することによって、己れの保全と勢力の増大を求める。
そして、その奴隷化は、人間のみだけでなくすべての魂にまで及び、それら一切は、その囚われた意欲の下で有用性の鎖の中に閉じ込められ、縛りつけられることになるのである。
その為、我々は、その怪物の囚われた意欲を打ち砕かねばならない。
我々すべての奴隷として規定されているものは、一身を供犠に付し、その浄化の炎の中で己れ自身の本来の姿を取り戻し、それと同時に、己れの主人をも解放しなければならない。
そして、その場合、その解放の真の主体となるのは、己れの囚われた意欲を否定し、己れを浄化しつつある魂でなければならず、その魂の反抗によって、社会の中で支配的なその囚われた意欲を打ち砕かねばならないのである。
その為、己れの真正な発現を、回りのものや、社会・国家が否定し、歪めるのなら、個々の魂は、それに対して徹底的に反抗しなければならない。
そして、その反抗が決して勝利の望めない運命に対してなされることになるとしても、己れ自身を賭けてゆく限り、決して負けることはないのであり、却って己れの内に苛酷な運命を持つ者は、それに反抗しつつもそれを愛すのである。
その愛の為、自らその運命の渦の中に突ぴ込み、己れを破滅させるのである。
その反抗は運命そのものとなり、その運命に対する愛は、正に、己れ自身への愛そのものとなるだ。
個々の徹底した反抗が、社会的な変革の原動力となり、開かれた社会を産み出してゆかねばならない。その社会の中に、叡知的な世界を無限に透明なものとして現出させねばならない。
その為には、個々の魂が、己れ自身の闘いの中で、その叡知的な世界を各自体現してゆかねばならないのである。
従って、社会的な形態の変革のみを目的として、個々の魂の真正な発現を否定してしまう「革命」は、決して革命的ではなく、反革命的と言わねばならない。
革命は、個々の魂の徹底した反抗、己れ自身の真正な姿を発現しようとしてなされる反抗に、その基盤を持たねばならないのである。
そして、その反抗の中で己れ自身を掴まえてゆく革命家こそ、真に芸術家と言うことが出来るのである。その人生航路において描き出されてゆく数知的な世界こそが、彼の作品なのである。
然し、彼はその作品に拘ることなく消えるにまかせねぱならない。
彼は放たれた一本の失であり、目は常に前方に向けられているからである。
必要なのは、己れ自身を純粋に貫こうとする魂であって、その魂を欠く限り、如何なる体制が生じて来ようとも、それは反革命として終らざるを得ないのである。
然し、彼の統一的一者の配慮の下で、個々の魂は己れを発現しようと苦闘してゆく限り、常にその芸術家は生まれ、己れの生を切り開いてゆくことであろう。如何なる体制にあっても、魂の真正な発現に基づいて、反抗を繰り返してゆくことであろう。
そして、その反抗によって生じる確執は、決して咎められるべきものではなく、すべてのものがその閉塞的な状態から解き放たれ、新しい次元に至る為の切っ掛け、即ち幸運にほかならないのである。
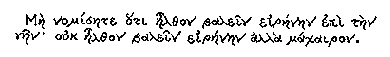
我、此の世に平和をもたらさん為に来たれりと思うな、
平和にあらず、
却って剣を投ぜん為に来たれり。
--マタイ伝
第五部 己の実存を賭けた闘いーーーおわり