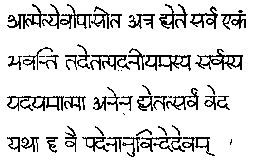
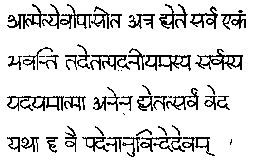
人は宜しくアートマンとして讃えるべし。
何となれば、ここにおいて、
これら一切のものは一つに合流すればなり。
そのアートマンは、
この一切に足跡を置くものなり。
実に、これによってこそ、この一切を知る。
恰も足跡から(その対象を)見出す如くに、
(アートマンによって一切を見出す。)
まず、ソクラテスの哲学的問答法(διαλεκτικη)に倣って、日常我々が〈存在〉するとしている様々なものを、一つの本質的な相にまとめ、そして次に、その相を、それぞれの〈存在〉が持つ自然的な性質に従って、幾つかの異なった領域に区分することが必要である。
そこでまず、我々に与えられる一切の〈存在〉は、表象内で表され、確認される一切のものであると、このように総観することが出来るであろう。
従って、その表象内に表されて来るものが如何なる類いのものであろうとも、我々はそれに〈存在〉としての地位を与えねぱならないのである。
そして次に、性質上異なった〈存在〉が、それぞれどの領域に帰属することになるのかを調ぺてゆくことになるのであるが、その領域を正確に区分し、その各領域における〈存在〉が如何なるものとして表されて来るのかを正確に規定するには、単に表されて来た〈存在〉を、それぞれが持つ自然的な性質に従って区別し、分類するだけでは不充分であると言わねぱならず、その為、我々は、統一し、それぞれの領域の〈存在〉を表すもの、そのものの働きにまで注意を向けねばならなくなるのである。その表象機能として働く統一主体※(1)によって、一切の〈存在〉が表象内に表されることになるからである。
その統一主体の働きを正確に辿ることによって、初めて我々は、各〈存在〉の帰属する領域を明確に規定し得るのである。
この第一部では、その統一主体の働きを辿って、各〈存在〉の領域を区分、設定してゆくことにする。
※(1)この統一主体は、決して自律的に働くわけではなく、現象の中では、個体の持つ魂(生命)の働きの一つとして位置付けられることになる。
ところで、我々にはこの統一主体の働きをそのまま追うことは出来ず、その働きの結果つけられた足跡から、事後的にその働きを推測することしか出来ない。
何故ならば、統一の先端において、常に統一しつつある主体は、決して統一されることはなく、即ち、同一の統一点において、同時に統一しつつ、統一されるということはあり得ないからである。
その為、統一主体は、己れの働きを辿る為には、その統一の先端において、以前の己れ自身の働きを統一の対象とするしかなく、従って、これから述べる表象機能の働きも、絶対的なものではなく、推測によって得られたありそうな話としての意義付けぐらいしか持ち得ないとすることも出来るであろう。
然し、残され、得られた足跡から、その統一主体の各領域における働き(表象機能)を仮定することは出来、そして、その仮定と残される足跡との対応関係を根気よく調べて、仮定を修正してゆきながら、出来る限りこの〈存在〉を表す統一主体の働きを正確に推測し、設定してゆくことは出来るのである。
そこで、その統一するものとしての主体に就いて更に詳しく調べてみることにしよう。
まず、このものの働きは、前述通り、魂の働きの一部として、知性の光を受け持っており、この光によって〈存在〉を照し出し、または浮かび上がらせることになる。 その為、光を燈すもの、即ち統一主体と、その光の下で表される〈存在〉とは、表裏一体、不分離の関係にあると言えるのである。
次に、その働き方は、その知性の光を順次投げ入れて〈存在〉を継起させることになる。そして、この継起性を内容とする統一形式に従って表されて来る諸〈存在〉すべては、「時間」として示される継起の相互的な規定関係を持たされることになるのである。
ところで、前述通り、統一の先端において常に統一しつつある主体そのものは、決して表されることはなく、その相互的な規定関係の中に入り込むことはない為、その常に統一しつつある主体と、その規定関係の中で表されて来る一切の〈存在〉とは、まるで無としてしか規定し得ない何か或るものの深淵※(1)と、そこから次々と浮かび上がっては消えてゆく泡沫(うたかた)とに喩えることが出来るであろう。
そして、今ここで設定された常に統一しつつある主体も、我々の反省内で表されているものである以上、それも泡沫として浮かび上がった〈存在〉以外の何ものでもないのである。
然し、その深淵に浮かび上がる一切の〈存在〉が泡沫のようなものだとしても、その表されて来るものを充分な認識の下で現象にまで高め、そこから、その深淵の領域に対して、我々の能力が許す限りの水平線にまで、認識の光を当てることが今必要なことなのであり、このような現象的な把握によってでしか我々は、その無としてしか規定し得ない何か或るものの何らかの姿を推測することが出来ないのである。
※(1)この深淵は、一切の魂の状態を体現し得るものであり、個別的な状態を云々する必要は全くない。従って、行為時の表象を云々する場合でも、実際には、行為時の状態を体現しているその深淵から、その表象が浮かび上がって来るのである。
さて、いよいよ今度は、統一主体によって統一され、表されるようになる各領域の〈存在〉を、統一主体の働きと共に見てゆくことになるが、まず最初に、情意として示される領域の〈存在〉を調べてゆくことにしよう。
ここで表されるものは、個体の魂の状態が統一主体に直接反映されているものであり、その反映に統一主体が統一を向け、己れの持つ知性の光の下でそれを内的に確認し、覚えることによって、その情意としての〈存在〉が獲得されることになるのである。
それは、統一主体も、個体の魂の働きの一つとして、当然その魂の持つ状態を体現していなけれぱならず、それが即ち、情意として内的に表されて来るからである。
その為、この情意として表されて来るものは、統一主体が働く所では常に認められ、その表れは、魂自身が己れの状態を確認する意味合を持つ。
このようにして、「喜び」、「悲しみ」、「苦しみ」、「怒り」などと言い表されている状態が、この領域において覚えられ、〈存在〉を獲得することになるのである。
そして、これらの情意は、他の領域において表されるに至る〈存在〉(直観及び反省内での)に対して、自身が持つ特別な色合を投げ掛けることになる。
そのことは、同一なる対象を照し出している場合でも、喜びの中にある時のものと、悲しみの中にある時のものとでは、それぞれ全く異なった色合が与えられ、その同一対象の持つ意味合が異なってしまうことからも察せられるであろう。
そしてまた、この情意として表されて来るものが、現象的な把握の中では、魂の諸状態に対応するものであることから、我々はこの情意の領域において魂の様々な状態を体現し、覚えることによって、初めて万有の持つ魂の諸状態を知り得ると言わねばならない。
ところで、表象を浮かび上がらせる内的な深淵の中では、他の領域の〈存在〉に常に反映されているこの色合は、その深淵に広がる暗黒の海が持つものと言え、統一主体は、その海に浮かび、舵を操る只一つの知性の光であると喩えることが出来るであろう。
そして、この情意として覚えられるものは、ここでは、その暗黒の海が主体を揺すったり、引っ張ったりするのを、そのまま己れの知性の光の下に内的に表すことによっていると言えるであろう。※(1)
それは、恰も舵を操るものが、描き出される回りの風景に注意を向けていたのが、今度は、己れを浮かばせ、支えている海の状態に注意を凝らすような場合に似ているであろう。
但し、その状態の確認の仕方は、直観内でのように、感覚的な〈存在〉を対外的な世界の中に照し出すと言うのではなく、己れ自身がその海の一部として、その海の中に標いながら、その動きを全く内的に主客合一の内に覚え、確認するのである。
また、魂の状態として把握されるその情意の海は、他の領域において表されることになる〈存在〉に対して遥かに根源的なものとしてあり、その強烈な情意の働きによって、その〈存在〉が全く無視され、否定されてしまう例は数限りなく生じて来るであろう。
※(1)情意の海の様々な動きは、魂が己れ自身を発現しようとする過程において伴う。即ち、魂は、統一主体の光の下で対外的に照し出される実在的な世界に対して働きかけ、己れを発現させてゆくが、その場合、その〈存在〉の中のある対象に対して働きかけ、己れの意欲を顕在化してゆき、その過程において、直接我々の内的な深淵には、情意の様々な渦が生じて来るのである。然し、現象的な把握によっても、それ以上のことは規定し得ず、「何故その対象に対してそのような情意を持つに至ったのか」に就いては、その根拠を、その内的現象の背後に控える叡知的な領域に委ねなければならないのである。
さて次に、情意とはまた別な領域における〈存在〉を検討してゆかねばならない。
まず、ここで取り扱う〈存在〉の全領域を総観して、一つの相の下にまとめ、それを「直観」と呼ぶことにする。
そして、この直観内で働く統一主体の段階的な機能に対応して、その働きから照し出されて来る〈存在〉を、直覚、知覚、直観の各領域のものに区別し、順次調べてゆくことにしよう。
然し、その前に我々は、その直観内の全〈存在〉に具体的な内容を与えることになる素材としての「感覚」に就いて少し触れなければならない。
この「感覚」と言い表されているものは、前述の直覚、知覚、直観のような、統一主体の働きに応じて設定される形式的な〈存在〉の領域とは異なり、それは、それらの領域において照し出されて来る一切の〈存在〉の素材となり、実質的な内容となるものなのである。
それ故にこそ、この感覚を内容として満たしている一切の〈存在〉を、直観として一つの相に統べることが出来たのである。
従って、この感覚とそれらとは同一に論じてはならないのである。
次に、この感覚を土台とする世界が、何故備えられるに至ったのかに就いては、高度に分化、発展して来た魂の発現を助ける為に、表象能力が開花して来たと言うことが出来るであろう。その能力によって、初めて我々は、己れを発現させる為に働きかける対象を、対外的な世界の中に表すのである。
その感覚を土台とする世界が知性の光によって燈されるのは、恰も窓が少し開けられ、一条の光が暗闇の中に差し込み、そこから初めて外の世界が望まれる如くに、初めてこの知性の下で、対外的に〈存在〉が照し出されるのである。
ところで、この直観内では、情意の場合とは異なり、統一主体は己れの状態を主客合一の内に確認するのではなく、何らかの刺激(光の下に照し出されて初めて感覚として覚える)に対して統一を向け、己れに対して他者を照し出す。
その為、その他者は、当然己れとは対立する己れ以外の〈存在〉としての性質を持たされ、その対外的な世界の中に表されることになるのである。
それ故に、その表されて来るものが、たとえ味覚や嗅覚のようなものであっても、統一主体はそれを他から働きかけて来るものとして、対外的な世界の中に照し出すのである。
その上、聴覚になると、その働きかけは空間的な方向性を持つものとして表され、そして、触覚や視覚に至っては、三次元の広がりを持たされ、統一主体はその空間の広がりの中で、己れとは異なった〈存在〉を表してゆくことになるのである。※(1)
また、この直観の世界の素材としてある感覚は、統一主体の投げ掛ける知性の光に照し出されない限りは、その深淵の闇の中に隠されたまま、情意と何ら区別されることなく、その海の表面に漂っているとすることが出来るであろう。そして、その表面に漂う幻想的な波の働きかけ(刺激として)に対して、統一主体は統一を向け、己れの光を投げ入れて、この直観として示される実在的な世界を己れの回りに照し出し、描き出す。
その場合、その闇の中で漂うものは、常に己れの存在性を主張し、統一主体の注意を引こうとしているのであるが、その働きかけが緩慢で、何らの変調も持たないような時には、強引にその注意を向けさせることは成し得ず、そのものはそのまま闇の中に止まることになる。
これに対し、そのものが急減な変調を持つ時には、統一主体は強引にその働きかけに引き摺られ、否応無くその方向に注意が向けられ、そのものを己れの知性の光の下で照し出し、確認することになる。
ところが、表象能力が発達して来ると、そのような急激な働きかけに対してだけでなく、自然で、何らの変調も持たないものに対してまでも統一を向け、〈存在〉として照し出し、確認することが出来るほどにまでなるであろう。
さて、次に、この感覚を内容として持つ〈存在〉も、情意の場合と同様、統一主体の統一形式に従って継起し、その為、その統一の過程上のずれを考慮する限り、刺激として働きかけて来るものと、知性の光の下に照し出されるものとは、全く同一なものと言うことは出来ず、何らかの異なった種類のもの同志と言わねぱならないのである。
何故ならば、我々はややもすれば、その統一の過程上のずれを無視して、その表されて来る〈存在〉に遡及的な地位を与えてしまう為、その〈存在〉が外から働きかけていたものと見なしてしまうことになるのであるが、然し、その働きかけは、決して「外」からのものではなく、己れの内なる深淵から発しており、それに統一主体が統一を向け、対外的な世界の中に、感覚を内容とする実在的な世界を表すことになるからである。
その働きかけに対して照し出されるその〈存在〉は、正に知性の下で照し出される知的な光の戯れとしての性質を持たされているのである。
従って、以上のことから、「感覚器官」や「身体」とされているものも、決して感覚を表すものとしてそれに先立つとすることは出来ず、それらは、その感覚を土台として描き出される知的な光の戯れとしての性質しか持ち得ないであろう。※(2)
現象的な把握では、それらは魂の感覚上の直接的な表れであり、従って、魂そのものの働きかけすべてに対して、それらの表されて来るものは、極限定された一側面上の影としての意味合しか持ってはいないと言うことが出来るのである。
然し、だからと言って、その表された〈存在〉が全くの光の戯れに終ってしまうと言うのではなく、己れの身体であるなら、統一主体は、己れの内に魂の様々な状態を体現し、それを情意として覚えるのであり、その体現の中で、その知的な光の戯れは、それ自身とは別な何らかの実質的な意味合を持たされているのである。
また、他者の身体であっても、表され、得られるに至った感覚的表象から、そのものの魂の状態を察することは出来るのである。
その為、我々がその「身体」の概念を、その知的な光の戯れに止まらせたくないのなら、それは、直接己れの内なる深淵そのものを指し示すのでなけれぱならないであろう。現象的な把握では、魂の働きそのものであると言えるであろう。
※(1)このように見れば、空間形式とされるものは、感覚を土台とした世界を表す際に認められる、主体に対する客体の定立そのものが持つ、対外的な関係の発展したものとして把握されることが出来るであろう。
ところで、この空間形式の適用は、感覚を土台とするこの直観内で初めて固定され、諸〈存在〉は、空間内での位置の明確な相互的規定関係を持たされることになるが、これに対し、反省内で適用される場合では、表される諸〈存在〉(イメージとして)は、たとえ以前直観されたものであっても、その規定関係は曖昧なものとならざるを得ないのである。
※(2)光の戯れとして表されるものは、単に視覚におけるもののみではなく、知性によって照し出され、確認される一切の感覚におけるものである。従って、「痛い」、「冷い」、「臭い」、「苦い」などの感覚も、それが知性の光の下で初めて確認されることになるのである以上、知的な光の戯れを構成するのである。
ところで、情意として表されて来るものも、知性の光を必要とし、同じ光の戯れの中に入るが、然し、その領域が持つ根源性から、前者のものとは全く性質を異にすると言わねばならない。前者では、正にその光の戯れこそが、魂の発現を助ける手段として備えられねばならなかったのである。
さて、以上のように、直観内での素材として、そこでの〈存在〉の内容を満たす感覚に就いて検討して来たが、今度は、いよいよ直観内での統一主体の働きに応じて、そこでの〈存在〉の各領域を区分し、調ぺてゆくことにしよう。
そこで、まず、この感覚を土台とする世界の基礎となり、一番重要な〈存在〉の領域を、「直覚」と呼びならわすことにする。
これは、統一主体が情意の海の表面に漂うものの働きかけ(刺激として)に対して知性の光を投げ込む時、その光によって照し出されるものである。そして、この光の一投によって、初めて実在的な此の世界が表されて来ることになるのである。
それまでは、統一主体は未だ充分なる能力を持つに至らず、只情意の海に揺られながら眠るだけだったのであるが、やがて、深い眠りから醒め、重い瞼をこすりながら己れの燈した光を確めようとすることであろう。でも、暫くの間は慣れずに、正確には対象を認めることは出来ないであろう。
然し、時が経つにつれ、様々な働きかけにぶつかりながらも、たどたどしい動作で光を投げ込み、〈存在〉を表すようになる。
それと時期を同じくして、生まれながらにして備わっている空間形式を、触覚を表す時に適用し、徐々に〈存在〉に持たされる位置の相互的な規定関係を把握して、それから、その把握を基準として、今度は視覚における空間の把握を訓練することになる。
そして、そのように訓練を積んだ統一主体は、やがて明瞭な光の下で、正確に対象を空間内に描き出し、働きかけることが出来るようになるのである。
ところで、この領域のみで働く統一主体は、万有の中における最初の知性として、その光は非常に弱く、その為、暗闇の情意の海に漂うもの一切を、一瞬の閃光の下にすべて照し出すようなことなどとても出来ず、その燈された弱い光を次々に投げ込みながら直覚を表してゆき、実在的な世界を描き出すことになるのである。
そして、その統一の仕方(継起性)は、反省内でも承継されることになる。※(2)
然し、この仕方では、光を投げ込み、闇の中を照し出して獲得した〈存在〉は、彼が少しでも注意を怠れば、直に元の闇の中に消滅してしまい、また別の新たに照し出される〈存在〉が継起してゆくことになるであろう。
だが、このように、一度生成したものが跡形もなく消滅してしまうのでは、常に世界は、その統一の先端において燈されつつある、相互に何らのつながりもなく点滅するこの直覚一点のみと言うことになり、その貧しさを憐れんだ神は、その世界をもっと豊かなものにしようと試み、生成したものすべてをそのまま光の下に止めておくことは、統一主体にはとても出来ないことから、その生成する〈存在〉を、統一主体の内にある柔かい何度でも使うことの出来る「版」の上に刻み込み、それを記録し、保存させるようにしたのである。
その結果、一度生成して、消滅してしまったものも、何らかの働きかけによって、再び浮かび上がって来ては己れの〈存在〉を告げるようになるのである。※(3)
ところで、生成するものが同じように刻印されるわけではなく、その刻印の程度は、魂自身がその時持つ意欲の状態に左右され、そして、浅くしか刻印されなかった印影は、直に忘却の深淵の内へと投げ捨てられ、消されてしまい、反対に、深く刻印されたものは、生涯消されずにその跡を残すことになる。
だが、表象能力の発達によって、たとえその刻印が浅くとも、何度も同じものを押し刻むと、徐々にその印影は深さを増し、長い期間その跡を残すことも成され得るようになるであろう。
※(1)刺激に対して統一が向けられるが、既にそれに対応する〈存在〉を照し出し、確認することが出来ないような場合には、その刺激に対して統一が向けられる限り、少なくとも、浮かびつつあった何らかの感覚として意識されることになるが、然し、確認されない以上、それに〈存在〉の地位を与えることは出来ないであろう。
※(2)統一形式における継起性は、直覚を一つの点とする断続性であり、その断続性を反省内で埋めることによって、不可分な連続性を内容に持つ「時間」の概念が成立することになるのである。
ところで、表象内で最初に時間性(継起性)が生じて来るのは、点として区分される異なった直覚が二つ続く時である。そして、「瞬間」の概念は、その点と点との間にあって両者を橋渡しする刹那的な間合をその内容として持つのである。
この統一形式が一体如何なる根拠に基づいているのかに就いては、すべての領域における統一主体の働きがこの形式に基づいており、また空間形式の場合のように、主体に対する容体の定立といった働きのみにその形式の根拠が限定されると言うようなこともないことから、(実際、主客合一の中で表される情意にあっては、空間など全く問題とはなり得なかった。)その統一形式の根拠は、その統一主体そのものをも統一する何か或るものにまで辿ってゆかねばならないであろう。
※(3)このようにして表される〈存在〉は、直観内におけるものとは異なり、その版に刻印された印影がイメージとなつて浮かび上がって来るのである。
次に、直覚として与えられる諸〈存在〉を魂の関心の元で一つに連結し、得られる〈存在〉の領域を、知覚と呼びならわすことにする。
ところで、もし統一主体の働きが直覚のみを点滅させるだけなら、そこで照し出される世界は、互いに分断された何らの連結性も持たない光の継起としてしか表されないであろう。
その世界では、まだ様々な感覚的性質が、直覚の段階でそれぞれ分離・独立したまま生成、消滅するのみで、諸性質の総合体としての対象なり、物体の形態なり、または、性質の変化なり、物体の運動なりは、未だ表されては来ないのである。
然し、やがて表象能力が発達するにつれ、諸直覚を連結し、対象の知覚の状態を表すようになる。そして、その場合、統一主体は次々と光を投げ込んで直覚を点滅させ、その生成して来るものを次々と己れの内にある柔かい版に刻み込んでゆき、ある一定の系列が完結すると、その幾つもの刻み込まれた印影は、一つに連結されたまま記録されることになる。そして時には、それが知覚的なイメージとなつて浮かび上がることにもなるのである。
以上のことは、統一主体の刻印作用が充分発達し、記録が容易になされるようになって初めて認められることになるであろう。
ところで、その諸直覚を系列とする連結の本来の主体は、統一主体を支える魂そのものであると言わねばならず、その魂が持つに至った関心が、統一主体によって表されて来る諸直覚を、一本の因果的な鎖に縛り上げることになるのである。
従って、諸直覚を系列とする連結は、単に統一主体の知的な能力のみに基づくのではなく、その連結の本来の主体を、魂そのものの持つ関心に求めてゆく必要があるであろう。
即ち、魂が直覚において己れの意欲の対象を認めると、それを切っ掛けとして、その対象に関する後の諸直覚が魂そのものの関心の元で強く結びつけられ、その対象の知覚の状態が描き出されることになる。
そして、そのように、魂の持つ関心の程度によって諸直覚の系列も、そのつながりを強くしたり弱くしたりする為、意欲の対象が見出されないような時には、諸直覚は散漫な結合しか示さず、そして、その連結の鎖が極度に弛められる時、その世界に表される一切の〈存在〉は、幻のように何ら取り留めのない薄れた陰影となつて通り過ぎるだけのものとなる。
そしてまた、その連結の程度に対応して、情意の色合も、濃いものになったり、薄いものになったりするのは、どちらとも魂そのものの状態を根拠としていることから当然であると言えるであろう。
以上のように、諸直覚を系列とする連結は、その直接的な根拠を、魂そのものが持つに至る関心に求めねばならず、その系列を因果関係の中で把握し得るようになるには、反省内での操作を俟たねばならないのである。
また、前述通り、その刻印される印影は、魂の関心に従ってその刻印の深さの程度に差が生じて来る為、ここで得られる知覚の状態も、その深く刻み込まれるものによって、大部分その内容は決定されることになるであろう。
さて、それでは次に、知覚において表される様々な〈存在〉の状態を、その自然的な性質に従って幾つかに区別し、整理してみることにしよう。
(1)まず、感覚的諸性質の総合体として、対象を認める場合に就いて。
この場合には、直覚として表される様々な感覚的諸性質から、それらを連結し、一つに総合して、対象の全体像を確認する。触覚、嗅覚、味覚、聴覚、視覚の一切のものが連結の素材となる。
(2)次に、(1)の特例として、触覚及び視覚において適用される空間形式によって、物体の形態を認める場合に就いて。
この場合には、空間形式の適用によって表されて来るもの同士が持たされる位置の相互的な規定関係から、その対象の持つ空間内での形態を確認する。そして、その相互的な規定関係とは、三次元の広がりにおける諸部分の位置に関するものであり、それは、それぞれの部分は、その位置に関しては、ほかのあらゆる部分によって規定されており、またそれらを規定していることを内容としている。
(3)次に、対象が持つ感覚的性質の変化を認める場合に就いて。
この場合には、対象が持つある特定した感覚的性質の変化の有無を確認することになるが、その変化の有無は、以前に照し出され、刻印された印影の強さの度合と、今照し出されているその感覚的性質の強さの度合との差の、直接的な確認である。
その確認は、反省内での同異の判断とは性質を異にし、刺激として示される働きかけに応じて、直接変化の有無の状態を表すのである。
また、この「度合」という概念は、あの感覚として表されることになる働きかけの強弱の程度も、知性の光の下で当然確認されることから生じて来るのであって、その程度に従って、刻印される印影も度合を持つに至るのである。※(1)
ところで、この感覚的性質なり、その印影なりが持つ度合は、前述の、魂の関心に基づいて刻み込まれるものとは性質を異にすると言わねばならない。前者における度合の強弱は知的なものであるが、後者における刻印の深浅は情意的なものである。
その為、我々は、ほんの些細な感覚に対しても、魂そのものにとっては原子爆弾のように受け取られ、刻み込まれることも、また、強い刺激によって強い度合の感覚が表され、印影に刻み込まれるとしても、それが魂にとって関心のないものであれば、直に忘却の深淵に消し去られてしまうことも、難なく説明し得るのである。
さて、前に戻って、その以前に刻印された印影の持つ度合と、今照し出されているものが持つそれとが、何らの差異もないものとして表されている場合には、無変化の状態にあるとされ、その今照し出されているものが異なった度合を持って表されて来る場合には、変化の状態にあるとされる。
また、前二者が同一なる度合を持つものとして表されていたが、今照し出されているものがそれと異なった度合を持つものとして表されて来る場合には、無変化の状態から変化の状態への移項が認められ、反対に、前二者が異なった度合を持つものとして表されたが、今照し出されているものが手前のものと同一なる度合を持つものとして表されて来る場合には、変化の状態から無変化の状態への移項が認められることになる。
そして、無変化の状態から変化の状態へ、または、変化の状態から無変化の状態へと移項する時に指摘される「瞬間」の概念は、前述通り、今照し出されているものとその手前にあるものとの間にある、深淵を橋渡しする刹那的な間合を内容としているのである。
(4)最後に、(3)の特例として、空間形式の適用によって物体の運動・静止を認める場合に就いて。
この場合には、上述の感覚的性質の変化の有無に取って代って、特別に空間形式の適用によって、照し出される同一対象の空間内における位置の変化の有無が問題となるだけに過ぎない。
従って、(3)では感覚的な性質の度合の同異が問題となったが、ここでは、位置の同異が問題となるだけで、静止の状態、運動の状態、そして、静止の状態から運動の状態へ、運動の状態から静止の状態への移項の確認は、本質的には(3)の場合と何ら異なることはないのである。
※(1)その感覚的性質の度合の確認・測定は、知性の光の下で初めて可能となるのであり、従って、感覚的諸性質の度合に対して微妙な点にまで識別を成し得るには、明らかに表象能力の高さが、そして、それを前提として、経験の中で充分な訓練を積むことが必要である。
※(2)同一対象に統一が向けられ続けている場合、以前に確認されたものが消滅しても、その消滅後新たな生成に至るまでのものは、浮かび上がりつつあった何らかの感覚として意識され、統一主体の確認を経て〈存在〉が生成することにより、その〈存在〉に遡及的な地位が与えられることになる。
その為、その同一対象は、統一が向けられ続ける限り、いつも〈存在〉し続けているものと見なされてしまうことになるのである。
然し、統一が向けられ続けるとしても、統一主体は己の光を常に燈し、確認し続けるようなことは出来ず、照し出され、確認されたものは、再び漠然とした感覚的な状態へと消滅するのである。そして、そのような状態では、何らの〈存在〉も確認されてはいないと言わねばならない。
その為、変化の状態だけでなく、無変化の状態を認める際にも、只一つの直覚としての〈存在〉が表されているのではなく、複数のそれが継起しているとしなけれぱならないのである。
特に、変化の状態を認める場合には、その同一対象は統一が向けられ続ける限り感覚は浮かび上がりつつあるものとしてあり、その感覚的なものの変調に対して、知性の光の下で変化が確認されることになるのである。
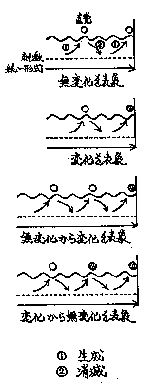
以上のように、感覚を土台として、統一主体によって照し出され、描き出される一切の世界を、「直観」と呼ぶ。
従って、その中には、直覚、そしてその直覚を系列項とする知覚等の一切が含まれるのである。
この直観の領域において表される〈存在〉は、諸知覚を内容とする直観的な世界の状態(その世界の空間的な把握も含めて)にまでその範囲が及ぶことになるのであり、その地点から、知覚の段階で表されるに至った様々な状態をぐるりと見回すこととなる。
そして、この段階で表されて来る諸知覚同志の関係は、前述の知覚での場合のように、諸知覚を強い一本の鎖で連結するというわけにはいかず、諸知覚同士の独立性は強いと言わねばならない。
然し、この場合でも、魂の持つ関心の程度によって、諸知覚同士は強い結びつきを持たされて来ることもあるであろう。
ところで、直観と呼ばれている世界がこのような性質を持つのであってみれば、被統一面において直接実在性を持って照し出されて来る〈存在〉は、直覚としてだけであり、知覚なり、直観なりは、直覚を構成要素とする非実在的な〈存在〉の領域を形作るに過ぎないと言えるであろう。それらは、統一主体の働きに応じて設定される形式的な〈存在〉であるに過ぎないからである。
この直観内で働く統一主体を悟性と呼び、その働きを直観作用とすることが出来るであろう。
さて、ところで前述の通り、統一主体の持つ統一形式の為に、実際に光の下に照し出されているのは、その統一の先端において統一が向けられ、確認されているものだけであり、それまでに生成して、既に消滅してしまったものは、これから生成するであろうものと同じ闇の深淵に投げ捨てられていると、このように言うことが出来るであろう。
然し、後者が全く無限定であるのに対して、前者は既に一度生成して〈存在〉を獲得するに至った以上、統一形式に基づく継起の相互的な規定関係を、またその上、あるものは、空間形式に基づく位置の相互的な規定関係を持たされた上で、感覚的諸性質が刻み込まれ、印影となつて記録され、保存されているのであって、その印影が何らかの働きかけによって、イメージとなつて表象内に浮かび上がって来るのである。
このようにして、直観内で刻印されたもので、そのまま表象内に浮かび上がって来るイメージを、記憶と呼ぶ。
そして、それには、統一主体の働きかけなどによらず、全く自然に浮かび上がって来る場合と、反省内での統一主体の働きかけ(想起作用)によって浮かび上がらせられて来る場合とがある。
前者の場合には、ショーペンハウェルによって喩えられているように、「いつも折り目をつけておくと、その後はいわばひとりでに折れるようになる一枚の布」とすることも出来るであろう。
その場合には、統一主体が同一対象を繰り返し刻み込むことによって印影が濃くなり、ちょっとした切っ掛けから、それがイメージとなつて浮かび上がることになるのである。
然し、その場合よりも、魂そのものの関心の元で強烈な印象が深く印影に刻み込まれるような場合の方が、その自然発生的な記憶は成されやすいものであり、たとえ様々な表象が中間に入り込んで来て、一時記憶が速断えることがあるとしても、そのような記憶は何らかの切っ掛けから直に、鮮明な形で蘇るものである。
単に知的な操作のみによって得られる印影は、たとえその時何度繰り返し刻み直されたとしても、やがて時の経つにつれその印影は薄れ、そして、二度と記憶となつて浮かび上がっては来ない場合がほとんどであろう。
一方、後者の場合には、前者と同様な喩えによって表現すれば、「以前析り目をつけておいたものを、後になって確認し、再び折り直す一枚の布」とすることが出来るであろう。そして、この場合のものは後に詳しく取り扱うことにする。
ところで、記憶がイメージとなつて浮かび上がる場合、そのイメージは当然実際に照し出されたものの陰影としての性質を持ち、そこで表されて来る〈存在〉は、その照し出される実在的な〈存在〉に対応して、直覚的イメージ、知覚的イメージ、そして直観的イメージと区別し、設定することが出来るであろう。
このように、統一主体の働きが直観作用のみに止まる限り、表象内に表されて来る〈存在〉は、照し出される実在的なものか、若しくは記憶として自然に浮かび上がって来るものか、その執れかの内の一つと言うことになり、このような世界では、まだ、生成し、浮かび上がって来るものが一切であり、彼はそこで表されて来る世界に一体となったままであると言えるのである。
さて、我々は、統一され、表されて来ることになる第三番目の〈存在〉の領域、即ち「反省的な世界」に入る前に、それを準備することになる表象能力の発達を調べておく必要があるであろう。
その為、反省内での統一主体の働きの中で最初の段階に位置するもの、即ち以前刻印された印影を随意に浮かび上がらせようとする想起作用が備わるまでの、その段階的な発展を、経験として与えられている足跡から推測し、その道筋を追って調べてみることにしよう。
ところで、以前、自然発生的な記憶の所で、直観作用において突如、具体的に照し出されているものとは別に、記憶がイメージの形を取って浮かび上がって来ることを述べたが、それは別に統一主体(悟性)が働きかけて浮かび上がらせるわけではなく、何らかの切っ掛けから自然に浮かび上がるのである。※(1)
その為、それを浮かび上がらせる直接的な働きは知性ではなく、その根拠を己れの内なる深淵そのものに求めなければならず、言い換えれば、魂そのものの働きとすることが出来るのである。※(2)
そこで、ここでは、この自然発生的な記憶から、想起作用に基づく記憶が成されるまでの、段階的な過程を推測しなければならない。
(1)まず最初の段階において。
この段階では、統一主体によって照し出されるものを切っ掛けとして、以前刻印されたものの中で、それと同様なものの印影がイメージとなつて浮かび上がる。
ここでは、未だ表象能力が充分に発達していない為、魂そのものにとって生死にかかわるほどのよほど重大な事柄においてしか、記憶として浮かび上がらない。
それは、以前経験した危険や災難を再び繰り返さないように、魂そのものが統一主体に忠告を発する意味合を持つのである。
このように、この段階で記憶として浮かび上がって来るものは、魂そのものの重大な関心の元で深く刻み込まれたものに限定されるであろう。
そして、ここでの表象能力は、知覚を成す程度にまでは発達していなければならない。
即ち、記憶として意識されるには、実際に照し出されているものと、印影からのイメージとの明確な区別が成されていなけれぱならず、その区別は、正に両者を対比し得る連結関係の中で初めて可能となるのであり、そのことが成されるのは、知覚の段階以上においてであるからである。
その場合、諸直覚を照し出し、連結している統一主体は、その間に突如として浮かび上がって来るイメージを、己れが今実際に照し出しているものとは異なるものとして直接認めるのである。
ところが、表象能力が直覚の段階で止まるなら、そこで刻印されるに至った印影は、たとえイメージとして浮かび上がるとしても、それは、記憶としてではなく、幻覚として表されて来ることになる。※(3)
即ち、その段階での諸直覚の点滅には何らの結びつきもない為、たとえ直覚的なイメージが浮かび上がるとしても、他の実在的な諸直覚とは何ら区別し得ず、分離されたまま点滅する諸直覚と同様に、これもその中で全く独立して表されて来るからである。
そして、そのことから、たとえ知覚を成し得る表象能力が備わっていても、その知覚的なイメージが、照し出される実在的な世界から全く切り雄され、それのみが統一主体の光の下に浮かび上がって来るような場合にも、記憶は成立し得なくなるのである。
このようにして、この段階においては、直覚や知覚の状態を認める際に、以前統一され、刻印されたものの中で、それと同様なものが、直覚的イメージや、知覚的イメージとなつて記憶の中に浮かび上がって来ることになる。
その場合、最初の直覚か、またはある複数の諸直覚が連結されながら照し出され、点滅していった後に、以前刻印されるに至ったものの中で、それと似たものがイメージとなつて浮かび上がり、直覚的なものは、それのみが単発的に、また、知覚的なものは、一つの鎖によって結びつげられた諸直覚の系列が、一つの全体像となつて浮かび上がるのである。
(2)次の段階において。
この段階においては、統一主体によって照し出されるものを切っ掛けとして、以前照し出され、刻印されるに至ったものの中で、それとは異なるが、何らかの関連を持たされたものの印影が、イメージとなつて記憶の中に浮かび上がるほどになる。
そして、この段階においては、充分な直観まで描き出す能力が備わっていなければならないであろう。それは、ここでは知覚時の諸直覚のようには結びつきがあまり強くない、直覚や知覚同志の関連が問題となつて来るからである。※(4)
この段階における具体的な例として、条件反射と説明されているものを挙げることが出来るであろう。
ここでは、その照し出されるものから、それと何らかの関連を持たされたものが浮かび上がるが、それは、以前に、その照し出されているものと同じようなものが、そのイメージとなつて浮かび上がるものと、何らかの関連を持たされながら刻み込まれたことによるのである。
そして、正にそのことから、この段階で、第三者としての、己れとは異なった同一対象のイメージを浮かび上がらせる媒介物、即ち感覚的な符号が登場することになるであろう。
然し、この段階では、未だ照し出されるものから本質的な要素を抽出する能力を欠く為、その符号には概念内容が認められず、只それは、その照し出される対象やそのイメージと、因果的な結びつきを持たされているに過ぎないと言わねばならない。
(3)最後の段階において。
この段階においては、以前照し出され、刻印されたものが、今照し出されているものとは全く無関係に、イメージとなつて頻繁に浮かび上がり、ある場合には、全く自由にイメージが溢れ出てしまうほどにまでなる。その時には、そのイメージは、単に記憶としてより、イメージそのものだけの世界を表出させることになるのである。
恐らく、そのイメージが表象を満たしてしまうほどのものとは、生存的な欲求の対象(獣や鳥、魚などの狩猟の対象として)や、性的な欲求の対象であったであろう。
かくして、表象能力の高度な発達によって、魂そのものの持つ意欲が直接イメージとなつて表象を満たし、感覚として働きかけて来るものを無視してしまうほどにまでなると、表象能力が何らかの切っ掛けから高まり、意欲が制えられたまま、統一主体がそのイメージで満たされた世界の中に遊ぶようなことが成され得るようになり、その時初めて、芸術性の領域が切り開かれることになる。
例えば、子供の頃に、青空に浮かび、様々に変化してゆく雲を眺めながら色々な空想に耽ったり、また、壁などに付けられているシミの模様から、今まで見たことのない幻想的な情景を描き出したりする、そのような時期を誰でも持ったことがあるのを覚えているであろう。
その時期では、未だ魂の意欲が強烈に発現されて来てはいないので、統一主体はこの溢れ出るイメージの洪水の中で自由に遊び、夫高く飛翔することが出来るのである。
そして、そのような表象能力の高まりを、旧石器時代のある者達も持つに至ったのであろう。彼等が残したとされる各地方の洞窟の壁画が、そのことを如実に証明しているのである。
ところで、それを残した彼等は恐らく成人に達しており、意欲も当然強烈に発現されていたであろう。然し、彼等の持つ意欲は誠に無邪気な性質のもので、その日その日の欲求を満たせば足りたのであり、その意欲は、当面必要不可欠なもののみを対象とし、不必要なものや、将来の先のことどもに対してまで向けられることはなかったのであろう。だからこそ、年齢的に意欲が支配している時期においても、己れの意欲を制えて、その溢れ出るイメージの世界の中を純粋な鏡となつて飛翔することが出来たのである。
恐らく洞窟内にあるシミや岩の模様が、彼等に様々な馴染のある獣の群を思い浮かばせたのであろう。己れの内に湧き上がり、氾濫するそのイメージをどうしても定着しようとして一生懸命になっている眼に、そこで出会うのである。
このように、泉のように溢れ出てしまうことが芸術性を獲得する唯一の指標となるのであるが、この場合には、己れの内奥において制えられていながらも強く発現しようとしているその意欲を、透明なものとして写し出している為、それが我々を呪力的な力で引きつけるのである。
さて、ところで、反省内での想起作用を準備するには、これほどの表象能力の高まりは必要ではなく、今照し出されているものとは無関係な印影が、記憶の中に頻繁に浮かび上がるほどの程度で足りるとすぺきであろう。
その程度の表象能力の発達によって初めて、知性自身がその印影に統一を向け、イメージとして浮かび上がらせる働きを負うことが出来るようになって来るのである。
※(1)悟性自身が働きかけて、浮かび上がらせることがないとしても、己れ自身の燈している知性の光で、その浮かび上がって来るものを見ることは出来るのである。
※(2)統一主体も、魂の働きの一都であり、魂と区別することは矛盾であるが、魂そのものの発現の為の手段としての知性である以上、機能的な差異が認められるのである。
※(3)幻覚とは、その浮かび上がって来たイメージと、実際に照し出されているものとの区別がつかず、そのイメージを実在的なものと見なしてしまうことによる。この場合、浮かび上がるイメージは、魂そのものが働きかけ、浮かび上がらせることになるが、記憶とは異なったものとして浮かび上がって来ることになるのである。
※(4)関連づけるものや、または関連づけられて浮かび上がるものが、直覚や直覚的イメージであっても、それらの直覚的な〈存在〉は、知覚的な〈存在〉の系列の中にあるものとは異なり、独立して〈存在〉し、対象を示すのであって、それらの〈存在〉が持つ関連は、当然知覚以上の直観を描き出す表象能力が必要となって来るのである。
さて、我々はここで、初めて第三番目の〈存在〉の領域、即ち反省的な世界に入ることになる。
この世界において実際に表されて来る〈存在〉は、直観内で刻印された印影を元として浮かび上がるイメージだけであるが、それが前述の自然発生的な記憶や幻覚、そして夢などと異なるのは、それが反省内での統一主体の働きかけによって表されて来るという点にある。
その為、この反省内においては、その表されて来る〈存在〉が如何なる働きかけに基づいているのかが重大な問題となるのであり、単にイメージとしてしか表されない〈存在〉を足跡として、その〈存在〉を表すに至る様々な統一主体の働きを充分注意深く追ってゆき、明確な光の下に晒してみなければならないのである。
そこで、まず、反省内での統一主体の働きの中で、最初の段階に位置するものから調べてゆかねばならない。
即ちそれは、想起作用と呼ばれているもので、以前刻印された印影をそのまま随意に浮かび上がらせようとする働きである。
この作用において、統一主体は、既に消滅して闇の中に沈んでいる印影に対して統一を向け、己れの光の下にそのもののイメージを浮かび上がらせる。そして、ここで得られる記憶は、その反省内での統一が介入して来る点で、自然発生的なそれとは区別されることは前述通りである。
その想起作用が備わって来る意義は、今までは、魂そのものが直接記憶を浮かび上がらせることしか出来なかったのが、今度は、魂そのものの働きの一部として備えられたその作用を介して、随意に記憶を浮かび上がらせることが出来るということであろう。
恐らくは、この作用が備わる初期の段階では、魂そのものの働きに基づいて何らかの切っ掛けから記憶が自然に浮かび上がろうとしているのに対して、それに手を貸し、浮かび上がらせようとする補助的な役割を果しているに過ぎないのであろうが、この作用が充分発達して来ると、本来では自然には浮かび上がって来ないほどの印影に対してまでも統一を向け、何らかのイメージとして記憶の中に浮かび上がらせることが出来るほどにまでなる。
そして更に、その作用を誘う外的な誘因としての符号や言葉(両者を広義の言葉とする)が発明されると、想起作用に基づいて成される記憶の範囲は飛躍的に増大し、以前刻印されるに至った影の薄い印影に対してまでも、直観の助けを借りずに統一を向けさせ、イメージとして浮かび上がらせることを可能ならしめるにまでなるであろう。
然し、そのような印影の薄いものに対して統一を向けても、そこで得られ、表されるイメージは、自然に浮かび上がって来るものよりもずっと不鮮明であるし、時には、全く記憶の中に浮かび上がっては来ない場合も生じるのである。
ところで、直観内で照し出されるものと、その印影から浮かび上がるイメージとは、性質上異なることは既に見て来た通りであるが、同一の印影から浮かび上がるイメージ同士も、統一形式に従って継起して来る時には、多少なりとも異なったものとして表されて来ることになるであろう。
それは、その刻印された印影自身恒常的なものではなく、新たに刻み込まれて来るものによって常にその印影は薄れ、変容してゆきつつあり、その上、その同一の印影に統一を向ける統一主体、延いては魂そのものの状態も、変わりつつあるからである。
次に、この想起作用においても、統一主体の持つ統一形式に従ってイメージは継起し、あるものは空間の中に表されて来ると言わねばならない。
然しながら、ここで注意しなければならないのは、その継起の中で浮かび表されて来るイメージは、直観内で継起した通りの順では必ずしもないということであり、また、空間の中に浮かび表されるといっても、そのイメージは、感覚的な土台の基で直接照し出され、その位置が固定されるということはなく、常に不安定に揺れ動く一塊の雲のようであるということである。
ここでは特に、前者に関して更に詳しく調べてみることにしよう。
直観内で照し出され、刻み込まれた印影は、その時の悟性の統一形式に従って継起の相互的な規定関係を持たされているのであるが、然し、ここでは、この想起作用によって、それが働く統一形式に従って、その闇の中で保存されている印影は、新しい継起の相互的な規定関係を持たされながらイメージとなつて浮かび上がって来ることになる。
そして、その場合、イメージとなって継起するものは、直観内で持たされた相互釣な規定関係を背後に引き摺っている為、その想起作用に基づく新たなイメージの相互的な規定関係が、その直観内でのものとどのように異なっているかを、我々は意識することが出来るのである。
従って、ここでの記憶の中では、直観内で持たされた規定関係に対して、恣意的に全く逆から辿ることも成され得、その場合、その記憶の中でのものが持つ新たな継起の相互的な規定関係が、直観内で持たされたものと全く逆の方向であることも意識されることになる。
即ち、直覚的なものそれ自身では、その単発性からして、直観内で持たされた規定関係を逆に辿るようなことは不可能であるが、知覚的なものにおいては、関心という一本の強い鎖によって結びつけられた一つの知覚の状態から、それを構成している諸直覚的なものを解き放ち、それらが持たされるに至った継起の順を逆に辿ってゆくことが、そして諸知覚的なもの同士においても、その継起した順を逆に辿ってゆくことが成され得るのである。
また、直観内で持たされた規定関係通りに記憶を辿る場合では、知覚的なものは、諸直覚的なものが強く結びついて刻印されている為、それをその継起通り再現することは容易であろう。※(1) 然し連結がさほど強くはない諸知覚的なもの同志をその継起通りに再現するとなると、曖昧な点が生じて来る為、その継起を正確に再現し、辿ることは容易ではなくなるであろう。
※(1)対象の静的な状態では、特に強く刻印された印影を中心として、一つの全体像が浮かび上がるだけであり、それを諸直覚に分解し、その継起を再現することは容易ではないかもしれない。
ところで、前述のように、表象能力が発達し、この想起作用の働きが充分機能して来ると、今度は、曾て刻印されるに至った様々な印影を勝手に合成して、印影の忠実な再現としての本来の記憶とは異なったイメージを浮かび上がらせることが出来るようになる。
それは、初めには、想起作用によって闇の中に深く隠された印影を無理矢理に引っ張り出そうとする時、その浮かび表されるイメージの不明瞭さを補うものとして働くのであるが、次第に、記憶の原型を保たせる為にではなく、記憶とは懸け離れたものが合成されるようになる。
従って、その合成作用は、その性質上想起作用の延長線上にあるものとして、本質的な働きは同じであると言わねばならない。
そして、ここで得られるイメージは、直観内で刻印されるに至ったものの忠実な再現ではないが、然し、その素材は、そこでの印影から取り出されて来るのでなければならないのである。
以上のような合成作用によって、現実に経験したことのないもの共がイメージとなつて表象を満たすような時、それは空想と呼ばれる。
ところで、その空想に対して、この合成されたイメージの乱舞が、何らこの反省的な作用を介することなく、魂そのものによって直接表象内に満たされる時、それは夢と呼ばれる。
従って、夢は反省的な世界における〈存在〉ではなく、強いて言えば、自然発生的な記憶と同一な領域に入れることが出来るであろう。
反省内での合成作用が衰え、そこで満たされている空想が夢のように流れ出ているような状態では、その作用の働きは、只その流れの動きを変えたりするだけの想起的なものにもどる。
やがて、統一主体の働きによって世界が描き出され、または方向づけられている状態から、そのような世界は徐々に退場し、もはや既に働きかけることは止めながらも依然として知性の光を燈し続けている統一主体の前には、魂そのものの働きかけによって夢が上演されることになる。
その為、夢とは、直観や反省内から退きながらも極僅かな知性の光を燈し続けている統一主体に対して、魂(生命)そのものが、己れ自身の姿をそのイメージの戯れの中で告げているものとして把握され得るであろう。
然し、己れ自身の姿を告げると言っても、その表されて来るイメージ自体が、その働きかけて来るものの形象化であり、象徴化である以上、その表されて来るもの自体はさして問題とはならず、それを浮かび上がらせる何か或るものが問題となつて来るのであり、我々は、そのイメージの戯れからそれを推測しなければならないのである。
ところで、その己れの内なる深淵に控える何か或るものを、現象的な把握において便宜上魂として設定して来たが、それはあくまでも一限定であり、同じ現象的な把握においてもまた別な限定を成す必要が生じて来るであろう。※(1)
然し、その何か或るものは、何らの積極的な規定に縛られることなく、それ自体として有るのである。
さて、それでは、その何か或るものに基づく統一主体の働きを概観してみることにしょう。
まず、統一主体は、直観内では感覚を土台とする世界を己れの持つ光の下に照し出し、反省内では様々なイメージを浮かび上がらせることになるが、二つの世界に燈される光の内では、直観内でのものの方がはるかに強烈であり、統一主体がその世界に係わっている時には、滅多にイメージなど浮かび上がっては来ず、そこで照し出されるものの光の反射が強い為、星の輝きほどの光の下でしか表されて来ないイメージの戯れは、その背後に隠されてしまうことになるのである。※(2)
然し、目覚めてはいるが、直観の世界から遠ざかっているような時には、今までその強い光の背後に隠されていて浮かび上がっては来れなかった様々なイメージが、浮かび表され、戯れ出すことになる。
この状態において深い思考を成している場合には、出来るだけ感覚の働きかけを避け、内奥における極微な光を頼りに、闇の地平線を探り回らねばならない。
そして、そのような思考の中では、針一本落ちる音によってさえも、統一主体はその働きかけに引き摺られ、そこで投げ込まれる強い光の為、思考は粉々に砕け散ってしまうことになる。
そして元いた領域に戻り、そこでの極微な光に慣れて来るまでには、多少の時間が必要となって来るのである。
そして、眠りに入る手前の休らっている状態においては、直観及び反省内での統一主体の働きは極度に低下し、その直観の世界や反省の世界は、曖昧模糊となつて、流れ出るような空想的なイメージの乱舞の中に入り乱れる。
そして、もはや統一主体が自ら世界を描き出し、または方向づけることが出来なくなるような時、それらの世界は誰そ彼れの中に消え去り、その空想的なイメージの乱舞は夢となつて取り留めのない戯れへと移行してゆくことになる。
この夢の中で、既に働きかけて世界を描き出し、方向づける機能を失なった統一主体は、灰かな知性の光を保ちながら表象内を明るませてはいるが、然し、そのものは何も統一することなく、只一人観席の中からじっと、舞台の上で繰り広げられているそのイメージの乱舞を見守るだけである。
そして、その目前で演じられている劇に一喜一憂することになる。
やがて深い眠りが彼の下に訪れると、彼の燈す光もついには吹き消され、そのまま舞台も幕となる。彼は深い安らぎを求めて内奥における深淵の闇の中に入り込み、その中で漂い休らぐ。彼は何も描き出すことはなく、何も観ることはない。
ところで、目覚めている時には、直観や反省内で与えられるものを切っ掛けとして、己れ自身を発現しようとしながら魂は己れの状態を変えてゆくが、夢の場合には、そのような直接的な発現の為の外的誘因として表されて来るのではなく、魂自身の姿や状態を直接内的に暗示するものとして表されて来るのである。
その為、我々は、夢からその源泉を、己れの魂の極表面的なものから頗る内面的なものにまで、また時には、魂の個体性を超え出た所にまでも辿り、求めてゆくことが出来るのである。
それは、高い表象能力を備えた者の魂の状態が、鏡のように凪いでいる場合においてのみ起こり得、このような条件において、初めて個体性を超越した所から働きかけて来るものを、統一主体は夢の中で観ることになる。
然し、如何に個体性を超越した所からの働きかけを夢の中で表すことが出来るとしても、夢として表されて来る以上、その背後には必ず何らかの働きかけがあり、その為、統一主体は、その働きかけに応じて表されて来る全宇宙の様を、居ながらにして目撃することになるとしても、あの虚空として示され、全宇宙を統一しながら自らは決して統一されることのない何か或るものの領域の内へと超越することも、またその姿を写し出すことも出来はしないのである。
そして、己れの光を消し去り、深淵の中に休らっていても、だからといってそのものの支配から逃れているということにはならず、統一主体は、そのものの統一力の中で標いながら休らっているに過ぎない。統一力の中で働きかけを受けてはいるが、己れの光を消し去っているので、その受け取るものを表すことがないだげである。
やがて、その知性の光が再び燈される時、彼は夢を観、そしてまた、自らが働き出す時、実在的な世界が照し出され、反省的な世界が表されることになる。
※(1)己れの内なる深淵を現象的に把握し、まず個体性としての魂を、次に、その個体性を超越して全宇宙の万有を統一する統一力を、そして最後に、その統一力をも支配する何か或るものとしての一者を、それぞれ設定することにする。
※(2)深夜、星空を見上げると、無数の星達が語りかけて来るように思われるのは、決して根拠のないことではなく、我々は、己れの内なる深淵に、無数の「星」を秘めており、それらがいつも何かを伝えようとして、我々に囁きかけているのである。
さて、前述の想起作用が発達し、闇の中に保存されている印影を、容易にイメージとして浮かび上がらせることが出来るまでになると、初めて「何故」が生じて来て、それを切っ掛けとして、物事を考えようとする能力が発現し出すことになる。
そして、この場合の思考は、言葉を必要とせず、想起作用によって得られるイメージを、思考作用によってそのまま継起の相互的な規定関係に基づいて連結することになる。
ところで、諸イメージが連続して浮かび上がるという、統一され、表されて来た事実だけからでは、はたしてそれが記憶としてなのか、空想としてなのか、夢としてなのか、それとも思考としてなのか、敦れであるのかは決して決定し得ない為、ここでは、その諸イメージの継起の背後には、どうしても思考の働きが認められねばならず、その働きがここでの中心的な課題となるのである。
そこでまず、統一主体が照し出されている実在的な世界と一体となっている時にも、そこで表されて来る対象の状態なり、運動・変化なりを切っ掛けとして、直観的な疑問の状態を持つ場合が生じて来るのであるが、それは、その対象の状態や運動・変化に対する知的な好奇心であったり、それらに対してどのように対処すぺきであるかを、その瞬間に問われる為に見せる戸惑いであったりするにしか過きず、未だその時期においては、反省的な思考に入ることは出来ないままであると言わねばならない。
然し、その表されて来るものに対して直観的な疑間の状態を持ちながら、それを結果として、「何故そのものがそうであるのか」の原因となるものを、想起作用によって浮かび上がらせられる諸イメージの中に追い求めようとする時、初めて思考が芽生えて来ることになるのである。
そこで浮かび上がらせられる諸イメージを分析・判断して、その結果に対する原因を探し出し、連結することになるのである。
そして、その思考能力が充分発達し、一人立ちする時には、直観内で照し出されるものを切っ掛けとするだけではなく、想起作用によって浮かび上がらせられるイメージをも結果として、その原因を同じイメージの中で追い求めることまで成され得るようになる。
また、そのように、何らかの対象を結果として、その原因を追い求める方向から、やがて今度は、実在として照し出され、またはイメージとして浮かび上がる対象を原因として、その結果をイメージの中で追い求めてゆくことも成されるであろう。
このように、実在的な世界に一体となっている時には、魂の関心の元で統一形式に従いつつ対象を注意深く観察することしか出来ないのに対して、ここでは、その思考の働きによって、直観内で継起するものに対して因果関係を設定することが出来るようになるのである。
この様に、この因果関係は、直観を成立させる為の形式的な根拠ではなく、直観内で持たされる継起の相互的な規定関係に従いながら、問いから答えを思考によって求める為に生じて来るのであって、思考(判断に基づく諸対象の連結)が成立する為の一様式でしかないと言わねばならない。※(2)
従って、直観内での諸直覚や諸知覚の連結は、全く魂の関心の元で成されるが、反省内での物質現象は、思考によって、継起性の中で因果関係を持たされることになるのである。
そして、その現象内で設定される因果関係は、正に、直観内での諸直覚や諸知覚が魂そのものの関心の元で連結され、表されるのと同様、それは、この物質現象を統一する、魂と同質な力によって規定されていることが明らかとなるのである。
また、問いから答えとして追い求められる原因なり、結果なりは、直観内で持たされる継起の相互的な規定関係を基準にして、以前生成したもの、または、以後生成するであろうものの中に在るものとして表されることになる。(然し、その表されて来るものは、常に統一の先端において〈存在〉するのではあるが。)
ここでの思考の対象となるものは、直観内で照し出される実在的な世界と、その印影に基づくイメージの世界であることから、何ら概念化の道を辿らなくとも、表象内に表されて来るそれら一切のものを、その対象とすることができ、その上、そこで表されて来る物質現象一般に関しても「何故」は発せられ、それを結果としてその原因を求め、その現象の背後に控えている別の世界に対してまでも注意が向けられて来ることになるであろう。
恐らく、この段階で持つに至るであろう最も重大な意義を含む「何故」は、「何故此の世に生まれ、何故死なねばならぬのか」、という問いであろう。そして、その問いから、同列の規定不可能な領域に関する問い、即ち、「何処から、如何ようにして此の世に生まれ、死後、何処ヘ、如何ようにして赴くのであろうか」、という問いが発せられることになり、それらの問いは、「何故在るのか」、という一つの問いに向けられて来ることになるのである。
然し、統一主体の注意がこの物質現象のみに向けられ、その中で、問い・答えを見出そうとする限り、その原因のその又原因と辿る場合にせよ、またはその結果のその又結果と辿る場合にせよ、因果の連鎖は無限に引き延ばされ、そのような果てしない旅の中で結局は、中途半端な所でその追跡を断念せざるを得なくなるのである。
そしてまた、物質現象一般に対してその原因を求め、その背後に別の世界を設定するとしても、我々にはその世界に何らの積極的な規定も持たせることは出来ず、その上、その不可知な世界が、物質現象一般の原因として因果関係の中にあるものとされる為、その世界は、この具体的な物質現象の延長線上に設定される抽象的な現象の地位に止まり、我々万有を含むこの物質現象一般とは全くかけ離れた所から、我々の此の世界を支配するものとして描き出されることにもなってしまうのである。
然しそれは、その物質現象そのものが表象内で統一され、表されたものであり、それを統一する何か或るものが、己れの内なる深淵に控えていることに未だ気付いていないからである。(だが、精神現象において、己れの内なる深淵にその何か或るものが控えていることを認識するとしても、そして、その認識が、そのもの自体に対応するものとして示されるとしても、それは、依然として表象内に表される〈存在〉の内の一つに止まるのではある。)
さて、この因果関係の連結による思考においては、体系的な認識の為に問いが発せられるのではないが、ここでは、既に調べた直観面での〈存在〉の諸領域に従って、その問いと答えとを体系づけて見ることにしよう。
まず、照し出される実在的なものや、表されて来るイメージを切っ掛けとして、問いが発せられ、その答えを因果関係の中で求めようとするが、その問いと答えとが取り扱われる領域は、第一に、直覚的な、第二に、知覚的な、第三に、直観的な、それぞれの領域であり、そこでは、感覚的性質や知覚の諸状態、そして直観の状態が、それぞれ問い及び答えの対象となるのである。
※(1)思考とは、判断に基づく対象の連結を言い、その場合、そこでの対象は、具体的な実在やイメージであっても、または概念であっても構わない。
そして、その連結の様式は、ここでのように、直観内で持たされる継起の相互的な規定関係に基づいて、因果関係を設定し、対象を連結する場合と、後述のように、その規定関係に拘束されずに、同一性の判断を成し、対象を連結し包摂してゆく場合とがある。その連結を成立させる思考形式は、後に譲ることにする。
※(2)因果関係が反省内での思考の一様式である以上、直観内での悟性が持つ統一形式に縛られず、同一の出来事を反省内で様々な角度から検討し直し、その同一事実に対して、異なった幾つかの因果系列を設定することが成され得る。
(その一)では、思考は、直観内での統一形式に基づいた因果関係の設定という形で働いたが、ここでは、概念化の際の対当、または包摂関係の設定という形で働くことになる。
まず、一般化の方向において、特に物質現象を中心に据えて、概念体系を構築してみることにする。その場合、対当関係においては同一性の判断が、包摂関係においては描出判断が、それぞれ働くことになる。
次に、特殊化の方向において、精神現象を根拠律に基づいて把握してみることにする。その場合、まず被統一面から統一面を探り、被統一面における同一性の判断の適用から、統一面における表象形式を抽出することにする。
ところで、ここでの思考は、直観内で持たされる継起の相互的な規定関係に拘束されることなく、それから切り離されたものとしての対象同士を連結するのである。
そこでまず、我々は、一般化の方向にこの概念化を進めてみることにしよう。
そこで、前述の因果的な関係の設定が内的な思考そのものであるのに対し、この一般化における対当、及び包摂関係の設定においては、その直接的な目的を己れの意図の伝達に持つことがまず注意されねばならない。
即ち、言葉とこの一般化の働きとは、切っても切れない関係にあり、それは、社会集団を形成する人間が己れの意図を伝達する為に、まず伝達しようとするものの特徴や本質を分析・抽出し、次に、その本質的な要素を内容とするものを概念として、それを表示する感覚的な符号、即ち言葉を登場させることになるからである。
さて、ここでの始原的な働きは、表されて来る森羅万象の世界の中から、まず何らかの点で同一性を持つ二つの区別された対象を見出すことである。そして、この場合の同一性の把握は、前述の記憶のように自然に浮かび上がって来てそれを告げるようなものではなく、諸対象が持つ要素を比較・分析する作用が介入して、初めてそれと把握されるのでなければならない。
また、その同一性の判断の対象として表されて来るものが、直観内で照し出される実在釣なもの同士であれ、想起作用によって浮かび上がらせられる記憶としてのイメージ同士であれ、またはその両者に渡る場合であれ、それらにおいて働くその同一性の判断は、何ら変わることはない。
そこにおいては、実在としてであれ、イメージとしてであれ、個別具体的なものとして表されて来る対象の持つ感覚的性質や、継起及び位置の相互的な規定関係に関して、諸対象を比較・分析し、如何なる点で同じであり、また、如何なる点で異なれるかを検討することになるのである。
まず最初に、諸対象を比較し、個別の間で認められる共通の要素を、同一性の判断を繰り返してゆきながら抽出してゆき、徐々に、余分で非本質的な要素を抽捨し、本質的なものを煮詰め、その本質的な要素を、個別を包摂する概念の内容として描出する。
このようにして、初めて個別から、その本質的な要素を内容とする概念が作り上げられることになるのである。
そして次に、同様にして、概念体系の中でも底辺にある下位概念同士を比較・分析し、それらが持つ内容に対して同一性の判断を繰り返してゆきながら、共通なる要素を描出し、本質的な要素を煮詰め、それらの上に、それを内容とする上位の概念を設定してゆき、やがては一切を包摂する最高概念にまで到達することになる。
以上のことから、如何に最高概念が一切の個別を含むと言われるとしても、そこでの個別は抽象化されてしまっており、個別そのものが持つ様々な、微妙に異なりゆく内容までをも示すことは出来ないのである。個別そのものを概念化する際に、その微妙に異なれる要素はすべて非本質的なものとして取り捨てられてしまうからである。
ところで、個別同士の間で成される比較・分析では、その判断の対象となるものが、実在として照し出されるものや、または具体的なイメージとして浮かび上がらせられるものであるから、それをそのまま表しながら検討すればよいのであるが、その対象が概念となる場合には、その内容は抽象化されてしまっている為、その概念が包摂するある限定された個別のイメージを、そのまま判断の対象とするだけでは未だ充分ではないと言わねばならない。
その為、その段階においては、概念同士が持つ抽象的な内容を押えながら比較・分析し得る、抽象的な思考能力が必要となって来るであろう。※(1)
然しながら、この概念同士を連結する際に伴う個別具体的なイメージは、たとえ概念そのものを表すものではないとしても、その概念同士の連結を手助けするものとして重大な意義を持ってはいるのである。
ところで、概念同士を連結する場合、如何なる要素を本質的なものとして抽出するのか不明確な点が露になって来る為、この抽象的な領域において正確な判断を下すには、充分なる認識力が不可欠となるのである。
さて、それでは、実際に一般化の方向において、概念体系を構築してみることにしよう。ここでは特に、直観面に基づいてその世界を体系づけることにする。※(2)
まず、直覚的なものの領域では、個別として具体的に表される感覚的性質を比較・分析し、それぞれ同一性を持つ領域が、本質的な要素に基づいて区分されるようになったら、それらの要素を内容とする下位概念を設定し、それから順次同様な作業によって上位の概念を設定して行き、最後に最高概念に至る。
例えば、個別具体的な段階において、〃赤い〃と表される感覚的性質は、無限に異なった明るさや彩度を持って表されて来るであろう。然し、それらの異なって表されて来る個別に対して、それぞれを異ならせる微妙な要素は抽捨し、本質的な要素のみを抽出し、それを内容として、それを持つ一切の個別を包摂する概念を設定する。
そして今度は、そこで設定された下位概念の「赤」という内容は、それと同様にして得られる下位概念の「青」という内容や、「黄」という内容などと一緒に比較・分析されることになる。
それらのものの内で、非本質的なものは描捨し、それらに共通する更に一段高い本質的な要素を描出し、それを、それらの下位概念に対する上位概念の内容とする。それが上位概念の「色覚」という内容である。
そして、それは、空間形式に基づいて表され、「視覚」という内容を持たされて来ることになる。
そして、以上と全く同じ様に、以前区分された他の領域においても、「痛い」、「軟らかい」、「熱い」などの諸概念は、「触覚」という上位概念に、また、様々な匂いを特徴づけられた諸概念は、「嗅覚」という上位概念に、「廿い」、「苦い」、「すっぱい」などの諸概念は、「味覚」という上位概念に、そして、様々な音を特徴づけられた諸概念は、「聴覚」という上位概念に、それぞれ包摂されることになる。そして、その五つの概念は、今度は、「感覚」という一つの概念に包摂されることになるのである。
また同様にして、知覚の領域において認められる、「遠い」、「深い」、「高い」などの距離的要素を特徴づけられた諸概念、及び、「三角形」、「正四面体」などの、図形的要素を特徴づけられた諸概念は、それぞれ「空間」という一つの概念に包摂されることになる。
また、統一の先端において統一され、生成するものが持つ「現在」、既に統一され、生成してしまったものが持つ「過去」、そして、これから統一され、生成するであろうものが持つ「未来」などの、継起の相互的な規定関係を要素として特徴づけられた諸概念は、「時間」という一つの概念に包摂される。
そして、「一」、「二」、「三」、……という、統一形式に基づく継起の回数を特徴づけられた諸概念は、「自然数」という一つの上位概念に包摂される。
次に、同様にして、知覚的なものの領域において、感覚的性質の変化や物体の運動を特徴づけられた諸概念は、「生成」という一つの概念に包摂される。
対象の総合的な状態なり、形態なりを特徴づけられた諸概念は、概念同士で幾つかの包摂関係を経て、「無機物」、「植物」、「動物」、「人間」というそれぞれの概念に、そしてそれらは、「万有」という一つの概念に包摂される。
そして、直観的なものの領域において、「等」・「不等」、「大」・「小」、「似」・「不似」などの、二つの対象間で比較・分析され、設定される関係を特徴づけられた諸概念は、「同」・「異」という一つの比較関係を内容とする概念に包摂されることが出来るであろ。※(3)
また、諸知覚の総合的な状態を特徴づけられた諸概念は、「自然」なり、「社会」なりの諸概念に包摂されてゆき、最終的には、「宇宙」という一つの概念によって包摂されることになるのである。
そして、そのように一般化が進むと、今度は、物質現象としてのその「宇宙」の延長線上に、その原因としての「神」の概念が消極的な規定によって設定されることは前述通りであり、それと同時に、両者を因果的に結びつける何らかの力を内容とした、「統一力」なり、「魂」なりの概念も設定されることになるのである。
※(1)然し、抽象的な思考能力といっても、その思考の基本的な対象は、やはり、個別具体的な実在なり、イメージである。その個別具体的なものを数多く持てば持つほど、その抽象的な把握にも、内容が満たされて来ることになるのである。
※(2)勿論情意の世界も概念化されるが、その直観内で描き出される世界には姿を見せることはなく、それとは異なった領域において別に概念化され、一般化されることになる。そして、その領域における最高概念を、「情意」として以前示したのである。
※(3)この概念は、直観面に対して同一性の判断が介入して来る為に認められるようになる。そして、「因果関係」の概念も、正に思考の一様式そのものを内容とすることは見て来た通りである。
ここでは、例えば、感覚の度合や、時間の長短、または空間の面積などに関して、対象同士が比較され、「等」なり、「不等」なりの判断が成されるが、それは、統一主体が自身の知性の光の下で、一定の基準となるものを刻み込み、その基準以下、または以上のものは、「異」なる基準を持つものとして「不等」を、その基準と一致するものは、「同」なる基準を持つものとして「等」を、それぞれ判断することになるからである。
ところで、その統一主体内に刻み込まれる基準となるものを、特に恒常的な現象を呈するものによって補い、視覚化し、その測定を数値化することによって、測定値の「同」・「異」は、その「等」・「不等」を正確なものたらしめることになる。
さてところで、以上のように、(その一)での因果関係の設定にせよ、また概念体系の構築にせよ、そこで取り扱われているのは、特に直観面で照し出されて来るものに基づいて描き直された反省的な世界であり、それを統一し、表す方面に関しては未だ充分なる注意が向けられてはいないのである。
そこで、ここでは、直観面のみならず、被統一面として表されて来る一切の〈存在〉から、それを表す統一面へと辿ってゆき、まず表象機能が持つ諸形式を推測してみることにする。
ここでの特殊化は、伝達の必要性に基づいて成される概念の一般化とは異なり、(その一)での因果的な思考作用同様、「何故」がその追求の切っ掛けとなるであろう。
その場合、前者のものでは、物質現象として表されて来る対象間でその追求が成されるが、この特殊化においては、その表されるに至るものすぺてからそれを表すものへと追求が向かうことになり、その追求の方向性を、前者の因果律と区別して、根拠律とすることが出来るのである。
そして、前述通り、統一形式に従って、統一の先端で常に統一しつつある主体を同時に統一を向け、表すことは不可能な為、その統一主体は、そこで表されるに至ったものを足跡として追跡し、事後的にその統一面に隠されているものを推測するしかないのである。
ここでは、その表されて来る一切のものを充分念入りに分析し、調べてみなけれぱならない。それらのものの中で一体何が共通な要素として隠されているのか、それを調ベ、抽出して見る必要があるのである。
(1) 直観形式
そこでまず、その追求の切っ掛けとして、「何故この世界は生成し続けるのか」、といった類いの問いが発せられることであろう。
そしてその答えとしての根拠を、己れの内奥にある統一面に迫い求め、その場合、その共通な要素をまず継起性として描出することができるのである。
即ち、この表されて来る一切の〈存在〉は、同時にではなく継起して表されて来るという事実から、その統一面においてその継起性を内容とする形式が推測されるのである。そして、その形式を、統一主体が働く際に持つ形式として、統一形式と呼んだのであり、この統一形式によって、初めて一般化の中で「時間」という概念が認められることになったのである。
次に、触覚と視覚において共通な要素を、空間性として抽出することが出来るであろう。即ち、この両者の感覚を土台とする一切の〈存在〉は、三次元の広がりの中で表されて来ることから、その統一面において何らかの根拠として、空間性を内容とする形式が推測されるのであり、それを空間形式と呼んだのである。
そして更に、その形式の実体を追求してゆくと、それは、感覚を土台として統一主体自身が、己れに対して客体を対外的な関係の下に定立することに由来していることは前述通りである。
そしてまた、その空間形式は、感覚を土台として初めてその中で固定されるが、然し反省内では、例えそれが適用され得るとしても、そこで表される位置の相互的な規定関係は曖昧なままで止まることも前述通りである。
以上の二つの形式に従い、初めて、「物体の生成・消滅」が表されて来るが、それは、この統一面の直観作用が持つ両形式のア・プリオリな表現にほかならないのであり、その両形式によって、実在的な世界や描き直される物質現象は、その〈存在〉の仕方を枠付けられることになるのである。
然しながら、その形式的な枠付けに、如何なる実質釣な内容が持たされ、表されて来るのかは、その形式を超えた所からの実質的な働きかけに俟たねばならないであろう。
(2) 思考形式
次に、反省内での思考においては、「何故対象が連結されるのか」を切っ掛けとして、その思考・判断が如何なる仕方で成されるのかを追い求めることになる。
そして、直観内での継起の規定関係に基づいて両対象を因果的な関係の中で連結する場合であれ、概念化の際に両対象を対当・包摂関係の中で連結する場合であれ、一切の思考においては、その共通の要素として、同一性を保つ両対象が、同一領域の同一側面上に固定されながら、同時に相反することをしたり、されたりすることはできず、そしてその連結は、矛盾的に対立する二つのものの内の一つである、ということが認められるのである。
その為、思考においては、その統一面に以上のことを内容とする形式が推測され、その内容を、同一律、固定律、矛盾律、排中律に区別することが出来、それらをまとめて思考形式と呼ぶことにする。
即ち、同一律は、思考が向けられる両対象が同一の内容を保つということを、次に、固定律は、両対象が同一領域の同一側面上に固定されるということを、そして、矛盾律は、両対象が同時に相反する立場を取らないということを、※(1) 最後に、排中律は、両対象の連結が矛盾的に対立する二つのものの内の一つであるということを、以上四つの原理をこの思考形式は持つのである。
そこで、両対象間に因果関係を設定する思考においては、まず、生成界の流れの中に在るものとして表される両対象の同一性を確認し、その両対象をそれぞれ限定された時間・空間の中に固定し、それらの設定条件の中で、今度は、その両対象が同時に相反する連結を持つことなく、その連結が矛盾的に対立する二つのものの内の一つに確定することによって、思考は成立し、両対象の因果的な連結の是非が確定することになる。※(2)
また、概念化の中で両対象間に対当・包摂関係を設定する思考においては、まず、生成界の流れから切り離された個別的なものなり、概念なりを対象として、その同一性を確保し、その両対象を連結しようとする領域と側面を同一なものに固定し、それらの設定条件の中で、後は上述の場合と同様に連結を確定することになる。
以上のように、思考というものは、二つの対象を比較・分析し、否定的にせよ、肯定的にせよ、両者を連結する働きとしてあり、その連結を確定させ、思考を成立させる為の仕方が、ここでの思考形式なのである。
ところで、論理形式なるものは、この「言葉を伴わない思考作用」においては問題とはなり得ず、それは只、言葉による思考の内で、その言葉の概念が一般化に基づく概念体系内のものである場合にだけ問題となるであろう。
何故ならば、その論理形式というものは、概念の一般化の際に持たされる、諸概念同士の対当・包摂関係の言い換えにしか過きず、言葉の使用によって初めて、その体系という形式的論理性の中で、その言葉の持つ概念の形式的な位置付けが求められて来るからである。
※(1)この場合、相矛盾し、対立する二つのものの内の一つのものは、無限に進行してゆく可能性を持つが、然しながら、述語がAとされるにせよ、非Aとされるにせよ、そのいずれかの定立によって、思考そのものは成立することになるのである。
例えば、述語がAか非Aかで、非Aが即ちBであることが確定している場合には、二者択一はそこで止まるが、非AがB・Cを含む場合には、順次、Aか非Aか、非Aの時には、Bか非B(即ちC)かが問題となる。そして、非AがB・C・D …… ∞となる場合には、無限にその二者択一は成されてゆくことがあり得、その場合、無限に思考は成立してゆくのである。
※(2)思考形式の内、同一律・固定律は、思考の設定条件とし、矛盾律・排中律は、思考の確定条件とすることが出来るであろう。
(図)単一性としてある原理的な形式は、それを通して数多性の中で投影されるすぺてのものに、己れの跡を残す。
以上のように、特殊化によって、被統一面から統一面に辿り、表象機能が持つ諸形式を推測し、抽出して来たが、今度は、順序からすれば、その統一面で働く表象機能そのものに対して注意が向けられることになるのであろう。
然し、本書では、その構成上、その様々な働きを既に述べて来てしまっているので、再びそれを繰り返すことはしない。
だが、事の性質上、そこで設定されたものは、あくまでも推測の域を出ることはなく、別の全く異なった推測も成立し得ることは銘記されるべきであろう。被統一面から、それを統一する方向に逆に辿って推測され、設定されたものも、また表象の中に表されるに至ったものの一部であり、統一面に控える深淵に対するありそうな話、即ち精神現象に止まるからである。
また、物質現象との対応から、その精神現象の背後に、個体の魂を、そして更に内奥に、個体性を超えた所から働きかけて来る統一力を、そして最内奥には、一切を統一する何か或るものとしての一者をも設定することが成されるであろう。
そのようにして、己れの内の深淵としてある統一面に対して光を当て、より深い領域を推測し得るのであるが、然し、そこでの推測は、物質現象での因果的な把握の跡が残されており、しかも、深淵そのものに対するありそうな話としての性質も、前の場合と少しも異なることはないと言わねばならないのである。
ところで、その因果的な把握は、被統一面から統一面に辿ってゆく場合には、根拠律に取って替えられるべきであり、その統一面としてある深淵には、原因ではなく、根拠を求めねばならないことを考慮すれば、統一の先端において、現象としてのありそうな話を含め、統一され、表されて来る一切の〈存在〉は、その根拠を常に統一しつつある何か或るものに求めねばならないのである。そしてそのことのみが全く確かな認識として認められねぱならないのである。
それは、その深淵の闇の中に座し、統一の先端において一切の〈存在〉の世界を描き出す。そして、それ自身がその描き出される世界に縛られ、執着している間は、その描き出される〈存在〉の世界がすべてであるように思われ、それを統一し、描き出す己れ自身に対しては、闇の深淵の中で何ら規定し得ず、無としてしか思われない。
然し、やがてその〈存在〉の世界から全く切り離され、虚空の中で己れ自身の姿を初めて知るに至る時、その無としてしか思われなかったものこそがすべてであり、反対に、今まですべてであると思い込んでいたものは、全くの無であることを知るのである。
だが、その為には、己れ自身を無として有る何か或るもの、としてしか規定し得ない反省的な認識によってではなく、それとは全く別な認識が必要となつて来るであろう。
言葉は、個別具体的なものや概念を、感覚的な符号で表示することによって成立し、それによって他人との伝達関係が容易に達成されることになる。
ここでは、その言葉がどのように発生して来るのかをまず検討し、次に、その言葉の性質に就いて、そして最後に、その言葉を介して成される思考に就いて調べてみることにしよう。
ところで、個別具体的なものとしてであれ、概念としてであれ、思考が成され、それらの対象が連結される際、言葉(感覚的符号)が介入するか否かはさして問題とはならず、思考そのものは、言葉なしで充分成されることは前述通りである。
そして、その言葉の持つ伝達の機能によって我々は、成された認識を蓄積し、想起を容易ならしめ、より高度な認識へと赴くことが可能となるのであるとしても、その認識を支えるのに充分な深い思考が伴わない限り、そこで蓄積され、想起される認識は、ほとんど内容を持たない単なる感覚的符号のままで止まらざるを得ないと言わねばならないのである。
そしてまた、言葉の持つ感覚的符号は、それによって表示される内容とは異なるものであるのに、そのものが即ち内容そのものであると思い込んでしまうことから、それが内容を無視して一人歩きをしてしまうことにもなるであろう。
そして時には、何らの内容をも持たない単なる感覚的な表示が、何らかの内容を持つ言葉として思いなされることにもなるのである。
その為、言葉の使用の際には、その内容を明確に把握しておく必要があるのであり、そのことは取りも直さず、体系立った正確な認識に立っていることがその前提となるのである。
また、言葉による伝達において、その伝達される内容は、個別具体的なものとしてであれ、概念としてであれ、それは、送り手・受け手両者とも、異なったイメージの下で伝達されることになるであろう。
何故ならば、内容が概念的なものなら、両者はそれぞれ、その概念が包摂する無数の個別の内、己れ自身が持つもののみをイメージとして浮かび上がらせることしかできないのであり、また、その内容が両者それぞれに共有される個別具体的なものである場合でも、両者において照し出され、刻印される印影は、それぞれの魂そのものの状態によって微妙に異なって来るからである。
※(1)概念に対してそれを表示する感覚的符号を狭義の言葉とし、個別を表示するものと一応区別する必要があるが、ここでは、両者を広義の言葉として認め、一括して「言葉」で表現することにする。
※(2)概念が成立する以上、それは何らかの内容を持たされており、全くの空虚なる概念など成立し得ないことは、その概念の成立過程からして明らかである。空虚な内容を引き摺るのは、感覚的な表示によって初めて成されるのである。
1 言葉の発生
さてそこで、言葉がどのように発生して来るのかを調べてみることにしよう。
一言で述べるなら、他者に対する伝達の必要性から、直観内で照し出され、刻印されたものをイメージの中で再現しながらそれを分析し、それが持つ特徴的な要素を抽出して、それを感覚的な符号で表示する時、初めて言葉の発生が認められて来ると言えるであろう。
その場合、まず最初には、伝達しようとする対象を分析し、特徴的な要素を抽出して、それを身振りや絵によって相手の視覚に訴えて、伝達を試みることになるであろう。
そして、その際、その身振りにせよ、絵にせよ、伝達しようとして表現されるものは、その対象のあるがままの状態ではなく、相手に出来るだけ容易に解らせる為にその対象から抽出した特徴的な要素である。
その要素を身振りなり、絵なりで強調して表現し、伝達を試みようとする時に、初めて言葉の発生への第一歩が踏み出されることになる。
そして相手は、その特徴付けられて表現されるものから、己れの表象内にイメージを浮かび上がらせながら伝達の内容を把握しようとするが、その浮かび上がったイメージが送り手の意図するものと本質的な点で一致する時、初めて伝達は成立することになるのである。
このようにして、送り手が、伝達を意図する対象を分析し、特徴的な要素を身振りや絵によって表現していたのが、やがて、視覚に訴える方向において絵文字が発明され、それが象形文字として発達することになる。
ところで、内容を表示するその感覚的符号が、視覚に訴える種類のものだけでは伝達の敏捷性に欠ける為、別に、聴覚に訴える感覚的符号がそれと足並みをそろえて発達して来る必要性があるであろう。
それは、聴覚が視覚同様に、他の諸感覚よりも知的であり、その為、知性の光の下で微妙な点まで識別することが出来るということと、それに基づく伝達の随意性・敏捷性という利点とが重大な理由となるからである。
そして、初めの段階においては、その聴覚に訴える感覚的な符号は音声としてのみあり、未だ音声を表記する文字なるものは当然発明されてはおらず、ある決った音を持つ少ない音節の音声によって、数少ない主要な対象を表示するに止まったものと思われる。
それは、恐らく、直観内での対象と緊密な関係を持たされる音が、その対象を表示する感覚的符号にまで高められることになるのであろう。
例えば、ある時には、数人の間である対象を観察し、一人が驚きの声を上げるとする。するとその音声が、観察によって抽出された特徴的な要素を内容として、その対象としてある個別や、その要素を内容とする一切の個別を表示する、音声的な言葉となるのかもしれない。
またある時には、一人が、己れの見て来たある対象を他の者達に伝達しようとしているとする。その時、彼はその対象の特徴的な要素を相手の者達に伝える為に、身振りで表現しようと努めるであろうが、それと同時に、たまたま発せられる無意味な音声が、その対象の特徴的な要素を内容として、その対象や、その要素を内容とする一切の個別を表示する、音声的な言葉となるのかもしれない。
そしてまた、ある時には、観察している対象が何らかの音を発するとする。その場合には、その音が、そのままその対象の特徴的な要素を内容として、その対象や、その要素を内容とする一切の個別を表示する、音声的な言葉となるのかもしれない。
以上のようにして、言葉としての機能を持たされた音声は、やがて音を表す文字によって記号化され、それによって広範囲な世界への伝達と、記録・保存とが容易に成されることになるのである。
そして、前述の絵文字・象形文字などの表意文字も、音声による伝達の利点から発音を伴い、日常生活に支障がないように配慮されているので、発生上視覚を重視したのか、それとも聴覚を重視したのかにかかわらず、実質的な働きは同じであると言えるのである。
2 言葉の性質
さて、以上のように、言葉の発生に就いて調べて来たが、今度は、実際に言葉が何を表示することになるのかが検討されねばならないであろう。
然し、概念を表示する符号としての狭義の言葉の場合には、既に調べられた諸概念に対応してその内容を表示すれば良いのであるから、ここでは繰り返すことはしない。
個別を表示する言葉の場合には、正にその個別の持つ直観の状態が、そのまま内容となつて表示されることになる。従って、その内容を表示する言葉は、概念化において切り捨てられる微妙な要素も、そのまま表示することになるのである。
次に、言葉が持つ文法上の性質を、それが表示する領域ごとに区別して、調べてみることにしよう。
まず、直覚的なもの及び知覚的なものの内で、対象の静的な状態や形態を内容とするものは、名詞を、知覚的なものの内で、感覚的性質の変化や物体の運動・静止を内容とするものは、動詞を、そして、直観的なものでは、直観的対象が持つ状態や、諸対象間に成される比較の状態が内容となり、それぞれ名詞を取ることになる。そして、以上の動詞と名詞を骨格として、言葉の連結の際に働く文法的な構造に従って、それらの形が変化したり、それらとは異なった品詞が生じて来たりすることになるのである。
また、語法としては、情意的な要素や反省が全く加わらず、感覚を土台として照し出されて来る世界をそのまま言い切る直接法、そして、願望法や命令法などのように、その世界を情意的なものの中で言い切るもの、また、意図・期待・推量等を内容とする接続法などのように、その世界を反省的なものの中で言い切るもの、以上の三つに大別し得ることであろう。
3 言葉による思考作用
それでは次に、言葉による思考が説明されねばならないが、それは取りも直さず、言葉が表示している内容の連結に過きず、前述の言葉を伴わない思考と同じである。
然し、この場合には、前述のものとは逆に、言葉が切っ掛けとなってその内容を吟味し、その連結を確定するといった過程を取る為、その連結には充分な根拠が求められねばならなくなるのである。
即ち、その認識根拠として以下のものが問題となる。
(1)まず、その連結が確定し、思考そのものが成立する為の思考形式は、ここでも当然認められねばならない。
(2)次に、その言葉の表示する内容を正確に決定し、その連結を実質的なものにまで高める為の根拠として、まず第一に、先験的な直観形式が認められ、その統一形式、及び空間形式が持つそれぞれの性質が、先験的に実質的な認識をもたらす。
その性質とは、統一形式では、継起性の中において表されるものが持たされる継起の相互的な規定関係が、そして、空間形式では、三次元の広がりの中において表されるものが持たされる位置の相互的な規定関係が、それぞれその内容となる。
そして第二に、その実質的な根拠として、経験的なものが認められ、この場合には、統一され、表されて来る一切の〈存在〉が、言葉の表示する内容を満たし、その連結を実質的なものとする。
そして第三に、消極的ではあるが、その実質釣な根拠として、あの規定不可能な領域も認められて来るであろう。
何故ならば、その領域の自覚によって、言葉の表示する内容が如何なる性質のものであるのかを認識し、積極的に連結が成され、認識が得られる領域を、明確に決定することが可能となるからである。
(3)最後に、言葉による思考で、その内容の連結が一般化に基づく概念体系の中で行われる時には、前述の実質的な根拠以外に、論理上の形式的な根拠が認められるようになって来る。
即ち、この論理形式は、ある与えられている概念同志の連結から、その概念体系が持つ形式的論理性の中で、それとは異なった別の新しい連結の表現を見出すことを可能にするのである。つまり、その概念体系が持つ形式的論理性は、一般化の際に働く同一性の判断と抽出作用に基づき、そのようにして得られる一切の概念は、それぞれ他のものに対して対当関係か、あるいは包摂関係に立つことになるのであったが、ここで認められる論理形式なるものは、与えられる認識、即ち連結関係から、その概念体系が持つ諸関係の形式的な枠組みのみに注目し、それを通して別の認識を導き出す根拠となるのである。
然し、その別に導き出される認識は、何ら目新しい内容を持つことはなく、その形式的論理性の中で与えられるものの単なる言い換えとして、既に予定されているものなのであることを、ここで承認しておかねばならないであろう。
以上のように、(2)、(3)の、実質的、形式的両根拠に基づき、(1)の思考形式に従って、内容の連結が成されることになるが、その場合、前述通り、思考形式の内容、即ち、同一律・固定律・矛盾律・排中津がそれぞれ満たされていなければならないことは当然であろう。そして、もしその内の一つでも満たされない時には、その連結は確定せず、認識は成立しないことになるのである。
では、そのことを具体約な例を取って調べてみることにしよう。
「存在するものが多であるならば、それは似ていて似ていない」、を例に取ると、その仮定・帰結では、思考形式の内容を満たしていない為、認識は成立しないことになる。その為、それが何故成立しないのか、思考形式の設定条件にまで辿って調べてみる必要があるのである。
そこで、同一律に関しては、その主語概念及び述語概念の同一性をまず確認しておかねばならない。
その場合、主語概念の(多としてある)「存在」は、〈存在〉として表されるに至る一切の表象であるのか、それとも、ある特定された領域において〈存在〉として照し出され、描き直されるものなのか、それとも、その領域において〈存在〉として照し出されるものだけなのかによって、その内容が変わることになる。
また、述語概念の「似」・「不似」は、以上の各領域の内のいずれにおいても、対象同士間に下される比較の状態をその内容として持ち、この場合には内容が一定している。
その為、この同一律においては、主語概念の内容が同一のものに固定されない限り、その連結は確定されることがないままである。
次に、固定律に関しても、その両概念が取り扱われることになる領域において、如何なる側面からその連結を成すのかが固定されない限り、やはりその連結は確定されることがないままである。
ところで、ここで異なった側面から、二つの全く矛盾的に対立する述語が設定されることになるとしても、その為に思考が成立しないということにはならず、その場合には、その異なった側面に応じてそれぞれ異なった思考が成立して来ると言わねばならないのである。
即ち、同一律によって前述の主語概念が定まり、設定領域が与えられたとして、例えば、表象内で表されるに至る一切の〈存在〉において、その〈存在〉同士が似ているか否かが問題となっているとしよう。
その場合、如何なる側面において、その連結が成されるのか固定されていない限り、思考は成立しないままである。
その表されて来る一切の〈存在〉を、その被統一面の中でそのまま個別的に見てゆくのか、それとも、統一され、表される影として、統一面から見るのか固定されない限り、依然としてその連結は確定されないままである。
然し、そのいずれかに固定される時、初めてその連結は確定条件に従って確定され、思考が成立することになる。
即ち、一切の〈存在〉を被統一面の中で見てゆく時、一切の〈存在〉は似ていない。然し、一切の〈存在〉を影として統一面から見る時、一切の〈存在〉は似ている。
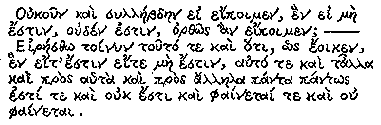
(そこで、要約して言うとして、もし一が存在しないとするならば、何ものも存 在しないと言えるであろう。では、そのように言われるべきだとして、更にまた、 次のように言うことが出来るであろう。一が存在してもしなくても、一も一以外の ものも、自分自身に対しても他のものに対しても、あらゆる意味ですべてでありも しまたありもせず、すべてであるように思われもしまた思われもしないと。)
第一部 表象機能−−−おわり