| こどもそTOPへもどる/英語TOPへもどる |
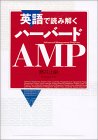 4月の「アラビアの夜の種族」につづき、5月じっくり読む本は「英語で読み解くハーバードAMP」。 4月の「アラビアの夜の種族」につづき、5月じっくり読む本は「英語で読み解くハーバードAMP」。
って、いきなりタイプの違う本ですが、内容は、 ハーバード・ビジネス・スクールが世界に誇る経営者育成プログラム「AMP」で実際に使われている教材を原文(英語)で紹介。同プログラムに実際に参加した著者が、グローバル・ビジネス・リーダー育成のためのエッセンスを語る。 ってな本です。 別にグローバル・ビジネス・リーダーになりたいわけじゃなくて、頭の部分を立ち読みしたら面白かったので。、というのが1つめの選択理由。 2つめは、英語が読めるようになるといいなーと思っているので、英語関連の本が読みたい、と。 が、よくありがちな児童向けの洋書を読むってのは、やってみればわかりますが、つまらない。 文章は、言葉遊びとかあったり、ニュアンスがつかめないと楽しめないものが多かったり。 しかも読み終わっても、なんか得たものは少ない感じがするし。 ということで、凝った文章じゃなくて、すっきりとした文章を使うビジネス書が読みやすいだろう、と。 が、いきなり全部英文のものは挫折しちゃうといやなので、教材の英文を使って日本語で説明している本書にした、というわけです。 3つめは、世界大手企業の重役クラスの人間が"full-time"かつ"residential(全寮制)"に特訓するハーバード・ビジネス・スクールってどんなんだろーという単純な好奇心。特訓合宿地獄の7日間!とか、行くきはねーけど、どんなんだろ?と思ってたり、そーゆー興味は深々なんで。 というわけで、 「英語で読み解くハーバードAMP」を連休明けから、じっくり読みはじめます。また掲示板もつくるので、ぜひご参加を(って、「アラビアの夜の種族」掲示板は結局おれしか書き込んでないし淋し)。 |
第1章は「AMPとは何か」の説明。 AMPは、Adbanced Management Programの略で、「世界最強の経営者教育」。 full-timeで、residential(居住型)なAMPのprogramは、intensive(集中的な)な、executives(幹部)教育体験だ、と。 で、いかにハードで、優れているプログラムであるかが述べられるため、威勢の良い言葉がぽんぽん出てきて、気持ちいい。 offers a powerful solution:強力な解決を提供する conquering real-world challenges :現実世界でのチャレンジを克服 While the door to prosperity is open to all: 繁栄への扉は万人に開かれている dynamic and challenging bussiness environment :ダイナミックでチャレンジングなビジネス環境 sustainable advantage :維持可能な優位性 leading-edge :追随を許さない優位性 フレーズだけ抜き出すと、ちょっと自己開発系の宗教っぽいな。 他に気になった単語&フレーズ participants:参加者 faculty:教授 insight:洞察力 concrete,actionable ideas:具体的で、行動に移せるアイデア changes yet to come:今後起こる変化 |
第2章「AMPの内容」だが、1章の「AMPとは何か」と、どーちがうのかわからず。 そのまま続いてる感じだ。 気になった単語&フレーズ global perspective:グローバルな視野 *perspective drawing:透視図 chief executive officer:最高経営責任者(CEO) program is structured as follows:プログラムは次のように構成される a holistic view:全体図 a powerful global cometitor:グローバルに力強く競合を行う企業 *competitor analysis: 商売敵の研究 *competitor on a quiz show:クイズ番組の解答者 strategic alliance:戦略的提携 *alliance partner:同盟国 |
ケースメソッドとは、ケースライターが書いたシチュエーションで、どう対処すべきか分析し、議論するというようなものらしい。 また例によって凄いよー役に立つよーということが述べられる。威勢がよくて面白いけど、もうちょっと具体例を書いてもいいんじゃないか。 this note briefly describes…:このノートでは…を簡単に述べる sharpen their analytical skills:分析能力を鋭くする *sharpen an ax:斧を鋭くする quantitative and qualitative evidence:治療的かつ定性的な証拠 problem-solving:問題解決能力 face and deal:直面し行動する useful questions:有用な質問 come to sense:気がつく |
ひきつづきケースメソッドについて。前半の内容を補強するもので、議論がこのメソッドの重用部分であることがわかる。明快な唯一の解答などないとはっきりと述べているところがアメリカっぽい。 No single way works for everyone.:1つのやり方が、万人に通用するわけではない。 Read the first few paragraphs,:最初のパラグラフを2、3読んでから relevant considerations:関連する事項 a set of recommendations:一連の提案 the pros and cons:賛否 *「プロコンを述べよ」という言い方が紹介されていて面白い(けど、いやなヤツだよね、そんな言い方するヤツ) you know what you would do in aspecific situation:ある特定の状況で、あなたは何をするかを知っている |
いよいよ本格的にその内容か!と思いきや、また概略を述べるとか言っております。学ぶとはどういうことか、といったことが述べられていて、うむうむもっともです!という感じ。 What is the bottom line?:要するにどういうこと? This note is intended to provide an overview〜:このノートは〜の概要を述べることを意図している。 a once in a lifetime opportunity:人生一度きりの機会 get the most out of〜:〜から最大限のものを手に入れる I will absorb what I need to know:知るべきことは吸収するだろう |
とはいえ、3つのテーマとかでてきて、今までより手ごわい感じになってきました。 読むペースも落ちてしまっている。 来週から英語文庫「アガサ・クリスティ短編集」に突入なのに、がんばれ俺。 Maximize profits. Minimize costs.:利益を最大化せよ。コストを最小化せよ。 competition and strategy:競争戦略 relevant documents:関連書類 relevant remarks:関連発言 |
本当なら、英語文庫「アガサ・クリスティ短編集」に突入しているはずなのに。 あうん。 英語文庫「アガサ・クリスティ短編集」は、6月から突入ってことになるか。 |
4章にはいって、内容もおもしろくなってきた。システムについてのテキストは、概要ちゅーか、あたりまえのことが書いてあるのだけど、英語で読むとえらくなった気分だな。 Thinking Systematically About Complex Problems:複雑な問題についてシステマティックに考える substantive issues under discussion:検討中の重要な話題 The Tacit Dimension:『暗黙知の次元』 |
こういった学習ガイドといった啓蒙的な文章は、キーワードが繰り返されるので読みやすい。1つのキーワードのまわりを監視衛星のようにぐるぐる廻るような文が多いので、そのキーワードの深い意味や、使い方が、よくわかってくる。 fashionの意味がgive a particular shape or form:makeであるというのは興味深い。 Remember,there is usually no single right solution.:正解は通常1つではないことを覚えておいてほしい。 I beg to differ.:失礼ですが、意見が違います。 Insights about diverse values and cultures.:多様な価値観や文化に対する洞察。 fashion an agenda for change:変革のための行動計画を作る |
ぐはっ。まだ、英語文庫「アガサ・クリスティ短編集」に突入できない。あよーん。 AMPは、この手の本に必須でしょーの5つのAとかが出てきました(喜)。 グローバルビジネスで成功するための5A's。Accept Adopt Adapt Attack Appreciateだそうだ。 Good managers enable others to act effectively.:すぐれたマネージャーは他者が効果的に動けるようにすることができる。 This is what leadership is about.:これがリーダーシップの本質である。 |
ようやく読了。来週から英語文庫「アガサ・クリスティ短編集」に突入だ。 「The Meyers-Briggs Day」が興味深い。個人の思考と行動特性を4つの次元で文ル視する手法。以前からこの手のものは、うさんくさいだけだと思っていたが、人種のmelting potであるアメリカ社会(しかも個人タイプを明確にすることで関係を築く国だからなー)ではある程度、有効かもしれない。 外向的(Extravert=E) ---内向的(Introvert=I) 直感的 (Intuiting=N)---知覚的(Sensing=S) 感覚的 (Feeling=F)---思考的(Thinking=T) 判断派 (Judging=J)---感知派(Perceiving=P) の組み合わせで示す。たとえば「ISTJタイプ」とか。 |