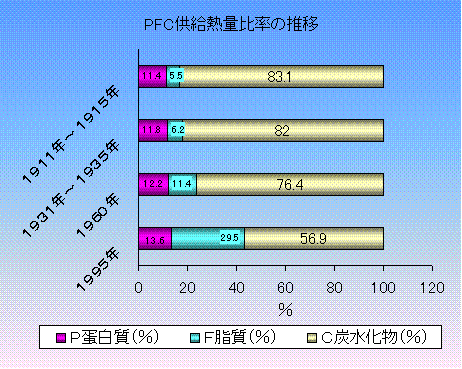
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |
|
第一位 |
肺炎、気管支炎 |
226.1 |
結核 |
212.9 |
脳血管疾患 |
160.7 |
|
第二位 |
結核 |
163.7 |
肺炎、気管支炎 |
185.8 |
悪性新生物 |
100.4 |
|
第三位 |
脳血管疾患 |
159.2 |
脳血管疾患 |
177.7 |
心疾患 |
73.2 |
|
第四位 |
胃腸炎 |
133.8 |
胃腸炎 |
159.2 |
老衰 |
58.0 |
|
第五位 |
老衰 |
131.0 |
老衰 |
124.5 |
肺炎、気管支炎 |
49.3 |
|
総計 |
|
2、077.1 |
|
1、649.6 |
|
756.4 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |
|
第一位 |
脳血管疾患 |
156.7 |
悪性新生物 |
156.1 |
悪性新生物 |
211.6 |
|
第二位 |
悪性新生物 |
122.6 |
心疾患 |
117.3 |
脳血管疾患 |
117.9 |
|
第三位 |
心疾患 |
89.2 |
脳血管疾患 |
112.2 |
心疾患 |
112.0 |
|
第四位 |
肺炎、気管支炎 |
33.7 |
肺炎、気管支炎 |
42.7 |
肺炎 |
64.1 |
|
第五位 |
不慮の事故 |
30.3 |
不慮の事故 |
24.6 |
不慮の事故 |
36.5 |
|
総計 |
|
631.2 |
|
625.5 |
|
741.9 |
戦前までは結核が第一位で次いで肺炎、気管支炎だったが昭和30年より脳血管疾患が第一位、悪性新生物が第二位となる。昭和60年には悪性新生物が第一位になり、心疾患も第二位まで上がってきた。悪性新生物は昭和35年から平成7年までの間に二倍となり、今後も益々増えていく傾向にある。悪性新生物の部位別で見てみると男女とも大腸ガン、肺ガン、そして女性は乳ガンの増加が著しい。全体の死亡率は年次ごとに減少していたが平成の年号に変わってからは一転して増加傾向を示している。
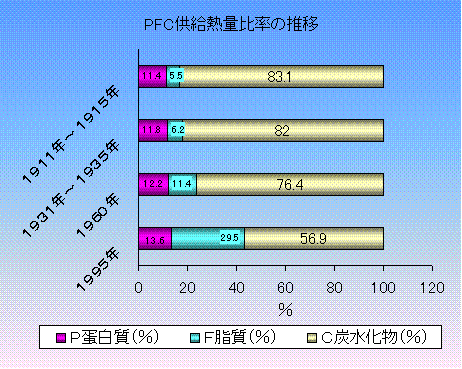
上記を見てみると、グーンと一番増えたものは脂質だ。明治の頃と比べると約6倍近く増えたことになる。そして、その代わりに減ったものが炭水化物、いわゆる主食にあたるご飯だろう。脂質摂取を増加させるものは油を使った料理−揚げ物、炒め物−、肉類の多食。油を使って料理をしたり、お肉を焼いた時の香りは確かに香ばしく、食欲をそそるものではある。でもそればかりを食べ過ぎてはいないか?もう一度考えてみよう。脂肪は1gで9Kcal、炭水化物は1gで4Kcal摂取できる。これは脂肪が少ない量で手っ取り早くカロリーが摂れることを意味する。でも同じカロリーを摂る時あなたはどちらを選ぶ?油を大さじ3杯飲むか、それともごはん2膳食べるか。お腹がしっかりとふくれるのはどっちだろう。