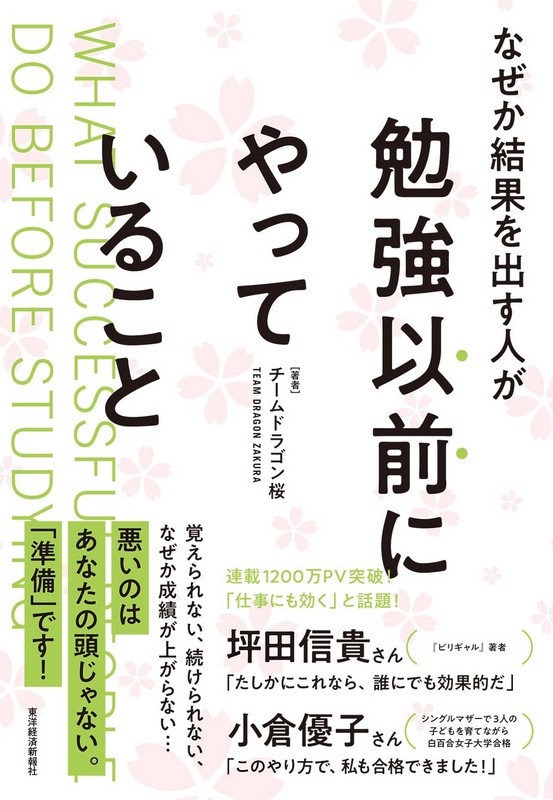
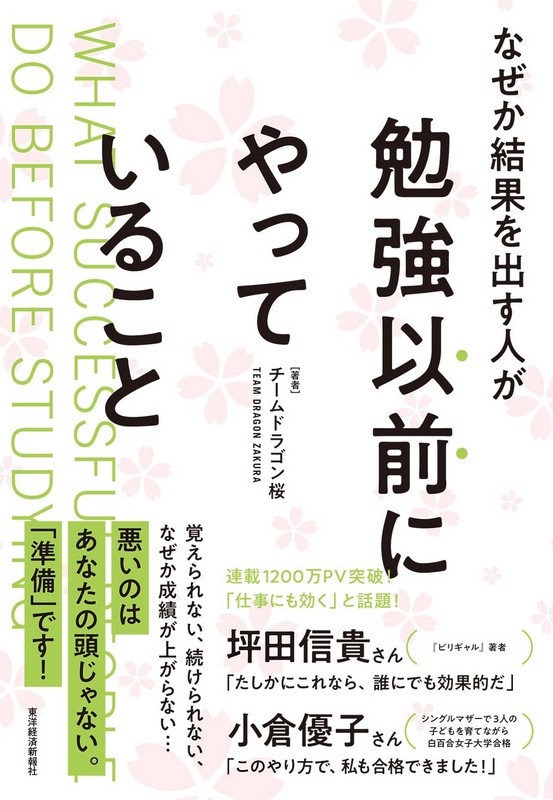
僪儔僑儞嶗偱徯夘偝傟偨栚昗傊岦偐偆峫偊曽傪徯夘偟偰偄傑偟偨丅
偙偆偄偆杮偑丄杔偑巕嫙偺崰偁偭偰撉傫偱偄偨傜偲巚偄傑偡偑丄偙偆偄偆傕
偺傪庴偗擖傟傞帠偑偱偒偨偐丠偲偄偆偲擄偟偄偐傕丠
栚昗傊嵟抁嫍棧偱恑傓堊偵尰嵼埵抲偲栚昗偺埵抲傪攃埇偡傞帠偲偄偆偺偵偼丄
桴偒傑偔傝偱偟偨丅摉偨傝慜偺榖側傫偱偡偑丄側偐側偐偱偒側偄傫偱偡傛偹丅
亂栚師忣曬亃
偼偠傔偵
乽儕傾儖僪儔僑儞嶗乿傪惗傒懕偗偰傢偐偭偨両
寢壥偼乽曌嫮傪巒傔傞慜偺弨旛乿偱寛傑傞
俬俶俿俼俷俢倀俠俿俬俷俶
曌嫮寵偄偱傕帪娫偑側偔偰傕俷俲両
乽儅僩儕僋僗乿傪彂偗偽
乽帺暘偵崌偭偨曌嫮朄乿偑偐側傜偢尒偮偐傞
俹俙俼俿侾丂乽岲偒亊嬯庤乿偺曌嫮朄
婃挘傜側偄偱俷俲両
乽栚揑丒栚昗偺僽儗僀僋僟僂儞乿偱
帺暘偵崌偭偨乽惓偟偄搘椡偺曽岦惈乿偑尒偮偐傞
俹俙俼俿俀丂乽寵偄亊嬯庤乿偺曌嫮朄
帺暘傪曄偊側偔偰俷俲両
壢妛揑側乽儖乕僥傿儞偯偔傝乿偱
乽帺摦儌乕僪乿偱曌嫮偑巒傔傜傟傞
俹俙俼俿俁丂乽寵偄亊摼堄乿偺曌嫮朄
乽柺搢偔偝偑傝乿偱俷俲両
乽僞僀僷嵟戝壔乿偺係俽俿俤俹偱
乽嵟彫偺帪娫乿偱乽嵟戝偺岠壥乿傪僎僢僩偡傞
俹俙俼俿係丂乽抧摢乿偑傛偔側傞廗姷
婘偵岦偐傢側偔偰俷俲両
乽側偤丠乿傪偮側偘傞巚峫朄偱
乽惗偒偰偄傞偩偗乿偱摢偑傛偔側傞
俹俙俼俿俆丂搘椡傪懕偗傞廗姷
乽嫮偄怱乿側傫偰側偔偰俷俲両
乽儅僀儞僪僙僢僩乿偺惍偊曽偱
搘椡傪乽岠棪揑乿偵乽宲懕乿偱偒傞
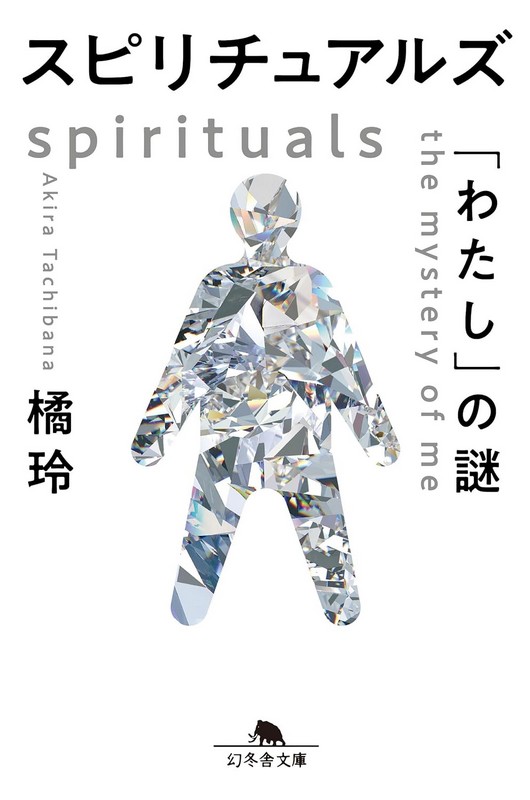
俁擭慜偵敪攧偵側偭偨杮偱偡偑丄崱撉傓偲懠偺杮偱撉傫偩撪梕偑寢峔懡偔偰怴
慛枴偑柍偄偺偑巆擮偱偟偨丅偦傟偱傕徻偟偄忣曬偑彂偐傟偰偰嫽枴偁傞偲偙傠
偼柺敀偐偭偨偱偡丅乮戝娋乯
LSD偺僩儕僢僾懱尡傪乽僒僀働僨儕僢僋乿偲柤偯偗偨偺偑僇僫僟偺惛恄壢堛偺
僴儞僼儕乕丒僆僘儌儞僪偩偦偆偱偡丅偁偲尃椡梸丄嫟姶惈偺寚擛丄帺屓垽偺
俁偮偺惈奿偑懙偆偲乽僟乕僋僩儔僀傾僪乿偭偰尵偆偦偆偱偡偑丄僪僫儖僪丒
僩儔儞僾傪傄偭偨傝偲偟偰偄傑偟偨偑丄屄恖揑偵偼偪傚偭偲堘偆傛偆偵巚偆
偺偼杔偑挊幰傛傝曐庣揑側峫偊偩偐傜側傫偱偟傚偆丅
撪梕偲偟偰偼丄乽恖娫偺惈奿丒帒幙偼丄乮堄幆偱偼側偔乯乽柍堄幆乿偑寛掕偟丄
偨偭偨俉偮偺梫慺偱峔惉偝傟傞丅
嘆柧傞偄乛埫偄
嘇妝娤揑乛斶娤揑
嘊摨挷惈偑崅偄乛掅偄
嘋憡庤偵嫟姶偟傗偡偄乛椻扺
嘍怣棅偱偒傞乛偁偰偵側傜側偄
嘐柺敀偄乛偮傑傜側偄
嘑抦擻偑崅偄乛掅偄
嘒奜尒偑枺椡揑乛偦偆偱側偄
偱丄偙偺慻傒崌傢偣偱偟偐側偄丅乿偱偦傟偧傟偺夝愢偱偟偨丅
偪側傒偵杔偺惈奿偼丄偙傫側姶偠偱偟偨丅
宱尡傊偺奐曻惈 3
寴幚惈 1
嫤挷惈 3
忣摦偺埨掕惈 2
奜岦惈 -1
-4乣+4
奜岦惈偑丄儅僀僫僗偱偡偑丄宱尡傊偺奐曻惈偲嫤挷惈偼僾儔僗丅
偦偺懠偼晛捠偱偟偨丅
屄恖偺惈奿偼丄壠掚娐嫬傛傝傕桭恖娭學乮梀傃拠娫偺娫偱偺僉儍儔僋僞乕乯偺
曽偑塭嬁偑戝偒偄偲尵偆偺偼丄杔傕惓偟偄偲巚偄傑偡丅帺暘偺巕嫙偵乽偙偆偟
偰梸偟偄乿偲尵偭偰傕暦偐側偄偱偡偹丅乮徫乯杔傕帺暘偺恊偺偄偆帠傪暦偄偰
偄傑偣傫偱偟偨丅乮敋乯
偲偄偆帠偼丄壜擻側傜巕嫙偺桭恖傪慖傇偺偑椙偝偦偆偱偡丅乮妛峑偲偐娐嫬側
傫偱偟傚偆偑丒丒丒乯
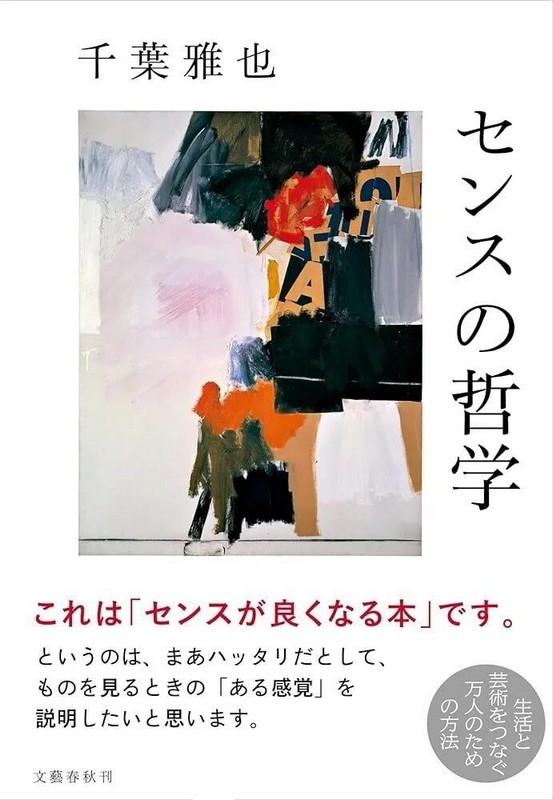
乽偁側偨偺僙儞僗偑椙偔側傞杮両乿
偲偄偆乽偀傖偟偂乿僐僺乕偵堷偭偐偐偭偰撉傫偱傒傑偟偨丅
挊幰偼係俆嵨偲尵偆庒偝側偑傜僼儔儞僗偺尰戙揘妛偺尋媶幰側偺偱丄柇偵屆偄
悽戙偺廘偄偑姶偠傜傟傞杮偱偟偨丅偙偺杮偱偼乽僙儞僗乿偺掕媊傪乽傕偺偛偲
偺捈姶揑側攃埇乿偲偟偰乽儕僘儉乿偲嵞掕媊偟偰傑偟偨丅懳徾偼尰戙旤弍丄壒
妝丄塮夋側偳偲峀傔偱偡偑丄楡幚廳旻偑弌偰偒偨傝偲屻捛偄側傫偱偟傚偆偑丄
斸昡偺楌巎傪僩儗乕僗偝傟偨傛偆偱偡丅
杔帺恎偼丄巕嫙偺崰乽嫵梴乿傪愊傫偱峴偒偨偄側偀偲巚偄丄傾乕僩嶌昳偲偐僋
儔僔僢僋壒妝偲偐偼丄偲傝偁偊偢尒暦偒偟偰偒傑偟偨丅崙撪偺旤弍娰偱偼偁傑
傝姶偠偰偄側偐偭偨傫偱偡偑丄奀奜弌挘偲偐偱儘儞僪儞傗僯儏乕儓乕僋偲偐偱
旤弍娰傗攷暔娰傪偩傜偩傜娤偰夞傞偺偑岲偒偱揥帵偝傟偨嶌昳偲帺暘偺懳洺偲
偄偆偐丠偳偆偄偆巋寖傪庴偗傞偺偐丠姶偠傞偺偑妝偟偐偭偨婰壇偑偁傝傑偡丅
偢偭偲帺暘偼丄怓傫側傕偺偵懳偟偰乽僙儞僗偑埆偄乿偲巚偭偰偄傑偡偑丄幚偼
偦傫側偺偳偆偱傕偄偄偲傕巚偭偰偄偰乽岲偒側傕偺乿乽巋寖傪摼傜傟傞傕偺乿
偑帺暘偵偲偭偰戝帠偱偟偨丅偱傕丄偙偺杮偺僐僺乕偵堷偭偐偐傞偲偄偆帠偼
乽偳偙偐偱僙儞僗偑椙偔側傞偲偄偄側偀乿偲巚偭偰偄傞傫偱偟傚偆偹丅乮徫乯

傾儅僝儞偱僾儗儈傾儉壙奿偵側偭偰偄偨杮丅
徏杮偺恾彂娰偱庁傝偰丄栺敿暘撉傒傑偟偨丅嵟屻傑偱撉傓婥偵側傝傑偣傫丅
棟桼偼丄儊儞僞儖儌僨儖偲偄偆巚峫朄傪娙扨側愢柧偱300埲忋宖嵹偟偨傕偺偱
偡丅僕儍儞儖偼懡嵤側偑傜丄偦傟偧傟偺峫偊曽傪偙偺杮偩偗偱棟夝偡傞帠偼丄
擄偟偄偲巚偄傑偡丅堄奜偲宖嵹偝傟偨傕偺偺懡偔偼丄寢峔億僺儏儔乕側傕偺
偺傛偆偵巚偄傑偡丅杮彂傪栚師偲偟偰棙梡偟偰丄壽戣偵栶偵棫偪偦偆側傕偺
偺杮傪撉傓偺偑丄惓偟偄巊偄曽偩偲巚偄傑偟偨丅
偲堦扷彂偄偨傫偱偡偑丄寢嬊嵟屻傑偱撉傒傑偟偨丅
姶憐偲偟偰偼乽XXX岠壥乿偲偐僱乕儈儞僌偑戲嶳暲傫偱偄偰婰壇偵巆傜側偄
報徾偱偟偨丅傑偀丄偦偺嬈奅偱偦偙偦偙偺惉壥傪弌偣偰偄傞傫偱偟傚偆偑丠
帺暘偺壽戣偵巊偊傞偐偳偆偐偼丄傗偭偰傒側偄偲暘偐傜側偄傛偆側婥偑偟傑
偟偨丅寢嬊嵟弶偺乽栚師偲偟偰巊偆乿偑惓偟偄傛偆偵巚偄傑偡丅
俀侽俀係擭俇寧侾擔