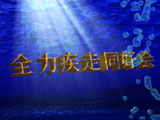|
小人閑居して不善をなす
リニューアル・オープンということで、いくつか新規の記事も起こしているのだが、
画廊伝説は間に合わなかった。トップページのタイトル画像に手間取ってな。
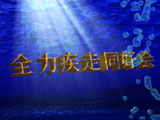
コレだコレ
タイトルをこういうのにしたのは、トップページのリニューアルのためのコンセプトが「深海」だったため。
決して、「青の6号」に影響されたのではない。
いまさら言っても、言い訳にもならないな。
タイトル画面そのものは、「青の6号」(以下「青6」)を見る前に完成していたのだが、
「青6」を見てから、すべて作りなおしたしな。
絶対にそうだとは言い切らないが、3DCGやってると、つい深海ネタをやってみたくなるのよ。
深海(というか、海の中)は、水面の水のゆらめきとかの表現が手描きでは面倒だし、
動画となるともうどうしようもない。
逆に、3DCGだと結構それらしいものが、割と簡単に作れてしまうのだ。
まあ、腕試しにちょっと手を出してみたくなるものなのよ。
★
その一方で、俺の中には「海」に対する憧れと恐怖が混在している。
俺は基本的に泳げない(プールでせいぜい50mというのを泳げるとは言わんだろう)ので、
自分の目で、海の底から海面を眺めるような経験をすることはほとんどない。
スキューバダイビングなんてのも、ちょっと興味があるが、
やっぱし「死ぬ」のが恐いから、やらないような気がする。
溺死ってのは、かなり辛い死に方らしいし。
「死ぬ」っていうことで言うと、これにもまた憧れと恐怖が混在する。
生きている状態を維持したまま、「死ぬ」ということを体験することはできない。
「自分が死んだらどうなるんだろう」なんて考えるのは、とても恐いことだ。
その反面、すべてのしがらみから解放されるという見方もできる。
「馬鹿は死ななきゃ直らない」ってことだ。
いわゆる、「地獄」と「極楽」という存在は、宗教でいう「死」という恐怖からの救済と、
「生前、悪いことをしたヤツは地獄に落ちるゾ」と、「死の恐怖」を増幅する道徳的な意味があるのだと思うが、
俺は、そんなもの信じていない。
死んだら、焼かれて灰になるだけだ。
せめて土葬してもらえれば、そのへんの木やら植物やらの養分として生命が連鎖していくのだが、
日本でそれやると、犯罪(死体遺棄)だからな。
余談はさておき、「地獄」も「極楽」の存在も信じていない俺だが、
「地獄」=「恐怖」、「極楽」=「解放(解脱といってもいい)」という観点において、
なんとなく、イメージとして理解することができる。
そういう、「地獄」と「極楽」のイメージが、俺にとっての「海」のイメージそのものなのだ。
「海」もまた、「生命の始まり」のイメージがあり、同時に「人間の生きていけない世界」というイメージが同居する。
「ABYSS」という映画は、深海での人間と知的生命体との邂逅をモチーフに、
「裁かれるべき人類」と「裁くべき位置にいる存在」について描いた作品だが、
「ABYSS(日本語でいうと奈落とかそういう意味)」が、深海にあるっていうのも、
実に深い(シャレではない)意味を感じるね。
★ そんなわけで、「海」モノには果てしない興味があるわけで、
海洋モノは、たいていハマるね。
「グラン・ブルー」なんて、今更言うまでもない。
古くは、「海底2万里」とかね。
で、同じ古いって意味では、日本の海洋SFの巨匠、小澤さとるの名を忘れるわけにいかんだろう。
「サブマリン707」の方がメジャーかもしれないが、「青の6号」も彼の作品。
もちろん、今は「青6」が旬だ。
書き下ろしの新作も発売されたし、今回のテーマであるビデオ版もなかなか凄い。
どうやら、いよいよ本題らしい。
変な位置だが、タイトルいってみよう。
「海」−そこにある恐怖と悦楽−
いつにも増して、余談が長いな。
仕事もヒマになって、絶好調というところか。
ただ、ビデオ版「青6」の凄いところって、専門的(というかマニア的)だったりする。
作品自体のテーマも、けっこう深い内容になりそうな予感があるのだが、
なにしろ第1話を見ただけなので、なんとも言えない。
第1話ってのは、完成度の高いプロローグって感じで、
具体的な説明はほとんどなく、いきなりキャッチーなアクションが連続する。
という、最近のシリーズものの基本的な構成になっているので、
作品的な評価は、もうちょっと待たねばなるまい。
問題は、「青6」がフルデジタルアニメーションだってことだ。
アニメーションのデジタル化ってのは、 セル画の彩色をパソコンでやる(使える色数が増える)、という原始的なものから、
背景との合成から、特殊効果まですべてパソコンで行う、というものまで、
一部だったり、すでにいろいろな作品で行われている。
実際、現代のアニメ界のひとつの流行なわけだ。
「青6」に関して言えば、「現時点」における集大成と言っていいと思う。
「青6」では、人物は手描きでメカと海面の描写は3DCG、背景は状況に応じて使い分け、という構成。
手描きと言っても、作業そのものはパソコンでやっているので、
グラデーション使った彩色なんかが結構見物。
3DCGに関しては、専門誌なんかではもっと凄いのもあったりするが、
間違いなく最高峰レベル。
で、それが何かいいことあるのかというと、
「アニメの制約」のほとんどを取り払うことができるわけだ。
例えば、実写ではロングカットから一気にズームアップしていくなんて簡単なことだが、
アニメではとても難しい(というか面倒)。 だって、ロング用のカットには、細かい部分なんて描いていないし、
逆にクローズアップ用のカットを引き延ばすとすると、
どれだけでかいセル画が必要なのか想像もできん。
このへんを、今まではカット割なんかでうまくごまかしてきたわけだが、
実写では当たり前のようにやっていることができないのは辛い。
そのうえ、実写ではアニメが得意とした「手軽に」現実に再現できない場面を映像化することを、やはりCGで可能にしている。
じゃあ、アニメでもやるしかないだろう。って訳だ。
もう、実写もアニメも見た目の絵柄(フォトリアリスティックか、ピクチュアライズか)以外に大きな差はないね。
3DCGを採用する理由は、一番大きな理由は「その方が簡単だから」だろう。
毎週土曜日の深夜フジテレビ系で、放送されている「頭文字D」の例では、
車の走行シーンが3DCGなわけだが、
これ、アニメでやったらとても大変。
ドリフトアングルの変化なんて、全部描いてたら毎週放送できん。
実写でやったら警察に捕まるだろうし。
で、3DCG。
「青6」の場合は、メカそのものを「動かしやすい」って意味では同じだし、
冒頭でも書いたように、水の表現に関しては3DCGの方が効率がいいからだろう。
その意味で、海洋SFというか潜水艦バトルもののアニメ化ってのは、
フルデジタルアニメのメリットがいかんなく発揮でき、かつ効率も良いという、
作り手サイドとしては、実にナイスな企画だったわけだ。
現状では、まだまだコスト削減まではいかないだろうし、
本当に効率が良くなってくるのは、これからだろうと思うが。
問題はここからだ。
それは、アニメ業界とアニメファンにとっては、素晴らしいことなのだが、
一般の人にはほとんど意味がない。
そういうこと、気にしないでしょ、普通。
少なくとも、そういうことで金払わないでしょ。
これまでできなかった、「できて当たり前のこと」をやっているだけだから。
手描き部分と3DCGの合成も、かなり良く出来ているのだが、
ちょっと違和感を感じる部分もあるしね。
要は手描きの質感(グラデーションかけたり、けっこう努力はしているが)と、
基本的にフォトリアリスティックな3DCGの質感とのギャップが目につくわけだ。
このあたりは、10回以上見ると慣れる(笑)。
慣れるというか、こういうのもアリだと素直に見られるようになる。
3DCGでも、「スーパーセルシェーダー」とかを使うと、
アニメ絵風な質感でレンダリングすることも可能だが、
そこまでするなら、手描きでもよかんべえ。
「スーパーセルシェーダー」とかは、あくまで表現手法のひとつとして、
使い手が選択して使用するべきだろう。
(ファミリーマートのCM、アレも3DCGだよ)
それ以上になあ、映像が凄えんだよ。
ダイナミックなんだよ、大迫力なんだよ。
多少の違和感なんて、軽くふっとぶね。
これは見てみないとわからない。
で、さらに凄いのは「音」
アニメ初ではないが、(dts版も出てるしな)
ドルビーデジタルによる5.1chサラウンド音声が凄い!
ちなみに、これまでのドルビー・プロ・ロジックとドルビーデジタルは、
臨場感がケタ違いに差がある。
本気で、サラウンドシステム揃えたくなります。
というのも、ハリウッド映画なんかでのサウンドデザイン(サラウンド再生における音の配置)は、基本的にセンター(前方チャンネルの真ん中にある)にセリフが定位するようになっている。
セリフをしゃべっている登場人物が右にいても、左にいても、だ。
これはこれで正しい。
が、「青6」だと、場面の登場人物の配置に沿って音の配置が変わる。
連続するシーンで、複数のカットによって構図が変わる場合は、
カットに合わせて音の位置が変わる。
例えば、画面の中でセリフをしゃべっている登場人物が右から左へ歩いていくようなシーンでは、
音もきちんよ、右から左へ移動する。
(普通は音だけは真ん中で動かない)
こうしてしまうと、見た目の映像としてはリアルなのだが、
ちょっと、見る人が忙しいんだね。
セリフなんてのは、一番聞きたい音だから、
そんなに右へ左へ動かれると疲れるわけ。
そういうわけで、これも人によって好き嫌いがあるのだが、
俺は大賛成。
人によっては、「酔う」かもしれないが(耳ってそういう器官なので)、
俺は大丈夫だ(仕事上、訓練しているので)。
フォーマットの制約のため、ビデオ版のみ音声がドルビー・プロ・ロジックだが、
LDとDVD版には、ドルビーデジタルが記録されているので、
買うなら、LDかDVDでしょ。
ま、さっきも言ったとおり、こういう「技術うんぬん」に関心のない人は、
見てもその良さがわかりにくかもしれないけれど。
大多数の人は驚くんじゃないかな。
あくまでも「今のところは」ね。
作品的に凄いことになってくるのは、
これからだからな。
|