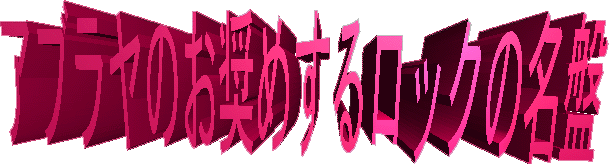
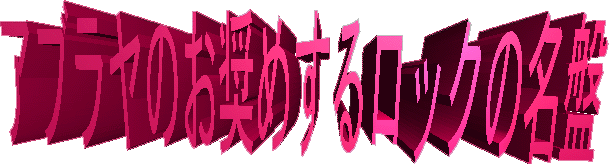
![]()
 『Grand Hotel』Procol
Harum
『Grand Hotel』Procol
Harumしかし…かつて昭和という激動の時代を、一介の高校生として健気に生き抜いてきたに者とって(笑)レコード盤
を買い求めるという行為は、きょうび気軽にレンタルCDやMDを利用しているだろう現在の高校生達には、きっと
想像もつかない程厳正な儀式だったような気がするのであります。なにしろ店頭で逡巡している時間の長かった事といったら(笑)
月々親から貰う僅かな小遣いを少しづつ貯めては、ワクワクしながら地元のレコード屋さんに駆け込んでは、夢にまで見ていた
アーティストやグループのレコードを手に入れた時の喜びといったら、何者にも代えられない至福の時だったのでありました。
さて…今回此処に紹介させていただくのが、久しぶりに英国のバンド、プロコルハルムの『グランド・ホテル』なのであります。
たぶん、普段あまりロックを聴かない方々にとっても、彼等にとって最大のヒット曲である「青い影」などは、きっと何処かで耳
にした事があるかと思うのですが…何を隠そうヘソ隠そう(笑)実はかくいう私も高校を卒業する頃までプロコルハルムといえば、
やはり「青い影」しか知らなかったのであります。たしか大学受験を無事に終えて、ホッと一息ついていた頃だったと記憶してい
るので、おそらく1977年の春先だったのでせうか…普段何気なく自転車で走っていた商店街の一角に古道具屋さんがありました。
或る日たまたま偶然店内に、段ボール箱一杯のLPレコードが入っているのを発見した私は、思い切って薄暗い店内に足を踏み入
れたのでありました。そして…其処が私にとってのお宝の山だという事に気がつくまで、さほど時間はかかりませんでした。
たしか一枚平均大凡500円前後の値札が付いていたように記憶しているのですが、カクタスやバニラファッジ、ホークウィンド、
デッドにシカゴやTYA等々…貧相な私のレコード棚が、アッと言う間に充実していく様は、まさに感動的だったのだ。(-。-)y-゚゚゚
さて…ってな訳で、その古道具屋通いの時代に買い集めた数々のアルバムの中に、今回紹介するアルバムがあったのでありました。
そう、それが此のプロコルハルム『グランド・ホテル』(1973年)なのですが、燕尾服にシルクハットでバッチリと正装した彼等
が、真っ白な洋館の前に佇むジャケット写真に惹かれて、真っ先に買い求めたのですが、私の直感(?)どおり素晴らしいアルバム
だったのでありました。たしかこのアルバムのライナーを書いていたのは、当時はまだ作詞家として駆け出しの頃の松本隆氏だった
ように記憶しているのでありますが、其処で彼が絶賛していたのが、プロコルハルムの専属作詞家であるキース・リイドが書く詩の
世界だったのでありました。所謂、如何にも英国…いや、っていうよりも黄昏のヨーロッパとでも表現したら良いのでせうか、如何
にもエレガントな気品さえ漂う、ひたすら美しくて悲しい、彼等独特の音世界が展開している作品だと思います。それに生ピアノと
ハモンドオルガンという、所謂ツィンキーボードという編成というと、ほぼ彼等と同時期に大西洋を隔てた米国にも、ちょっとばか
り肌触りを異にするのですが、ザ・バンドという郷愁漂うバンドがおりました。まるで哀愁漂う黄昏の欧州を音像として我々に提示
するかのようなプロコルハルム。そして片や、朦々と砂塵を巻き上げながら、見渡す限り荒涼と広がる広大なアメリカの大地を疾走
するかのような…ザ・バンドの音。どちらも哀愁を帯びながら、ずっしりとした感触のサウンドには何処かしら相通じるものがある
ような気がします。そういえば昔、某映画評論家が大変に興味深い話しを或る映画のパンフレットの中に書いておられました。
彼曰く、映画を大雑把に分類すれば、”グランド・ホテル形式”と”駅馬車形式”という、現在では古典になってしまいましたが、
共に名画として評価を受けている二つの作品に行き着くそうなのであります。つまり或る一定の場所(グランド・ホテル)を起点に
して、そこに集う人々達が繰り広げる人間模様だったり、逆に或る場所から他の場所に移動するマシン(駅馬車)を舞台に展開され
る事件をとおして描かれる人間模様という、切り口によっては果てしなく相反していきそうな二つの形式…。 まさに此のアルバム
は、そのタイトル通り「グランド・ホテル形式」を代表する”音楽”なのではないかと、今まさに認識を新たにしております。
 『Family Style』The Vaughan Brothers
『Family Style』The Vaughan Brothersたしか私が現在の女房と結婚した年だったっけ…。普段はスケベ話ばかり言ってくる仕事仲間が、突然真面目な顔して
「アブラヤさん、アメリカ人で結構有名なギタリストが飛行機事故で死んだそうだよ。」と話しかけてきたのでありま
した。思わず「誰!誰!なんて名前の人?」と彼に訊ねたのですが、「えっとね…、ボーンさんっていうギタリストを知っている?」
と、逆に質問されて「ボーンさん?う〜みゅ…そんな名前のギタリストいたかな〜。」と思案に耽ったのがつい昨日の事のように思い
起こされるのであります。そして、その晩に当時のバンド仲間から「飛行機事故でスティーヴィー・レイ・ヴォーンが死んだぞ…。」
と聞かされて、改めて吃驚したのでありました…。1990年8月27日未明、ウィスコンシン州イースト・トロイからシカゴへと飛び発っ
た4機のヘリコプターの内、彼やスタッフを乗せたヘリコプターが折からの濃霧のために山の斜面に激突したとのニュースでした。
折しもスティーヴィー率いるダブルトラブルが、エリック・クラプトンやオーティス・クレイ達との全米ツァー中に起きた惨事だった
のでありますが…享年35歳、まだまだ今後も素晴らしい活躍を楽しみにしていただけに、私も随分とショックを受けた記憶があります。
そして、それから間もなく発表されたアルバムが、今回紹介させて頂く『Family Style』(1990年)なのでありますが、これは彼
が率いるダブルトラブルではなく、スティーヴィーより3つ年上の実兄でファビラス・サンダーバーズを辞めたばかりのジミー・ヴォー
ンと初めて一緒に組んで作ったコラボレーション・アルバムであると同時に…皮肉にもこれが彼の遺作となってしまったのでありました。
思い起こしてみれば…ロックを聴かなくなっていた80年代前半頃、ふとしたキッカケで耳にした『Texas Flood』(1983)にブッ飛んで
以来、スティーヴィー・レイ・ヴォーンのギターは、私の一番感じやすい部分を刺激してくれる(?)唯一のプレイヤーだったような気
がします。あのジミ・ヘンドリックスやアルバート・キング直系のパワフルで繊細な、彼特有のブルース・ギターは素晴らしかった。
さて、このヴォーン・ブラザーズの『Family Style』なのですが、一聴する限り殆どの曲を弟のスティーヴィーが派手に弾きまくり歌い
まくっていて断然、舎弟の勝ち!(笑)ってな印象があったのですが、今回久方ぶりに聴いてみると改めて色々と新しい発見が出来ること
に吃驚している40親父だったりします。弟のケレンミたっぷりのプレイに目を細めながらも、肝心な要所要所を兄貴のジミーが締めてい
るおかげで、アルバム全体を通して絶妙なバランスが取れているような気がしますし、いかにもテキサスっぽい雰囲気を醸し出している![]()
のは、間違いなくジミー・ヴォーンのセンスなのではないかと実感した次第なのでありましたが…良い兄弟だったんだろうなー。
因みに私、7曲目の「Tick Tock」を聴くと涙腺がブチ切れます。チックタック♪時は流れてゆく…子供達は未来に期待している♪
…と、あのジョン・レノンの「イマジン」に通じるようなイノセントで肯定的なメッセージには、からきし弱いんです僕…。(T^T)
今頃彼は天国で、あのジミヘンやアルバート・キング達に囲まれて、ブルース・セッションでも楽しんでいるのかしらん?(-。-)y-゚゚゚
 『Boz Scaggs』Boz
Scaggs
『Boz Scaggs』Boz
Scaggsセピア調のアルバムジャケットの向こうで、やけに「にんまり」と喜色満面の青年が佇んでいる。
それにしても、彼が立っている場所はサンフランシスコ辺りの街角なのだろうか?やけに勾配の急な坂道なのである。
いや…実はそんな事よりも他に、先程から気になっている事が一つだけあるのだ。何故、彼は左手を腰の後ろに回しているのだろうか?
ひょっとして、その隠し持っているのモノをしっかりと掴んでいるので、彼は得意げな顔をしているのだろうか?
取りあえず、彼が若き日のボズ・スキャッグスだという事、そして今回私が手にしているアルバムは、彼がスティーブ・ミラー・バンド
を辞めた後に、遙々アラバマ州はマッスル・ショールズに出向いて録音されたアルバムで、彼がアトランティックに唯一残したアルバム
であるという以上に、今は亡き南部が生んだ或る天才ギタリストの壮絶なプレイが、現在でも語り草になっているようなのであります。
1969年、当時のマッスル・ショールズ・サウンド・スタジオには、オールマン・ブラザーズ・バンド結成前夜のデュアン・オールマン
が、まだ一介のスタジオ・ミュージシャンとして、あのロジャー・ホーキンスやエディー・ヒントン達と仕事をしていたという事実は、
ボズにとっては一期一会とでもいうべき奇跡的な僥倖だったのではないだろうか…。現在でも入手できる国内盤のアルバム・タイトルが
『ボズ・スキャッグス&デュアン・オールマン』と、まるで二人のコラボレーション作品かと見間違うかのようなタイトルで販売されて
いるように、ボズの切々としたヴォーカルに呼応するかの如く、アルバム全編に渡ってデュアンのハート・ウォームでスリリングなギター
が泣きまくっている名盤です。特に、このアルバムについて語る時に、必ずと云っていい程出てくる有名な収録曲に「Loan me a dime」
というフェントン・ロビンソン作の古典的なブルース・ナンバーがあります。心の襞を一枚一枚削ぎ落としながら、深い闇の中に沈んで
行くかのようなボズの歌に、時にはじゃれ合ってみたり、また絡みつくかのような鬼気迫る凄まじいギターを聴くことが出来るのですが、
おそらくデュアンの一世一代のプレイを聴くだけでも、此のアルバムを買う価値は充分にあるのではないかと思います。素晴らしい!!
今回、久しぶりに『Boz Scaggs』(1969年)を聴き返してみて思ったことなのですが、ヒップでサイケなサンフランシスコに背を向け
たボズ・スキャッグスが、南部の地方都市であるマッスル・ショールズにて、心の底から土の匂いを楽しんでいる姿が目に浮かびます。
シーケンサーで打ち込まれた性急なビートに閉塞感を覚える現在の私にとって、このゆったりとした懐の深い音が味わい深く響くように、
目眩がしそうな程にヘロヘロなサウンドの中に身をおいてきたボズにとって、きっとロジャー・ホーキンスとデビッド・フッドの醸し出す
リズムは、それこそ豊かな大地に身を任せているような、心地よい開放感があったのではないでしょうか?
そもそも私が初めてボズ・スキャッグスを知ったのは、ずっと後年に発表された『Silk Degrees』(1976年)を、ほぼリアル・タイムで
聴いたのでありましたが、ジェフ・ポカロやデヴィッド・ペイチ等々、当時のLAを代表するスタジオ・ミュージシャン達が織りなす、都会
的で洗練されたそのサウンドには随分とショックを受けたものでした。そして暫くは『Silk Degrees』のような音を探しては聴き漁る毎日
だったのですが…或る日気がついたのです。「なんだか…どれもこれも金太郎飴みたいにシンガーの声以外は、サウンドは皆似たり寄った
りではないかい?」(笑)と、飽きるのも早かったような気がします。勿論『Silk Degrees』は素晴らしい名盤だと思いますが、このアル
バムの大ヒットを契機として、それこそ猫も杓子も都会的で口当たりの良い軟派?な路線に走り出したのではないかと思っています。
今回紹介した『Boz Scaggs』のアルバム・ジャケットの中で、ボズが嬉しそうな顔をしているのは、ひょっとしたら10セント硬貨を掴![]()
んでいるからではないだろうか?そして、その10セントでサンフランシスコに残してきた仲間達に電話をかけようと思ったのだ。
「マッスル・ショールズに来たのは大正解だったよ。此処の連中のおかげで漸く探していた音が見つかったんだ。最高だよ!」
 『Chicago Ś』Chicago
『Chicago Ś』Chicago今から思い起こせば、たしか私が無事中学2年生に進級した1972年の初夏だったように記憶しています。
どこまでも抜けるような青い空の下、同じクラスの仲間達と共に秘境を目指すサイクリングに出かけたのでありました。
そして、もう誰だったのか忘れてしまいましたが、自宅からラジカセを背中に背負ってきた奴が一人いて、彼は大音量でカセットテープ
から流れてくるサウンドに酔いしれながら、さも気持ちよさそうに(鼻歌を歌いながら)ペダルを漕いでいた姿が印象に残っています。
どこまでも果てしなく続くような、埃っぽい田舎道と抜けるような青い空…そして擦れ違う人々が吃驚する程の大音量で流れてきたのは
ビートルズやローリング・ストーンズ、スリー・ドッグ・ナイト等々のナンバーだったのですが、彼の御陰で御機嫌なサイクリングにな
ったものでしたっけ。やはり黙々と自転車を漕ぐよりも、バックで音楽が鳴っていた方が全然気持ちが良いに決まっているのだ。(笑)
そして長い道中、とうとう彼の手持ちのカセットが無くなり、仕方なくFMラジオに切り替えた途端、あのピアノのイントロに導かれて
流れてきたポップな曲が、シカゴの「サタディ・イン・ザ・パーク」だったのでありました。(-。-)y-゚゚゚
あの日から既に四半世紀近くもの歳月が経過しているし、この「サタディ・イン・ザ・パーク」にしても、今までに何百回聴いたか定か
ではないのですが、狭い自分の部屋で膝を抱えて聴くよりも、やはり広々とした大空の下で聴いた時の印象が今でも鮮烈に残っていて、
今回久しぶりに彼等のアルバムを聴き返した際にも、冒頭にお話しした大昔のサイクリングを思い出してしまう私だったりします。(笑)
さて今回紹介させて頂きますのは、あのシカゴが1972年に発表した、彼等の5枚目のアルバム『Chicago Ś』なのであります。
たしか、それまでに発表された彼等のアルバムは全て2枚組ないし4枚組!という、貧乏な中学生にとっては高嶺の花とでも云うべき存在
だったように記憶しているのですが、この『Chicago Ś』は堂々たる?シングル・アルバムとして世に出た最初の作品だったのではないか
と思っています。1967年のデビュー以来、彼等の最大のセールスポイントであったブラスサウンドは、どうも発表するアルバム毎に段々と
後ろの方へ引っ込んでいったような気がしないのでもないのですが、それと平行するように歌詞の内容も徐々に政治的なメッセージも影を
潜めていった結果、極端に長尺の曲や「いったい現実を把握している者はいるだろうか?」みたいな、やけに長い題名の曲もなかったりす
るし(笑)、何よりもポップで洗練された世界は、現在改めて聴き返してみても充分に楽しめるアルバムなのだと再発見しました。
しかし、未だバリバリの現役で活動している、シカゴの歴史を振り返ってみると、まるで一人の男性が成長していく過程を見ているような
気がするから不思議だ…。ベトナム戦争や人種問題等々、社会に対して痛烈なメッセージを声高に訴えていた学生時代、そして程なくして
それらは全て砂上に描いた共同幻想に過ぎなかったという現実に直面、就職して社会の枠組みの中に取り込まれる事に対する挫折感。
それから歳月が過ぎ、如何にしてビジネスの第一線で生き残って行けるかどうかという、猜疑心に苛まされる?中年にさしかかった現在…。
しかし今回紹介した5枚目などは、彼等がポップで洗練されたバンドとして、まさに油の乗りきった時代のアルバムなのではないかと思う![]()
のでありますが、今にして思えば彼等ほど、その時代特有の雰囲気に反応してきたバンドはいないのではないかと思っています。
 『Frampton Comes Alive!』Peter Frampton
『Frampton Comes Alive!』Peter Framptonたしか私が高校3年生の頃でしたっけ…、或る日突然ラジオから例のトーキングボックスを使ったギターのフレーズが
飛び込んできたのでありました。「むむむ!!ジェフ・ベックにしては随分とあっさりとしたフレーズだばい…ハテ?
これは一体誰が演奏しているのかしらん?」と胸騒ぎを覚えた記憶があります。♪ニョ〜♪ニョニョニョニョニョ〜♪(笑)
それから程なくして、それがピーター・フランプトンの「Show me The Way」なる曲で、彼の最新のライブ・アルバムに収録された曲
だっていう事が判明したのでありましたが、それからは毎日のようにラジオから♪ニョ〜♪ニョニョニョニョニョ〜♪が流れてきたので
ありました。いや〜本当に大ヒット曲とは、この曲の事を云うのでせうね〜。(-。-)y-゚゚゚
さて、今回紹介させて頂くアルバムは、ピーター・フランプトンの『Frampton Comes Alive!』(1976年)なのであります。
このアルバムはフランプトン及び彼のバンドが行った、1975年の春先から秋口までの全米ツァーを収録したライブ・アルバムなのですが、
当時としては驚異的な800万枚という空前の売り上げを記録したそうで(しかもLP2枚組だから実質的には1,600万枚!)後に1,000万枚
を売り上げたという、あのフリートウッドマックの『噂』(1977年)と共に70年代を代表する大ヒットアルバムなのであります。
しかし当時の私にとって「なんで此のアルバムが爆発的に売れるのだろうか?もっと格好良いアルバムだって沢山あるのに…。」というのが
正直な気持ちだったのですが、改めて久方ぶりに聴きかえしてみれば無茶苦茶良かったりするのだから…まったく不思議ですよね…。(^^ゞ
ま、当時の私は(どちらかと云えば)ハードにドライビングするギタリストが好みだったので(あまりギタリストとしてのエゴを感じさせな
い)フランプトンのプレイには、若干物足りないモノを感じていたというのが嘘偽りのない正直な気持ちだったりします。
なにしろギタリスト至上主義だった?高校生にとっては、全体のサウンドよりも先ずギターが全てだったのでした。…そう、まるで木を見て
森を見ず…。もしくは女性を見ても人柄よりもスリーサイズに気をとられるような若造だったのだにゃ…。(笑)
ところでピーター・フランプトンというと、咄嗟に私が思い浮かべるのが例のギター(3ピックアップの黒いレスポール・カスタム)なの
ですが、彼がソロとして出発する迄に参加していたハンブルパイの時代から使用しているらしく、このレスポールを弾いている映像を何処か
で拝見した記憶があります。もともとジャンゴ・ラインハルトに一番の影響を受けたという彼らしく、とてもクリアーで抑制の効いたプレイ
は当時から彼の持ち味だったのでせうが、それにヴォーカリストとしても、その端正なルックスとは裏腹に?エモーショナルな歌いっぷりも
素晴らしいと思います。このアルバムにおいても静と動、アコースティックとエレクトリックなナンバーを絶妙に配置して、まさに聴いてい
る内に自分自身がコンサート会場に居合わせているような気持ちになってくるのですから、まさに名盤なのではないかと思います。
因みにプロデュース及びアレンジは、当のフランプトン自身が手がけておりまして、彼のヴォーカル&ギター、ドラムスにジョン・サイモス、
ギター&キーボードがボブ・メイヨー、ベースがスタンリー・シェルドンという少数精鋭4名からなる演奏は、些かの弛みもなくタイトで、
しかも岩のようにタフでありながら、ガラス細工の如くデリケートという絶妙な演奏を聴かせてくれています。
のっけから「とうとう俺の時代がやって来たんだ」と、フランプトンが力強く宣言するかのような1曲目「Something's Happening」で
幕が開き「Doobie Wah!」「Show Me The Way」…と、ほぼ全編に渡り、ひたむきで前向きなメッセージを切々と歌う彼にシンパシーを
感じるのは私だけではないと思います。ステージが進行するにつれて、フランプトンの体が徐々に火照ってくるのが、ステレオの前に座って
いる私にも充分に伝わってきますし、会場に居合わせたオーディエンスとのコール&レスポンスも濃密な関係を実現しているという意味で、![]()
まさに究極のライブ・アルバムの筆頭に数え上げられる作品なのではないでしょうか?
そして何故かこの名盤を聴いている内に、私の脳裏に浮かぶ言葉があるのですが…名言です。「念ずれば花開く…。」m(__)m
 『Gumbo』Dr.John
『Gumbo』Dr.Johnルイジアナ州ニューオリンズと聞いて、まず咄嗟に私の脳裏に思い浮かぶ亜米利加映画が二つほど有ります。
先ずはマーロン・ブランド、ヴィヴィアン・リーが出演した、テネシー・ウィリアムス原作の「欲望という名の電車」、
そしてミッキー・ローク、ロバート・デ・ニーロが共演した「エンゼル・ハート」なのでありますが、どちらもスクリーンをとおして
ミシシッピー川河口に位置するという、ニューオリンズのじっとりと湿度の高そうな気候風土が、観ている此方側に伝わってくるような
作品だったように記憶しています。特に後者の「エンゼル・ハート」では、彼の地に古くより伝わる密教であるブードゥー教をイメージ
させる怪しげで官能的な場面が大変印象的だったのでありました。かつてはフランス領だった土地柄なのでしょうか、前世紀末に大流行
したというアールデコ風の建築物や調度品がしっくりと似合う異国情緒漂う佇まいは、いつか私も訪れてみたい町の筆頭だったりします。
さて…ってな訳で今回は、彼の地が生んだ御大ドクター・ジョンの『Gumbo』(1972年)を紹介させて頂きたいと思います。
たしか聞いた話によれば“ガンボ”というのは、豆や肉類等を時間をかけてグツグツと煮込んで作る、ニューオリンズでは比較的庶民的
な料理なのだそうですが、この『Gumbo』で聴ける人なつっこい温かなサウンドは、彼が幼い頃からどっぷりと親しんできたに違いない、
まさに本場ニューオーリンズR&Bのスタンダードを“ガンボ”したアルバムなのであります。(o^^o)
たしか私がドクター・ジョンの名前を知ったのは、あの細野晴臣氏が20年ほど昔に発表していた、一連のニューオリンズ風の作品がキッ
カケだったように思うのですが、この『Gumbo』を聴いた際に、改めて元ネタに触れた気がして感動した記憶があります。
のっけから彼の(コロコロと鍵盤上を転がって行くかのような)ピアノと塩辛い歌声が大変に印象的な「IKO IKO」(アイコ・アイコ)
から始まるのですが、ラスト「Little Liza Jane」迄の12曲全てが、柔軟でズブズブと腰まで浸かるようなニューオーリンズ・ファンク
の御機嫌なグルーヴで一杯の素晴らしい名盤であります。そしてアルバム全体をとおして、“ゆったりとしたしゃっくり”が幾つも複合的
に重なったような(笑)独特のノリが心地良いのですが、これが所謂ニューオリンズ原産のセカンドラインと呼ばれるリズムだそうです。
もともとドクター・ジョンという名前は、ブードゥー教史上に実在する伝説的な人物の名前だったらしいのですが、60年代になって西海岸
に流れ着いた彼が、サイケデリックな彩色を施して『Gris Gris』(1968年)で(不本意ながら?)演じたキャラクターでもあり、折しも
70年代初頭に英米を中心に巻き起こったという“亜米利加南部音楽探検症候群”の追い風に乗って、漸く彼や、彼の周辺にも『Gumbo』
を発表できる環境が整ったのでしょう。そして、それまで自分の血となり肉と化した故郷のスタンダードを改めてレコーディングする際に、
ドクター・ジョンを演じてきた所の本名マック・レベナックの胸には、果たして一体どのような思いが去来したのだろうか?![]()
「まさか…こんなローカルな音楽が商売になるってか?ま、エキセントリックなブードゥー教の祠祭よりも全然楽しいけんどもさ。」
「これから俺の演奏する音楽は“More Gumbo less Gris Gris”と呼んで貰ってもかまわないっす。」
故郷ニューオリンズから遠く離れたLAの地にて、改めて自分の足元に存在する豊穣な音楽に驚いたのは他ならぬ彼自身だったように思います。
 『Teaser』Tommy Bolin
『Teaser』Tommy Bolinたしか私が高校二年生になろうかという春先の事だったかと記憶しているのですが、たまたま立ち寄った友人の家で
「ディープ・パープルからリッチー・ブラックモアが脱退!」という衝撃的ニュースを小耳に挟んだのでありました。
「むむむ!!!リッチーが脱退ってか?するっていうと…やはりパープルは解散を余儀なくされるのか?そ、それとも彼以上の強力
なギタリストを参加させるのか?何れにしても半端な奴では務まらないだろうな。」と、事の重大さに衝撃を受けた記憶があります。
そして数ヶ月後、新メンバーにトミー・ボーリンなるギタリストを迎えて発表された『Come Taste The Band』を聴いたときの驚き
は並大抵のものではなかったような気がするのだ。「おおっ!これは随分とメリケンっぽいサウンドになったもんだ!」と、戸惑い
半分、(今後への)期待感半分というのが正直な気持ちだったように思います。どちらかといえばエゴを剥き出しにしてバリバリと弾
きまくっていたようなリッチーと比較すれば、新ギタリストのトミー・ボーリンはソロイストというよりも、全体のサウンドを一歩引
いた場所から支配しているかのようなプレイをしていたような気がしますが、彼を迎え入れた他のメンバー達の思惑も、何となくです
が理解出来るような気がしました。しかし怒濤のハードロック・バンドだった時代からの信者達は、諸手を挙げて彼等を迎え入れる事が
出来なかったのでしょう…『Come Taste The Band』は、大した評価もされず、程なくしてバンドも(第一期)解散になってしまったので
ありました。しかし…彼の参加したパープルの次作を聴いてみたかった気がするな…。
さて、今回改めて紹介させて頂きますのは、そのトミー・ボーリンが1975年に発表した『Teaser』なのであります。
実は、この『Teaser』がレコーディングされたのは、彼がディープ・パープルに参加する前なのでありますが、既にビリー・コブハムの
『Spectrum』(1973年)や、ジェームズ・ギャングの『Bang』(1973年),『Miami』(1974年)を通して、彼の実力は周囲のミュージシャン
達も充分に認めていたのでしょう、ジェフ・ポーカロ、デビッド・フォスター、フィル・コリンズ、ヤン・ハマー等々、今から考えて
みれば夢のようなミュージシャンが大勢このアルバムに参加しています。そしてアルバムに収録されている全9曲が、大変バラエティに
富んでいて、現在聴いてみても彼の懐の深さと確かなテクニックに裏打ちされたプレイには感嘆させられます。そして決して上手いとは
言えないものの、甘ったれたように絞り出すかのようなトミーのヴォーカルも味わい深いものがあります。
1曲目の「The Grind」で聴かれる御機嫌なスライド・プレイ、2曲目「Homeward Strut」のファンキーなインストルメンタル、3曲
目のしっとりとしたバラード「Dreamer」、ジャージィなオクターブ奏法が見事なボサノバ風の4曲目「Sanvannah Woman」…等々。
この『Teaser』を聴いた後で、ディープ・パープルの『Come Taste The Band』を聴けば、彼のスタイルは既に此のアルバムで確立さ
れているということに気がつくのではないでしょうか。次作『Private Eyes』(1976年)も良いのですが、収録された楽曲の良さという
点では断然此方のアルバムの方が好きです。何れにしても当時24才の前途洋々たる若きギタリストの底知れぬ可能性を感じさせる名盤だと
思います。しかし…彼自身のバンドTommy Bolin Bandで活動をしていた1976年の暮れに、突然の(ドラッグによる)死亡ニュースには
吃驚しました。享年25才、まだまだ彼の素晴らしいプレイを聴かいてみたかったのですが、きっと今頃は天国でジミヘンとジャム・セッシ![]()
ョンでもして楽しんでいるのかも知れないにゃ…。<合掌>
 『Steve Winwood』Steve Winwood
『Steve Winwood』Steve Winwood「才能が有れば世の中は甘い。」という言葉を某有名ミュージシャンのインタビュー記事で拝見した事があります。
成る程…。そう云われてみれば、プロ野球界に於けるオリックスのイチロー選手などの活躍をテレビ等で見ている限
りは、いかにもその天性の才能をフルに活かして伸び伸びと楽しんでいるかのように思えるから不思議なのであります。
しかし悲しいかな…野球では遙か大昔の中学時代に自身の限界を悟り、その後ギターを弾き始めたものの大して上手くなる事もなく
立派なオッサンになってしまった私などにとって、自身の才能をフルに発揮して頑張っている人達を見るにつけ、心の底より羨望の
眼差しで彼等の一挙手一投足に注目したりする次第なのであります。(o^^o)
これから紹介するスティーブ・ウィンウッドなどは、有り余る才能で十代の頃より世間から天才少年と賞賛されてきたミュージシャン
なのですが、彼のソウルフルな歌と洗練されたキーボードやギターのプレイぶりを聴いていると、つくづく天性の才能っていうのは
彼みたいな人を指す言葉なのかなと思う程に、類い希な実力を伴った素晴らしいミュージシャンだと思います。
たしか私が彼の名前を始めて知ったのは、トラフックでもスペンサー・デイヴィス・グループでもなくて、ましてやGOでもなく
、アルバムジャケットが衝撃的だったブラインド・フェイスや、あのエリック・クラプトンのレインボー・コンサートのレコード
を通じてだったように記憶しているのですが、特にブラインド・フェイスに於けるウィンウッドには目を見張るような存在感があり
ました。クラプトンのギターを目当てに聴いたはずだったのですが、結果的には彼の歌の素晴らしさを知ったアルバムでしたっけ。
さて今回紹介させて頂きますのは、そのスティーブ・ウィンウッドが1977年に発表した初のソロアルバム『Steve Winwood』
なのであります。折しも西暦1977年というと、たしかその頃世間では所謂ディスコ・ブームなるものが一世を風靡していまして、
片やアメリカンドリームの終焉を歌ったイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」が大ヒットしていて、尚かつセックスピストルズ
を始めとしたパンクムーブメントの足音がヒタヒタと迫り来る時代だったように記憶しています。(-。-)y-゚゚゚
その頃の私は既にスタイリッシュでインテリジェンスな?ブリティッシュ・ロックを聴かなくなりつつあった頃だったのですが、
ウィンウッドのこのアルバムに参加している、西海岸を代表する名うてのリズムセクションであるアンディ・ニューマーク(Drums)
とウィリー・ウィークス(Bass)の名前を小耳に挟んで、思わず速攻で買い求めたというのが真相だったりするのでした。(笑)
しかし流石にウィンウッドの歌を聴いていると、ブリティッシュもアメリカンもピンクレディも(笑)比較するのが馬鹿らしくなって
しまうくらい、歌心に溢れた彼の声とその圧倒的なクォリティの高いサウンドに感動してしまう私なのであります。
1曲目の「Hold On」などで聴かれるサウンドは、現在聴いてみても全然古さを感じさせないし、続く「Time is Running Out」で
聴ける、彼の弾くエレクトリック・ピアノのツボを心得た広がりを感じさせるコードワークといい、地味ながらもセンスの良いギター
のフレーズはさすがだと思いますし、ウィンウッドがそれこそ隅々までサウンドメークに神経を使っているのが分かります。![]()
そしてラストの「Let me make something in your life」を聴くと、未だに泣けてしまう私は善人なのかしらん?(笑)
この『Steve Winwood』があったからこそ、後に大ヒットを記録した『Back in The High Life』に繋がっていくような
気がします。ウィンウッドの音楽に対する熱い思いが満ち溢れている名盤です、皆様も心して聴いて頂けたらと思います。m(__)m
 『Sailor』The Steve Miller
Band
『Sailor』The Steve Miller
Band随分前に亜米利加西海岸を旅した事があります。ロス〜アナハイム〜ラスベガス〜サンフランシスコ〜ハワイ
という日程で訪れた訳なのですが、なかでも自分にとって一番に印象的だったのがシスコでありました。
サンフランシスコは起伏に富んだ町であります。あのスティーブ・マックィーン主演の映画「ブリット」にも見られるように、
急勾配の坂がやたらと多いので、乱暴に車の運転をした日には足周りを壊すのは必至な事は確かですので御注意下さい。(笑)
しかし坂の上から一直線にフルスピードで駆け下りたら、ひょっとしてそのまま上昇気流に乗って遙か彼方まで飛んで行けそうな
錯覚に陥りそうな気がしてくるから不思議なのですが、兎にも角にも私にとっては再び訪れてみたい町の筆頭だったりします。
今回紹介させて頂くのはシスコと云うよりも、今やアメリカ全土に於いてもメジャーなバンドであるスティーブ・ミラー・バンド
が、1968年に発表した彼等のセカンド・アルバム『Sailor』であります。(o^^o)
人呼んで、“スペースカウボーイ”の異名を持つスティーブ・ミラーなのですが、彼は5歳の頃にレス・ポールからギターを貰っ
た上に手ほどきまで受け、その後シカゴでブルース漬けの日々を送っていた時代には、あのTボーン・ウォーカーに師事していた
そうで、まさに骨の髄までブルース・ミュージックに首まで浸かっていたのではないかと思います。
しかし何の因果か1966年、当時は文字通りに花盛りの真っ直中だったサンフランシスコに、その活動の拠点を移した彼が結成した
バンドなのでありますが、因みに参加メンバーは、前作『Children of The Future』(1967)の時と同じでスティーブ・ミラー
(g,v)ボズ・スキャッグス(g,v)、ジム・ピーターマン(key)、ロニー・ターナー(b)、ティム・デイビス(dr)の5人から
構成される、いわゆるスティーブ・ミラーの第一期黄金時代とでも呼べる時代だと思います。
彼等と同時期に、彼の地サンフランシスコで活躍したジェファーソン・エアプレインやグレートフルデッド、QMS等の他のバンド
と比べてみた場合、スティーブ・ミラー・バンドは、当時のトレンドであったサイケデリックやヒッピーと云った風潮に対して否定
的なスタンスを取っていた数少ないバンドなのではないかと思うのですが、自身のルーツをしっかりと見据えていたように思います。
このアルバムから唯一シングルカットされて、現在でも彼等の重要なレパートリーになっている「Living in The USA」は、当時の
“皆でラリれば何でも有り”状態を痛烈に皮肉っているような曲なのですが、当時のシスコでは異端だったのではないでしょうか。
それに後年になって、AORのシンボル的な存在になるボズ・スキャッグスが、未だシスコの顔役(笑)と呼ばれる前の初々しい熱唱
も、3曲目「My Friends」とラスト「Dime-a-Dance Romance」の2曲で聴くことが出来ます。(o^^o)
きっと誰でもまだ小さな子供の頃に抱いた夢に、大空を自由自在に舞う事への憧れって有ったのではないかと思うのですが、彼等の
音を聴いていると、大空高く飛翔することへの強い思いを感じ取れるような気がします。それこそ![]() 鷲のよう空高く…。
鷲のよう空高く…。
しかし、シスコの坂道を全速力で駆け下りては駄目ですよん。飛翔どころかクラッシュ・ランディングしてしまいます。(笑)

今から思い起こしてみても一時期、T-REXの人気っていうのは凄いモノがあったように思うのであります。
何しろ当時は、彼等の曲がラジオから流れない日など無い程の大人気で、ビートルズ以外はまったく眼中に無か
った私でも、彼等の一連のヒット曲である「ゲット・イット・オン」や「メタル・グルー」「テレグラム・サム」などは、嫌でも
耳にこびりついてしまうほどの猛威を振るっていたのですが、グラム・ロックという言葉を知ったのもその頃だったのでした。
当時は未だ紅顔の美中学生?だった私にとって、T-REX…というよりもマーク・ボランの縮緬のような独特のヴィブラートが大変
にゾクゾクするほどに印象的でありまして、よく仲間内で喉ぼとけの辺りを指で振るわせながら「♪ゲリロ〜ン♪ゲリロ〜ン♪」
と「ボランごっこ」をして遊んでいた無邪気な子供を一人知っております。ははは…。(^^;)
その後、私が高校受験を迎える頃になると、さすがに一時期のグラム・ロック・ブームも落ち着いてきたようで、私も受験勉強に
集中する事が出来まして(笑)、御陰様で無事に大宮市内の某市立高校に入学の運びとなりました。(o^^o)
そして丁度そんな時期に、再び彼等の曲がラジオから流れてきたのでありましたが、中学生から高校生へとなり慌ただしい環境の
変化に戸惑っていた私にとって非常にしっくりときたのが、「ティーンエイジ・ドリーム」だったのでした。(-。-)y-゚゚゚
そして、その「ティーンエイジ・ドリーム」を聴きたいが為に近所のレコード屋さんで彼等の新譜を買い求めたのでありました。
…ってな訳で今回紹介させていただくのは、そのT-REXが1974年の春に発表したアルバムなのでありますが、そのタイトルは
『Zinc Alloy & a Hidden Riders Of Tomorrow/A Creamed Cage in August』とやけに長いのであります。
因みに邦題は、“ズィンク・アロイと朝焼けの仮面ライダー、または8月のクリーム状の鳥籠”と混乱するようなタイトルだった
りするのですが、なんでもマーク・ボランが前年に来日した際に、たまたまホテルのテレビで「仮面ライダー」を見てインスピレ
ーションを受けて付けたと(当時のライナーに依れば)聞いておりますが、このアルバム・ジャケット写真での彼は殆どスッピン
で、それまでの派手なイメージとはガラッと変わり、逞しいが妖しげなボランと云った印象があります。
なんでも当時のボランは、それまでにマスコミ等からつけられた「グラム・ロックの貴公子」などというレッテルを葬り、それと
同時にグラム・ロックの幕引きを念頭に置いていたそうで、本当はT-REX及びマーク・ボランという名前を使わずに発表しようと
したらしいのですが、色々な事情があったようで上記のタイトルに落ち着いてしまったそうなのでありました。
このアルバムから唯一シングルカットされた「ティーンエイジ・ドリーム」を久方ぶりに聴いてみたのですが、やはり大昔に夢中
になって聴き狂った時にタイム・スリップしてしまうくらいに素晴らしい名曲だと思います。あのトニー・ヴィスコンティによる
ストリング・アレンジが悲しい程に美しくて、ボランの曲には欠かせないプロデューサー、アレンジャーだと思います。そして、
何て表現したら良いのだろうか…ボランのヴォーカルの不思議なところなのですが、あの独特のヴィブラートとセクシーな溜息は
本当に唯一無比の、それこそグラマラス・ヴォーカルだったのではないでしょうか…。それに、これまでにあまり語られる事の無![]()
かった彼の書く非常に感覚的な歌詞の世界も、改めてじっくりと読んでみれば素晴らしいと実感しております。