物語の発端と継之助のよりどころ:
時は安政5年、井伊直弼が大老に就任、幕権回復のためいわゆる安政の大獄といわれる思想弾圧が開始する。そういう時、河井継之助は、藩はどうあるべきか、侍はいかに生くべきかを考え、藩外に出たい旨申し出、許され江戸出府と諸国遊歴を許される。
継之助は王陽明を敬慕し、知識と行動は一つでならないとする一見激越な思想を持つ。
この男の知的宗旨である陽明学の学識のせいか、つねに他人を無視し、自分の心をのみ対話の相手にえらぶ。 たとえば陽明学にあっては、山中の賊は破りやすく、心中の賊はやぶりがたし、という。
難路がある。これも、継之助の思考方法から見れば山中の賊であろう。 継之助は、難路そのものよりも、難路から反応した自分の心の動揺を観察し、それをさらにしずめ、静まったところで心の命令を聞く。(その心を、仕立てあげにゆくのが、おれの諸国遊歴の目的である)
印象に残る場面:
◇継之助が官軍の岩村軍艦と会見した小千谷慈眼寺(じげんじ)での場面
それまでにとってきた継之助の作戦(最新の兵器を集めて武装独立しつつ、官軍派でもなく、会津派でもなく、ないばかりか、その両者の調停役たらんとする。)で会談に臨んだが、会談に至る前の状況は非常に好ましい状態であったが、直前になって会談を邪魔する事態が生じ、雰囲気は一気に反転してしまう。 しかも、24歳という若い軍艦との折衝で決裂、ついに長岡藩を上げて決起せざるを得なくなってゆく。
そのあたりは物語の頂点に当たり、継之助の心情が読者に突き刺さってくる。 選択は継之助の生きる哲学(武士の美学)が決起を決意させる。
 
◇慈眼寺山門 ◇会見の間
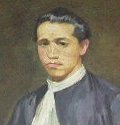 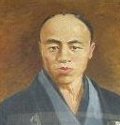 ◇岩村軍艦と河井継之助総督 ◇岩村軍艦と河井継之助総督
(慈眼寺のホームページ他より)
|