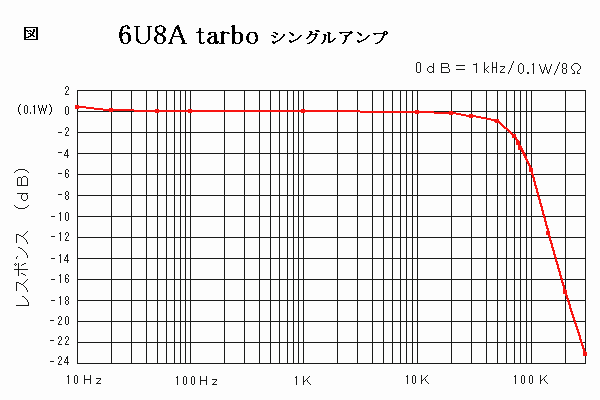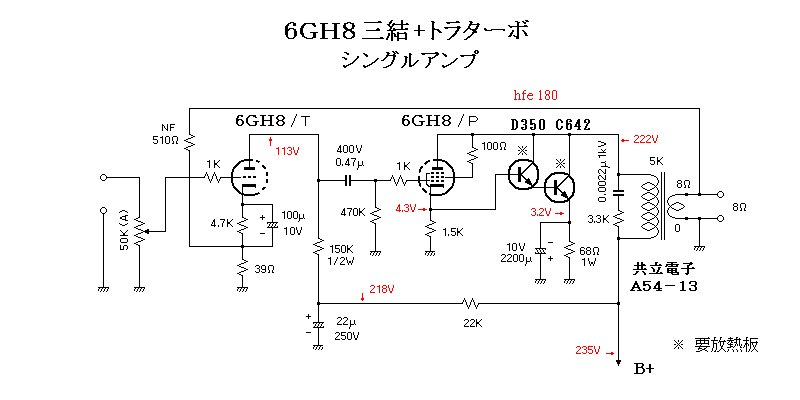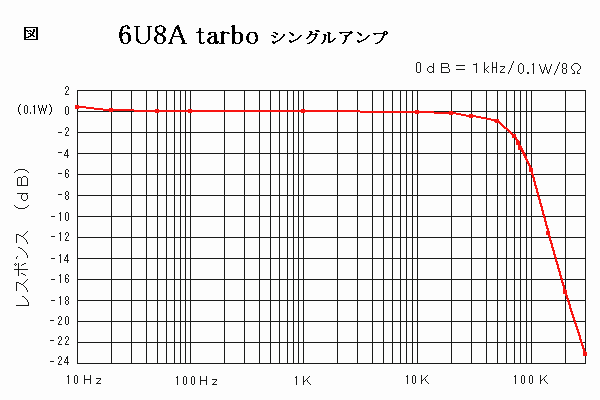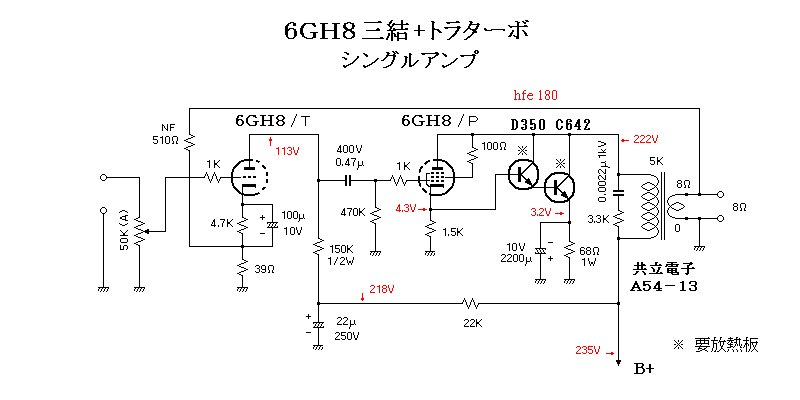今回のトラターボアンプの試作では、当初は高域特性は諦めていました。上記で述べたように出力トラン
ジスターの保護の為には、高域を犠牲にするしかなかったからです。それでもここまで伸ばせれば、実用上
は必要十分な高域特性を確保出来たように思います。
後 記
この試作機をモノアンプ状態で聴いているのですが音的にも悪くは無いのです。当初はステレオ化を見据
えて部品の選別をしたのですが、内心では特性的に広帯域は望めずバラック実験で終わるように思っていま
した。しかしこの特性なら、試聴会に持ち込んでも皆さんの試聴に耐えられるのではないかと思うので、今
は本製作に傾いています。ただ本製作となると、10Wものコレクタ損失になるトランジスターの放熱板も
しっかり確保しなければならず、(試作機では薄いアルミ板に貼り付けましたが、長時間動作の後はアルミ
板に触れないほど高温になってました。)そうなると結構面倒な組み立て作業になるので、この夏は思案し
ながら過ごす夏になりそうです。
ドライブ管を
6GH8
に変更
些細な事ですが、上記tarbo試作アンプのノンクリップ出力が2.5Wとなると、どうせなら3Wの
出力にしたいと思ってしまいます。電源電圧を上げれば簡単ですが、先に述べた理由で電源電圧は上げたく
ないので、他の方法を考えてみました。このシングルアンプで3Wの出力というのは、他章でも述べている
ように汎用アンプとしての条件の一つと思うのです。もっとも実際は2.5Wでも大して変わらないのですが
本機は試作機なので、思い付いた事は「何でも試してみよう精神」で小改造してみました。
既に述べたように、上記の試作機は計算上の出力が得られなかったのですが、どうもドライブ段が上手く
動作していないのではないか?と推測してみました。つまり、ドライブ段の負荷もパワー段と同じ5kΩの
負荷なので、三結時にrpの高い球だと負荷が低すぎて動作が制限されてしまうので、ここをrpの低いド
ライブ管に変更すれば出力が増えるのではないかと考えました。それでも、このドライブ管を出力管にした
のではトラターボの特徴が薄れてしまうので(オリジナル回路では6BM8を使っていましたが、6BM8
なら単体でも3W程度の出力は得られる。)あくまで電圧増幅管の中から、三結時にrpの低そうな球を探
してみたところ、6GH8が良さそうでした。
という事で、ドライブ管を6GH8に変更し、それに伴ってカソード抵抗値とエミッタ抵抗値を変更して
以下の回路となりました。
|