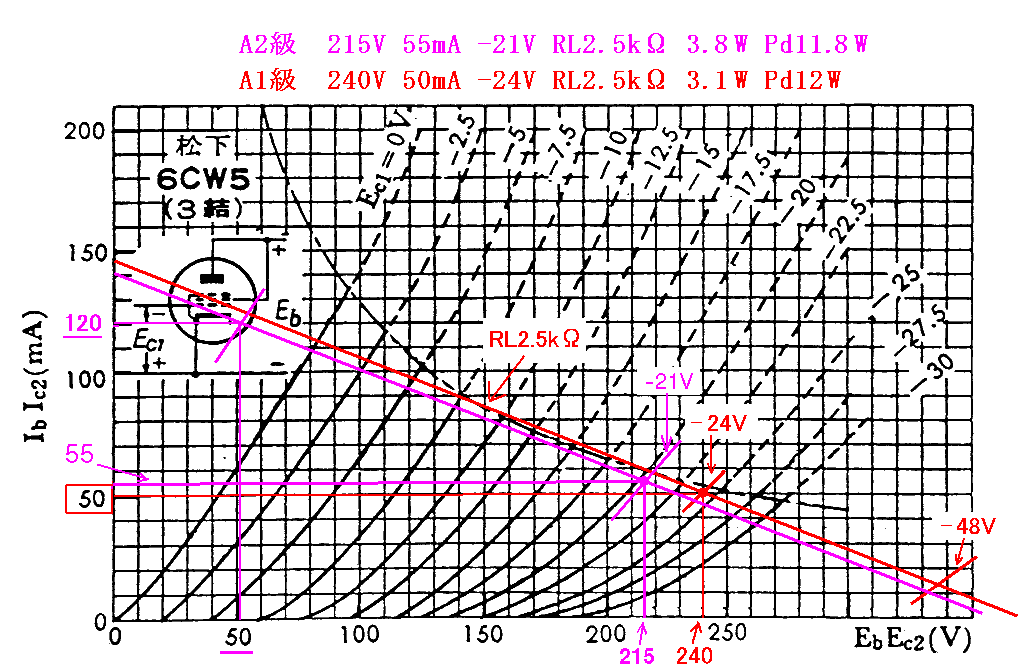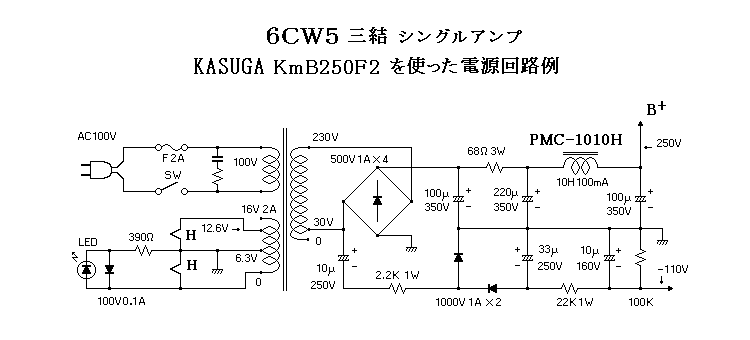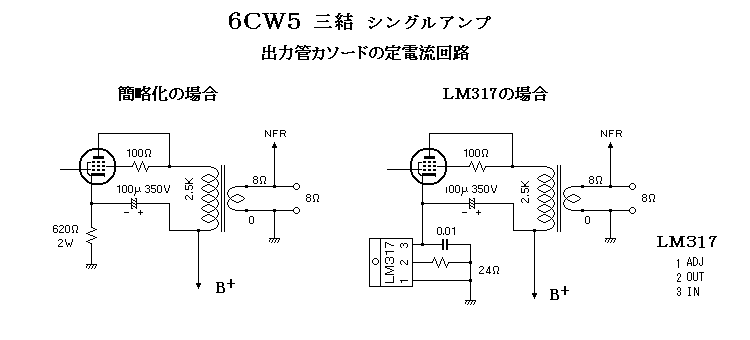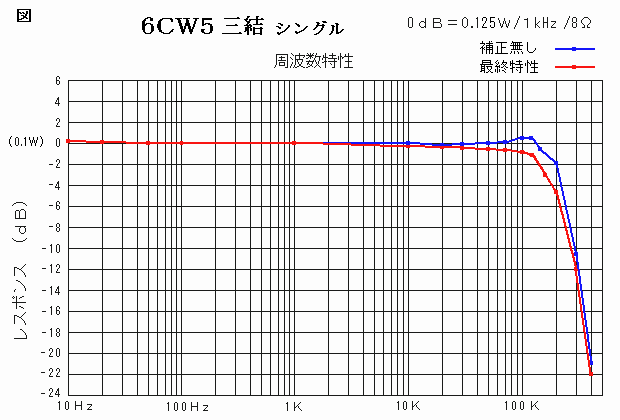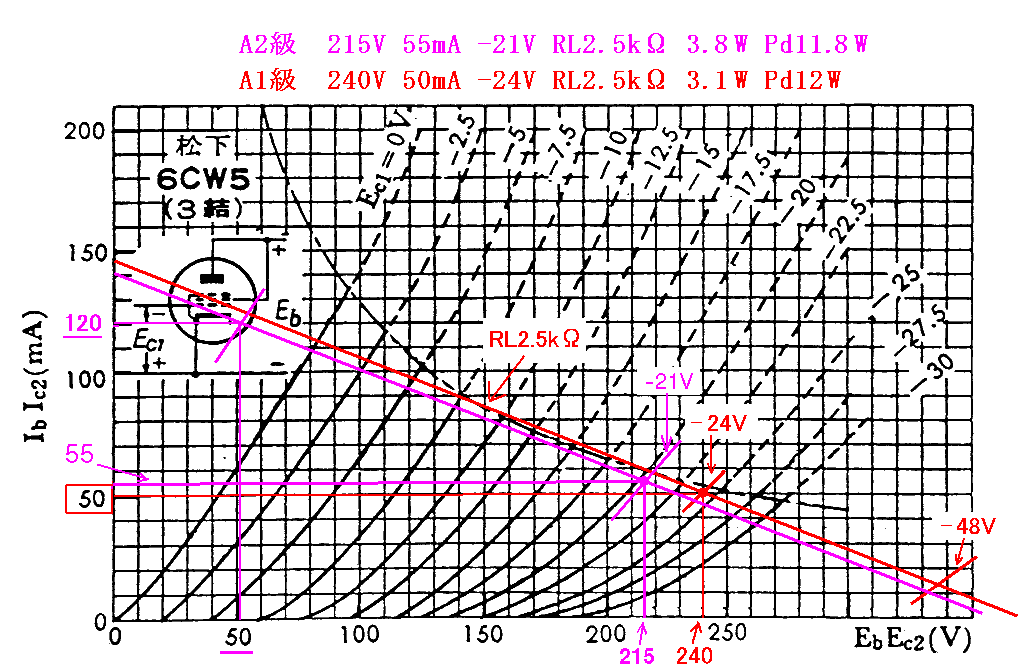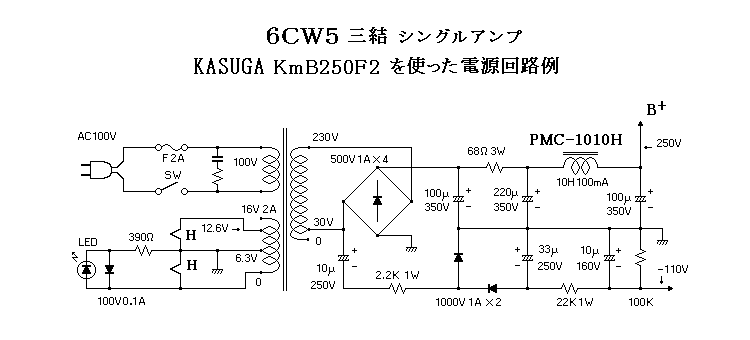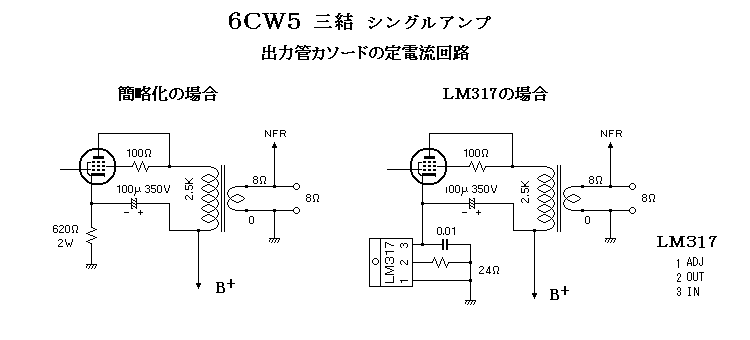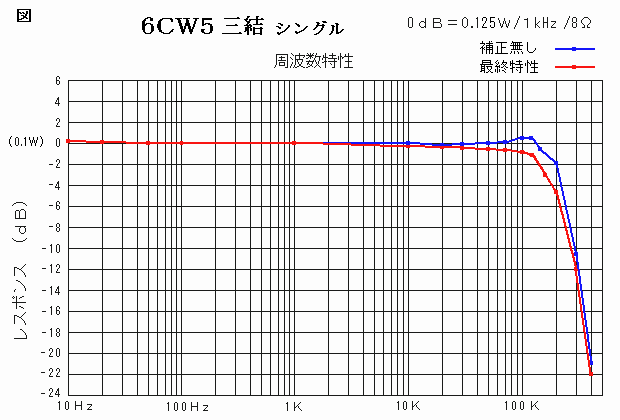前回6CW5を採用しなかったのは、市販品に適合する仕様のOPTが無かった為で、最大プレート電圧
が低く内部抵抗の低い6CW5を、例えばRL5kΩとかで使ったら、3Wの出力はとても得られそうにあ
りません。しかし今回のアンプでMT三極管による出力3Wのアンプが実現出来たら、あの6R−A8の再
来になると考えていたので、ダメ元でARITOさんに相談してみたところ、新規に1次側インピーダンス
2.5kΩのOPTを巻いて頂ける事になり、これで、ようやくMT三極管による出力3Wのアンプが実現
出来る運びとなりました。
6CW5三結のグラフにRL2.5kΩロードラインを引いてみたところ、計算上では3Wの出力が得られ
そうですが、実際にはロスなどで1割程度は減るものなので、このままでは出力3Wを下回ってしまいそう
です。そこでA1級での動作は諦めて、A2級の動作点で計算して見たら4W近く得られそうなので、これ
なら1割のロスを差し引いても3W以上の出力が確保出来そうです。
|