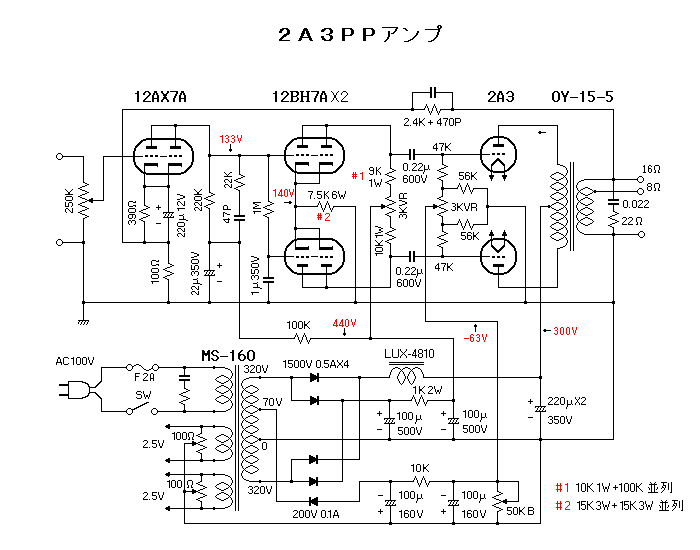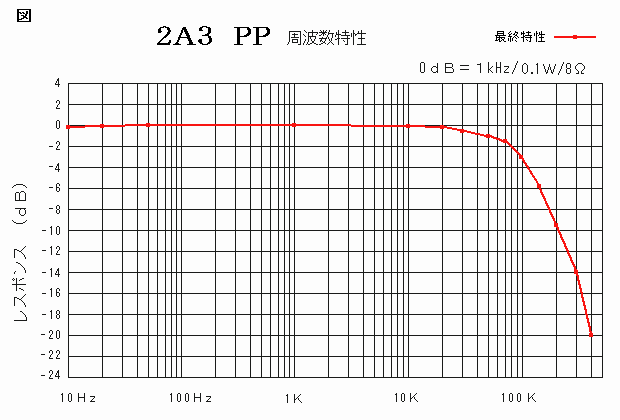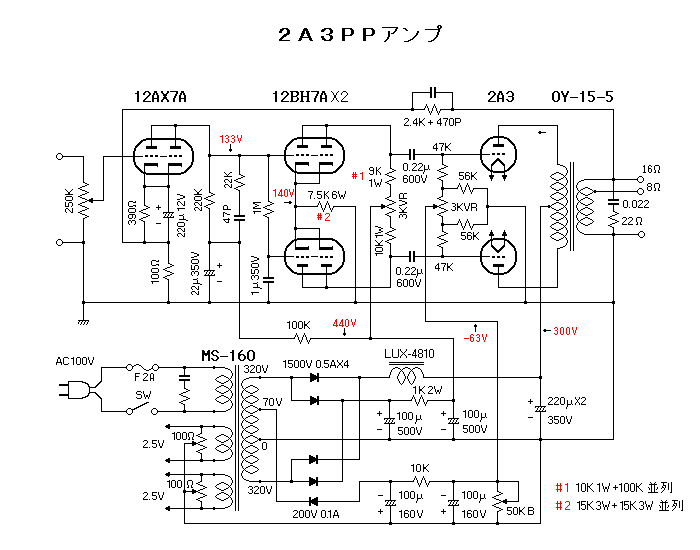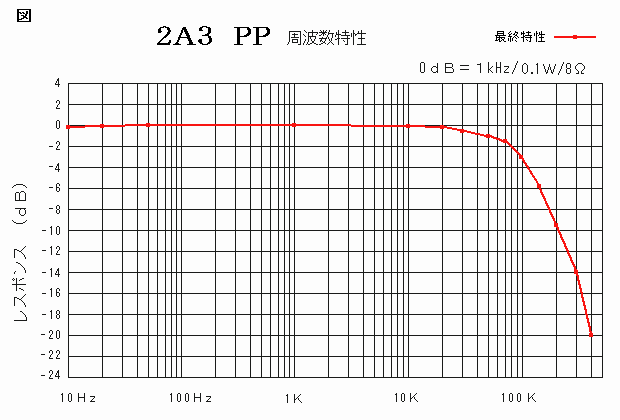この球の製作例はいくつかあったのですが、自分流のアンプを作りたいと思いマニュアルを見てみると
励振電圧が 90V近くも必要なことが分かり、なんて扱い難い球なのだろうと思いながら、いくつかの回路
図を握りしめたまま数年を過ごしていました。
そんな時、武末数馬先生が"ラジオ技術 "誌1970/1月号に発表した2A3PPアンプの記事を数年たって
から目にして、「コレだ!!」と思ったのでした。
それまでの2A3アンプの回路は、電源電圧を2A3に合わせていた為、ドライブ段はそれより低い電
圧で動作させる事となり、90V 近いドライブ電圧を生み出すのには、とうてい無理がありました。そこで
回路図にあるようにチョークインプット整流とコンデンサーインプット整流を併用して、一つの巻き線か
ら2A3用の低電圧とドライブ段用の400Vを超える高電圧をとりだし、2A3をフルスイングさせるとい
うものでした。さらに初段に可変のPG負帰還をかけて全体の利得が変化しないようにしながら、オー
バーオールの負帰還量を切り替えて、低NFの音や無帰還の音が楽しめる、というようなものでした。こ
の回路が発表された時は、まだNFアンプが主流だったのですが、先生はすでにその先のアンプを見据え
ていたのかも知れません。私が製作を始めた頃には、多くの諸先輩が「高NFアンプは音がつまらない」
とか言っていたのですが、簡略化のために低NFでいくことにし、初段を三極管に変更して利得を合わせ
ました。
と言うことで以下のようになりました。自分流なんて背伸びしていたのですが、初段以外は武末先生の
発表された回路に沿っていますので、亜流武末アンプと言ったところでしょう。
|