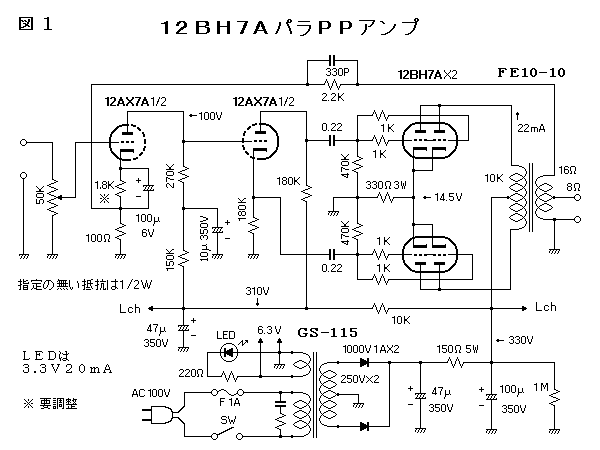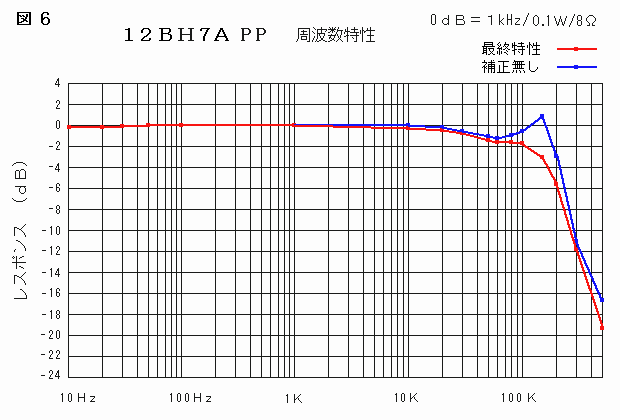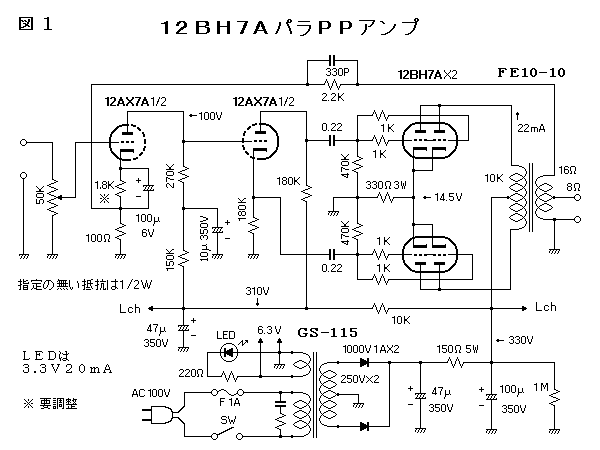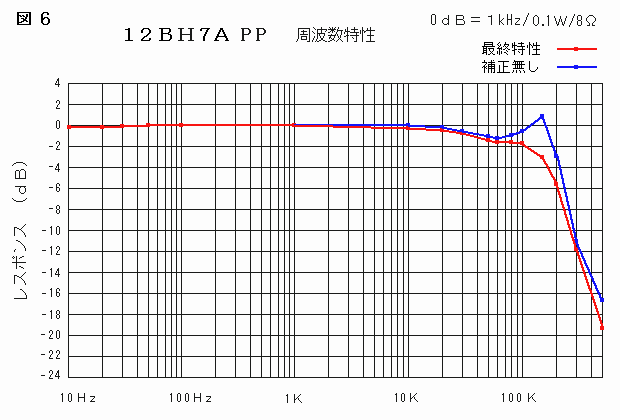|
前章、前々章とシングルアンプを紹介し
たのですが、手軽なはずのシングル方式も
特性を上げようとすると、直結ドライブに
したり、局部帰還を併用したマルチループ
NFにしたりと、なかなか手軽な方式とは
言えなくなってしまいます。
また良好な低域特性を確保しようとする
と、高価な大型出力トランスを使わざる得
ないので、結果的に同出力のプッシュプル
|
(以下PP)アンプよりも高価になってしまいます。一方のPP方式は、球の数や部品点数が多くな
るので最低の予算でとはいきませんが、小型の出力トランスでも割と平坦な特性が得られ、一般的に
同予算ならばPP方式の方が良い結果が得られるようです。
そこで本章では三極管による5W程度の、手軽に作れるPPアンプを紹介したいと思います。どう
して5Wなのかというと、三極管の場合10Wクラスのセットになると使える球の種類も限られ、と
たんに予算が跳ね上がるので5W程度に抑えました。このクラスの球で一般的なのは6BQ5や6V
6等の三結動作ですが、今回は変わったところで手持ちもあった12BH7Aにしました。この球は
オーディオアンプでは電圧増幅用としてドライブ段などに使われることが多いのですが、本来はテレ
ビの垂直発振用の球で、見かけによらず馬力のある球です。また双三極管の両ユニットをパラにする
とちょうど5W程度の出力が得られます。さらに電圧増幅用としては低ミューですが、出力管として
なら高感度な方なので、ドライブ段など前段は12AX7A一本で十分にドライブ出来ます。という
事で以下のような回路になりました。住宅密集地に住む私には5Wでも十分で、電気代も気にせずに
すむので気軽に鳴らしています。
|
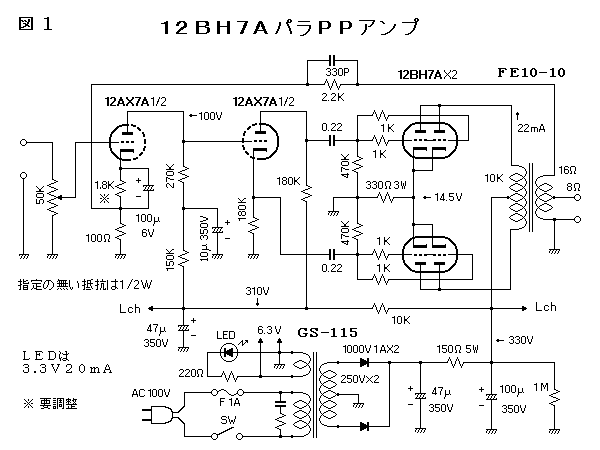
製作のポイントとしては
1.本機は書籍に掲載する為に体裁を考えて角型ケース入りのOPTを使ったのですが、少出力です
から東栄や春日の廉価なOPTでも問題ありません。ただ本機でも高域にピークを生じていたの
で、OPTを変更するなら念のため負帰還は減らした方が良いでしょう。
2.出力管には他にも6FQ7や6CG7等が、ソケット周りのヒータ配線に変更が必要ですが同様
に使えます。
3.その出力管ですが、本来は電圧増幅管でペアチューブなどは無いので、入手した四本の中でも良
いのでプレート電圧を比較して、大体同じ電圧になる様に組み合わせを変えて下さい。
4.それ以外は調整箇所も無く、配線間違さえしなければ一発で動作すると思います。二枚プレート
の純三極管の音が(何処かで聞いたようなフレーズですが)手軽に楽しめます。
諸 特 性
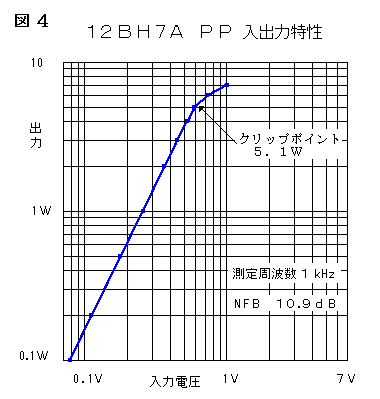
当初は入力1V時に最大出
力になるようにと考えていた
のですが、本機では0.6V
付近で定格出力となるので、
もう少し負帰還を増やしたい
ところですが、10kHzの方形
波やF特を見るとやや乱れが
見られるので、この程度に抑
えた方が良さそうです。
無歪出力5.1W THD3.2%
NFB 10.9dB(3.5倍)
DF=6.2 on-off法1kHz 1V
利得 21.1dB(11.3倍)1kHz
残留ノイズ0.58mV
|
次に歪率特性は上昇カーブを描いていてあまり見栄えがしないのですが、これは差動アンプの特性
によく似たカーブになっています。本機は前段がPK分割式なので全段差動方式ではありませんが、
ゲインに余裕があったので出力段のカソードコンデンサーを省いたのもので、このように定電流素子
ではなくカソード抵抗だけでも、ある程度の差動的な特性を見せるようです。
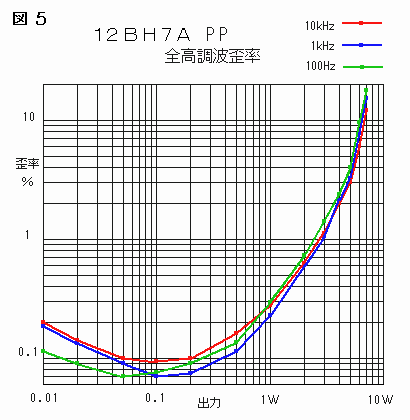
さらに周波数特性ですが、当初は150kHz付近にピークを生じていたので微分補正330PFを
追加したところ、ピークも消えて緩らかなカーブになり、最終的に10〜150kHz/−3dBの
良好な特性が得られました。
|
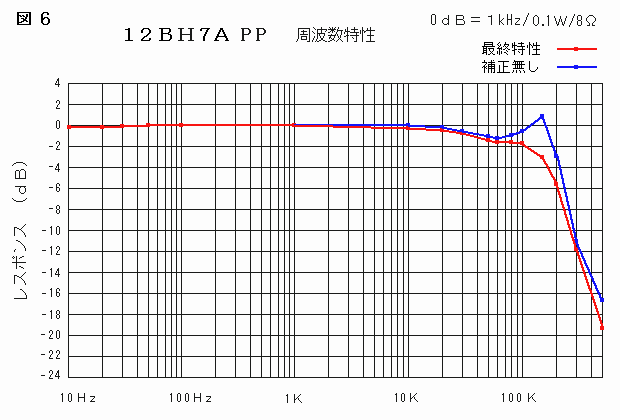
最後に10kHzの方形波応答を見てみると、補正無しでは少しリギングが見られますが補正後はきれい
な方形波になっています。写真は省略しましたが負荷開放でもまったく安定しています。
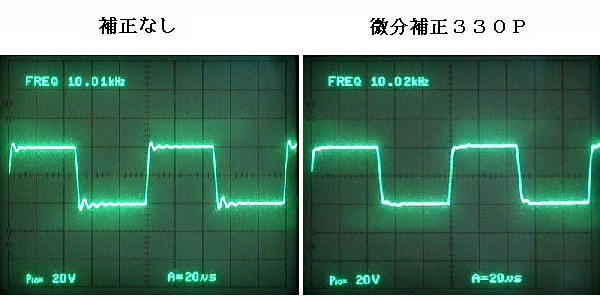
|
以上のようにデータ的には広帯域低歪と中々好ましい特性を見せていて、さすがにPP方式の本領
発揮というところだと思います。
雑 感
今回は手持ち球の有効利用という事もあって12BH7Aを取りあげたのですが、同クラスの専用
出力管にも遜色のない出来だと思います。また負電源等も必要ないようにとか、PPであってもなる
べく簡潔な回路を考えたのですが、それでも低域の伸びなど音的にもシングル方式とは数段違うよう
に感じました。
目次へ →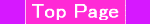
|
|