その後風の便りに、名前も内装も経営者も一変し、日本にでもいるよう
な華やかなクラブになったと聞いたが、縁遠い存在となった。
暗い天井からスタジオのような照明器具がぶら下がり、風格のある紳
士たちがグラスを傾け、そして(全裸に近い)半裸の美女たちが生き生
きと踊っていた、あのスパイの舞台「マレー・クラブ」を、瞼の中に永久
に残るしておきたかったからである。
憶良氏の手許には、青紫のインクで印刷された厚紙のメンバーシップ・
カード「R1・62192」号が、夜霧のロンドン記念品として保存されること
となった。
(嘘のようだがイロニイク二号とは乙なナンバーだった!)
古き良きロンドンの夜の雰囲気をお伝えするには、憶良氏はいまいち
経験不足・役不足のようである。
読者諸氏の人生には、一つや二つどころか、もっと多くの楽しい思い
出があろう。
今宵はブランデー・グラスや酒杯を傾け、しっぽりとした昔日の情緒を
瞼に、(口には出さず)しばしタイムスリップしようではないか。
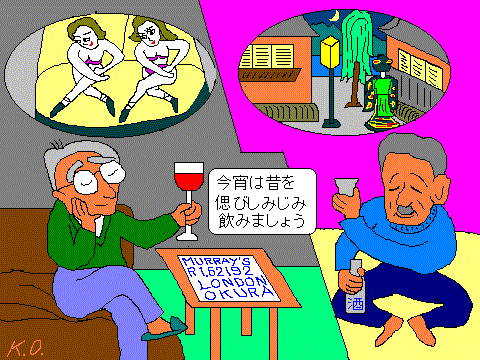
「ロンドン憶良見聞録」の目次へ戻る
ホームページへ戻る