


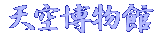
 |
 |
 |
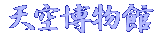
|

|
いろいろな現象を観るために
★注意!★
太陽のすぐそばもかなり眩しくなります。 うすい雲が掛かっていると、太陽の光が散乱されて、 太陽の周り、特にすぐそばはとても眩しくなります。 晴れている場合も、雨上がりなど、 大気中にほこりの少ないときはそうでもないのですが、 空気が汚れているときなどは相当眩しくなります。 直後は大丈夫でも、後から影響が出てくる可能性もあります。 眼を傷めないよう、充分ご注意下さいませ。 なお、カメラ用の減光フィルターは赤外線をあまりカットしないそうですので、 それもお気を付け下さい。 一般的な話太陽の遮蔽ということで、太陽と同じ側の空に現れる現象を観るときは、 太陽の遮蔽が重要になります。 手で隠すよりも、ちょっと離れた建物などで隠すほうがより確実ですし、 見やすいです。 さて、このときに簡単なコツがあります。 太陽が例えば建物で自分の眼から遮蔽されている、ということは、 自分の眼の位置が建物の影の中にはいっているということです。 すなわち、まず地面に映った影を確認して、 自分の頭の影が建物の影に入っていれば、 太陽は遮蔽されています。 自分の頭の影が、建物の影のぎりぎりのところ (ちょっと動けば日なたに出るところ) にあれば、太陽はぎりぎり隠されています。 これをうまく利用すれば、 隠したつもりが間違って太陽が目に入ってしまうことが避けられます。 予測できるか?!大気光象は、日食や月食、惑星同士の現象などとちがって、 事前に計算して起こる時刻や場所を予測することはできません (たぶん天気予報より難しいです^^;)。 とはいえある程度は天気の移り変わりから 「今日は見える可能性が高そうだ」 ということを把握することができます。 夏場、午後の早めの時刻に夕立がきそうならば雨上がりの虹が期待できますし、 冬場の関東地方では低気圧が近付いてきたときに、 その先ぶれの巻雲や巻層雲が広がりそうならば暈が期待できます。 土地柄もあるので一概にはいえませんが、 何度かいろいろな現象を目にしていると、 そのうち見えやすいパターンが判ってくるでしょう。 何かの現象を見たときはその周囲や前後の時間の空の様子も一緒に見ておくとよいでしょう。 各現象について内暈・幻日・タンジェントアーク など
幻日は、とても明るく色がはっきりしているときもありますが、 白くぼやっと明るいだけ、ということも多くあります。 そういうときには雲の色のむらと見分けづらいかもしれませんが、 雲が移動しても明るいスポットの位置が動かなければきっと幻日です。 太陽に近い側がちょっと赤ければ、より確実です。 虹
「雨が降っているところに日が射し込む」という状況の起こりやすさが、 場所によって違うようです。 京都や函館では (特に秋から冬の時雨の季節に) 虹がよく見られる、 と聞いています。 海外ではハワイが有名ですね。 逆に東京辺りでは意外と虹にはお目にかかれません。 主虹が見えたら、その外側ちょっと離れたところの副虹や、 紫色のすぐ内側の過剰虹も探してみて下さい。 これらは特に雨粒が大きいときに見えやすいようです。 海や湖の向こうに虹が見えるときは、虹の足元をじっくりと眺めて、 反射虹も探してみて下さい。 彩雲・光環彩雲は、雲の生成・消滅が激しいときによく見られます。 見えやすいパターンにはいくつかあります。 分類して勝手に^^;名前を付けてみると、
大雑把な分類ですし、これ以外のパターンでも見られますので、 あくまで参考程度にお考え下さい。 大きめの巻層雲や高層雲で、比較的広い範囲が一様な感じに見えるときは、 円形の光環が見られます。 雲のムラがあると円形から形が崩れますが、 どこまでが光環でどこからが彩雲かは悩ましいところです^^;。 まあ、あまり厳密に区別しても意味はないとは思います。 「空気のきれいなところでないと彩雲は見えない」と言われることもありますが、 「見えない」わけではありません。 太陽のすぐそばで見えることが多いため (太陽を直接見ないよう、ご注意下さい)、 大気中に埃などが多いと太陽のそばの空自体が眩しくなって見づらい、 というのはあります。 低気圧の通過後などの埃の少ない状況のほうがきれいに見えることは多いです。 しかし、眩しいとはいえ彩雲にはなりますし、 (特に高積雲で見えるタイプなどの場合) 太陽からけっこう離れた方向 (内暈の近くくらい) でも彩雲は見られます。 眩しい彩雲の場合は、減光して写真に撮ったほうが判りやすいかもしれません。 雲自体も、埃と同じで、太陽のすぐそばでは (色がつこうとつくまいと) 眩しくなります。 ですから、 太陽が薄い雲に覆われていることが必要で、 太陽のすぐそばにしか現れない光環を見ることは意外と難しいかもしれません。 太陽を隠して、 さらにサングラスやフィルターで減光しないと判らないこともあるでしょう。 それに対して、月の光環は楽に見えます。 月光で彩雲も見えることがありますが、逆に暗くて判らない場合も多いかと思います。 月本体と光環や彩雲との明るさの比は太陽の場合とあまり変わらないので、 写真を撮る場合には気を付けなければなりません。 環天頂アーク・上部ラテラルアーク
さて、どういう空模様のときに探せば首を痛くする甲斐がありそうかというと、 判りやすく可能性も高いのは、刷毛で掃いたような筋状の雲 (巻雲) が空に広く現れているときです。 そして、太陽が 10度〜25度くらいのときが見えやすい時間帯です (約32度より高いと見えません)。 東京だと冬至の頃には 14:00前でも見えますが、 夏至の頃には 17:00過ぎくらいにならないと見ることができません。 環天頂アークは特に単独でも見えることも多いですが、 筋状の雲が出ていてさらに内暈や幻日が見えているときには、 上を見上げると環天頂アークも見えているかもしれません。 上端接弧 (上部タンジェントアーク) が見えているときには上部ラテラルアークも見えているかもしれません。 アークの端のほうが二股に分かれているようだったら、 それはきっと環天頂アーク+上部ラテラルアークです。 |
 |
Contact:
aya@ |
Copyright 1998-2025, AYATSUKA Yuji |