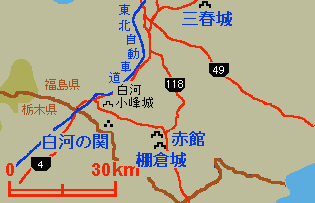
変なタイトルで適当ではないですが、中通り地方というのは福島県中央の南北に走っている平野部のことをいい、東北新幹線や東北自動車道も走っているエリアですね。
このような交通の要所には城が集中するもので、福島県の城郭の大半は、この”中通り”に集中しているようです。そんな中で栃木県に近い南側の城を紹介いたします。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
福島中通りの城
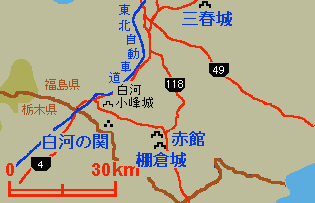
変なタイトルで適当ではないですが、中通り地方というのは福島県中央の南北に走っている平野部のことをいい、東北新幹線や東北自動車道も走っているエリアですね。
このような交通の要所には城が集中するもので、福島県の城郭の大半は、この”中通り”に集中しているようです。そんな中で栃木県に近い南側の城を紹介いたします。
1つ前に戻る ホームへ戻る
赤館
|
所 在:福島県 東白川郡棚倉町棚倉
地図[MapFanWeb] 交 通:JR水郡線 磐城棚倉駅下車 徒歩30分 種 別:中世 山城 古くから城があったようで、永禄3年(1560年)に蘆名盛氏が再構築した後は、蘆名氏、結城氏(白河)、佐竹氏との間で、激しい奪回戦が何度もあったようです。 小田原の役後は佐竹の居城となり、関ヶ原前哨戦の上杉討伐で、幕府に反抗的な佐竹義宜はこの赤館で布陣し、出羽秋田に国替えのきっかけとなりました。 その後、立花宗茂、丹羽長重が入城し、寛永元年(1624年)に長重が棚倉城に移ってからは廃城となります。 遺構は良く確認できませんが、主郭跡がきれいな公園になっています。所々ある平削地も、駐車場やお花畑などになっています。 写真は山頂から北側を写したものです。標高350mですが比高は100mぐらいでしょう。 しかし、この台地の南側には久慈川へ通じる平野部が広がっており、北側は白河方面の道(国道289号)と、郡山方面への道(国道118号)の道の分岐点で、関東と東北を分断する分水嶺でもあるため、非常に重要な要所です。 |
棚倉城
|
所 在:福島県 東白川郡 棚倉町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR水郡線 磐城棚倉駅下車 徒歩10分 種 別:近世 平城 寛永元年(1624年)幕府は丹羽長重に、関東の入り口を守るにふさわしい城郭の構築を命じます。長重は、赤館から南へ2kmの久慈川河岸の台地にあった都々古和気神社に目をつけ、この神域を移した後、輪郭式(本丸、二の丸)の広大な城郭を構築します。 長重は、安土城築城の奉行であった丹羽長秀の子で、長重と家臣団はこの後、東北ではめずらしい総石垣造りの白河小峰城を築城することになります。 また、長重の子光重は二本松城を築城するなど、丹羽家は思いっきり幕府に利用されますが、家名は二本松藩で維新まで続いたので幸運だった方でしょう。 その後城主は、内藤氏、太田氏、松平氏などめまぐるしくかわり、阿部氏で維新を迎えました。 棚倉城の遺構は、本丸と内堀が残ります。石垣はなく全て土塁によるものですが、本丸には大型の土塁がぐるりと囲んでおり、掘も完全な水掘になっています。 上写真は本丸の西南の角で、水掘に噴水があるためその規模の大きさが分かると思います。 現在本丸内は、公民館や図書館などの公共施設があり、城の建造物をモチーフにした建物もみられました。 下写真は本丸北側にある門跡で、食い違いになっているのが良く確認できます。写真左奥には櫓門があり、左手前にも門があったようなので、内桝形を構築していたようです。 失礼ながら、現在棚倉はさみしい街で、この場違いの城郭には驚きますが、幕府はこの要地を重く見たのでしょう。当時、仙台には独眼流が健在でしたからね。 |
白河の関
|
所 在:福島県 白河市 旗宿
地図[MapFanWeb] 交 通:JR東北本線白河駅から車で20分 種 別:古代 関所跡 城じゃないですがかんべんして下さい。 関所が置かれたのは古代で、大化の改新後には存在していたものと考えられており、13、14世紀には廃止になっています。この関所を有名にしているのは文学の世界で、多くの古歌に詠まれており、芭蕉も奥の細道で”春立てる霞の空に白河の関越えん”と詠んでいます。 関所の実態は不明な部分が多く、白河神社を取り囲むように、竪穴式住居跡や中世の館まで、たくさんの遺構や出土品が出ています。神社の入口に白河藩主の松平定信が立てた”古関蹟”の碑もあります。 写真は白河神社の南側にある土塁、空掘で、結構大型なものですが、いつの時代のものかは不明です。 |
三春城
|
所 在:福島県 田村郡 三春町
地図[MapFanWeb] 交 通:JR磐越東線三春駅 下車徒歩30分 種 別:近世 山城 永正元年(1504年)田村義顕が築城し、清顕の時代には隆盛を極め、相馬氏、白川結城氏などと肩をならべます。清顕の死後は伊達政宗に下り、秀吉の奥州征伐で領地を奪われますが、のち伊達忠宗の三男宗良により、一関藩にて田村氏は再興されています。その後の三春城は、秋田氏が入封し明治を迎えました。 上写真は三春城の遠景で比高80mほどの山ですが、回りも山があるので全然眺望はききません。このため清顕は一度も籠城戦を行うこと無く、常に城から出て戦ったようです。 山頂の遺構は、最高位の奥の間、一段下がって大広間とあり、二つで本丸と称していたようです。本丸には神社跡と思われる石垣があり、秋田氏の慰霊碑が建っています。 本丸から西側にさらに一段下がると、旧二の丸(秋田氏時代はここも本丸)で、南に大手、北に搦手の門があったようです。 下写真は、旧二の丸の西端に建っていた御三階跡で、そんな雰囲気が感じられますね。 城山の南側登山口(車も入れます)付近に、若干ですが石垣の遺構もあります。 |