ジャズは
ニューオリンズで
今世紀の初めに生まれた。


ジャズは今世紀の初頭、ニューオリンズの町で産声を上げた。元々黒人労働者や奴隷の間出歌われていたワーク・ソングや黒人霊歌などの要素に、西洋音楽の手法も取り入れ、そこにニューオリンズ伝来のブラス・バンドが組み合わさって、ジャズのプリミティブなスタイルが誕生する。この町から輩出したミュージシャンには、”初代ジャズ王”と呼ばれたバティー・ボールデン、「1902年にニューオリッンズでジャズを創造した」と公言してはばからないジェリー・ロール・モートン、そしてジャズを創造的な音楽に成長させたキング・オリバー達がいる。彼等の活躍によってジャズはアメリカ各地に広まっていくが、なかでも希代のエンターテイナーだったルイ・アームストロングは、1920年代になるとニューオリンズからシカゴやニューヨークに進出して活躍。それぞれの地にジャズを根づかせるのに大きく貢献した。とりわけ1920年代後半から30年代にかけて彼が結成していた”ホット・ファイブ”と”ホット・セブン”はニューオリンズ・ジャズの初期における最大の成果として現在でも高く評価されている。ニューオリンズ・スタイルのジャズは、セカンド・ラインと呼ばれるベース・ラインとリズムが特徴で、そこに独自のブラス・アンサンブルが加わったものだ。最近では同地出身のウイントン・マルサリスが現代的な演奏のなかにその要素を巧みに取り入れ、大きな反響を巻き起こしている。

1929年秋に始まった株の大暴落は、またたく間に世界中で連鎖反応が起こり、好景気湧いていたローリング・トエンティの時代に終止符を打つこととなった。それまでのジャズはニューオリンズ・スタイルやディキシー・ランド・ジャズが主流だったが、こうした不況を背景に、人々は賑やかなものよりスィートでスィンギーな演奏を好むようになってくる。そうして登場してきたのがスイング・ジャズだったアンサンブルを中心に大編成で演奏されるスイング・ジャズは、それまでのジャズが黒人主体だったのに対し、白人が主導権を握ったことでも特記すべきものだ。スイングジャズのブームは1930年代後半にっやってくる。ちょうど第2次世界大戦が始まる直前までが、スイング・ジャズの大ブームだった。ベニー・グッドマンを筆頭に、グレンミラー、トミー・ドーシー、アーティ・ショウといった白人バンド・リーダーが率いるオーケストラは、各地のボールルームやホテルで大きな評判を呼ぶ。そしてこのスイングジャズのブームと共に、人気を獲得したのがそれぞれのバンドに参加していたシンガー達であった。中でもトミー・ドーシー楽団んい在籍していた若き日のフランク・シナトラが圧倒的な人気を誇り、スイングジャズが黄金時代を迎えることに一層の拍車をかけたのだった。しかしやがて戦争が勃発し、経費の嵩むビッグバンドは商業的に難しくなり、この黄金時代も終焉を迎える。
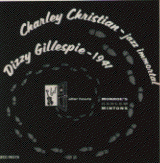
太平洋戦争が勃発した1941年、ニューヨークのハーレムではジャズの世界を大きく変える出来事が起こりつつあった。チャーリー・クリスチャン、ディジー・ガレスビー、セロニアス・モンク、チャーリー・パーカー、マックス・ローチーといった気鋭の若手達がレギュラーの仕事を終えるやあちこちのクラブに集まって新しいジャズを創造し始めたのである。スイングジャズに飽き足らない彼等は、リズムを複雑なものにし、スピード感溢れたテンポで自分達の考えるジャズを夜な夜な演奏していた。そうした中から、ビバップと呼ばれるモダン・ジャズが誕生。とりわけ熱心にこうした活動を行っていた拠点がモンローホテルの1階にあった”ミントンズ・プレイハウス”で当時のセッションを記録した「ミントン・ハウスのチャーリー・クリスチャン」は、ビバップ誕生の瞬間を捕えた歴史的傑作としてジャズ界における最高のドキュメントとして評価されている。ビバップの誕生によって、まずはニューヨーク中にミュージシャン達がこの新しいスタイルのジャズに宗旨変えしてしまう。その結果スイング・ジャズがすたれてしまったのは当然の成り行きだ。スイングジャズはどちらかと言えばダンス向きの音楽だった。しかし激しいビートを主体としたビバップはダンスに適さず、鑑賞用の音楽として人々に向かえられた。ジャズクラブが続々とオープンしたのも、こうした理由による。
1950年代はモダン・ジャズの黄金時代だった。ニューヨークを中心としたイースト・コースとでは、ビバップが一般的になったため、次なるハードバップが登場してくる。ビバップもハード・バップもホットな演奏に特長があったが、その反動というか、そうした熱狂的なプレイに批判的だったミュージシャン達が台頭してきたのもこの時代だ。その代表格はレニー・トリスターノ、リー・コニッツ、ウオーン・マーシュたちだ。一方ウエスト・コーストでは、ニューヨークのクール派にも一脈通ずる演奏が大きな反響を呼んでいた。知的でクールなサウンドはアンサンブルにも工夫が凝らされ、これらの演奏はやがてウエスト・コースト・ジャズと呼ばれるまでになる。ウエスト・コースト・ジャズが発展した背景としては、戦後になって映画産業が盛んになり、多くのミュージシャンがイースト・コーストからウエスト・コーストへに流れていったことが上げられる。そしてウエストコーストジャズの立役者であるチェットベイカーやジェリーマリガン達が優れたアルバムを吹き始めたのが1950年代半ばのことだった。
ハーレム問衛馬黒人の巣窟のように思われているが、その昔は豪華な社交場が並び、ニューヨーク・エンターテイメントのメッカとして知られていた。映画”コットンクラブ”で紹介さあれたように、実在した高級クラブ”コットンクラブ”では、1927年からデユークエリントンのオーケストラを専属に迎えて大評判を呼び始める。同オーケストラは1931年まで出演し、その後に登場したのがギャップ・キャロウエイ楽団だった。この時点でキャロウエイは「ミニー・ザ・ムーチャー」の大ヒットを飛ばしており、ハーレムでは絶大の人気を誇っていた。同楽団が、”コットンクラブ”に正式な形で連続出演するのは1932年からのことで、これは1934年まで続く。この時代になると世界大恐慌も深刻になっており、次々とこうした高級ナイトクラブが閉鎖中、”コットンクラブ”は孤軍奮闘。1934年にはジミー・ランフォード楽団を専属バンドに迎えて、面目躍如たるラインナップを継続している。
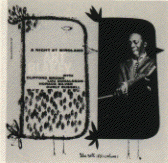
1940年代にブームとなったビバップは、1950年代に入るとビートを一層躍動的なものとしたハードバップへと発展していく。なかでも1951年に吹き込まれたマイルス・デイビスの「ディグ」(プレステージ)あるいは1954年の「アートブレーキ/バードランドの夜」(ブルーノート)は、ハードバップ初期の熱気を伝える名盤だ。ハードばっぷはビバップに比べると、シンコベーションが多く、メリハリの効いたビートに特長がある。ソロにもそうしたリズミックなフィギアを取り入れたため、演奏全体が躍動感に富むものとなった。特にこの時代のアート・ブレーキーと彼のジャズメッセンジャーズ、クリフォード・ブラウン=マックスローチ・クインテッド、マイルス・デビスやソニー・ロリンズなどの演奏に典型的なハードバップのサウンドが認められる。そしてハードバップの中でもブルージーな要素を強調したものが後のファンキージャズに繋がっていく。例えばハンク・モブレーやルー・ドナルドソンは、1950年代半ばに早くもそうした傾向を示していたし、ファンキーピアノの元祖ホレス・シルバーやソニー・クラークも、同じころからファンキーなタッチを聴かせていた。なかでもファンキーな要素を巧に取り入れて人気を獲得していたのがジャズ・メッセンジャーズで、彼らの「モーニン」(ブルーノート)はハードバップ〜ファンキーを代表する傑作となった。
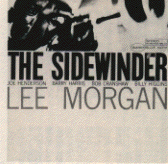
1960年代になると、世の中が再び騒がしくなってきた。ベトナム戦争が泥沼化し、公民権運動の高まりと共に、黒人に意識革命が起こってくる。それにつれてジャズの動きにもさまざまなものが出てきた。1950年代後半に頂点へ達したビバップをベースに、ジャズあるいはモードジャズやフリージャズと、ジャズのスタイルがそれまでにないほどの多様化を示していく。ジャズは社会の流れと連動しているようだ。世の中が平和ならジャズもおっとりとした内容のものとなる。しかし、1960年代のように大統領が暗殺されたり、抜け道のない不毛な戦争をやっているときは、ジャズもアグレッシブなものとなる。その象徴がフリージャズだった。そしてビートルズを始めとしたブリティッシュロックの台頭によって、音楽シーンは未曾有うのロックブームに巻き込まれる。ジャズは次第に片隅に追いやられ、その結果登場してきたのがジャズロックだった。この中からハービー・ハンコックの「ウオーターメロン・マン」や「ザ・サイドワインダー」が大ヒットとなるが、これは時代の落とし子のようなものだろう。ジャズロックはやがてイージーリスニングジャズやクロスオーバーと名を変えて現在のフュージョンにまで継続されるが、その過程でマイルス・デビスが発表した「ビッチェズ・ブリュー」(ソニー)は、歴史を揺るがす傑作だった。
ハードバップやファンキージャズが盛り上がりを示す一方で、マイルス・デビスはそれだけに飽き足らず、アレンジャーのギル・エバンスと君で、モードジャズの探求にも乗り出す。モードジャズは音階を用いてアドリブを行なう手法で、コード進行に沿ってアドリブを行なっていたそれまでのジャズと大きく要そうを異にするものだった。マイルスとギルは、民族音楽や現代音楽からヒントを得手モードによる奏法を考え出す。その成果は1959年に吹き込まれた「カインド・オブ・ブルー」(ソニー)の中に認められるが、彼らの運動とアルバムの成功によって、ミュージシャンのあいだでも除々にモードイディオムを取り上げるひとが増えていく。そして1960年代に入るとモードジャズがジャズの主流としてクローズアップされて来る。マイルスの門下生達によってモードイディオムに乗っ取った演奏法が普及した結果、ついに新主流派と呼ばれるスタイルまでに消火されたのだった。

1960年にマイルスデビスがレコーディングした「ビッチェズ・ブリュー」は、発表当時多くの話題を集めた問題作だった。マイルスがロックのイディオムを大胆な形で導入したこの作品は過去に彼が残してきた知的でリリシズムに溢れたジャズとは全く様相を異にするものだったからだ。もちろんマイルスはこの暫く前から、除々にスタイルを変えていた。しかし、それまではジャズの範囲で理解の出来る内容だった。それが「ビッチェズ・ブリュー」では、ジャズの要素が姿を消してしまう。それまでのファンはおおいにとまどったことだろう。しかし常に前向きなマイルスは、ジャズと決別して新たな時限に向かっていたのである。その結果、多くのミュージシャンがマイルスの音楽に刺激されて、大きく影響されて、1970年代のシーンを形成していく。この時代を彩る最重要グループのウエザー・リポートは、マイルスと長年コンビを組んできた。テナー奏者のウエイン・ショーターと、「ビッチェズ・ブリュー」他で斬新なプレイを聴かせたキーボーディストのジョー・ザビヌルが発足させたグループだ。その他マイルスグループの卒業生hが結成したグループには、チック・コリアのリターン・トー・フォエバー、ジョン・マクラブリンのマハビシュヌオーケストラ、ハービー・ハンコックのヘッドハンターズ・トニーウイリアムスのライフタイム、ジャック・ディジョネットのコンポストなどがある。
フリージャズが大きな動きとなってきた1964年、ニューヨークの”セラー・カフェ”で10月1日から4日間、「ジャズの10月革命」と呼ばれるイベントが開催された。これはトランペターのビル・ディクソンが主催したもので、ライブ演奏と討論会を通して、フリージャズの理解を深めようというのがその主旨だ。参加したミュージシャンはポール・ブレイ、サンラ、ラズウエル・ラッド、チャールズ・モフェットなど20数組みで、収容人員90名のこの店に、延べ700人以上のファンが参加。フリージャズへの感心が如何に高いものであるかを証明したと同時に、ミュージシャンサイトにもこのイベントを通していくつかの動きが認められた。中でも最大の成果と期待されたのはジャズ・コンポーザーズ・ギルドの結成で、この団体は2ヶ月後にコンサートを開き、その後メンバーのカラブレイが中心となってJCOA(ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラ・アソシエーション)設立へと発展していく。

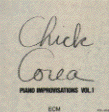
フュージョンが華やかな時代に、エレクトリックサウンドたは全くかけ離れたアコーステックピアノによるソロブームが突如として巻き起こった。ことの発端は、チック・コリアとキース・ジャレットが相次いで素晴らしいソロピアノ集(共にECM)を発表したこと。この2作の成功によって刺激され、レコード会社も本腰を入れ始めた。代表的な作品には、レイ・ブライアントの「アローン・アット・モントルー」(アトランチック)、ポール・ブレイの「オープン・トゥ・ラブ」(ECM)、マッコイ・タイナーの「エコーズ・ア・フレンド」(ビクター)などがある。フュージョンの台頭によってアコーステックジャズがおいやられていた時代、一方でこうした良質な作品も作られていた。しかもこれらの多くが日本やヨーロッパのレーベルによって制作されていたことも、当時のジャズ状況を示すものだ。70年代以降、ジャズはアメリカよりも日欧で盛んとなる。
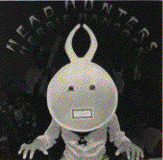
マイルスの「ビッチェズ・ブリュー」(ソニー)によって膜を開けたフュージョン時代だが、それにしても絢爛豪華にこの時代の音楽は華開いた。フュージョンといってもさまざまな音楽との組合せがあり、ロックやファンクにとどまらず、クラシックや民族音楽との融合も認められる。また多くの実験的な演奏もフュージョンという名のもとに行なわれ、いわゆる4ビートジャズの存在は霞んでしまったが、この時代はこの時代で音楽が非常にたわわな実を示した時代であった。重要なことは、それまでのジャズが比較的小人数のオーディエンスを対象にしていたのに対し、フュージョンはビッグオーディエンスを獲得し、ミュージックビジネスとしても大きな成功をもたらした点であろう。結局このことが両刃の剣になってしまうのだが、それでも当初は、それまで不遇を見ていたミュージシャン達が成功するなど、ポジティブな面も多く認められた。ジャズを身次かなものにし、誰もが楽しめるといったイメージにしたその功績も極めて大だ。中でも最大のヒットが、ハービー・ハンコックの「ヘッド・ハンターズ」(ソニー)とドナルド・バードの「ブラック・バード」(ブルーノート)だった。これらはチャートの上位にランクされ、ジャズを超え広く一般の音楽ファンに支持された。こういう作品が突破口となり、フュージョンは厚いファン層を確保したのである。

1980年代に入ってジャズの様相が一変した。それまでのフュージョンブームから脱却して、再びメインストリートジャズにファンの関心が戻ってきたのである。最大のきっかけは、ウィントン・マルサリスのデビューだ。ニューオリンズに生まれた彼は、1980年にニューヨークに出てくるや、伝統に立脚した演奏でたちまち大きな注目を集める。その彼が牽引車となって、光景する若いミュージシャン達が次々とストレートなジャズを演奏するようになったのだ。一方、フュージョンでお茶を濁していたベテランミュージシャン達も、ウィントンの成果に刺激されてメインストリームのジャズシーンに戻ってきた。ウィントンが開けた扉は、80年代半ばになるとジャズの世界で主流となり、メインストリームジャズが再び大きな勢力となるに至った。そのウィントンは、現在自己のセプテットを解散し、クリエイティブディレクターを勸めるリンカーンセンターのジャズプロジェクトに勢力を注いでいる。個人的な見解を述べさせていただくなら、ウィントンの兄でサックス奏者のブランフォード、あるいは彼らと同郷のトランペッター、テレンス・ブランチャードやアルト奏者のドナルド・ハリソンたちが中心になって、以後のメインストリームジャズシーンは動いてきた。1980年代後半には次世代の、そして現在は次々世代の新人達が世に登場してきている。彼らのパワーがあるかぎり、モダンジャズは顕在だ。
